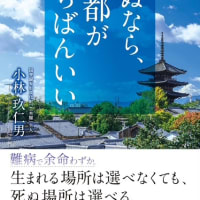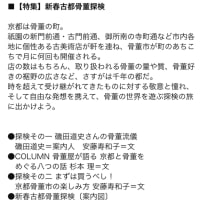京都・木屋町通り沿いに流れる、「高瀬川」の名は、森鴎外の同名の歴史小説によって、よく知られている。
春には、この高瀬川沿いの、桜の木々が咲き乱れ、二条近くにある、「一の舟入」の辺りから、五条まで、えんえんと、桜の小道、とでも呼ぶべき、景観を創り出す。
高瀬川に覆いかぶさるようにして、まさに、春爛漫といった感じで、咲く桜の花々、キラキラと春陽に輝く川面、桜の花弁を運ぶ川の流れ、等々、
たとえば、もし、禅僧か何かに、「生きている歓び」、というものを視覚的に表現したら? とでも、問われたなら、
躊躇なく、桜が満開に咲く高瀬川の春の光景を、指差すのではないか、と思ってしまう位、春の高瀬川沿いは、私の好きな場所の1つだ。
ところで、この高瀬川については、「角倉了以・素庵父子によって人工的に創られた運河」といった程度の知識しかなく、以前から、気になっていた。
- 高瀬舟の運行というのは実際どのように行われていたのだろう?
- いつ頃まで、高瀬舟の運行というのは、行われていたのだろう?
- 物資の運搬に、何故、鴨川などの自然の川が使われず、人工運河などという手間と資本の要る途が選ばれたのだろう?
- 高瀬舟が運行していた当時の川深は、どれ位あったのだろう?
- 角倉了以や、その子の素庵というのは、どういう人々だったのだろう?
等々、高瀬川については、疑問がいくらでも湧いてくる。
 |
京都 高瀬川―角倉了以・素庵の遺産 価格:¥ 2,310(税込) 発売日:2005-08 |
石田孝喜さんという方の書かれた、「京都・高瀬川~角倉了以・素庵の遺産~」は、これら誰しもが抱く、高瀬川に対する素朴な疑問に、1つ1つ答えてくれる、高瀬川の百科事典のような本だ。
石田さんが、本書を執筆した当時には、未だ生存されていた、高瀬舟が運行されていた当時の実際を知る、古老の方からの、聞き取り調査の内容も載っており、
京都の歴史ファンには、欠かせない一冊と言える。