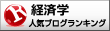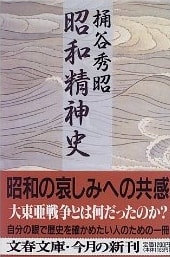大江健三郎『ヒロシマ・ノート』を埋葬する(その1)
当ブログで、ちょっと前に大江健三郎氏の『沖縄ノート』を取り上げ批判しました。今回は、『ヒロシマ・ノート』を取り上げようと思います。
率直に言えば、大江氏の政治評論に接するとまずは理屈抜きに「虫が好かない」という思いが湧いてきます。読み手を自分のフィールドに引き込もうとする氏の手つきに、人間の弱点につけこんで読み手を黙らせようとする不健全なものを感じるからです。その場合の「人間の弱点」とは、痛めつけられた悲惨な弱者の存在を執拗に振りかざして、それに寄り添おうとする、書き手である自分の良心的であるかのような身振りを独特の粘着質の文体で見せつけられ続けると、不愉快ながらもなにやら文句が言いにくくなり陰にこもってしまうという人間の不可避的な心の傾きのことです。大江氏の政治評論は、それにつけ込むことで成り立っているように感じられるのです。だから、読後にとても嫌な気分になります。そこには、ニーチェが鋭く見抜いたような、弱者のルサンチマンが隠し持つ青白い不健全な権力欲が感じられるのです。
彼の『ヒロシマ・ノート』一冊を読み通すのにどれほどの時間を費やしてしまったことでしょうか。なかなか先に進まない読書を自分に強いている間、気持ちが乗らない読書は苦行のようなものである、という感慨が幾度も湧いてきました。本書を放り投げてしまったらどれほどスッキリするか、と思ったのも一度や二度ではありません。
″だったら、読まなきゃいいじゃないか″という声が聴こえてきます。むろん、その通りなのです。が、他方で″自分の目が黒いうちに、大江健三郎的な政治思想はすべて埋葬してしまいたい″という止み難い欲求があることもまた確かなのです(朝日新聞に対しても同じ思いを抱いています)。大江健三郎の政治言説には、戦後思想のダメなものが集約されている、というのが私なりの見立てなのです。悪口を言うには、一応彼が書いたものを読まなければなりませんものね。で、しぶしぶ読み始めてみたら、なかなか先に進まなくて難渋した、というわけなのです。あの独特の、悪文としか言いようのない癖のある文体にも閉口しましたけれど。小説で成功した文体を政治評論や社会評論にそのまま持ち込むことには大きな問題があると私は考えています。それについてもいずれ触れようと思います。
若くてナイーヴで心優しき読み手は、本書が内包する陰湿な猛毒にあてられたならひとたまりもないのではないかと思われます。そうなると、いわれのない罪悪感と過剰な放射能コンプレクスを抱え込まされて、物事をバランスよく考えることができなくなってしまうのですね。それは、実のところ倫理なるものとまったく関係のない、時間を空費し頭が悪くなるだけの馬鹿げた経験にしかなりません。そういう犠牲者をひとりでも少なくすることに、当論考がいささかながらでも貢献できたら、などと柄にもないことも考えております。一応馬齢を重ねていますから、若い人たちのことがそれなりに気にかかるのです。若者たちよ、大江氏がノーベル章を獲ったからって、変に信用しちゃだめですよ、彼は一種のカルトなんですよ。
いささか前置きが長くなったようです。では、始めます。
大江氏の、ルメイへの叙勲に対する憤りは分かるが、その理由づけには賛成できない
不満なところだらけの本書のなかで、一点だけ、素直に首肯できる箇所があります。まずは、それについて触れておきましょう。次が、その箇所です。
東京ではひとつの叙勲が行われていた。勲一等旭日大綬章をうけた米空軍参謀総長カーチス・E・ルメー大将は広島、長崎への原爆投下作戦に、現地で参画した人物である。この叙勲について政府の責任者はこう語ったとつたえられる。《私も空襲で家を焼かれたが、それはもう二〇年も前のこと。戦争中、日本の各都市を爆撃した軍人に、恩讐をこえて勲章を授与したって、大国の国民らしく、おおらかでいいじゃありませんか》
この鈍感さは、すでに道徳的荒廃である。
このように大江氏は、当時の日本政府が、カーチス・ルメイに叙勲したことに強く憤っています。私も大江氏とともに大いに憤りたいと思います。しかし憤る根拠について、私は、大江氏と大きく意見を異にします。大江氏は、いま引いた文章に続けて、次のように言っています。
広島の人間の目でそれを見れば、これはもっとも厚顔無恥な裏切りであろう。
要するに、″ルメイには、広島・長崎に原爆を投下したことに対する当事者責任があるので、叙勲などとんでもない″と大江氏は言っているのです。空爆の司令官だったルメイが、組織上の原爆投下の責任者だったことは確かです。しかし彼は、原爆の投下に一貫して反対の立場だったのです(以下の展開は、日高義樹氏『なぜアメリカは日本に二発の原爆を落としたのか』(PHP文庫)を踏まえたうえでのものです)。DVDにもなっている、NHKの『東京大空襲』という番組のために日高氏が彼にインタヴューしたとき、ルメイははっきりと次のように述べています。すなわち、「原爆を使わなくても、我々が日本に圧力を加えつづけていたので、無条件降伏させられることは確実だった。日本本土への上陸作戦も必要ではないと思っていた」と。ルメイは、事あるごとにそういう発言をしています。ちなみに、アイゼンハワーやマッカーサーやニミッツなどの軍の首脳も、原爆投下には反対していました。一般市民の瞬時の大量殺戮を惹起するような原爆投下を敢行しなくても、戦争は事実上ほぼ終わっていたし、日本を降伏させるのは時間の問題だと判断していたからです。戦争の現場を知る者のまっとうな認識が感じられますね。その意味で、彼らはクレイジーではなかったようです。
″だからルメイには、原爆投下の責任などまったくない″と言いたいわけではありませんよ。組織上の立場からすれば、当然ある、とすべきでしょう。しかし、それを根拠に叙勲をとんでもないこととするのはちょっと無理があると言いたいのです。当時のトルーマン大統領が、自分の権限において、自分の政治的な立場を強化するためにだけ、身を乗り出して小躍りしながら原爆投下の意思決定をしたことと比べると、ルメイの責任など消し飛んでしまうほどなのです(その詳細については、いずれ触れます)。もしも当時の日本政府が、トルーマン元大統領への叙勲をしようとしたならば、原爆の投下責任を根拠に憤るのはまったくもって正しいとしか言いようがありません(想像するだけで気分が悪くなってきますが)。
ルメイへの叙勲がとんでもないことである理由は、別にあるのです。
それをはっきりさせるために、ルメイの前任者であったヘイワード・ハンセル司令官に触れておきましょう。ハンセルは、ルメイが超低空から東京全体を焼き尽くし、数十万の市民を殺戮するという非情な爆撃を指揮したのとは対照的な指揮ぶりでした。彼は、B29で超高空から爆撃するとき、雲がかかっている場合は、市民への爆撃を避けるために、爆弾を落とさないまま爆撃機をグアム島に戻しました。爆撃部隊の首脳は爆撃の効果が上がらないことに業を煮やしてハンセルをファイヤーし、ルメイを東京爆撃の責任者にしたのです。
日本の諸都市への、ルメイの爆撃は徹底していました。原爆投下までに、日本の人口五万以上の二六都市がすべて爆撃され、一〇万トン近い爆弾や焼夷弾が落とされ、五〇万人の市民が命を落としていました。それは、広島・長崎の犠牲者の約五倍に当たります。そのなかでも特筆すべきは、一九四五年三月一〇日の東京大空襲です。同空襲において、焼夷弾をごく短い間隔で投下し、その上からガソリンを撒くという殺戮のための爆撃が敢行されました。このとき、三三四機のB29がナパーム弾を七〇〇メートルという低空から投下しました。爆撃は夜の一〇時から午前五時まで続き、東京の東半分の四一平方キロが焼け野原となり一夜で約十万人が死にました。これは、どう言い逃れをしようとも、無差別爆撃であることは間違いありませんし、正真正銘のホロコーストであるというよりほかはありません。ルメイは、この大爆撃を揺るぎない確信をもって敢行したのです。ルメイへの叙勲がとんでもないのは、不本意な原爆投下をしたからというよりも、軍事的に正当な行為であるという確信をもって東京大空襲という大量無差別殺戮を敢行したからなのです。
大江氏は、どうしてそのことが視野に入らなかったのでしょうか。同書を刊行した一九六五年当時には、そういう情報が不足していたのでしょうか。ならば、その後そういうふうに訂正すればいいいだけのことですが、そういうことをしている事実は、寡聞にして知りません。
『沖縄ノート』で沖縄県民をそうしたように、同書で、原爆の悲劇的な犠牲者を祭り上げ聖別しようとする大江氏の志向性やモチベーションがあまりにも強すぎて、東京大空襲という惨事がその視野に明瞭には入らなかったのではないかと、私は考えます。
では、なぜ大江氏は、原爆の被害者を特別視し聖別し祭り上げようとするのでしょうか。それは、そうすることで、読み手を黙らせて異議申し立てを封じ込み、自己卑下教という幻想共同体への強制参入を図り、自分はその陰の司祭に成り上がろうとしているように私には感じられます。氏の、晦渋な、もって回ったような奇妙な言い回しの行間から、そういう腐臭がしてくるのです。それは、半分以上、潜在意識のなせる業ではないかとも思われます。氏の体質それ自体に、そういうひねこびた陰湿な権力志向がこびりついているということであります。
それにしても、ルメイに勲章をくれてやろうとする神経はまともではありませんね。精神病理的なものをすら感じます。つまり、こうです。耐えがたいほどの屈辱を受けた者は、屈辱を与えた当の相手に対して大げさな許しのポーズを示すことで、相手に対して精神的に優位に立ったと思いたがりますが、実は、その行為全体で、屈辱を与えた相手にその後もなお精神的に屈服していることを示しています。なぜなら、彼はほかのあらゆる振る舞いはしますが、相手に歯向かうという振る舞いだけは決してしようとしないからです。むろん、日本国民に対して確信を持って無差別大量殺戮を敢行したルメイに勲章を授けようとする日本政府の振る舞いが、「大げさな許しのポーズ」に当たります。そういう汚辱に満ちた倒錯を、日本政府はいつまで続けるつもりなのでしょうか。この倒錯心理と、大江氏の原爆観とは、実は無縁ではありません。 (つづく)
当ブログで、ちょっと前に大江健三郎氏の『沖縄ノート』を取り上げ批判しました。今回は、『ヒロシマ・ノート』を取り上げようと思います。
率直に言えば、大江氏の政治評論に接するとまずは理屈抜きに「虫が好かない」という思いが湧いてきます。読み手を自分のフィールドに引き込もうとする氏の手つきに、人間の弱点につけこんで読み手を黙らせようとする不健全なものを感じるからです。その場合の「人間の弱点」とは、痛めつけられた悲惨な弱者の存在を執拗に振りかざして、それに寄り添おうとする、書き手である自分の良心的であるかのような身振りを独特の粘着質の文体で見せつけられ続けると、不愉快ながらもなにやら文句が言いにくくなり陰にこもってしまうという人間の不可避的な心の傾きのことです。大江氏の政治評論は、それにつけ込むことで成り立っているように感じられるのです。だから、読後にとても嫌な気分になります。そこには、ニーチェが鋭く見抜いたような、弱者のルサンチマンが隠し持つ青白い不健全な権力欲が感じられるのです。
彼の『ヒロシマ・ノート』一冊を読み通すのにどれほどの時間を費やしてしまったことでしょうか。なかなか先に進まない読書を自分に強いている間、気持ちが乗らない読書は苦行のようなものである、という感慨が幾度も湧いてきました。本書を放り投げてしまったらどれほどスッキリするか、と思ったのも一度や二度ではありません。
″だったら、読まなきゃいいじゃないか″という声が聴こえてきます。むろん、その通りなのです。が、他方で″自分の目が黒いうちに、大江健三郎的な政治思想はすべて埋葬してしまいたい″という止み難い欲求があることもまた確かなのです(朝日新聞に対しても同じ思いを抱いています)。大江健三郎の政治言説には、戦後思想のダメなものが集約されている、というのが私なりの見立てなのです。悪口を言うには、一応彼が書いたものを読まなければなりませんものね。で、しぶしぶ読み始めてみたら、なかなか先に進まなくて難渋した、というわけなのです。あの独特の、悪文としか言いようのない癖のある文体にも閉口しましたけれど。小説で成功した文体を政治評論や社会評論にそのまま持ち込むことには大きな問題があると私は考えています。それについてもいずれ触れようと思います。
若くてナイーヴで心優しき読み手は、本書が内包する陰湿な猛毒にあてられたならひとたまりもないのではないかと思われます。そうなると、いわれのない罪悪感と過剰な放射能コンプレクスを抱え込まされて、物事をバランスよく考えることができなくなってしまうのですね。それは、実のところ倫理なるものとまったく関係のない、時間を空費し頭が悪くなるだけの馬鹿げた経験にしかなりません。そういう犠牲者をひとりでも少なくすることに、当論考がいささかながらでも貢献できたら、などと柄にもないことも考えております。一応馬齢を重ねていますから、若い人たちのことがそれなりに気にかかるのです。若者たちよ、大江氏がノーベル章を獲ったからって、変に信用しちゃだめですよ、彼は一種のカルトなんですよ。
いささか前置きが長くなったようです。では、始めます。
大江氏の、ルメイへの叙勲に対する憤りは分かるが、その理由づけには賛成できない
不満なところだらけの本書のなかで、一点だけ、素直に首肯できる箇所があります。まずは、それについて触れておきましょう。次が、その箇所です。
東京ではひとつの叙勲が行われていた。勲一等旭日大綬章をうけた米空軍参謀総長カーチス・E・ルメー大将は広島、長崎への原爆投下作戦に、現地で参画した人物である。この叙勲について政府の責任者はこう語ったとつたえられる。《私も空襲で家を焼かれたが、それはもう二〇年も前のこと。戦争中、日本の各都市を爆撃した軍人に、恩讐をこえて勲章を授与したって、大国の国民らしく、おおらかでいいじゃありませんか》
この鈍感さは、すでに道徳的荒廃である。
このように大江氏は、当時の日本政府が、カーチス・ルメイに叙勲したことに強く憤っています。私も大江氏とともに大いに憤りたいと思います。しかし憤る根拠について、私は、大江氏と大きく意見を異にします。大江氏は、いま引いた文章に続けて、次のように言っています。
広島の人間の目でそれを見れば、これはもっとも厚顔無恥な裏切りであろう。
要するに、″ルメイには、広島・長崎に原爆を投下したことに対する当事者責任があるので、叙勲などとんでもない″と大江氏は言っているのです。空爆の司令官だったルメイが、組織上の原爆投下の責任者だったことは確かです。しかし彼は、原爆の投下に一貫して反対の立場だったのです(以下の展開は、日高義樹氏『なぜアメリカは日本に二発の原爆を落としたのか』(PHP文庫)を踏まえたうえでのものです)。DVDにもなっている、NHKの『東京大空襲』という番組のために日高氏が彼にインタヴューしたとき、ルメイははっきりと次のように述べています。すなわち、「原爆を使わなくても、我々が日本に圧力を加えつづけていたので、無条件降伏させられることは確実だった。日本本土への上陸作戦も必要ではないと思っていた」と。ルメイは、事あるごとにそういう発言をしています。ちなみに、アイゼンハワーやマッカーサーやニミッツなどの軍の首脳も、原爆投下には反対していました。一般市民の瞬時の大量殺戮を惹起するような原爆投下を敢行しなくても、戦争は事実上ほぼ終わっていたし、日本を降伏させるのは時間の問題だと判断していたからです。戦争の現場を知る者のまっとうな認識が感じられますね。その意味で、彼らはクレイジーではなかったようです。
″だからルメイには、原爆投下の責任などまったくない″と言いたいわけではありませんよ。組織上の立場からすれば、当然ある、とすべきでしょう。しかし、それを根拠に叙勲をとんでもないこととするのはちょっと無理があると言いたいのです。当時のトルーマン大統領が、自分の権限において、自分の政治的な立場を強化するためにだけ、身を乗り出して小躍りしながら原爆投下の意思決定をしたことと比べると、ルメイの責任など消し飛んでしまうほどなのです(その詳細については、いずれ触れます)。もしも当時の日本政府が、トルーマン元大統領への叙勲をしようとしたならば、原爆の投下責任を根拠に憤るのはまったくもって正しいとしか言いようがありません(想像するだけで気分が悪くなってきますが)。
ルメイへの叙勲がとんでもないことである理由は、別にあるのです。
それをはっきりさせるために、ルメイの前任者であったヘイワード・ハンセル司令官に触れておきましょう。ハンセルは、ルメイが超低空から東京全体を焼き尽くし、数十万の市民を殺戮するという非情な爆撃を指揮したのとは対照的な指揮ぶりでした。彼は、B29で超高空から爆撃するとき、雲がかかっている場合は、市民への爆撃を避けるために、爆弾を落とさないまま爆撃機をグアム島に戻しました。爆撃部隊の首脳は爆撃の効果が上がらないことに業を煮やしてハンセルをファイヤーし、ルメイを東京爆撃の責任者にしたのです。
日本の諸都市への、ルメイの爆撃は徹底していました。原爆投下までに、日本の人口五万以上の二六都市がすべて爆撃され、一〇万トン近い爆弾や焼夷弾が落とされ、五〇万人の市民が命を落としていました。それは、広島・長崎の犠牲者の約五倍に当たります。そのなかでも特筆すべきは、一九四五年三月一〇日の東京大空襲です。同空襲において、焼夷弾をごく短い間隔で投下し、その上からガソリンを撒くという殺戮のための爆撃が敢行されました。このとき、三三四機のB29がナパーム弾を七〇〇メートルという低空から投下しました。爆撃は夜の一〇時から午前五時まで続き、東京の東半分の四一平方キロが焼け野原となり一夜で約十万人が死にました。これは、どう言い逃れをしようとも、無差別爆撃であることは間違いありませんし、正真正銘のホロコーストであるというよりほかはありません。ルメイは、この大爆撃を揺るぎない確信をもって敢行したのです。ルメイへの叙勲がとんでもないのは、不本意な原爆投下をしたからというよりも、軍事的に正当な行為であるという確信をもって東京大空襲という大量無差別殺戮を敢行したからなのです。
大江氏は、どうしてそのことが視野に入らなかったのでしょうか。同書を刊行した一九六五年当時には、そういう情報が不足していたのでしょうか。ならば、その後そういうふうに訂正すればいいいだけのことですが、そういうことをしている事実は、寡聞にして知りません。
『沖縄ノート』で沖縄県民をそうしたように、同書で、原爆の悲劇的な犠牲者を祭り上げ聖別しようとする大江氏の志向性やモチベーションがあまりにも強すぎて、東京大空襲という惨事がその視野に明瞭には入らなかったのではないかと、私は考えます。
では、なぜ大江氏は、原爆の被害者を特別視し聖別し祭り上げようとするのでしょうか。それは、そうすることで、読み手を黙らせて異議申し立てを封じ込み、自己卑下教という幻想共同体への強制参入を図り、自分はその陰の司祭に成り上がろうとしているように私には感じられます。氏の、晦渋な、もって回ったような奇妙な言い回しの行間から、そういう腐臭がしてくるのです。それは、半分以上、潜在意識のなせる業ではないかとも思われます。氏の体質それ自体に、そういうひねこびた陰湿な権力志向がこびりついているということであります。
それにしても、ルメイに勲章をくれてやろうとする神経はまともではありませんね。精神病理的なものをすら感じます。つまり、こうです。耐えがたいほどの屈辱を受けた者は、屈辱を与えた当の相手に対して大げさな許しのポーズを示すことで、相手に対して精神的に優位に立ったと思いたがりますが、実は、その行為全体で、屈辱を与えた相手にその後もなお精神的に屈服していることを示しています。なぜなら、彼はほかのあらゆる振る舞いはしますが、相手に歯向かうという振る舞いだけは決してしようとしないからです。むろん、日本国民に対して確信を持って無差別大量殺戮を敢行したルメイに勲章を授けようとする日本政府の振る舞いが、「大げさな許しのポーズ」に当たります。そういう汚辱に満ちた倒錯を、日本政府はいつまで続けるつもりなのでしょうか。この倒錯心理と、大江氏の原爆観とは、実は無縁ではありません。 (つづく)