
近代とは何か。この大きすぎる問いは、日本の場合にはまた一段と深い陰影を帯びている。
アジアの東端(ヨーロッパで世界地図を見たとき、日本は一番右に描かれていて、なるほどfar eastだな、と納得したものだ)にある小さな島国が、およそ他に例を見ない急速な近代化を成し遂げた。文明の表層を見れば、確かにそう言える。嘉永二(一八五三)年、ペリーが来航するまでは、国民の大多数が鉄製の船など見たこともなかった(それ以前に、「国民」という概念そのものが一般にはなかった)のが、半世紀経って、世界最強と噂されたロシアの艦隊を撃滅するほどの造船及び軍事の技術を身に付けたのだから、凄いとしか言いようがない。
この巨大な成功はまた、それ以前にも以後にも、日本に身に過ぎた背伸びを強い、ついに大東亜戦争(本書の著者はこの呼称を使っていない)の悲劇を招いた。そのために、そこまでの日本の歩みを全否定するかのような言論(いわゆる「自虐史観」)が一時は支配的だったし、現在の我々もその呪縛から自由になったとは言えない。とりあえず、不健康な状況ではある。処方箋はいくつか考えられるのだが、本書の著者は、この時代の思想的な営みのうち、最良と考えられるものを提出してそれに充てようとする。
「(前略)後から西洋の模倣に明け暮れるのでもなく、負け惜しみ的に日本の特殊性を美質として強調するのでもなく、むしろ彼我の文化的違いをよく見極めて、その違いの自覚を通して西洋近代の思考そのものを相対化しようとした思想家、あるいは逆に、西洋の合理主義的思考を自家薬籠中のものとしながら、日本が克服すべき問題点を巧みにて剔抉(てつけつ)してみせた思想家は、戦前にも戦後にも、確実にいた」(P..15)のだから、彼らが成し遂げたことの評価を通じて、「文明開化」以後のこの国の現実、及び顕在化はせずとも底流を流れていたもの、さらには可能性としてはあったもの、まで描き出すことができるのではないか。
私には、この試みの成否を云々するにしては、教養も能力も欠けていることは告白しなければならない。つまり、この本をちゃんと評価できるだけの力量はない。ただ、本書を通読して時々引っかかった印象を手がかりにして、「日本の近代」に関する自分なりの考えを述べたいという欲求に駆られている。「批評というものは、どんな体裁をとろうが、じつは他人の作品をダシにして自分の自意識を表出する行為に他ならない」P.288)なら、こういうのもアリではないかと思うので。それにしても、著者や、本書ともっと本質的なところで向き合える頭脳に恵まれた読者にはただ迷惑なだけかも知れないが、世の中にはこういう読者もいます、ということは知っておいても、そんなに悪くないんじゃないかな、とだけ期待している。
本書に選ばれた七人の思想家は、著者の問題意識に従って配列されているのだが、ここでは敢えて、一人の例外を除いて、時代順に見ていきたい。
福澤諭吉(1835~1901)は、最も偉大な啓蒙家だった。日本近代の黎明期に生きて、拝外主義にも排外主義にも陥らず、新生日本の進むべき道を現実的に示し得たからである。西洋化とは痲疹のようなものであって、それ自体は好ましいものではないが、一度はこれに罹って抵抗力を身に付けなければ、今後の国際社会では生きていけないのだ、と言う。こういう冷静さは確かに好ましい。
ところで、これに関連して、著者は私の目からは少々奇妙に思えることを言っている(P.419~421)。「私たちは、この『近代』なるものが政治的にも文化的にも西洋から襲ってきたという感覚からなかなか自由になれないために、ともすれば『近代』概念と『西洋』概念とを同一視がちである。しかし、そういう考え方はもう古いと思う」。はて、世界のどこでも、「近代化」するとは幾分か「西洋化」することであって、それ以外に道はなかったのではないかと思うが? この点ではすぐ先を読めば著者の真意は明らかになる。「西洋においてたまたま…いち早く訪れた」近代には普遍性があり、「いずれどの国をも席捲すべき性格のもの」であることは認めつつ、現実の西洋をモデルとして近代化をよりすすめようなどというのはもう古い、と言うのだ。
「(前略)現在の日本はすでに完全に『近代化』を遂げており、戦後しばらくの間、日本の国民的課題と考えられていた『古い封建的遺制から脱して、西洋近代に追いつくこと(たとえば個人主義的自我の確立)』イコール『近代化』であるという理解は、もはや通用しない」
私のこだわりは結局、「たとえば」の、「個人主義的自我」の領域にある。ここでは、我々は「完全に近代化を遂げた」とは言い難いような気がするので。それがすばらしいから一刻も早く身に付けよ、と言うのではない。どちらかと言えば、それこそ疾病であり、無縁でいたほうが幸せなのかも。しかし、近代化が必然であるなら、どうしても避けて通ることはできない基本概念であることはまちがいない。とすれば、その本当の恐さも知らず、言葉だけがなんとなく流通しているような状況が、一番恐いように思える。
とりあえず、「ポストだもん」とかなんとかいうのが流行ったとき、「近代的自我とか主体なんてもう古い」などと言われたのは、軽薄でしかなかったと思う。本書の著者にしろ、挙げられている七人の思想家にしろ、そういう軽薄な輩だというわけではもちろんないけれど。
さてしかし、「確立した個人」は現にあるものだとして、それに基づいて倫理(人間はいかに生きるのが正しいか)を考えれば、必ず壁にぶつかってしまう。和辻哲郎(1889~1960)の業績がそのことを明らかにした。彼は、人間の本質とは人と人との間の「実践的行為的連関」にあるとした。支那語の「人間(じんかん)」は、人と人との間=世間という意味なのに、日本では人そのものを示す意味になったのはたいへん示唆的である。ごく常識的に考えても、他人がいなかったら、倫理なんて、どんな意味にもせよ、生じるはずはない。それ以前に、人と人とが関わり合って生きる、小は家族から大は国家にまで至る共同体こそ、人が現実にも理念的にも生きる場であって、「個人の本源」でもある。
さればとて和辻は、個人は必ず一定の共同態(和辻独特の用語で、「共同性」と考えて大過ない)に埋もれて生きろと要請したわけではない。それでは全体主義になってしまう。個人も社会も絶えず流動する。人間が必ず個人意識を持つ以上、必ず共同態からそれていく。それは人間の本源からそれることでもあるから、通常「悪」と呼ばれる。反面、一度それた個人が共同態へと復帰することは「善」と呼ばれる。「人生の真相」は、この往還以外のところにはない。してみると、前述の「悪」こそ「善」が生じるための前提だと言える。だからそれは、「そう見える」というだけで、本当の悪ではない。往還の道が停滞し、個人と共同態が離間したまま固定するような事態こそ、真の悪である、と。
以上は和辻倫理学の根本を著者が要約しているところを私がさらに祖述したものだが、人間を固定した視点から捉えず、往還の、運動の相の下に見ることから来るダイナミズムには、確かに魅力がある。しかし反面、共同態の予定調和が当然あるもののように言われるのはどうか、と思う。その紐帯を作るのは「信頼」だとされる。それだけで共同態が保たれる、などということがあるのだろうか。この点では筆者も、和辻は人間の暗黒面に目を塞いでいる、とちゃんと批判している。
共同体ならば必ず、信頼を裏切ったとされる者、つまり普通「悪」と呼ばれることをなした者には大小の罰が与えられる。信頼関係からの/への、往還が必然だというなら、どうして罰などの必要があるのか? そして、罰は常に正当だと言えるのか? 大小の共同体それぞれから要請されるものが矛盾する場合だってあるのだ。国家を守るために戦地で、敵と戦わねばならぬが、そのためには年老いたおっかさんを見捨てて行かねばならぬ、というような場合が。おっかさんの面倒を見るために国の命令に背いた者が罰を受けたとして、必ずまた国の、信頼関係の中に回帰するなどと期待できるだろうか? そうだとすると、家族中の信頼関係のほうはどうなってしまうのか?
つまり、人間は完全ではないのだから、その人間たちが形成する共同体も完全であるはずはない。だから、罪と罰の対応が常にうまくいくわけはない。個人の側から見たら、不当でしかない罰も必ずある。そうなれば、もう信頼関係を信頼することはできない。そのものが個人を圧迫する軛としか見えないであろう。
西洋世界が倫理の根源に唯一絶対神(元はユダヤ民族が発明したもの)を置くのは、「本来『ヨコ』であったものを『タテ』に」(P.401)したようなものだ、と著者は言う。その面もあるには違いないが、人間の世界を飛び越えた別次元に究極の価値あり、としたことの意義は、もっと別にあると私は思う。
絶対の存在=神の前では、個人はもとより相対的なものでしかない。とは言え、共同体もまた、国家といえども、やっぱり相対的である。多少とも神の「正義」を知ることができるなら、人間は、理念的には、たった一人で国家とも対峙できるのである。そういうのは迷妄と呼ばれたほうがいいかも知れないが、それなら共同体もまた「共同幻想」によって支えられるしかないのだから、その点でも遜色はない。
かくして、個人的自我が立つ。少なくともその可能性は見出される。人間を一番根底から規定し束縛するはずのものが、また最もラディカルな解放の原理ともなるのである。いかにも、日本人には馴染みづらい思考のようだ。しかしもちろん、結論めいたものを言うのはまだ早すぎる。
時枝誠記(1900~1967)の言語本質論には、和辻倫理学に共通するダイナミックな魅力がある。「言語過程説」として知られるそれは、言語を一定の社会的実体とみなさず、話し手の表現行為が聞き手によって受け取られる、その全過程を「言語」とする。
ここで少し私見を差し挟ませてもらうと、この説の真価は、「聞き手」を発見したところにあると思う。言表行為(言葉を発すること)が話し手の主体的な行為であることはごく普通に納得されるところだが、それだけで完結するはずはなく、発せられた言葉が他者に受け取られることではじめて「言語」は成立する。つまり、話す側と聞く側双方の主体の相互作用こそが重要であって、それを欠いた言語なるものは本来存在し得ないのである(独語とは、自分の中の他者へと向けられた言葉である、とこれは著者によって言われている)。
時枝言語学の批判的な検討は、本書の白眉と言えるほどに優れていると思う、とだけ言って、また自分勝手なことを述べる。
「述語格」論というものが好意的に紹介されている。文構造の本質は主語―述語の対応関係にあるのではなく、「文の基本はまず述語にあり、主語、客語、補語などは、述語の中に潜在していたものが必要に応じて後から表出されてきたものであるという説」(P.195)。それはそうだな、と思う。
述語になる代表的なものは形容詞及び形容詞的なものである。それが結局「一番言いたいこと」になる。他の要素は、例えば以下のような「必要」から「表出」される。
A:きれいだな。(述語のみ)
B:何が?
A:あの花が。(主語の登場)
B;あんなのちっともきれいじゃねえよ。
A:そうか? 俺にはきれいに見えるぜ。
最後の文を省略なしで書くと「私にはあの花がきれいに見える」、英語だとさしずめIt seems to me that the flower is beautiful./I find the flower beautiful.で、おそらく、日本語でも英語でも、その他何語でも、わざわざこんなふうに(ちゃんと?)言われる場合のほうが例外だろう。すると、「私」が登場するのはかなり後のほうであることがわかる。「花が・きれいだ」The flower ( is ) beautiful.という主語と述語のある文を外側から風呂敷で包むように、あるいは、この文全体を述語のようにして、「私には見える」という文が加わるのである。最初の「きれいだ」という形容動詞(橋本文法の用語で、時枝はこれを認めていない)は、花の叙述なのか、そう感じる「私」の情緒を現したものか、どちらとも決め難いし、日常生活の場面の多くで、人はそんなことを考えもしない。著者は、それこそが人間のプリミティブな世界把握の姿だ、と言っている。
「(前略)形容詞という品詞または形容詞的な表現は、もともとどちらかに分類可能なものではなく、『客体』とその知覚に不可分につきまとう『主体の情』とを二つながらに表現するに適した言い回しなのであって、そこにまさに『物心一如』の世界が出現していることを語ろうとした言葉(群)なのだということである」(P.199)
言わんとするところはわかるが、「物心一如」は少し大げさではなかろうか。上の例の最初の「きれいだ」では、「私にはそう見える/私はそう思う」はあまりにも当然の前提であって、わざわざ言う必要がないから言われないのだ、という理解もある。というか、(西洋化された見方では?)そちらのほうが普通ではないだろうか。動物にも「意識」があるのかどうか、詳しく知らないけれど、人間ほどには「こころ」を問題にすることはないという意味で「物心一如」に近い者たちは、そもそも「きれいだ」とも言わない。
つまり、「意味」のある言葉がある以上、それが伝達されるべき他者は、「自分の中の他者」も含めれば、必ずある。他者があるなら、後づけではあっても、自分もある。この事実こそ、言語過程説が定立したものだったのである。
時枝も、著者も、それを認めないわけではない。ただ、「自己=主観」も「他者・他物=客観」も、言語以前から実体としてあるもののように考える世界観に、危うさを感じているのである。
大森荘蔵(1921~1983)は戦後に、物心二元論、あるいは主客二元論を超克しようとする意欲を示した哲学者である。
二元論を定型化したとされるデカルトが言っていることを、できるだけ単純に言うとたぶんこうなる。「私」はよく間違える。しかしその時でも、間違える「私」はおり、一方には「間違いではない、正しいこと」もある。そうであれば、「私」は正しい方法を用いて「正しいこと」を知ることはできる。ここでもう既に「正しいこと(客観)」とそれを知ろうとする「私(主観)」が分離されていることがわかる。
それは常識的なことではないか、とも思えるだろう。日本でも、主観的・客観的という言葉は、日常語と言っていいくらいにありふれているし。すごいのは、デカルトの立場を受け継いだ人々が、こう分けたその上で、「正しいこと」とは何か、それを「知る」とはどういうことか、とどこまでも考えを推し進めて、「人間には結局絶対に『正しいこと』はわからない」までいってしまったところだ。西洋だって、日本と同じように、そこまで考える人はごく稀だろう。ただ、日本よりは多いらしく、「考えたってむだだと思えるところまで考える」土壌はあるように見える。
ひるがえって、このような二分法そのものがまちがっているか、あるいは不要なのではないか、と考える人は西洋にもいた。しかし、大森ほどの徹底ぶりを示した例はたぶんそんなにはいない。
「立ち現れ一元論」と呼ばれる彼のアイディアはおおよそこんなものであるらしい。風景があり、その一部として「私」がある。それがすべてであって、その背後または別次元に「正しいこと/本当のこと」などない。ある花がある人にはきれいに見え、他の人にはそう見えないというようなことがあるにしても、一方にある一定のもの(客観)があって、他方にそれを眺める「私」(主観)がある、などと考えるには及ばない。そのもの(この例の場合は花)はもともといろいろな感慨をもたらすようなものとしてそこにある、と考えればすむことだ。
これによって大森が成し遂げたことの一つは、外界・広い意味での自然を、生き生きとした活物として捉える視点を提出したことにある。西洋において、「正しいこと」を知ろうとする意欲には、自然を一定不変のものとして見ようとする指向がもともと備わっている。すべては生々流転することは事実だとしても、その生々流転には「一定の」法則あるいは構造があり、それをつきとめて記述する(言葉や数式などの記号を使って「書き留める」)ことが、ものを「正しく知る」ことだ、ということは、当然の前提になっているのである。これは結局、自分の身体までを含めた自然を、「死物」として扱うことに他ならない。それは倫理的に「良くない」ではなく、世界認識の方法として根本的に「正しくない」と大森はしたのだった。
と、言うわけで、大森哲学においても、「正しく知ること」への情熱が失われているわけではない。そしてそれはほとんど必然的に独我論的な論理(本当に存在するのは自分だけ)に結びつく。著者はそこを最も強く批判する。大森も、デカルトも、そう言っているわけではない(だいたい、本当にそう思っている人がわざわざ「言う」なんておかしい。上で見たように、「言う」とは必ず、「誰か(他者)」に向かって言うことなのだから)。ただ、普遍妥当な「正しいこと」は、主観、という名の人々の思いとは別にある、つまり、誰がどう思おうとも、知らなくても、やっぱり正しいと考えられる。ならば、それを「自分」が知ることは「自分」にとって重大だとしても、他人がどうかは結局問題ではなくなる。
この事情は、デカルトでも、彼のものの見方を批判した大森でも、同じことである。上の立場を推し進めた場合、自分と同じように他人もまた何かを感じて、考えて、生きているだということ、つまり他人にも主観=内面はあるのだということは、どうやって「客観的に」証明されるのか、という「他我問題」が起きてくる。が、そもそも内面なんてないんだ、とする大森哲学では、それ自体も大した問題になりようがない、という違いはあるにしても。
人間の共同性と、それがもたらす「内面」を重視する著者には、これはとうてい容認し難いことだ。「大森のように(もちろんデカルトのように)『心』という言葉を『物』との関係においてしか使用しないと、いくら『自然そのものが有情であり、心的なのである』として狭く押し込められた『心』を解放した気になったとしても、『普通人』は必ずその論理的枠組みそのものの自閉性、偏頗性を見破るであろう」(P.277~278、下線部は原文では傍点)と。これを踏まえて、「人と人との間」に人間の根源を見た和辻倫理学が称揚される(本書の配列順では、和辻は大森の次の次に取り挙げられている)。私はその論の正当性は認めつつ、その共同性から浮かび上がってくる「個人」について、著者よりもう少しこだわりたいと思っている者だ。
小林秀雄(1902~1983)に、「すでにこの時代(引用者註、昭和7年)の日本においてラディカルな『実存思想』の誕生」(P.297)を見る、と著者は言う。「歴史や社会を客観的な構造として把握する見方、人間をそのようなものによって規定されていると見る見方を根底から退けなければ、その日その日を取り返しがつかずに生きている実存者の内的感覚をけっして保存できないという確信を貫いた」(P.345)からである。
小林の批評の方法は、例えば「モオツアルトの悲しみは疾走する」という評言に端的に現れている。この言葉自体が詩であって、モーツアルトの音楽に触れて感動した心の文学的な表現である。論理はないので、反論できない。「モーツァルトは好きだけど、いくら聞いても『悲しみが疾走している』感じなんてしないよ」という人は、だから俺は小林より鑑賞力が劣っているんだ、などと思う必要はないが、小林との議論は成り立たたず、彼とは無縁でいるしかない。
つまり、ここでは論理的な、客観的な正しさは問題とはされない。それでもものが言えるのは、次のような事情からだ。人間は「正しさ」を全く気にかけないで生きることはできないが、それは結局人生の一部でしかない。我々は「正しい」から、飯を食ったり、恋愛をしたり、芸術に触れて感動したりするわけではないだろう。だがどうやってそこのところを把握して、紙の上に文字で書き記すことができるのか。共感によって。それで全部、でよいのだが、あんまり簡単にすませるのもなんなので、もう少し言ってみよう。
「解釈を拒絶して動かないものだけが美しい」(「無常といふこと」)と言われる場合の「動かないもの」とは、前述した不動の客観物ということとはもちろんまるで違う。ある人があるときに、こうであった、その他ではあり得なかった、そのぎりぎりの核のようなもので、しばしば「宿命」などとも言われる。モーツアルトが天才なのは、音楽についてあれこれ学んだ結果などではなく、ああいうふうに生きてああいうふうに表現せざるを得ない必然性を彼が持っていたからだ。その事実を、できるだけ深く感じ取ること。
では、相手になるのは天才だけなのか、と言うと、そうでもない。著者はその例として、小林の晩年に書かれた短いエッセイ「人形」の全文を挙げている。六十ほどの老夫婦が、大きな人形といっしょに食事のテーブルにつき、まるでそれが生きた子どもであるように扱う。この人形はその夫婦の、死んだ息子の代用なのかも知れない、とまでは見当がつくが、ここで何が行われているのか、その本当の内実は当事者にしかわからない。これを目撃した者は、人間にとってかけがえのない何かがここにあることを諒解し、無用な好奇心でそれを毀さないように配慮するしかない。とはいえそのような配慮は、この老夫婦の現状や彼らにかつて起こったことを「知る」・「理解する」ことより大切なのである。
小林秀雄を評価するか、無価値とみなすかは一にかかってこの点に、それこそ共感できるか否かにかかっている。「国民は黙つて事変(引用者註、大東亜戦争のこと)に処した」(「疑惑Ⅱ」)というような言葉から、彼はまるで戦争という人事をも自然災害のようにみなし、ためにこれを批判することを忘れさせ、結果として戦争を肯定してしまっている、とか、黙って処した人以外にも、この戦争の不条理さに怒りを覚えながら、その正当な怒りを圧殺された人もいるのに、それを無視している、とかいうような批判はよくあるが、そういうのは無効なのである。
なるほど、この戦争の無謀さを見抜いた人も、それに怒りを感じた人もいたろう。後述するように、それが無意味だとは決して言わない。だが大多数の国民にとって、戦争はあまりに大きすぎて、なぜそれが起きたか、などと問ういとまもなく、耐えて、要請される目前のこと(召集されて戦地へ行く、避難訓練を行う、など)に対処するしかないものである。そういうふうに生きたことを、事後に批判したところで、仮に本当に今後無謀な戦争が起こらなくするための役には立つとしても、当事者たちになんの意味があるだろう。そう生きた時間は、もはや取り返しがつかないのに。
さてしかし、特に戦後、このような立場から批評活動を展開した小林には、その限界を指摘できるのではないかとも思う。著者は他の六人に比べても小林にはたいへん好意的だし、私のような凡庸な文学青年だった者が小林秀雄にイカれたポイントはほぼ完全に言い尽くされており、そういう意味で懐かしささえ感じた。ほとんど唯一の批判が、「私の疑いは、小林の日本近代批判の道具が、意外とスノビッシュでステレオタイプな『昔日を惜しむ』心のパターンによって取り揃えられたものではないか、という点にある」(P.336)云々の部分のみである。
それは直接には、小林による西行評で、「歌の世界に、人間孤独の観念を、新たに導き入れ」た、などとしているところについて言われている。「孤独の観念」なんぞと言えば、日本の近代文学者がさんざん唱えたお題目であり、若き日の小林自身もそれとは無縁ではなかった。しかし彼は、「私小説論」(昭和十年)の段階では、その輸入元であった西洋の文芸事情からしたら、「孤独」という漢語が気楽に使えるようになってから以後の日本で(西行はもちろんこんな言葉は使っていない。「ひとり」と言ったのだ)、それが乙女チックなセンチメンタリズム以上のものになることはめったにないと、弁えていたはずなのである。
以下は勝手なこと、というより完全に「文責は由紀」になり、小林や著者が述べているところをひどく誤解している可能性もあることはお断りしたうえで、できるだけ手短に述べる。
西洋文芸上の「私」とは、絶対者(神)の前で「私とは何か」と執拗に問いかけるルソー「告白」(「私小説論」では「懺悔録」)の「気違ひ染みた言葉」から始まる。やがてルソーもその始祖の一人とする革命思想と、客観的な正しさを専一に追求する科学的合理主義が、宗教的厳格や身分制の桎梏からかなりの程度個人を自由にした社会を実現する。が、そこでも「気違ひじみた私」は、合理的なものとは言えないから、生きる場所を見つけるのは難しい。これを痛感したフロベールらが、問いを「では社会とは何か」という形に変換して、リアリズム文学の中に、かろうじて「私」の生き延びる場所を見出した。
日本にはこのような、切迫した「私」へのこだわりはもともとなかった。輸入された西洋文芸は「個我の解放」を教え、青年(戦前で大学教育まで受けられる、かなり裕福な家の青年たちだが)に自意識は与えたが、そんなのは一般社会では相手にされないことはいずこも同じ。しかし彼ら自身にとってそれはどこまで深刻な問題だったのか? 自意識なんて、青年期を過ぎれば自然に消えるそれこそ麻疹のようなものだった場合が大部分ではなかったか。
そういう意地悪な目で小林の業績を振り返ると、彼が主に取り上げたランボー、モーツァルト、ドストエフスキー、ゴッホらは、詩・クラシック音楽・小説・絵画の分野で、日本で最も人気のある西洋人だということに改めて気付かされる。スノビズム(高尚ぶりたい趣味)の種にされることも多く、そのために小林の批評文が役立ったところも小さくはなかったろう。それは別にかまわないとしても、彼らの実存の核として小林が取り出してみせたものには、社会や他者との葛藤にかかわる部分はかなり脱色されていることは否めない。
そういうわけで、「社会化された私(=日本では「私」はなぜ社会化されないか)」についても、指摘しただけで、自らのテーマにすることはなかった。日本で成熟しようとすれば、そうあらねばならないのかも知れない。
丸山眞男(1914~1996)は、近代以前の日本思想について、綿密で独創的な研究を成し遂げながら、小林秀雄のような方向で成熟しようとはしなかった。大東亜戦争について、彼は諦めと悲しさより、怒りを抱き、またその怒りは正当であって、今後の日本にとって必要なものだとさえ信じていた。
戦争を起こした日本人が邪悪だったと言うのではない。むしろ、「邪悪ですらなかった」ことが一番の問題とされる。即ち、大東亜戦争は、誰かが、「よし、やろう」と決断して始まったのではなかった。昭和天皇も、東條英樹も、みんなどちらかと言うといやだったのに、情勢が勝手にそちらへ動いていって、誰にもどうすることもできず、やらざるを得なくなってしまったのだ。その下には、「戦争中はただ命令に従っただけ」の政府や軍部の中間層がおり、さらに最下層には、「黙って事変に処した」一般国民がいる。自らの判断で事を行い、事後には責任を取る「自由で主体的な個人」はどこにもいない。丸山はそのことに心から苛立っている。
この見方に対する批判は既に様々に出ており、著者はそれをまとめている。今上に略述した部分に関することだけ挙げると、第一に、丸山はだらしなく矮小な日本の指導者たちに比べて、ナチスの高官たちは確信犯であり、悪の魅力を備えている、と言いたげである。しかし仔細に見れば、ドイツの戦犯たちも、嘘や言い逃れを使って、できるだけ罪を免れようとする者のほうが多かった。「潔く責任を取った」と言えるのは、日本と同様、ドイツでも少数だったのである。第二に、これも日本にもドイツにもあった(あるに決まっている)「命令に従っただけ」が事実である場合、それを道徳的に咎められるだろうか? 不当な命令なら断固拒絶する「強い個人」を、いつでもどこでも求めるのは、非現実的であり、それ自体が人間性を無視していると言えるのではないか。
そして第三に、自分の意思と決断でのみ行動する「強い個人」は、必ず好ましいと言えるのか。ヒトラーによるユダヤ人粛清は、誰かに強制されたわけでも情勢の然らしめたところでもない、完全に彼一個の「主体」による行為(もっとも、ヒトラーによるこれに関する命令書の類は見つかっておらず、「最終責任」はどこにあったか、ドイツでも必ずしも明らかではないようだ)である。だからすばらしいとは、まさか丸山先生も言わないだろう。
これらの批判はすべて正しい。第一と第二をまとめると、「自立した個人」は、西洋においても理念としてあると考えたほうがよく、その理念で現実を裁断するのは、知識人のお家芸とされてきたものではあるが、アンフェアとすべきだろう。ここから天皇制国家の「無責任構造」をいくら論じても、分析そのものはどれほど精緻であろうと、現実を動かす力にはなり得ないし、現になっていない。
それでも私は、『現代政治の思想と行動』所収のいくつかの論文を読んだときの衝撃を忘れることはできない。大東亜戦争の敗北に至る日本近代の歩みは、巨大な悲劇である、とは最初に書いた。しかしこの悲劇にはヒーローが、「人間の顔」が欠けている。邪悪であれ思い違いであれ、この戦いに意味を見出そうとする意欲が、ほとんど見当たらない。「大東亜共栄圏構想」や「アジアの解放」の理念は、後付けであったことはいいとしても(どこの国でもたいていはそんなものだろう)、何人がこれを本気で信じようとしたのか。
いくら巨大でも、戦争とは人事であり、この世に意味を作り出すのは人間である。日本人に一番欠けている感覚はこれだと思う。それでも、我々はぎりぎりのところで、自分たちの生死には意味があると思いたがっているのではないか。ならば、日本だけで二百万人にものぼる大東亜戦争の戦死者は、なんのために戦い、なんのために死んだのか。答えなんかない、という「真実」ほど、恐ろしいものはないのではないか。それは直ちに、人間が生きていることに意味などない、という真黒なニヒリズムを招来しそうだから。
丸山の苛立ちの根底はここにあり、だからこそ、上に述べたようないくつもの弱点はありながら、彼の一連の文章にはまだ人を惹きつける力があるのだと私は思う。「日本ファシズム」の図式的な批判が、「当時のインテリの倫理感覚をうまく刺激した」(P.27)ようなところにのみ、丸山の力を認めるべきではないだろう。また後年の「歴史意識の『古層』」などの論文で、日本人の変わり身の早さ(つまり、無原則、ということだ)を、「つぎつぎになりゆくいきほひ」という言葉で肯定的に描いたことは、いわば上の図式を裏返したようなもので、「まあ、そうも言えるな」以上の感慨を私にはもたらさない。彼が大東亜戦争中の日本人に感じた苛立ちには、民族に関するこのような図式を超えるものがあると信ずる。
吉本隆明(1924~2012)の戦争責任論にも、私は丸山と同種の怒りと苛立ちを感じる。大東亜戦争をまたいで活躍した多くの文化人が、戦前の左翼的・自由主義的な傾向から、戦中の軍国主義追従に移り、戦後はまた口を拭って民主主義を謳歌する。その変わり身の早さ、こだわりのなさは何事であろうか。
「注意しなくてはならないのは、吉本は転向それ自体を倫理的に非難しているのではないということである。ただそのような変節を重ねながらそのことに無自覚で、『自分は内心では終始、この戦争には反対だった』といったように自己欺瞞的な免罪符を得ようとする知識人の態度に、同胞たちの死に一番近い場所から憤怒を投げつけているのである」(P.92)
いやむしろ、自己欺瞞さえも特に必要としないかのような言葉の軽さこそ問題ではないだろうか。自由主義も軍国主義も民主主義も、時々の風潮によって現れては消えるだけ。ファッションの流行以上の意味はない。一般民衆にとっては、特に「~主義」と呼ばれるような事々しい言葉は、そんなものだろう。
しかし、広い意味での言葉の専門家であるはずの知識人までそうだとすると、もう言葉とそこに表象されているはずの人間の智慧によって世界を動かすなんて、一片の妄想に過ぎないことになる。またもちろん、知識人が依って立つ基盤も雲散霧消し、彼らは芸のない芸人のような惨めな者になるしかない。よくそれで平気でいられるな!
というところからだろうと思うが、吉本は言説者となった最初から、二つの原則を自らに課していた。一つは、戦争中は軍国少年だったことを恥じる思いから、誤ったイデオロギーに再び騙されることがないように、「客観的で正しい」世界認識の方法を身につけること。ただしそれは、ただ知ればいいという以上の、実践的な課題にまでならねばならない。そのためにも二つ目に、一般民衆から遊離した認識は無意味で、有害でさえあるので、「大衆の原像」は絶えず認識に繰り入れるようにすること。
前者の原則から、独力で言語や国家の本質論を打ち立てようとした試みは、その志は壮とすべきだが、著者によるとあまりうまくはいっていない。後者は、普通に生活している人の意識を忘れまいとする姿勢は、著者から高く評価されているが、どうも内容が無限定で、吉本の時々の都合によって勝手に使いまわされている感じは否めない。そのためもあって、晩年になってからの彼は、麻原彰晃を「世界有数の宗教家」と持ち上げたり、親鸞を全く誤読するなどの、迷走ぶりを示した。
私は、吉本から積極的に何かを学ぼうと思ったことはない。ただ彼が、「自分なんてないし、あっても意味はない。だいたい、そんなものはないほうが生きやすいんだし」が一般のように思えるこの日本の中で、絶えず「何者か」であろうとした歩みには、ある感銘を覚えずにはいられない。彼の人気の秘密はそこらにあるのではないかと思う。ただ、全共闘世代を中心に教祖様のように持ち上げられたのは、かえって不幸だったのではないかと思うが。
さて、いくらなんでも、もう長広舌をひっこめるべき時だろうと私の中でも声がしているが、小林秀雄を経由して最後のところまで来たおかげで、もう一つ弁解じみたことを言っておく必要があるようにも感じられる。と、言うのは、自分を意味あらしめようとする意欲は、必然を後から拵えようとすることであって、神を畏れぬ願望かも知れぬ。ならば、日本人がそういうところではあまり熱心ではなかったのは、身の程を弁えた賢明さだと称するも可。ただ、人間は既に、近代国家という、バベルの塔をも凌ぎかねない不遜の装置を作り出し、どうやら日本もまたその一つに数えられているとの由。ならば我らもこのことに頬被りはできまいと愚考して、云爾。










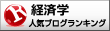

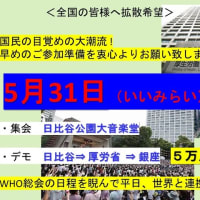















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます