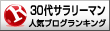※長文であることに気がつきました。
ですが、個人的には結構出来がいいです。
最近忙しいと口で言いますがいい加減飽きてもくるので、結局のところなんなのか、
という話を、今日はしましょう。
今日、空港でちょっとした事件がありました。
"金属探知機まで抜けたその地で、チケットがない。"
一応説明しますと、金属探知機を抜けるためにはチケットが必要なので、
そこから物理的にチケットを無くすってことはありえないわけですね。
でも、それは起こった。何故か?
…何かから急かされていると結構な確率でモノを無くしてしまう僕は、
(大して役にも立たない経験則から)またてんぱって無意識に変なところにチケットを入れたのだろうと思っていましたが、
実際は、間違って他のお客さんが持って行ってしまったということでした。
◆
さて、ここからがポイントです。
そもそもチケットを受け取った記憶がない僕は…
①「いや、俺は確かに取ってないな。多分誰か間違って持って行った、としか思えない。俺が持っていたら、後から謝ることにしよう。」
②「あれ、俺またやらかしたのか?嘘だろ… とりあえず、警備員さんに落ちているチケットがないか訊いてみるか(あわあわ)。」
僕が選んだ選択肢は残念ながら②でした。
(それでも事態が大きくならないうちに警備員さんに訊いただけ、これまでよりはマシなのですが。)
②の最初の一文で精神エネルギー50消費。
その後フライトが近づきます。
やはり、ない。
最初は警備員さんも"ないはずはない、ちゃんと探しましたか"と
さほど取り合ってくれませんでしたが、そのよそでビデオチェックをしてくれていました。
(主な目的はよくわかりませんが、あそこにはカメラがついているんですね。
今日まで知りませんでした。)
で、次に来たお客さんが、僕のチケットが入った箱に(箱の印刷と思ったかもしれません。)
荷物を入れ、一緒に持って行ってしまったという話を聞きました。
なんというか、多くの人を待たせている焦りばかりが募り
それを聞いても特にこれといった感情は湧いてきませんでしたが、
途端に冷静を装ったことだけは確実です。
結局飛行機の中では疲れとは裏腹に体が硬くなっていて、一睡もできませんでした。
眠っているときにCAが置いてくれる、アザラシのような形をした飛行機のシールも貼ってもらえず。
◆
ここでシミュレートしてみる。
①を選んでも、②を選んでも、
僕以外の人の行動ってそんなには変わりません。多分精神状態も。
ビデオチェックを行うまでの時間が早まった可能性はあるので全然変わらないわけでもないですが。
さてここで問題です、①と②の決定的な違いは、なんでしょう?
…僕が、チケットを持っていないことに自信を持っているか、あやふやなのか、そこですね。
その差で、僕の精神エネルギー(気疲れ)にとても大きな差が出てしまいました。
一つあやふやなことがあっただけで、その後のリソースに大きな差が。
でも、そういうことなんですね。
人は常に失敗からのリカバリを考えられるほど、タフではないわけです。
同じ量の仕事をこなしたとして、ポイントを押さえて失敗を防げた人に比べ、
失敗をしてなんとかリカバリを果たした人は、ずーーっと疲れてしまいます。
他の評価を気にしなくとも、勝ち負けがないものであっても、
自分の残リソースから改良を検討する方法ってのが存在するわけですね。
ですから、次以降は失敗をしないように、ということを考えるわけです。
家を出るときに、サイフ、ケータイ、鍵、社員証、とか、
忘れ物をしないためのルーチンを課すのも恐らくその対策の一種。
皆さんもやりませんか?
忘れ物をして痛い目を見たのがいつだったか、憶えているとは限りませんが。
これまでは自分で失敗して痛い思いをしないと人の説く話に共感できませんでしたが、
これからは少しは他人の振り見て我が振りを直せないかな?
◆
そこから教訓が生まれます。
"貴重品の管理はしっかりしろ"と。
今まで何度言われた台詞かよくわかりませんね。
その割には、"二度と言われないようにしよう"という闘志が湧きにくい言葉でもあります。
あるいは、そこから教訓も生まれます。
"物事をあやふやにしておくと、いつか痛い目を見る"。
この教訓もイメージとしてあやふやな感は否めませんが、
今日の内容を見れば出所がわかるのでそれもアリでしょう。
あるいは、こういう教訓も生んでみましょうか。
"備えあれば憂いなし"
あれ?どっかで聞いた言葉になってしまったな。
しかし、こうして考えてみると、
"備えあれば"の後に"憂いなし"という、
あくまで当人の感情に重きを置いたワードを置いているあたりは、
なかなかのセンスだなぁなんて思ったりもします。
というわけで備えがあれば憂いもアフターケアも不要なわけでした。
小学生の子は、予習をやっていれば先生の言っていることが(言わんとしていることが)わかって授業も楽しいし、
復習なんて大してしなくていいって意味だと思ってね。
ですが、個人的には結構出来がいいです。
最近忙しいと口で言いますがいい加減飽きてもくるので、結局のところなんなのか、
という話を、今日はしましょう。
今日、空港でちょっとした事件がありました。
"金属探知機まで抜けたその地で、チケットがない。"
一応説明しますと、金属探知機を抜けるためにはチケットが必要なので、
そこから物理的にチケットを無くすってことはありえないわけですね。
でも、それは起こった。何故か?
…何かから急かされていると結構な確率でモノを無くしてしまう僕は、
(大して役にも立たない経験則から)またてんぱって無意識に変なところにチケットを入れたのだろうと思っていましたが、
実際は、間違って他のお客さんが持って行ってしまったということでした。
◆
さて、ここからがポイントです。
そもそもチケットを受け取った記憶がない僕は…
①「いや、俺は確かに取ってないな。多分誰か間違って持って行った、としか思えない。俺が持っていたら、後から謝ることにしよう。」
②「あれ、俺またやらかしたのか?嘘だろ… とりあえず、警備員さんに落ちているチケットがないか訊いてみるか(あわあわ)。」
僕が選んだ選択肢は残念ながら②でした。
(それでも事態が大きくならないうちに警備員さんに訊いただけ、これまでよりはマシなのですが。)
②の最初の一文で精神エネルギー50消費。
その後フライトが近づきます。
やはり、ない。
最初は警備員さんも"ないはずはない、ちゃんと探しましたか"と
さほど取り合ってくれませんでしたが、そのよそでビデオチェックをしてくれていました。
(主な目的はよくわかりませんが、あそこにはカメラがついているんですね。
今日まで知りませんでした。)
で、次に来たお客さんが、僕のチケットが入った箱に(箱の印刷と思ったかもしれません。)
荷物を入れ、一緒に持って行ってしまったという話を聞きました。
なんというか、多くの人を待たせている焦りばかりが募り
それを聞いても特にこれといった感情は湧いてきませんでしたが、
途端に冷静を装ったことだけは確実です。
結局飛行機の中では疲れとは裏腹に体が硬くなっていて、一睡もできませんでした。
眠っているときにCAが置いてくれる、アザラシのような形をした飛行機のシールも貼ってもらえず。
◆
ここでシミュレートしてみる。
①を選んでも、②を選んでも、
僕以外の人の行動ってそんなには変わりません。多分精神状態も。
ビデオチェックを行うまでの時間が早まった可能性はあるので全然変わらないわけでもないですが。
さてここで問題です、①と②の決定的な違いは、なんでしょう?
…僕が、チケットを持っていないことに自信を持っているか、あやふやなのか、そこですね。
その差で、僕の精神エネルギー(気疲れ)にとても大きな差が出てしまいました。
一つあやふやなことがあっただけで、その後のリソースに大きな差が。
でも、そういうことなんですね。
人は常に失敗からのリカバリを考えられるほど、タフではないわけです。
同じ量の仕事をこなしたとして、ポイントを押さえて失敗を防げた人に比べ、
失敗をしてなんとかリカバリを果たした人は、ずーーっと疲れてしまいます。
他の評価を気にしなくとも、勝ち負けがないものであっても、
自分の残リソースから改良を検討する方法ってのが存在するわけですね。
ですから、次以降は失敗をしないように、ということを考えるわけです。
家を出るときに、サイフ、ケータイ、鍵、社員証、とか、
忘れ物をしないためのルーチンを課すのも恐らくその対策の一種。
皆さんもやりませんか?
忘れ物をして痛い目を見たのがいつだったか、憶えているとは限りませんが。
これまでは自分で失敗して痛い思いをしないと人の説く話に共感できませんでしたが、
これからは少しは他人の振り見て我が振りを直せないかな?
◆
そこから教訓が生まれます。
"貴重品の管理はしっかりしろ"と。
今まで何度言われた台詞かよくわかりませんね。
その割には、"二度と言われないようにしよう"という闘志が湧きにくい言葉でもあります。
あるいは、そこから教訓も生まれます。
"物事をあやふやにしておくと、いつか痛い目を見る"。
この教訓もイメージとしてあやふやな感は否めませんが、
今日の内容を見れば出所がわかるのでそれもアリでしょう。
あるいは、こういう教訓も生んでみましょうか。
"備えあれば憂いなし"
あれ?どっかで聞いた言葉になってしまったな。
しかし、こうして考えてみると、
"備えあれば"の後に"憂いなし"という、
あくまで当人の感情に重きを置いたワードを置いているあたりは、
なかなかのセンスだなぁなんて思ったりもします。
というわけで備えがあれば憂いもアフターケアも不要なわけでした。
小学生の子は、予習をやっていれば先生の言っていることが(言わんとしていることが)わかって授業も楽しいし、
復習なんて大してしなくていいって意味だと思ってね。