『風立ちぬ』堀辰雄著

〈0〉
「『風立ちぬ』は純愛小説ではない。それは大きな誤解だ」(某高校国語教師)。
〈1〉
今回の課題本『風立ちぬ』の冒頭に掲げられたエピグラフ、ポール・ヴァレリイの詩「海辺の墓地」の一節を、「風立ちぬ、いざ生きめやも」と訳した堀辰雄がすべてだと思います。
この美しい言葉は、例えば松本隆作詞の「風立ちぬ」(1981年)、宮崎駿監督のアニメ「風立ちぬ」(2013年)など、時代を超えて多くのクリエイターに影響を与え、歴史に残る作品を生み出してきました。そして、今日もここ牛込箪笥地域センターには、この小説に魅せられた善男善女が集まってきました。彼ら、彼女たちからは、さて、どのような感想が聞けたのでしょうか。
〈2〉
驚いたのは、再読の方が多くを占めるだろうと思っていたのに反して、けっこうな人数が初読みだったこと。実は、推薦者も本書を読むのは初めての体験でした。それでも読後に既視感を覚えたのは、「難病で亡くなってしまう恋人と、そんな彼女を看取る男の物語」というあらすじをいつかどこかで聞いていたからでしょうか。それが刷り込まれた結果、いつの間にか読んでいたような錯覚を覚えていたのかもしれません。イメージと思い込みが先行するパターンの典型です。
「十代のころに読んで以来の自分にとってオールタイム・ベスト」と言い切る筋金入りのファンからは、「若いころには退屈な話だと思っていたけれど、歳を重ねて読み返してみると実は緊張感に満ちている物語だとわかった。節子にとらわれていた〝私〟が、節子の死によって解放されたのだと感じた」という、再読者ゆえの感想がありました。
この〝私〟と節子の関係性については、「男の立場で描かれていて鬱陶しい。自分の気持ちばかりの押し付けで相手を思っているようで思っていないのでは? 節子の視点から書かれている部分もあればよかった」とか、「ピュアな恋愛小説には違いないが、節子の存在感が薄い。作者=男の気持ちだけの話で、節子とは何者なのだろうと思った」。あるいは、「知らない人にその人の恋愛話をとつとつと聞かされたような感じ」といった声が聞こえました。
初読みの方に多かったのは、「サナトリウムでの日々がたんたんと書かれている」、「景色や自然・風景描写は目に浮かぶようだ」と文書の美しさをほめる感想と、逆に、「目に見えることを何でも書いているような違和感を感じた」という相反する2種類の感想でした。また、「直接節子に対する自分の気持ちを述べるのではなく、距離感をおいて述べているのはまどろっこしい感じがする。自分の内面を見せないのは品位があるということなのだろうか」という意見もありました。
死が二人を分かつ、というモチーフには、「二人には生きることへの執着がないのでは? 結核が当時の不治の病ゆえ、〝死〟を受け入れてしまっているのでは」とか、「亡くなった人への思いを、〝愛情〟と感じるのか、〝束縛〟〝執着〟と感じるのかによって、物語の捉え方が違ってくるのではないか」といった感想に加えて、「時間が経って〝忘れられてしまうこと〟が別れに際して女性が一番怖いと思うことだろう」という考えを披露した方もいました。
この〝死〟と〝生〟、あるいは〝死〟と〝愛〟の相克というテーマは、その後もさまざまに形を変えながら文学、映像などで再生産されていくことは皆さんご存知のことです。
〈3〉
講師の菊池先生は、かつて先生が衝撃を受けたという本レポート冒頭の言葉を踏まえて、「本作は作者にとっては『聖家族』『物語の女』を経て次に至る過程に位置する作品。作品履歴から見れば〝純愛小説〟という単純なくくり方ではない、別の陽の当たり方が出てくると思う」としたうえで、「全部で5つの章で構成されているが、それぞれの執筆形態やストーリーのつなぎ方をものすごく考えている」と講評されました。そして、「小説には主人公の生き方を論ずるものと、論じないものがある。本作は後者」であり、「近代小説の確立を担った作品」。「〝死〟そのものを見つめて、そこから〝生〟を見つめる」と、まとめてくれました。最後の、「この先、この小説が若い人たちにどう読まれていくのだろう」という感想が印象的でした。
〈4〉
推薦者にとっては、毎年夏が終わり秋風の吹くころになるとなぜか読みたくなる『風立ちぬ』をようやく読めたことがよかったです。そこに描かれた「死の味のする生の果実」――〝死〟に裏打ちされた〝愛〟や〝生〟の姿が、コロナ禍でささくれだった心を癒してくれたようです。
なお、賢明な会員の皆さんは気が付かれていると思いますが、本作には節子の亡くなるシーンは描かれていません。あえて悲しみの沸点でもある「その日」を描かずに、「その日の前」の話と「その日の後」の話だけにすることで、読む者の想像力をかき立て、「古びない物語」(会員)に昇華させているのではないでしょうか。
〈5〉
1年8ケ月ぶりのリアル読書会。参加者は男性3人、女性8人(うち一人は見学者)でした。



















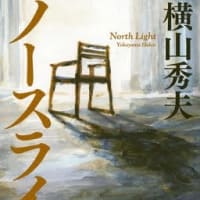






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます