
寛政期、西国の小藩である月ヶ瀬藩の郡方・日下部源五と、名家老と謳われ、幕閣にまで名声が届いている松浦将監。幼なじみで、同じ剣術道場に通っていた二人は、ある出来事を境に、進む道が分かれ、絶縁状態となっていた。二人の路が再び交差する時、運命が激しく動き出す。第十四回松本清張賞受賞作。
=例会レポ=
2月26日 17名出席(見学者2名含む)
菊池講師推薦による課題本は、多作な直木賞受賞作家・葉室麟氏の3作目という『銀漢の賦』。時代小説はイマイチ苦手という会員が多いせいか、大雨のせいか、集まりはあまりよくなかったのですが、その分意見交換が活発に。てことでぜんぶ書いた。
① デビュー時から読んでみたいと思っていたが、実は今作が初めて。血沸き肉躍る話ではなく、落ち着いた地味な印象。二人の男の生き様を描いた物語だが、カットバックが多い。いろんなエピソードを盛り込んではいるが、それが伏線として生きているか疑問。また、被支配者層である十蔵のエピソードが少ないのは寂しい。彼に感じる「負い目」が生きればよかったと思う。
② 書き方がきれいというか優等生的な感じ。話の起伏があまりなく、将堅と源五の二人にも男気が感じられない。もっとくずしてもいいのにと思った。
③ 時代小説は35年の読書歴でこの本が初めて。歴史が苦手で漢文という地雷もあり、コメントはうまくできないが意外に面白かった。次がどうなるのか先の展開を読みたいという気にさせられたので。終わり方も楽しい。特に解説の「友情の味は恋に似て・・」の一文がいいなあと思った。学生時代の友人の一人と仲たがいしたままになっているが、オーバーラップした。
④ 時代小説は男性が好んで読むものだと思っていたが苦手な人もいるんですね。この小説は盛り上がりなく終わってしまった。源五が堰を作るところ、十蔵の一揆、どちらももっと盛り上がっていいのに。将監との仲たがいも「それだけ?」という感じ。むしろ将監の叔父の仇討ちが一番わくわくした。『蜩の記』は面白かったのに、表紙絵が素敵なだけに残念。
⑤ 面白かった。初めて読んだ時代小説は『海鳴りやまず 八丈流人群像』で、以後も読んできた。特に藤沢周平は全作の5分の2くらい読んだ。葉室麟は今の時代小説では上位クラスの作家だと思うが、藤沢ならこんなに書き込まないだろうと思う。藤沢は自然描写がとても丁寧だが、もっと抑制している。それに比してこの作家はサービス精神が前面に出る。トップクラスの作家でさえ、今はこのレベルかという感じ。十蔵をもっと出せばいいのに。面白かったがもう一冊読みたいという気にはならない。
⑥ NHKドラマになっているせいか、図書館でも手に入らず、未読。『蜩の記』の話ばかり聞くので、この小説はこれから読みます。
⑦ レビューを見ると「男と男の友情物語」とあって、すんなり楽しめた。老年に入った男たちの物語には、苦いものが描かれている。将監が年を取り、かつて自分が追いやった九鬼幽斎と同じ立場となって、どこがどう違うのかと悩む。将監の脱藩を源五がなぜ助けたか気持ちを考えながら読んだ。さわやかな読後感が得られた。
⑧ 葉室麟は初めて。すらすら読みやすいが最後は都合よくいきすぎ。サラリーマン小説みたいなもの? 現代に置き換えても、人間の生き方は変わらないんだなと思う。でも藤沢周平の方が好き。
⑨ なぜ松平定信の時代設定なのか、身分の違う人間をどう絡ませていくか、時代小説の書き方や構成そのものの練った跡がありありと見える感じで、純粋に楽しむ読み方ができなかった。それでいて、ここに描かれる感情は今の人間のもの。最近は時代小説でも現代のエンタメ色が濃くなっていると思う。男のロマンチシズムを描いたとはいえ、最後は年寄りが若い女を娶るって、何じゃそりゃ。
⑩ 今回は楽しめた。時代小説は、いかにその時代にはめ込んでいくかが気になる。文学賞をとることを意識したようなまとめ方だが、最後の10年はいらない。娘に言われてそうなるというのは、これはないなと。もっと違う形で「あとで一緒に暮らしたのだろう」と想像させるくらいの終わり方でよかったのに。
⑪ 時代小説は、ふだんは読まない。これは男のナルシシズムが描かれた小説で、女が人形のように描かれているのが不愉快。この終わり方なら、男はそれは喜ぶだろうけれど腹が立つ。こんな時代に生まれなくてよかった。
⑫ 葉室麟は『乾山晩愁』を読んでいる。江戸に舞台を借りたサラリーマン小説。中高年サラリーマンに媚びているのがあからさまにわかる。読者は自分をどれかの男に当てはめて読むのではないか。途中からは「だろうと思った」という予定調和の展開。文字で全て描かれていて、エピソードが少ない。
⑬ 否定的な感想を持った。ドラマが先にあるかのような展開で、キャラクターがデフォルメされていて現代ものに近い感じがするのが残念。自分より一回り、二回り上の男性向けに書かれたような価値観が描かれている。決して悪いわけではなく読みやすいが、よく練り込まれて作られている仮想世界という感じ。
⑭ 日本史と漢文がダメな私でも楽しく読めた。時系列の混乱もなかった。登場人物が皆善人というわけではなく、物語に深みがある。自分のやりたいことを全うし、若い女を娶るのは、定年カウントダウンが始まったおじさんが絶賛しそう。
⑮ 構成がしっかりして面白いと思ったが、藤沢周平と比べると物足りない。漢詩だけが印象に残り、そこに全てが含まれているのに表現しきれていないように思う。
⑯ 山本周五郎以外、時代小説はあまり読んでいないが、読みやすかった。サラリーマン小説の構成。伏線には必要でないものもあり、深みも小難しさもなかったのが肩透かしをくらった感じ。ドラマチックというよりテレビドラマチック。百姓の十蔵はポジションがいいのに軽くあしらわれている。源五の行動も行き当たりばったり。将監だけが出世ばかりか芸術にも秀でてとんとん拍子の人生になる。うまいと思うがオチの軽さが物足りない。
⑰ 『蜩の記』も読んだが、好悪でいうと、いろんなことを詰め込み過ぎの感はあるが『銀漢』の方が好き。時代小説は最近読み出したので他との比較はできないが。コンセプトから入っているきらいはある。政治家かつ文人という将監は中国由来の文人像。理想の姿を将監に仮託したのだと思うので、そこは情状酌量してあげたい。絵画や美術のディスクリプションは非常に上手いと思う。会社の役員も何かと歴史の話をする。自分も15年勤めて最近は中高年男のファンタジーが理解できるようになった(てところで外野から「15年程度で何を言うか」のヤジ)。
それぞれに密な意見が飛び交いまして、さらに密度の高い“本領発揮”の講師論評。
●時代小説は、「時代」の場を借りることに意味がある。作者が描くのは現代の思いであり、批評である。現代の舞台では書けないようなヒーローものも時代を変えれば成り立つことがある。時代小説は、現代との「合わせ鏡」になっていることが重要なのだ。そのことを、読んだ後に浮かび上がらせなくてはいけない。
葉室が似ているといわれる藤沢周平は、時代小説を書いているのではなく、身の回りにいる人々を描いている。藤沢、司馬遼太郎に共通するのは「負け組」がどう一生懸命生きたかという主題。時代小説に付きものの御家騒動は、組織と個人という普遍的な問題を描いている。
時代設定にもそれが関わる。松平定信の享保は幕末に向かう直前の時代。だから御家騒動が成り立つ。藩の財政が底を付きはじめたこととも関わる。だからこの時代を舞台に選んでいる。徳川幕政では西側が弱い。そこで西側の藩をつぶして譜代大名を置く。大名の側からすれば、譜代になれば「老中」として幕政に関われる可能性も出てくる。今の会社組織と同じようなもの。
ただ、この小説の場合、藩の設定を架空のものにしたことで実在した藩にある事件がない。いろんなものを詰め込み過ぎて生かし切れていないという弱点はそこにある。十蔵のエピソードも書けていないので躍動感ある存在になっていない。しかし藩の権力に対して文化が勝つ、そのための道具立てとして将監は文人であるという設定が必要だった。まあ3作目ということで大目に見てください。『蜩の記』の方が完成度は高い。
日本で時代小説の礎となったのは、山岡荘八の『徳川家康』。彼は敗戦を目の当たりにして、苦労に苦労を重ねて天下を築いた家康を書こうとした。今川義元をアメリカ、織田信長をロシアに見立て、彼らに勝つ徳川を描いた。当初は西日本、静岡、北海道の3紙で、1年で終わる予定の新聞連載小説が「面白い」と十数年続くことになった。
昭和30年代にはもはや戦後でなくなり『眠狂四郎』などの虚無的なヒーローが生まれる。池波正太郎は高度成長期に合ったヒーローを描いたのであり、当時は立身出世が望まれていた。それを過ぎて負けた人間を描く藤沢、司馬が台頭する。
その後は作家が苦労する時代となっているが、時代小説が現代との合わせ鏡というのはそういう意味。今に生きる男と女を描くのが時代小説なのである。
というわけでロングロングなレポとなりましたが、出席できなかった会員の皆さま、本日の講師はカッコよかったですよ♪
聞き逃して残念だ~と思われた方は、ぜひお酒と時間のたっぷりあるときに講師におねだりしてみてくださいね。
本日のお言葉
「時代小説は現代との合わせ鏡」



















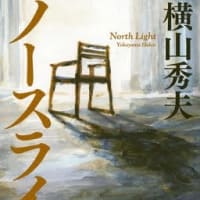






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます