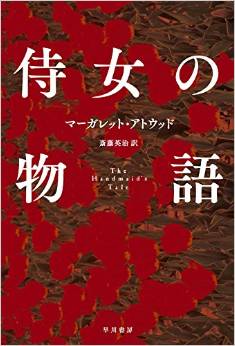
マーガレット・アトウッド『侍女の物語』
ハヤカワepi文庫 2001年
侍女のオブフレッドは、司令官の子供を産むために支給された道具にすぎなかった。彼女は監視と処刑の恐怖に怯えながらも、禁じられた読み書きや化粧など、女性らしい習慣を捨てきれない。反体制派や再会した親友の存在に勇気づけられ、かつて生き別れた娘に会うため順従を装いながら恋人とともに逃亡の機会をうかがうが…男性優位の近未来社会で虐げられ生と自由を求めてもがく女性を描いた、カナダ総督文学賞受賞作。
=例会レポ=
昨年11月、どさくさ紛れに決まった課題本なので、推薦人は不安でいっぱいでした。
が、お正月休みにぐいぐいと一気読み。読み終わって思いました。「2015年のベスト本は決まった…」と。
舞台は近未来の架空の国ギレアデ共和国。放射能汚染やAIDSをはじめとする伝染病で出生率が低下した中、キリスト教原理主義によって誕生した国家です。国は戦争および内戦状態にあり、支配者層である司令官たちによって、厳しい監視・管理がなされ、国民は身分、階級で色の違う制服の着用を義務づけられて、反逆者には過酷な刑罰や処刑が待っています。
そういう国で「侍女」は司令官の子どもを産むための道具として、行動を制限され、読み書きも禁止され、体を傷つけるようなものを一切取り上げられて暮らしています。
語り手の侍女は、夫と娘がいて、仕事を持っていた過去を思い出しながら、現在の境遇をしかたなく受け入れ、でもいつか逃げ出すことも考え…。
淡々と日々の出来事が語られる中で、少しずつ少しずつ、小説の中の世界のしくみが見えてきます。小さなピースがあるべき場所にぱちんとはまって徐々に全体像が見えてくる、ジグゾーバズルを完成させていくような読み心地は、大きな事件が起こらなくてもスリルと緊張感に満ちています。そして、見えてきた世界の恐ろしさに息を飲み、戦慄する…そういう体験って、そうそうあるものじゃありません。怖い! でも目を離せない。
と、すでに思い入れがぽろぽろわらわら溢れ出してしまった推薦人。
参加した皆さんは、どんな感想を語ったのでしょうか。
全員の感想を強引にひと言ずつにまとめてみました。「そこかよ!」の方、ごめんね。
A:あの世界にわたしがいたらリディア小母さん
B:なんとなく楽しくない
C:どんな社会でも人間の欲望がなくならないことが希望だ
D:うまいと思ったのは設定となる世界の説明をしないこと
E:おもしろいようなわからないような、でもリアル
F:びっくりして、先が気になって終りまで読んだ
G:脚色? だまされている? と思いながら…
H:理解がついていきませんでした
I:悪夢のような世界。なのに、どうして読み続けたんだ?
J:素晴らしかった! 古典として残る作品だと思う
K:振幅のない話は苦手なんです
L:振幅はないようでありますよー
M:体調の悪いときに読書してはいけないと思った
N:現在形と過去形が続く文章は偏執的でおもしろい
O:時間切れで150ページまでしか読んでない
P:初Kindle!
なるほどー。この話好きだろうなあと思った人が思った通りの反応でうれしかったです。そして、あの人は苦手だべと思った人はやっぱり来なかったり。苦手な方には申し訳なかったけれど、手放し絶賛の人が一人でもいれば推薦人としては満足です。
最後にK講師のお話も気になったフレーズセレクションで。
・ 現実は、ユートピアの中にディストピアの種子が
・ 1985年(著作年)に作者が感知した悪い種子を並べた
・ 制御不能と可能の間の物語
・ 語り=物語として書かれたことの意味
・ エロくないセックスシーンは「1Q84」に通じる
・ 言葉へのこだわりが「雪の練習生」みたい
・ 読み方を読者に委ねているところが作者の“凄腕”
1月2日にして、今年のベスト本に出会ってしまった2015年。「侍女の物語」を超える本にめぐりあえることを願って、2月以降の課題本に期待してます〜。



















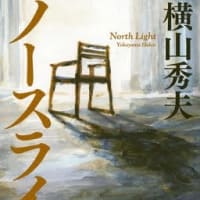






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます