『わたしを離さないで』
カズオ・イシグロ/著
土屋政雄/訳
早川書房(2006年)、ハヤカワ文庫(2008年)
 |
著者のどの作品をも超えた
鬼気迫る凄味をこの小説は獲得している。
個人的には、イシグロの最高傑作だと思う。
柴田元幸(本書解説より)
[あらすじ]
自他共に認める優秀な介護人キャシー・Hは、提供者と呼ばれる人々を世話している。キャシーが生まれ育った施設ヘールシャムの仲間も提供者だ。共に青春の日々を送り、かたい絆で結ばれた親友のルースとトミーも彼女が介護した。キャシーは病室のベッドに座り、あるいは病院へ車を走らせながら、施設での奇妙な日々に思いをめぐらす。図画工作に極端に力をいれた授業、毎週の健康診断、保護官と呼ばれる教師たちの不思議な態度、そして、キャシーと愛する人々がたどった数奇で皮肉な運命に……。彼女の回想はヘールシャムの驚くべき真実を明かしていく。英米で絶賛の嵐を巻き起こしたイシグロ文学の最高到達点。
ハヤカワ文庫
<例会レポ>
推薦人の手前ミソかもしれませんが、現役の作家の作品としては、ここ最近の課題本の中では全体の評価がかなり高かったように思います。
また、世間的な評価も非常に高く、話題作ということもあり、課題本になる前に読んだことのある人も普段より多かったような。
ただし、その中でも再読した方、再読しなかった方、原書を読み直した方、と様々でしたが。
さて。高評価という点では同じだったとしても、感想はそれぞれ違うのが読書会の面白いところです。
<最も多かった意見>
・特殊な閉ざされた環境での人間関係の描写が秀逸
・設定は特異だが、テーマは普遍的
・物語は静かに淡々と語られるのに、感情は大きく揺さぶられる
・キャシー、ルース、トミーの関係が濃密
・映画の出来も気になる
・同作者の『日の名残り』が良かった
<その他の意見>
・日本国内での家族承諾のみによる臓器提供の実施と時期が重なり、余計考えさせられた
・キャシーの一人称で語られているが、聞き手は誰か
・トミーのセリフの邦訳に違和感を感じる
・親が居ないこととファミリーネームがイニシャルであることには関連性を感じる
・食肉用に作られた生物(ブロイラー等)が実在している以上、臓器提供用の人間が作られる日も遠くないかもしれない
・ファミリーネームのイニシャルは、分類番号を意味しているのではないか
・親の庇護がないからこそ、子供達同士の関係性が濃密だと思う
・臓器提供用に作った人間に人格を与えることは残酷ではないか
・臓器提供の為だけならば施設で育てず、眠らせたままでも良いのではないか
・トミーの人格の「できない」部分の描写が、うまく積み立てられている
・部や章の分け方にも作者の技量を感じる
ここまでは、本書を肯定的に捉えた上での意見です。
ここで終わらないのが、読書会の更に面白いところ。
今回は男性陣から特に多く、好みでないという意見が出されました。
<否定的な意見>
・自分達の人生や運命について色々と考えることができるのならば、何故逃げようとしないのか
・構成があざとく、思わせぶりで面倒
・釈然としない部分が多く、読後感が良くない
・クローンや臓器提供の倫理面には全く踏み込んでいない
・反抗や逃亡だけでなく、葛藤や怒りすらないのは、描くべきことを描いていないように思う
・「過酷な運命の中で必死で生きていく」という世界感が好きになれない
・その後の不明な登場人物が多い
・つまらなかったという感想を言ってはいけないような気にさせる終わり方
・設定が非現実的で気味が悪い
言われてみればなるほど、という意見も皆それぞれにあったのではないでしょうか。
<講師から>
・作者にとっても、数年前から構想を練っていた大切な作品
・先ず設定を受け入れられなければ、肯定的に読むことは難しい
・クローンについては、単に物語の仕掛けであり、倫理を語るつもりはないので拘るべきでない
・「運命の受容」や「どう生きるか?どう生きたか?」が作家のテーマ
・リアリズム、英語的なロジック、緻密な構成等が非常に上手
・ジュディ・ブリッジウォーターの設定、歌の歌詞が特に良い
課題本3冊目にして、やっと講師からも高評価を頂きました。やはり嬉しいものです。
でも、世間の評価が良いことで満足するのは、まだきっと初心者。
他人には理解されずとも自分にとっては重要と思われる本を新しく見付けて課題本に推薦する、という第2ステージへ、いざ!
|


 2024年11月の課題本『ナイン・ストーリーズ』
2ヶ月前
2024年11月の課題本『ナイン・ストーリーズ』
2ヶ月前
 2024年10月の課題本『時穴みみか』
3ヶ月前
2024年10月の課題本『時穴みみか』
3ヶ月前
 2024年9月の課題本『ミシンと金魚』
3ヶ月前
2024年9月の課題本『ミシンと金魚』
3ヶ月前
 2024年6月の課題本『ザリガニの鳴くところ』
7ヶ月前
2024年6月の課題本『ザリガニの鳴くところ』
7ヶ月前
 2024年1月の課題本『暗い旅』
1年前
2024年1月の課題本『暗い旅』
1年前
 2023年7月の課題本 『嘘と正典』
1年前
2023年7月の課題本 『嘘と正典』
1年前
 2023年5月の課題本『同潤会代官山アパートメント』
2年前
2023年5月の課題本『同潤会代官山アパートメント』
2年前
 2023年4月の課題本『少女は卒業しない』
2年前
2023年4月の課題本『少女は卒業しない』
2年前
 2023年2月の課題本『雪沼とその周辺』
2年前
2023年2月の課題本『雪沼とその周辺』
2年前
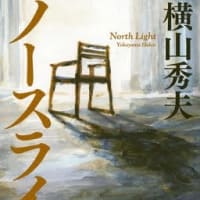 2022年10月の課題本『ノースライト』
2年前
2022年10月の課題本『ノースライト』
2年前
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます