
アントニオ・タブッキ『イザベルに:ある曼荼羅』
河出書房新社 2015年
ポルトガル・サラザール独裁政権下で姿を消した、謎の女イザベル。『インド夜想曲』『遠い水平線』の著者が遺した最後のミステリ。(Amazon内容紹介より)
=例会レポ=
イタリアの作家アントニオ・タブッキがポルトガル語で書いた未完の遺作だそうです。
よくわからない、おもしろかったが入り込めなかった、正攻法でミステリーとして書いたらおもしろかっただろう、立ち位置が全然違って好きじゃないなどの感想がありました。
他方、理屈で理解しようとする小説ではない、音楽みたいにいろいろな音が聞こえてくる、とめどなく会話が流れ感じるところがある、意外なおもしろさがある幻想小説、などの感想もありました。
講師の菊池先生は、先月の課題本「パルプ」と今月の「イザベルに」について、まったく予期しない小説をおもしろ本棚で紹介されたといわれました。
1930年代のヨーロッパで、スペインのフランコ政権、イタリアのムッソリーニ、ポルトガルのサラザールら右翼陣営が優勢で、今の世界情勢と似ている。
左翼運動にかかわって姿を消したイザベルをシリウス(おおいぬ座の星)からきたタデウシュがいろいろな人に聞きながら探し求めるが、それは自分探しであり、最後は無に帰せられる。この最後の場面が美しい。文体、構想力、語り口のすぐれた作品、作者の生涯がなぞられているそうです。
レポーターとしては音楽のような、詩のようなこの作品が好きですが、いろいろな方の感想や先生の講釈をうかがって、またタブッキの小説を読み返したいと思いました。



















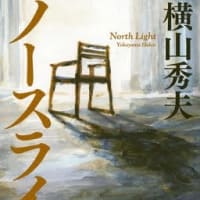






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます