
チャールズ・ブコウスキー『パルプ』
ちくま文庫 2016年
バーと競馬場に入りびたり、ろくに仕事もしない史上最低の私立探偵ニック・ビレーンのもとに、死んだはずの作家セリーヌを探してくれという依頼が来る。早速調査に乗り出すビレーンだが、それを皮切りに、いくつもの奇妙な事件に巻き込まれていく。死神、浮気妻、宇宙人等が入り乱れ、物語は佳境に突入する。伝説的カルト作家の遺作にして怪作探偵小説が復刊。(Amazon内容紹介より)
=例会レポ=
年度末の木曜日の例会は、やはり仕事で参加が難しかった方が多かったかもしれません。集まったのは12人プラス見学の方1名でした。
読書会自体は一見静かに、大きな議論もなく終わりましたが、レポートをまとめようとしてメモを読み返したら、一つの傾向が見えてきて、「あらら、おもしろい!」と思いました。
「途中で、筋を追うのをやめたら楽しくなった」
「こういう話なのだと割り切ったら納得できた」
「はじめは読みづらかったけど、くだらな〜い(ほめ言葉)と思ったらおもしろくなった」
そうなんです!
わたしもそうでした! 探偵がいて、依頼人がやってきて、事件を追って…ああ、探偵小説なのね、と思っているうちはつまらなかったのですが、途中で気がつくのです。なんだ、探偵小説じゃないんだ、と。
気持ちを切り替えると、死神も宇宙人もバイオレンスもナンセンスも汚い言葉も、なんでもありのブコウスキーワールドで自由に遊ぶことができました。
この小説の凄さはここにあるのでは?
それなりにたくさんの小説を読んできた会員さんたちですから、わたしももちろん、読書垢みたいなものが身についているのです。これはこうなるはず、こういうことなんだよな、なんて、わかったような気になって小説を読んでいるところがあります。
それをひっくり返してくれる小説でしたね〜、『パルプ』。ひっくり返されることは快感で、なかなか出会えない瞬間でもあります。それを味わわせてくれたブコウスキー、素敵です。
講師からは、
「なぜセリーヌを出したのか、なぜアメリカ・ハードボイルドの作法を取ったのかという2つの点がポイント。作者はセリーヌに心酔していたのであろう。その文体の影響が感じられるけれど、それでも独自の文体を生み出している。1930年代、大恐慌から戦争に向かう時代に少年期を過ごした作者が、亡くなる直前の1994年に発表したこの作品には、ナショナリズムが強くなり、追い詰められていく時代の匂いに似たものを感じたからではないだろうか。そして、今の日本の状況で、ちくま文庫からこの作品が再び発行されたことの意味も考えましょう」
というようなお話がありました。
参加できなかったけど「よかった!」と言っていたというHさんと、昨年忘年会のプレゼント本にこれを選んでいたSさんの感想が聞きたかったです。
最後に、「課題本なので義務感でやっと読んだけど、ラストシーンで報われた」というTさんの言葉をご紹介します。まだ読んでいない方は是非読んでみてくださいね。



















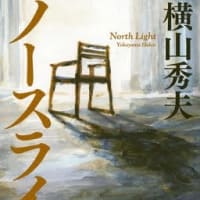






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます