
チャイナ・ミエヴィル/著、日暮雅通/訳 『都市と都市』
ハヤカワSF文庫 2011年
ヒューゴー賞/世界幻想文学大賞/ローカス賞/クラーク賞/英国SF協会賞受賞!カズオ・イシグロ氏が絶賛する話題作。
ふたつの都市国家〈ベジェル〉と〈ウル・コーマ〉は、欧州において地理的にほぼ同じ位置を占めるモザイク状に組み合わさった特殊な領土を有していた。ベジェル警察のティアドール・ボルル警部補は、二国間で起こった不可解な殺人事件を追ううちに、封印された歴史に足を踏み入れていく……。ディック-カフカ的異世界を構築し、SF/ファンタジイ主要各賞を独占した驚愕の小説
<早川書房>
●例会レポート
2012年2月例会はチャイナ・ミエヴィル『都市と都市』(ハヤカワ文庫SF)。ヒューゴー賞、ローカス賞、アーサー・C・クラーク賞、世界幻想文学大賞、英国SF協会賞を受賞した話題作であり、ひとつの地域を二つの都市国家が所有してお互い見えないふりをしているという、バカバカしいにもほどがあるアイデアに魅了されて推薦してみました。
が、おっかしいなあ、他の推薦本を抑えて課題本になったというのに19時になっても参加者少なめ。おもしろ本棚にSFは鬼門か、あるいはやはり参加者が少なく感じた昨年1月の松尾スズキ『宗教が往く』と同じく推薦者の好みあるいは推薦者本人に難アリか。参加者が少なめなことをぐっとこらえて講師の前説を聞いている間に徐々にメンバーは増え、最終的には23人(女16男7)。数えてみればそれなりの人数で、心の底でほっとしました。
さて、まず推薦者個人としては、バカバカしい設定を存分に描ききったエンタテインメントとして充分楽しめました。
ひとつ難を言えば、「同じ地域を二者が所有してしまいお互いが相手をいないこととして振る舞う」というアイデアが、40年近く前に書かれた筒井康隆の短編「融合家族」(徳間文庫『わが愛の税務署』、角川文庫『日本列島七曲り』等に収録)と丸かぶり、という点。
念のため同作が外国語に翻訳されているかどうかを調べてみましたが見つからなかったので、偶然アイデアがかぶっただけかと思われます(チャイナ・ミエヴィルが日本語堪能ではない、という前提での話ですが)。
続いてみなさんの感想の傾向ですが……。
◆ベジェル
・二つの都市が複雑に絡まりつつ分裂している理由がないがしろにされたままで納得できない。なぜ壁を作らないのか。
・言葉の意味がわからず読み進められない。
・ブリーチの存在意義がわからない。
・「見えないふり」がピンとこない。
・設定がどうしても理解できず挫折。
◆ウル・コーマ
・本を開くと必ず寝てしまう。
・いつかおもしろくなるだろうと期待して読み進めたが最後まで……。
・ブリーチの正体が意外にしょぼい。
・同じSFミステリーでもアイザック・アシモフに比べて物足りない。
・キャラクターが立っていない。
・五感を封じているはずなのに風景描写がしっかりされていることに違和感。
・主人公の背景や人生が見えないため、ラストのセンチメンタルな気分が薄い。
・SFとしての大風呂敷展開を期待したが、ラストはバタバタした謎解きに終わってしまって不満が残る。
と、なかなか手厳しいご意見が続々。とはいえもちろんそればかりではありません。
◆クロスハッチ
・迷宮的な世界の描き方がおもしろい。
・モザイク状の街というものを想像しづらいが、この長さを書けるということは作者自身が世界観をしっかり作りこんでいるということだろう。
・描写力があるおかげで、見ないようにしながら見るというバカバカしい設定を楽しめる。
・翻訳が良く、特殊な言葉がたくさん出てくるがスムーズに読める。
・ウル・コーマに入ることで街の風景の見え方ががらっと変わるのがおもしろい。
・異郷っぽいネーミングから、モデルとなった国や地域はどこだろうと想像しながら読んだ。固有名詞は大事。
・範囲を決めて「ベジェル=ウル・コーマごっこ」といった遊び方やワークショップができるのでは。
・本作に刺激を受けて都市論などを読み返した。
◆ディセンシ
・自分が頭の中で描いた都市の姿と作者が創造した世界が同じなのかどうなのか。
・小説を読むというよりゲーム感覚。自分が感情移入するのではなく、透明人間のようになって現代人の孤独として読むべきかも。
・正体不明な先史時代の遺物や、描かれない両国の歴史が気になる。
・これってSFなの?
◆ブリーチ
好意的な感想及びいくつかの疑問点等が出揃ったところで、いよいよ今月の菊池講師解読です。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
本編を読み解くヒントは冒頭の謝辞にある。
1)フランツ・カフカ
カフカ作品でも特に『城』と『審判』からの影響が強い。城や裁判所がそのまま都市であるという部分に刺激を受けたのではないか。
2)アルフレート・クービン
幻想画家。ドイツの表現主義映画『カリガリ博士』の幻想的な背景画を担当したことでも有名。
3)ジャン・モリス
もとは男性。『苦悩 ある性転換者の告白』で女性になった経験を書いている。本来は旅行作家で、『都市と都市』の風景描写に影響を与えている。
4)ブルーノ・シュルツ
謝辞にある『肉桂色の店』は非リアリズムの本家のような幻想的な作品。
こうした幻想的な作家陣の非リアリズム的なイメージを底本としつつ、同じく謝辞に並ぶレイモンド・チャンドラーによるフィリップ・マーロウものの捜査方法を使い、ミステリー仕立てで読者を案内していくのが『都市と都市』という作品。
チャンドラー風に普通の都市での殺人事件を追っていくと、非現実的なところへと導かれてしまう。が、その非現実的なことこそが現実であるというのが作者の視点。このことは次の部分からも読み取れる。
両都市をひとつにすることに身を捧げた人間と、両都市を遠ざける任務を果たしてきた権力との、血みどろの戦争なのだ。(P460)
これはリアルな今現在の世界情勢そのもの。さらにもう一箇所。
「盗まれたのはみんな、歯車のついた遺物だった」私は言った。「シア・アンド・コア社は遺物を調査している。科学的な実験だ」(P464)
アメリカに代表される、あらゆることに企業が入り込む今の世界、そういうものを作者は作品の中に出してきている。
細かな設定がいろいろ書き込まれているが、作中に出てくるものはいずれも我々が見聞きしている現実の世界で起こっていることと重なる。いたるところに地域紛争などの思わせぶりな表現が出てくるのは、作者がそうした意味をこめたかったからではないか。
SFというジャンルにこだわるのなら大風呂敷を広げてたたむ展開となるのだろうが、この本ではそうはならない。作者の結論は、事件が解決した後の次の文章に表れている。
私はその二つのうちどちらも選ばないという選択をした。私の任務は変わった。一方またはもう一方の法を維持管理するのではなく、法をあるべき位置にとどめておくためのいわば外皮を維持する役目になった。要するに、二つの法を二つの場所にとどめておくのだ。(P514)
◆オルツィニー
最後に推薦者から少々補足を。今回『都市と都市』を取り上げるにあたり、チャイナ・ミエヴィルのデビュー作『キング・ラット』(アーティストハウス)と第二作『ペルディード・ストリート・ステーション』(早川書房)、及び『SFマガジン』2009年8月号に掲載されたチャイナ・ミエヴィルのインタビュー等も読んでみました。
結果として見えてきた、というか思ったこととしては、チャイナ・ミエヴィルという人は異国や他者といった自らとは違う世界やモノゴトを、違うままに受け入れるべし、という意志を強固に持った人なんだろう、ということです。『都市と都市』において、相手国を受け入れようとしない右寄りな政治家及び両国の違いを認めない統一派を愚か者として描いているところや、上記の菊池講師が指摘しているエンディングにそうした意志が端的に現れていると思います。
要は異なるものを詰め込みながら、平らにならさずゴチャゴチャしたままをおもしろがりたい、ということではないか、と。そうした嗜好がそのままベジェルとウル・コーマの設定になったり、SFとは言い切れない小説になったりするのではなかろうか、と。
といいながら「これってSFなの?」という疑問には「これもSFです」と言わざるを得ません。そのあたり、話が『都市と都市』から少々それますが蛇足的に補足。
「SF」は「サイエンス・フィクション」の略称であり、であればSFとは空想科学小説であり、だったら科学技術や未来や宇宙に重点が置かれるものがSFなんじゃないか、というところから「これってSFなの?」という疑問が出ると思われますが、SFという言葉で括られる作品群は現在、必ずしもサイエンス・フィクションという言葉に厳密に対応したものばかりではありません。もっと幅広く、「現実にはありえない要素が含まれる作品」をカバーする用語としてSFという言葉が用いられている、というのが現状と思われます。
よって、私がおもしろ本棚に入会してからのここ3年間の課題本に限ってみても、SFレーベルから刊行されている『渚にて』や『月は無慈悲な夜の女王』のみならず、『マジック・フォー・ビギナーズ』や『わたしを離さないで』や『宗教が往く』や、『ポー短編集』と『グランド・マザーズ』の一部短編、さらにいえば『雪の練習生』だってSFといってもいいでしょう。
このあたり、「SFとはなんぞや」という問いはSFファンの間でも議論がつきず揉め続けている問題なのでこれ以上は深追いしませんが、繰り返すと「SF」とは「現実にはありえない要素が含まれる作品」の総称である、と大雑把に考えておけばいいかと思います。とりあえず私自身は「SF」という言葉をこのレベルの大雑把な意味合いで使っております。
ついでにもうひとつ蛇足的補足。両国分裂の理由や歴史的遺物は、アルフレッド・ヒッチコックがいうところの「マクガフィン」にあたる、あくまで物語を進めるための小道具であって、その正体には何ら意味はないのではないか、と思います。あるいは(ないと思うけど)続編のための布石とか。
ということで以上、かなり長くなってしまいましたが、2012年2月例会レポートでした。



















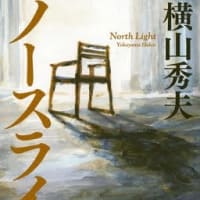






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます