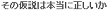いまどこ ―冒頭表示2
キーボードの2段めと3段目はなぜ互い違いになっていないの - 教えて!goo:
に答えてってな形で部分統合しようかナとも思う。
http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/c11db5b33d4a1d67900e568ab0dc6273ではちょっとスレ違うと思う。
http://www6.atpages.jp/~raycy/Q/ を http://www6.atpages.jp/raycy/blog2btron/door やらの作業経過を取り入れつつ、ふくらませるようなかんじで、、
http://www6.atpages.jp/~raycy/Q/ を http://www6.atpages.jp/raycy/blog2btron/door やらの作業経過を取り入れつつ、ふくらませるようなかんじで、、
アメリカ経済史の新潮流
岡田 泰男 編著
須藤 功 編著
目次
著者略歴
気鋭の執筆陣10名による論集。アメリカ経済史研究の最先端の動向を紹介するとともに、21世紀における新しい課題と展望を示す。取り上げるテーマは多岐にわたるが、今日最重要のもの、日本およびアメリカで関心を集めているものを中心とする。狭義の経済中心ではなく、広い視野から眺めた社会と経済の全般を扱う。単なる研究案内を超え、アメリカ経済史、より広くはアメリカに興味を持つ人々への知的挑戦の書。
アメリカ経済史の新潮流
目次
第1章 植民地時代の経済史研究―史料・方法・テーマ―(和田光弘)
第2章 アメリカ革命と新たな政治経済観の胎動(肥後本芳男)
第3章 市場革命―工業化と南北戦争前における政治文化の変貌―(安武秀岳)
第4章 自発的結社と株式会社-歴史的経路依存の視点から-(高橋和男)
第5章 ポリス・パワー―州主権と経済―(折原卓美)
第6章 フロンティアの経済史的意義―ターナー再読―(岡田泰男)
第7章 環境経営史―経営史・環境史・産業エコロジーへの問いかけ―(上野継義)
第8章 消費と国民化―大量消費社会の到来と行動規範―(松本悠子)
第9章 戦後通過金融システムの形成―ニューディールからアコードへ―(須藤 功)
第10章 移民と労働者(庄司啓一)
高橋和男(たかはし・かずお)
立教大学経済学部教授
主要業績:「地域開発・株式会社・共和主義――J.マジュウスキーの『市場発展』論」(『アメリカ経済史研究』創刊号、2002年);「アメリカ経済思想史における株式会社論――ヘンリー・ケアリーのアソシエーション論を中心に」(『立教経済学研究』50巻3号、1997年)
→
1952年の大統領選当日、ワトソンは、<UNIVAC>がコンピュータ業界のリーディング・カンパニーの地位をIBMから奪おうとするという「生涯で最も屈辱的なPR上の大問題」に直面します。著者は、1950年代の萌芽期のコンピュータ業界において、IBMは「動物園で育てられたトラが自然環境に放たれたように、毎晩同じ時間に目の前に夕飯が運ばれてくることなどない、と初めて知った」のだと述べています。<UNIVAC>幹部は1952年の大統領選の当日、CBSテレビに「開票結果を予測するコンピュータを提供しましょう」と申し出、CBSは「少なくともおもしろい試みではある」との理由から番組で<UNIVAC>を使用しています。一部地域からの開票速報を入力した結果、<UNIVAC>からは、接戦を予想した世論調査の予測を裏切り、「現在のところ、00対1でアイゼンハワーが優勢」という予測、すなわち、「アイゼンハワーが438票対93票でスティーブンソンを破り、地すべり的な勝利を手にする」という結果が予測されています。実際にはプログラムが2桁の数字しか想定していなかったためのトラブルで、100対1でアイゼンハワーが優勢、というものでした。
翌日の開票結果は、「442票対89票」という結果で、<UNIVAC>が誤差1%未満という正確さで予想を的中させたことが、「ユニバック」という言葉を「コンピュータ」の代名詞に押し上げ、IBMがコンピュータ製品を市場に出した際には、世間からは、「IBM製のユニバック」と呼ばれたことが述べられています。