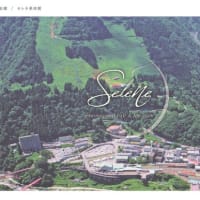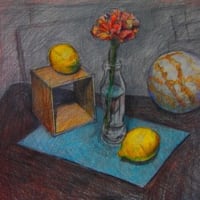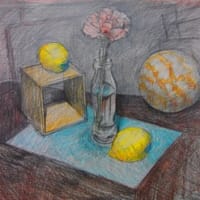最近、歌麿の浮世絵「深川の雪」が見つかったと、新聞やテレビで紹介されました。
たて約2メートル、よこ約4メートルの巨大な掛け軸で、版画ではなく肉筆の作品です。
NHKの番組を見ましたが、鮮やかな色彩に、大勢の人物たちの多彩なポーズ、
複雑な画面構成と、すばらしい作品でした。

その番組中でも紹介されていましたが、
歌麿が幕府から刑を受けるきっかけになった作品
太閤五妻洛東遊観之図 (文化元年 1804年)
たいこうごさいらくとうゆうかんのず
が、「幕末明治の浮世絵探訪展」に展示されています。

題名通り、太閤秀吉とその妻たち(北の政所や淀殿など)が、京都醍醐寺の三宝院で
お花見をしているシーンを描いた作品です。
なぜこの作品で刑を受けることになったかというと、幕府の法で「天正以降の武者絵に、
人物名や紋所などを書いてはならない」とされていたからです。
で、本作にはばっちり太閤の名や、石田三成などの名前が記されています。
また、「太閤記」そのものの出版も禁じられていたといいますから、つかまらないほうが不思議というものです。
歌麿は3日間の入牢、手鎖50日の刑を受け、その2年後に、53歳(推定。この方は生年不明なのです)で
失意のうちに死去します。

・・・じゃあ、なんでこの絵を描いたのか、そして出版したのか? となるのですが、これは諸説あって分かりません。
絵師のプライド説をとると、寛政の改革により、浮世絵などへの制約が強くなったことに反抗して、とも解釈できます。
そういえば、先に述べた「深川の雪」では、徳川家の葵の紋所をつけた女性が宴会をしているシーンがあり、
これも幕府への批判をこめたのでは、と言われていました。

本展では、浮世絵の美人画の時代が終わり、幕末にかけて武者絵、歴史絵へとシフトしていく
象徴的な作品として紹介しています。
(武者絵も単に人を描いているわけではなく、幕府への批判などが込められていました)

まあ、それは置いておき、純粋に絵をみますと・・・これが楽しそうじゃないのですね。
色彩が限られている(幕府の禁制です)のもありますが、お花見の華やかなシーン、
しかも天下人とその妻たちが大勢そろうシーンというのに、
秀吉はじめ誰も楽しそうではないのです。
不思議ですね・・・
やっぱり何か意味が込められているのかな?
そして、太閤秀吉はこの花見の約5か月後にこの世を去ることになります。
話は飛びますが「太閤五妻・・・」で受けた刑の後も、歌麿の人気は衰えず、
注文が殺到したため、その死因は過労死(!?)ではとの説も。
浮世絵の世界は予想以上に深いのでした。
----------------------------------------------------------
幕末明治の浮世絵・探訪展
~幕末の歴史絵から明治の開化絵まで~
期 間 平成26年 3月1日(土)~3月30日(日)
時 間 9時~17時30分(入館は17時まで)
休館日 毎週火曜日と、3月14日(金)~18日(火)の5日間
入館料 一般800円 高校・大学生700円 中学生以下無料
会 場 黒部市宇奈月国際会館・セレネ美術館 3階展示ホール
富山県黒部市宇奈月温泉6-3 TEL 0765-62-2000