ご無沙汰しています、宏美です。
今日は池袋、月の砂漠で、サズの大家大平清先生と、EvaBellyDanceStudioの人気講師、Ozmaとショウです。

今からでも予約は多分大丈夫。
ショウの為に、本日スタジオで17:00-18:00開講予定だった武術のクラスは休講となるので、代わりに、面白い文献をシェアしたいと思います。

私の学んでいる古武術は、大師匠が戸隠流忍術34代宗家である為に、よく、忍術と呼ばれるんですね。

※写真は今年2016年夏号の千葉ウォーカー、7月現在発売中
「忍」という字をよく見てみると、「心」に「刃」が刺さっているようにも、刃の下に心を隠しているようにも見えます。刺さっていれば、痛いはずだけれど、貫かれた心は安定していて、まったく動じません。そこにあるのは、痛みに耐える「忍耐」ではなく、痛みさえも感じない、つまり、心が動揺しないことこそ、本当の「忍」の境地であり、古人はこの字を通じて私たちに伝えたかったのかもしれないと、ある方がネットで書き記してくださっていました。
中国でも昔から「忍」の精神が語り継がれてきたそうです。
なるほどと思えるお話を
忍と検索して見つけたので、シェアします。
『漢の時代、劉邦の大将軍をつとめた韓信という名将は、小さい時から「忍」の精神が並の人ではなかったという。彼は少年時代から武術をたしなみ、武術者としていつも剣をさげていた。ある日、彼が街を歩いていると、ならず者が道の真ん中で仁王立ちして韓信に、「お前は偉そうに剣をさげているが、人を殺す勇気があるのか。殺せるものなら、俺の頭を切り落としてみろ。殺す勇気がなければ、俺の股下をくぐって行け」と挑発した。韓信は周囲のあざけりの中、本当にその股下をくぐった。どんな時も衝動に煽られず、「忍」という動じない心を持っているからこそ、後に偉業を成し遂げたのだと後世は彼を讃える。
また、安徽省の九華山で大興和尚が修行していたときのことである。ある日、突然お寺に大勢の人が押し寄せ、和尚を激しく殴り罵った。実は山の麓の村で、地主の娘が結婚前に出産し、父親が激怒し「相手は誰だ」と問い詰めたところ、娘がとっさに「大興和尚」と答えたのだ。地主は村の人々を連れて、けりをつけに来たわけで、生まれたばかりの赤子も和尚に押し付けていった。ほどなくして噂が広まり、かつて尊敬を集めていた和尚は、一気に罵りの的となってしまった。しかし、赤子を育てるため和尚は毎日恥に耐え、ミルクと食べ物をもらいに村まで来ていた。このように、日々の屈辱に耐えながら、赤子を育て上げた。
数年後のある日、突然お寺にまた地主達がやって来た。和尚が笑って、「ずっとお待ちしておりました」と。実は地主の娘は、ある書生と密かに誓いを結び身ごもったが、父親には和尚の子だと偽った。功なり名上げた書生が求婚に来て、娘はようやく真相を父親に告げた。地主は和尚の許しを請うたが、「怒ったことがないのに、何を許せと?子供を連れて行きなさい」と静かに答えた。
孔子の言葉に、「小忍ばざれば則ち大謀を乱る」(小さな事を我慢できないようでは、大きなことを成し遂げることは出来ない)がある。辱められても、勇気を持って耐え、動揺しない。刃が刺されても動じない。そういう修養と意志、真の意味での「忍」の心を持ちたいもの。』
というふうに、書かれていました。
私達は稽古中に、不動心、なんていう言葉をよく耳にするのですが、通じるものがあります。
武道とは、頭で哲学し、心と心で話し合い、身体と身体で相手と自分を知る、
私にとっては船と碇、旅を共にする船上員達との分かち合いに近いかもしれません。
ベリーダンスは?というと、船の帆が風にはためいて、追い風を一身に受けて、美しいなと思う瞬間や、船の上で聞く音楽、また、立ち寄った港での楽しいダンスや語らいそのものです。
人生という旅を、彩って楽しく、美しく、笑顔にしてくれるものは、私の愛する船であり、港です。
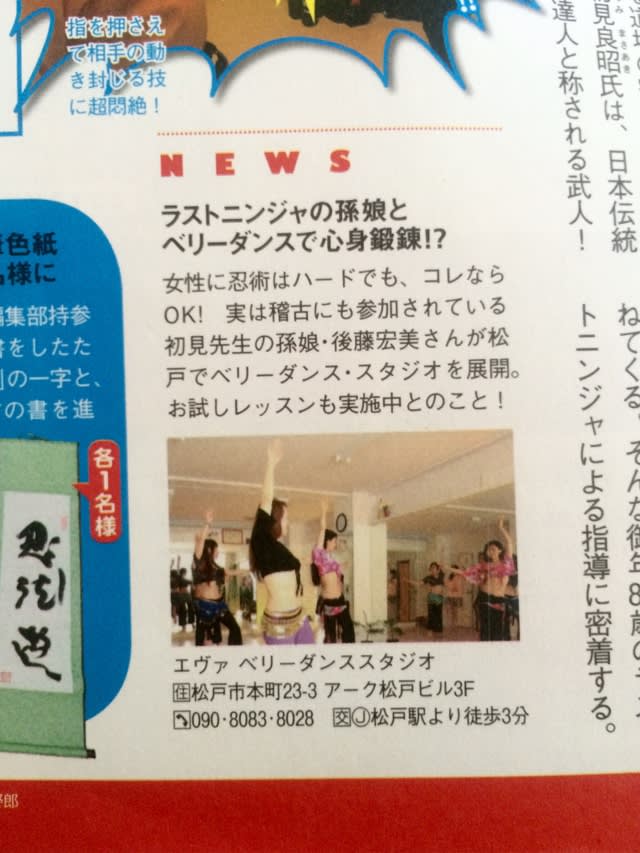
明日日曜は11:45から、3レッスン、しっかりみなさんと頑張りますので、
どうぞ、よろしくお願いいたします。
宏美
今日は池袋、月の砂漠で、サズの大家大平清先生と、EvaBellyDanceStudioの人気講師、Ozmaとショウです。

今からでも予約は多分大丈夫。
ショウの為に、本日スタジオで17:00-18:00開講予定だった武術のクラスは休講となるので、代わりに、面白い文献をシェアしたいと思います。

私の学んでいる古武術は、大師匠が戸隠流忍術34代宗家である為に、よく、忍術と呼ばれるんですね。

※写真は今年2016年夏号の千葉ウォーカー、7月現在発売中
「忍」という字をよく見てみると、「心」に「刃」が刺さっているようにも、刃の下に心を隠しているようにも見えます。刺さっていれば、痛いはずだけれど、貫かれた心は安定していて、まったく動じません。そこにあるのは、痛みに耐える「忍耐」ではなく、痛みさえも感じない、つまり、心が動揺しないことこそ、本当の「忍」の境地であり、古人はこの字を通じて私たちに伝えたかったのかもしれないと、ある方がネットで書き記してくださっていました。
中国でも昔から「忍」の精神が語り継がれてきたそうです。
なるほどと思えるお話を
忍と検索して見つけたので、シェアします。
『漢の時代、劉邦の大将軍をつとめた韓信という名将は、小さい時から「忍」の精神が並の人ではなかったという。彼は少年時代から武術をたしなみ、武術者としていつも剣をさげていた。ある日、彼が街を歩いていると、ならず者が道の真ん中で仁王立ちして韓信に、「お前は偉そうに剣をさげているが、人を殺す勇気があるのか。殺せるものなら、俺の頭を切り落としてみろ。殺す勇気がなければ、俺の股下をくぐって行け」と挑発した。韓信は周囲のあざけりの中、本当にその股下をくぐった。どんな時も衝動に煽られず、「忍」という動じない心を持っているからこそ、後に偉業を成し遂げたのだと後世は彼を讃える。
また、安徽省の九華山で大興和尚が修行していたときのことである。ある日、突然お寺に大勢の人が押し寄せ、和尚を激しく殴り罵った。実は山の麓の村で、地主の娘が結婚前に出産し、父親が激怒し「相手は誰だ」と問い詰めたところ、娘がとっさに「大興和尚」と答えたのだ。地主は村の人々を連れて、けりをつけに来たわけで、生まれたばかりの赤子も和尚に押し付けていった。ほどなくして噂が広まり、かつて尊敬を集めていた和尚は、一気に罵りの的となってしまった。しかし、赤子を育てるため和尚は毎日恥に耐え、ミルクと食べ物をもらいに村まで来ていた。このように、日々の屈辱に耐えながら、赤子を育て上げた。
数年後のある日、突然お寺にまた地主達がやって来た。和尚が笑って、「ずっとお待ちしておりました」と。実は地主の娘は、ある書生と密かに誓いを結び身ごもったが、父親には和尚の子だと偽った。功なり名上げた書生が求婚に来て、娘はようやく真相を父親に告げた。地主は和尚の許しを請うたが、「怒ったことがないのに、何を許せと?子供を連れて行きなさい」と静かに答えた。
孔子の言葉に、「小忍ばざれば則ち大謀を乱る」(小さな事を我慢できないようでは、大きなことを成し遂げることは出来ない)がある。辱められても、勇気を持って耐え、動揺しない。刃が刺されても動じない。そういう修養と意志、真の意味での「忍」の心を持ちたいもの。』
というふうに、書かれていました。
私達は稽古中に、不動心、なんていう言葉をよく耳にするのですが、通じるものがあります。
武道とは、頭で哲学し、心と心で話し合い、身体と身体で相手と自分を知る、
私にとっては船と碇、旅を共にする船上員達との分かち合いに近いかもしれません。
ベリーダンスは?というと、船の帆が風にはためいて、追い風を一身に受けて、美しいなと思う瞬間や、船の上で聞く音楽、また、立ち寄った港での楽しいダンスや語らいそのものです。
人生という旅を、彩って楽しく、美しく、笑顔にしてくれるものは、私の愛する船であり、港です。
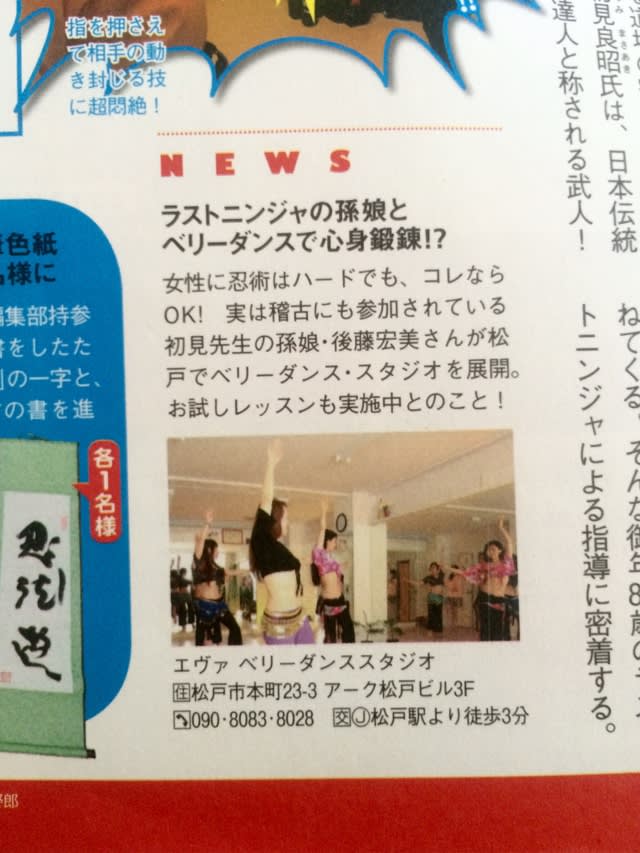
明日日曜は11:45から、3レッスン、しっかりみなさんと頑張りますので、
どうぞ、よろしくお願いいたします。
宏美















