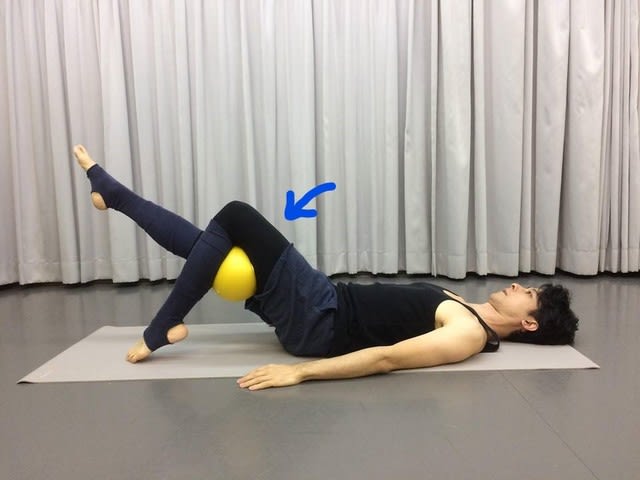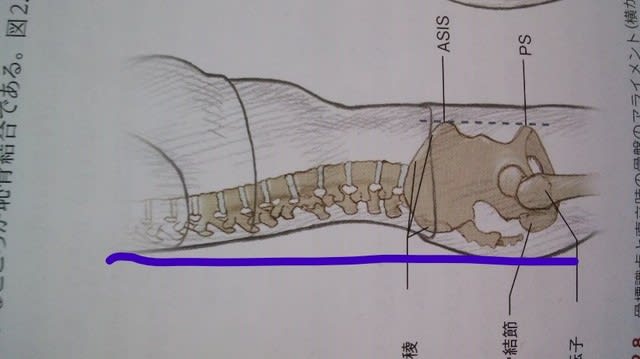今年も残すところ、あと数時間となりました。
三鷹ではクラスを始めて2年目となりますが、今年も昨年同様、
感じること、学ぶことの多い一年でした。
今年の学びをひとことで言えば、
「信頼する」ことでした。
それは単に人間同士の信頼という以上に、
身体の持っている時間、大げさに言えば命の時間に対する信頼、
だったのだと思います。
お仕事が忙しい日常のさなかにあって、定期的にクラスを受けて
身体を調整することが生活のおおきな支えになっている、という
ご意見もいただきました。
また、クラスにはなかなか来られないけれど、
「やっておくと身体が変わるから」と、数か月に一度でも
続けていらっしゃるという方もいます。
それぞれの生活のサイクルのなかで、身体の変化を丁寧に
感じとりながらクラスを受け、また日常の中でそれを生かして
いくこと。
ひとりひとりに、それぞれのペースがあるんだな、、、と
実感させていただいた一年でした。
皆様にとってどうか来年も良い年になりますよう、願っております!



三鷹ではクラスを始めて2年目となりますが、今年も昨年同様、
感じること、学ぶことの多い一年でした。
今年の学びをひとことで言えば、
「信頼する」ことでした。
それは単に人間同士の信頼という以上に、
身体の持っている時間、大げさに言えば命の時間に対する信頼、
だったのだと思います。
お仕事が忙しい日常のさなかにあって、定期的にクラスを受けて
身体を調整することが生活のおおきな支えになっている、という
ご意見もいただきました。
また、クラスにはなかなか来られないけれど、
「やっておくと身体が変わるから」と、数か月に一度でも
続けていらっしゃるという方もいます。
それぞれの生活のサイクルのなかで、身体の変化を丁寧に
感じとりながらクラスを受け、また日常の中でそれを生かして
いくこと。
ひとりひとりに、それぞれのペースがあるんだな、、、と
実感させていただいた一年でした。
皆様にとってどうか来年も良い年になりますよう、願っております!