
暇なわけではないのだけれど、先生から「こういうモノ」が欲しいと言われるとついついムキになってしまいます。ムキになっているというよりは趣味の世界に行ってしまっていると言うべきか。もともと何かを作ったり修理することが好きなので、安易に業者さんに出す前に自分で分解してしまいます。手に負えなければ業者さんへお願いするし、直れば修繕費が浮くので別のところに予算をまわせます。年末や年度末の定型業務が忙しい時期は無理ですが、時間に余裕がある時期は極力そのようにしています。
それで今回は何を作っていたかというと5・6年の理科で使う電磁石の材料なのですが、4㎝のアクリルパイプの両端にエナメル線が通る穴をあけ、そこの穴からエナメル線を通してパイプに巻いてコイルをつくり電磁石にするわけです。
1メートルのアクリルパイプを4㎝ずつに切断して25本、7本買ったから全部で175個つくったことになります。このアクリルパイプを切るためにも試行錯誤しました。まずは刃物を使って切り込みを入れてポキッと折る方法、カッターナイフ・剪定バサミ・ニッパー・ペンチ・金鋸・目立てヤスリ色々試して、一番割れが少ないのはカッターナイフだったのでしばらくはそれでやりました。でも切り込みを付けるために何度も刃をあてて転がして、それでも折るときに割れたり切り込みどおりに割れなかったり。穴をあける作業も初めはドリルを使おうとしたけれど滑るし割れるしで全然ダメでした。そんなわけではじめに使った学級は時間的に間に合わなかったので穴なしで巻くことに。両端はテープで止めることにしたそうですがテープが剥がれたりうまく止まってなかったりで大変だったとのこと。やはり穴は必要だということでどうやってあけるか思案していました。
偶然事務室に来た先生から「焼いた釘とかであけたら」というアドバイスをもらって、ハンダゴテに釘を取り付けて見ることにしました。写真のとおりなのですが釘1本だと不安定なので2本取り付けて見ました。もう一つのネジにはカッターナイフの刃を取り付けてみました。これがうまく行って作業効率と仕上がりが格段に上がりました。穴あけ作業は一発で割れることなくきれいな穴が開き、切断もカッターで一転がしすれば力を加えなくてもきれいに折れて後半50個の仕上がりが一番良かったです。モノを作るためにはそれなりの道具が必要だと思った出来事でした。
事務室に「あれが欲しい」「これが欲しい」とやってくるこの先生には実は一つのこだわりがあります。それはセット教材を使わないということ。セット教材だと作ることにだけ集中してしまい学びが薄いのだと言う。確かに電磁石の単元だとモーターカーみたいなやつが多くプラモデルとそう変わらなかったりする。タダでさえ忙しく理科専科でもない場合、セット教材が先にありきで自分で調達しようなどとは考えないだろう。ところがこの先生の場合、子どもたち自身がアクリルパイプにエナメル線を巻き芯の部分に鉄釘・銅釘・アルミ芯を入れて磁石になるかどうか実験する。巻き方も子どもたちの性格が出て面白いしそれが磁力にも影響することでしょう。たくさんの学びがあって考えるだけでもワクワクします。
この先生はセット教材が嫌い。そしてオレはセット教材だと保護者負担となるので、できる限り教科の予算(公費)で材料を購入し教材を準備して保護者負担を減らしたい。それぞれの思いが一致しているから労を惜しまないのです。そういう意味では良い先生と出会えたなぁと思っています。子どものひらめきや発見、その瞬間の目の輝きを大事にしたいしそういう学校であって欲しいと願っています。
それで今回は何を作っていたかというと5・6年の理科で使う電磁石の材料なのですが、4㎝のアクリルパイプの両端にエナメル線が通る穴をあけ、そこの穴からエナメル線を通してパイプに巻いてコイルをつくり電磁石にするわけです。
1メートルのアクリルパイプを4㎝ずつに切断して25本、7本買ったから全部で175個つくったことになります。このアクリルパイプを切るためにも試行錯誤しました。まずは刃物を使って切り込みを入れてポキッと折る方法、カッターナイフ・剪定バサミ・ニッパー・ペンチ・金鋸・目立てヤスリ色々試して、一番割れが少ないのはカッターナイフだったのでしばらくはそれでやりました。でも切り込みを付けるために何度も刃をあてて転がして、それでも折るときに割れたり切り込みどおりに割れなかったり。穴をあける作業も初めはドリルを使おうとしたけれど滑るし割れるしで全然ダメでした。そんなわけではじめに使った学級は時間的に間に合わなかったので穴なしで巻くことに。両端はテープで止めることにしたそうですがテープが剥がれたりうまく止まってなかったりで大変だったとのこと。やはり穴は必要だということでどうやってあけるか思案していました。
偶然事務室に来た先生から「焼いた釘とかであけたら」というアドバイスをもらって、ハンダゴテに釘を取り付けて見ることにしました。写真のとおりなのですが釘1本だと不安定なので2本取り付けて見ました。もう一つのネジにはカッターナイフの刃を取り付けてみました。これがうまく行って作業効率と仕上がりが格段に上がりました。穴あけ作業は一発で割れることなくきれいな穴が開き、切断もカッターで一転がしすれば力を加えなくてもきれいに折れて後半50個の仕上がりが一番良かったです。モノを作るためにはそれなりの道具が必要だと思った出来事でした。
事務室に「あれが欲しい」「これが欲しい」とやってくるこの先生には実は一つのこだわりがあります。それはセット教材を使わないということ。セット教材だと作ることにだけ集中してしまい学びが薄いのだと言う。確かに電磁石の単元だとモーターカーみたいなやつが多くプラモデルとそう変わらなかったりする。タダでさえ忙しく理科専科でもない場合、セット教材が先にありきで自分で調達しようなどとは考えないだろう。ところがこの先生の場合、子どもたち自身がアクリルパイプにエナメル線を巻き芯の部分に鉄釘・銅釘・アルミ芯を入れて磁石になるかどうか実験する。巻き方も子どもたちの性格が出て面白いしそれが磁力にも影響することでしょう。たくさんの学びがあって考えるだけでもワクワクします。
この先生はセット教材が嫌い。そしてオレはセット教材だと保護者負担となるので、できる限り教科の予算(公費)で材料を購入し教材を準備して保護者負担を減らしたい。それぞれの思いが一致しているから労を惜しまないのです。そういう意味では良い先生と出会えたなぁと思っています。子どものひらめきや発見、その瞬間の目の輝きを大事にしたいしそういう学校であって欲しいと願っています。















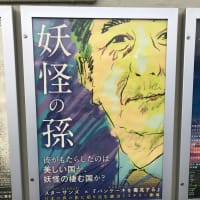










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます