岩波新書の「生活保護を考える」という本を購入しようと思って本屋に入ったら売ってなくて、代わりに「生活保護vs子どもの貧困」(PHP新書)という本があったので買ってみました。PHPはあまり好きではありませんがこの本は現場のケースワーカーや自立支援に携わる人の生の声や良心を感じることができる良い本でした。
著者の大山典宏さんは埼玉県志木市福祉事務所のケースワーカー、所沢児童相談所の児童福祉司を経て埼玉県社会福祉部福祉課で生活保護受給者の自立支援を担当し生活保護受給者チャレンジ支援事業(愛称:アスポート)に関わっている方のようで、現場の方の文章なので読みやすく一気に読んでしまいました。
前半の第5章まで生活保護に関する二つの論調を現場で働く中立的な立場で整理されています。2006年以降生活保護に対する世論は派遣村~反貧困と機を同じく政権交代がおこりマスコミが取り上げ、震災以降波が引いていくようにマスコミが取り上げなくなり、今度は揺り戻しのように生活保護バッシングへ移っていく世論のうつろいを分析しています。その世論誘導にNHKが大きく絡んでいたような気がしてなりません。2006年のNHKスペシャル『ワーキングプア』で貧困問題を取り上げ、2011年の震災後には『生活保護3兆円の衝撃』でバッシングをする。そして2012年にお笑い芸人の母親が生活保護を受給していたことを自民党の片山さつきがとりあげ世論が生活保護バッシングに流れた、あるいは関心が薄れたように記憶しています。
この生活保護をめぐる二つ論調を著者は「人権モデル」と「適正化モデル」とい表現を使って説明します。「人権モデル」は利用者(弱者)の立場に立って漏給や水際作戦を問題にし、貧困の原因は社会構造にあり公助を強調する立場。もう一方の「適正化モデル」では納税者の立場で濫給を問題にし貧困の原因は個人にあり、自助・共助を強調する立場でそれぞれの主張を分析していきます。
さらに具体的に「適正化モデル」に立つ財務相と、「人権モデル」に立つ日弁連の主張を比較分析していきます。どちらの主張も正しくどこまで行っても平行線で、揺れ動く世論の中で人手不足の福祉の現場で働く労働者の苦悩も垣間見えます。
双方の主張を踏まえた上で、著者は合意できる一致点を探る「統合モデル」という立場に立ちます。そして「生活保護」ではなく「貧困」そのものに注目し、とりわけ子どもの貧困解消という局面で一致点を見いだそうと主張します。生活保護受給者の中には、昼間から酒を飲んでパチンコに費やしてしまうような人が存在することも事実でしょう。しかし、だからと言って保護を廃止しても何も解決しません。もし保護を廃止すれば、その人に残された選択肢は、死ぬか、刑務所か、ホームレスか、精神病院かの四択になります。そして刑務所や精神病院は生活保護よりもコストがかかるから結局生活保護で初期段階で投資をして自立させて納税者になってもらうことが最良の手段であると言います。そういうスタンスで住宅支援の恒久化、就労支援、子ども・若者に対する支援など「貧困の連鎖」を断ち切るための施策の重要性を主張しています。
そして子どもの貧困対策として埼玉県の生活保護受給者チャレンジ支援事業(愛称:アスポート)の学習支援の取り組みを紹介しています。似たような取り組みが高知市、釧路市、熊本県、神奈川県など全国94自治体で行われているそうです。社会保障はコストではなく未来への投資であるという主張に共感しました。
第7章ではNPO法人キッズドアのタダゼミと呼ばれる、保護家庭の子ども達が「貧困の連鎖」を断ち切り自立させる教育支援の事例や、NPO法人ワーカーズコープの就労支援の事例を紹介しています。
残念ながら子どもの貧困対策はここまでで最終章では生活保護の話題に戻り、厚生労働省の政策や財源の論点に移ってしまいます。できればもっと子どもの貧困対策という一致点で学校の役割や保護者負担のこと、教育行政との連携まで踏み込んだ未来への投資について掘り下げられたらよかったと感じました。
それともう一つの論点として、ワーキングプア→生活保護という単層のセーフティネットだけでなく複層のセーフティネットや、根本の雇用環境の改善こそが必要なのではないでしょうか。
著者の大山典宏さんは埼玉県志木市福祉事務所のケースワーカー、所沢児童相談所の児童福祉司を経て埼玉県社会福祉部福祉課で生活保護受給者の自立支援を担当し生活保護受給者チャレンジ支援事業(愛称:アスポート)に関わっている方のようで、現場の方の文章なので読みやすく一気に読んでしまいました。
前半の第5章まで生活保護に関する二つの論調を現場で働く中立的な立場で整理されています。2006年以降生活保護に対する世論は派遣村~反貧困と機を同じく政権交代がおこりマスコミが取り上げ、震災以降波が引いていくようにマスコミが取り上げなくなり、今度は揺り戻しのように生活保護バッシングへ移っていく世論のうつろいを分析しています。その世論誘導にNHKが大きく絡んでいたような気がしてなりません。2006年のNHKスペシャル『ワーキングプア』で貧困問題を取り上げ、2011年の震災後には『生活保護3兆円の衝撃』でバッシングをする。そして2012年にお笑い芸人の母親が生活保護を受給していたことを自民党の片山さつきがとりあげ世論が生活保護バッシングに流れた、あるいは関心が薄れたように記憶しています。
この生活保護をめぐる二つ論調を著者は「人権モデル」と「適正化モデル」とい表現を使って説明します。「人権モデル」は利用者(弱者)の立場に立って漏給や水際作戦を問題にし、貧困の原因は社会構造にあり公助を強調する立場。もう一方の「適正化モデル」では納税者の立場で濫給を問題にし貧困の原因は個人にあり、自助・共助を強調する立場でそれぞれの主張を分析していきます。
さらに具体的に「適正化モデル」に立つ財務相と、「人権モデル」に立つ日弁連の主張を比較分析していきます。どちらの主張も正しくどこまで行っても平行線で、揺れ動く世論の中で人手不足の福祉の現場で働く労働者の苦悩も垣間見えます。
双方の主張を踏まえた上で、著者は合意できる一致点を探る「統合モデル」という立場に立ちます。そして「生活保護」ではなく「貧困」そのものに注目し、とりわけ子どもの貧困解消という局面で一致点を見いだそうと主張します。生活保護受給者の中には、昼間から酒を飲んでパチンコに費やしてしまうような人が存在することも事実でしょう。しかし、だからと言って保護を廃止しても何も解決しません。もし保護を廃止すれば、その人に残された選択肢は、死ぬか、刑務所か、ホームレスか、精神病院かの四択になります。そして刑務所や精神病院は生活保護よりもコストがかかるから結局生活保護で初期段階で投資をして自立させて納税者になってもらうことが最良の手段であると言います。そういうスタンスで住宅支援の恒久化、就労支援、子ども・若者に対する支援など「貧困の連鎖」を断ち切るための施策の重要性を主張しています。
そして子どもの貧困対策として埼玉県の生活保護受給者チャレンジ支援事業(愛称:アスポート)の学習支援の取り組みを紹介しています。似たような取り組みが高知市、釧路市、熊本県、神奈川県など全国94自治体で行われているそうです。社会保障はコストではなく未来への投資であるという主張に共感しました。
第7章ではNPO法人キッズドアのタダゼミと呼ばれる、保護家庭の子ども達が「貧困の連鎖」を断ち切り自立させる教育支援の事例や、NPO法人ワーカーズコープの就労支援の事例を紹介しています。
残念ながら子どもの貧困対策はここまでで最終章では生活保護の話題に戻り、厚生労働省の政策や財源の論点に移ってしまいます。できればもっと子どもの貧困対策という一致点で学校の役割や保護者負担のこと、教育行政との連携まで踏み込んだ未来への投資について掘り下げられたらよかったと感じました。
それともう一つの論点として、ワーキングプア→生活保護という単層のセーフティネットだけでなく複層のセーフティネットや、根本の雇用環境の改善こそが必要なのではないでしょうか。















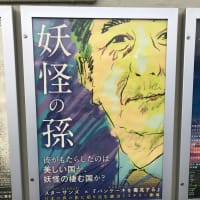










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます