南禅寺 三門で 頂いた 境内案内図です

南禅寺は 薄緑色が付いた 五ヵ所が 拝観料が要る場所ですが
拝観共通券が 無く
それぞれ 拝観したい 入口で 受付があり
別々に 拝観料を払います
三門の次は 正面にある 法堂

ここは 堂内は入れず 外からの 参拝のみです
|
創建当初の法堂は、応仁の乱の戦火で焼失 1606年(慶長11年)には豊臣秀頼の寄進によって大改修が行われたが、その建物も1893年(明治26年)に焼失 |
参拝の後 法堂の右手に 進むと

赤レンガの水路が見えます

南禅寺といえば 琵琶湖疎水が 流れる 「水路閣」が 有名
1890年、水不足に悩む京都へ、琵琶湖の疎水を運ぶために作られました。
水路閣の全長は93.2メートル。
橋の上には、現在も琵琶湖疎水の支流が流れています。
ローマの水道橋を参考に設計されており、
建設当時は南禅寺のすぐ側に洋風の橋を建てることに
批判も多かったようですが、
今では京都市指定史跡にも登録されています。
レンガ造りでレトロな建築物ですが、
和の風景にもなじむ魅力的なたたずまいです。
美しい建築物としてだけでなく、
京都の発展にも貢献している非常に大切な水路閣 と
(ネットより)


階段を上がると 疎水の流れが みえます


水を飲みにきたのでしょうか アオサギが 一羽

水路の上に 鐘楼堂

南禅院の 鐘楼堂のようです

水路をくぐった 上には 鎌倉時代 亀山天皇の
離宮禅林寺殿を 営まれた 場所で
南禅寺発祥の地 となった 南禅院があり
チケットを購入して 見学
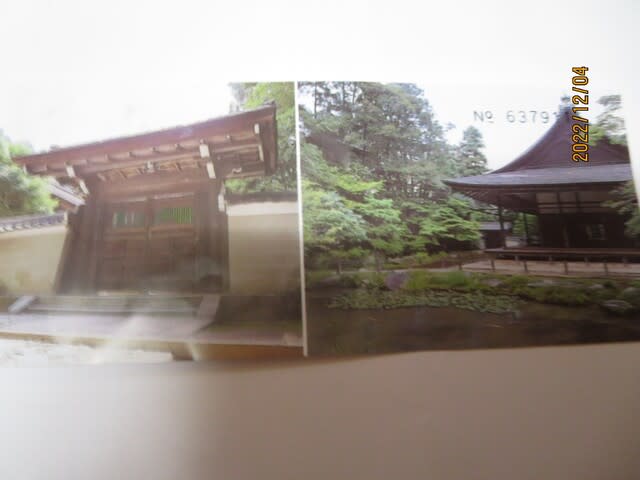
現存の建物は 元禄16年(1703)に 5代将軍徳川綱吉の母
桂昌院の寄進で 再建され
内陣中央には 亀山法皇御木像が安置されています



京都 三名勝史蹟庭園の一つに指定されている
池には 枯れ葉が 溜まっておりますが
静かな 佇まいの お庭 が 素晴らしい


池の周りの 散策順路を行くと 亀山天皇の分骨を
埋葬した御廟が 祀ってあります


池のそば この水の流れの先には

石組の滝口があり 池へと 流れ出ています



庭園観賞の後 南禅院の外に 出ると 目の前には 水路閣


東側の 水路閣を 降りて行くと 次は
法堂の後ろにある 方丈へと
続きは 又明日に
♦♫♦・*:..。♦♫♦*゚¨゚゚・*:..。♦









