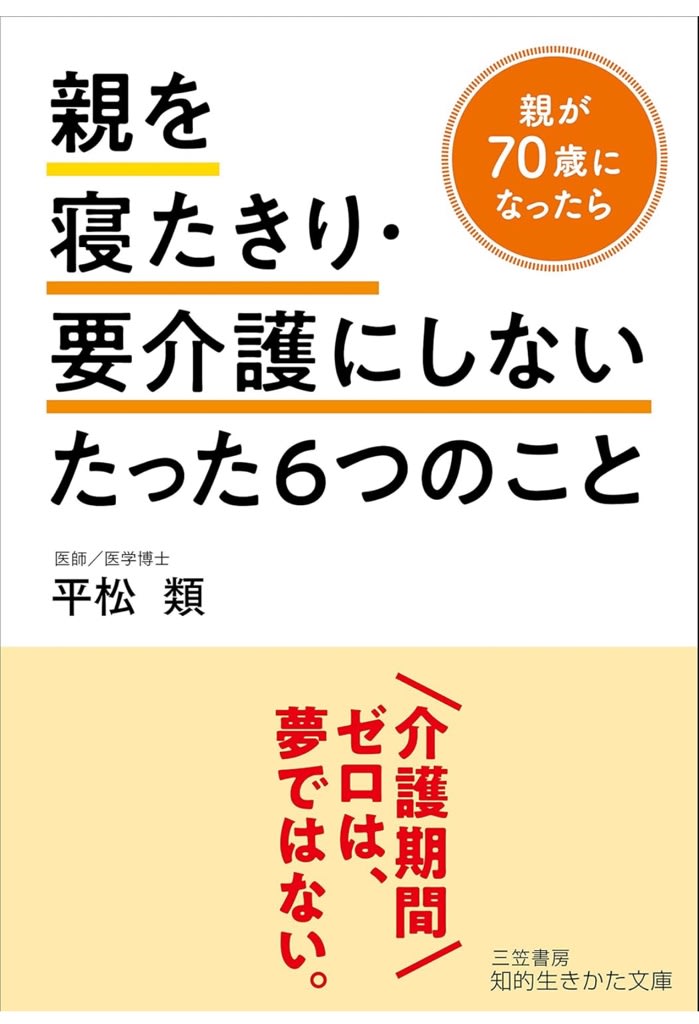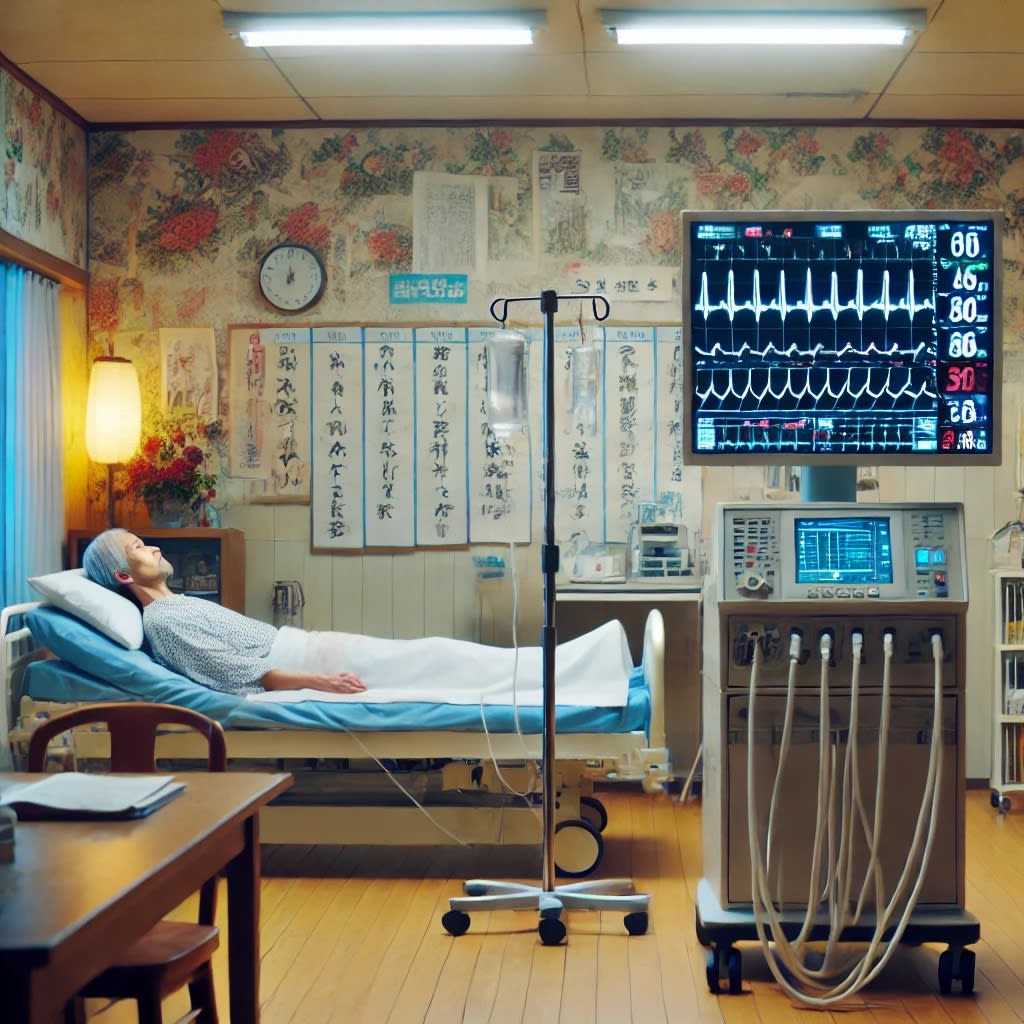
ある老人の一日(別の日)
目が覚めた。今日は何日だろうか。天井のシミを眺める。変わらない風景。だが、今日はいつもと違う気分だ。何かが重くのしかかっている。理由はわからない。ただ、胸の奥がざわついている。
看護師が来る。いつもの時間だ。
「朝ごはん、入れますね。」
淡々とした声。いつもの優しい看護師ではない。胃瘻から栄養が流れ込む感覚。もう慣れたはずなのに、今日は気持ちが悪い。
「終わり。じゃあまた。」
言葉が乱暴だ。何か嫌な感じがする。でも、私は何も言えない。言葉を発することも、表情を変えることもできない。ただ、心の中に小さな波紋が広がる。
昼前、喉が苦しくなる。
痰が絡んでいる。呼吸が詰まりそうだ。ナースコールを押せない。誰かが気づいてくれるのを待つしかない。
しばらくすると、足音が聞こえる。
「ちょっと待ってね、今やるから。」
乱暴な声。機械が押し込まれ、吸引が始まる。強引に喉の奥から痰が引き抜かれる。いつもより痛い。
「はい、終わり。苦しかったらまた呼んで。」
呼べないことを知っているくせに。そう思いながら、私は目を閉じる。
午後、背中が痒い。
だが、伝えられない。体は動かせない。声も出せない。たまらない感覚が広がる。背中の一点が熱くなり、かきむしりたくなる。だが、それは叶わない。
ただ耐えるしかない。
時計はない。時間が進んでいるのかさえわからない。ただ、痒みとともに時間が過ぎるのを待つ。
夕方、娘が来る日ではない。
誰も来ない。ただ、カーテンの隙間から見える空が少しずつ暗くなっていく。
不安な気分が押し寄せる。理由はわからない。突然、胸が締めつけられるような感覚に襲われる。寂しいのか、怖いのか、怒りなのか、自分でもわからない。ただ、言葉にならない感情が渦を巻く。
こんなとき、誰かに話しかけてほしい。だが、誰も来ない。私は目を閉じ、ただやり過ごすしかない。
夜、眠れない。
隣の部屋から叫び声がする。
「やめろ! やめろ!」
男の声。怒鳴り声が響く。
「うるさいよ! もう寝なさい!」
看護師の声がする。だが、収まる気配はない。
私はただ天井を見つめる。声が響くたびに、胸がざわつく。眠れない。
背中はまだ痒い。喉も違和感がある。何かがおかしい。何かが足りない。何かを訴えたい。でも、何もできない。
天井を見つめながら、朝が来るのを待つしかなかった。