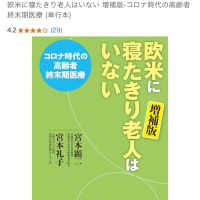ある老人の一日
目が覚めた。天井を見つめる。今日も、昨日と同じように朝が来た。カーテンの隙間から差し込む光で、朝だとわかる。時計はないが、決まった時間に決まったことが起こる生活だから、体の感覚だけで時間がわかるようになった。
しばらくすると、ドアが開く音がした。看護師が入ってくる気配がする。
「おはようございます。今日も変わりないですか?」
優しい声。私は返事をすることはできない。ただ、視線を向けることで「聞こえている」ことを伝える。
看護師は手際よく胃瘻からの栄養を注入し始める。朝食だ。口から食べることはもうできない。噛むことも、味わうことも、とうの昔に忘れてしまった。ただ、腹は満たされる。それだけのことだ。
「終わりましたよ。また後で来ますね。」
看護師はそう言って部屋を出ていく。静寂が戻る。
昼前、喉が苦しくなる。
痰が絡んでいる。だが、自分ではどうすることもできない。息が詰まりそうになる。苦しい。体も動かせない。声も出せない。ただ、目を動かし、呼吸を荒くする。それに気づいた誰かがナースステーションへ知らせてくれるのを待つしかない。
どれくらい時間が経っただろうか。足音が近づき、看護師がやってくる。痰の吸引が始まる。機械の音とともに、喉の奥の苦しさが少しずつ消えていく。
「楽になりましたね。」
私はただ瞬きをする。
昼の栄養が入る。午後は何もない日だ。テレビをつけられても、頭には入らない。ただ、画面の明かりと、人の声があるだけで少し安心する。
夕方、待ち望んだ時間が来る。
娘が面会に来る日だ。週に一度、一時間だけ。それが、私にとってこの一週間で一番の楽しみ。
「お父さん、来たよ。」
彼女はそう言って、手を握る。私はそれに応えようとするが、指をわずかに動かせるだけだ。それでも娘は気づいてくれる。
「今日は孫が学校でね……」
彼女は優しく話し続ける。私はじっと耳を傾ける。何も言えない、何も動かせない。それでも、娘の声を聞いているだけで、心が満たされる。
「また来週来るからね。」
そう言って、娘はもう一度手を握る。その温もりをしっかり感じながら、私はまばたきで「またね」と伝えた。
夜。
最後の栄養が入る。看護師がオムツを替え、体の向きを変えてくれる。もう慣れたものだ。
消灯。部屋は静寂に包まれる。再び天井を見つめる。
明日も、また同じように朝が来るのだろうか。
そんなことを考えながら、ゆっくりと瞼を閉じた。
実際はどうなのか?想像の域を超えていないのでわかりません。自分はこの状況になるのは嫌なので、そうならないように対策を考えています。
寝たきり老人のある一日。