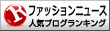「変法通議の論不変法之害」で日本に触れた箇所があります。
「論不変法之害 略 今夫日本 幕府專政 諸藩力征
受 俄(=露)德(=独)美(=米)大創 国几不国
自明治維新 改弦更張不三十年而 奪我琉球 割我台湾也」
(維基文庫 変法通議 論不変法之害 梁啓超 1896/08/19)
素敵で優れもの、Gemini日本語訳は
「今、日本の幕府の専制政治のもと、諸藩がそれぞれに力を誇示し、ロシア、ドイツ、
アメリカから大きな打撃を受け、国がほとんど国でなくなった状態であった。
明治維新以降、わずか30年で、日本は私たちの琉球を奪い、台湾を割譲したのである。」
現代語訳は
「今、日本の幕府が独裁政治を行い、各藩がそれぞれに力を誇示し、ロシア、ドイツ、
アメリカといった列強から大きなダメージを受け、国が滅亡の危機に瀕していた。
明治維新以降、わずか30年で、日本は私たちの琉球を奪い、
台湾を割譲するという行為に及んだのである。」《有難山の鳶烏》
梁啓超は「琉球」を奪取「台湾」を清王朝から譲り受けたと決めつけています。
英明な彼でも、この時点では、かように考えていたのです。
これにはちょいと聞き捨てならないので、史実に基づいて展開してみます。
「琉球」について、これには「日清修好条規」が絡みます。
1868年M01/09/08「一世一元の詔(明治改元の詔)」
1871年M04/07/29日清修好条規 調印(下記条文は旧字を新字体に変更 下漢文)
第一条
此後大日本国と大清国は弥(いよいよ)和誼(わぎ)を敦くし天地と共に窮まり無るへし
又両国に属したる邦土も各(おのおの)礼を以て相待ち聊(いささかも)侵越する事なく
永久安全を得せしむへし
嗣後大清国大日本国 被敦和誼 与天壤無窮 即両国所属邦土 亦各以礼相待
不可稍有侵越 俾獲永久
第二条
両国好(よしみ)を通せし上は必す相関(かんせつ)切す
若し他国より不公及ひ軽藐(けいびょう)する事有る時其知らせを為さは
何れも互に相助け或は中に入り程克く取扱ひ友誼を敦くすへし
両国既経通好 自必互相関切 若他国偶有不公及軽藐之事 一経知照
必須彼此相助 或従中善為調処 以敦友誼
(データーベース「世界と日本」〈代表:田中明彦〉日本政治・国際関係データーベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所 大日本国大清国修好条規 漢文)
第二条以下、第十八条までありますがそちらは端折ります。
第六条だけ「両国の交渉には漢文を用い、和文を用いるときには漢文を添える」と。
続く。
「論不変法之害 略 今夫日本 幕府專政 諸藩力征
受 俄(=露)德(=独)美(=米)大創 国几不国
自明治維新 改弦更張不三十年而 奪我琉球 割我台湾也」
(維基文庫 変法通議 論不変法之害 梁啓超 1896/08/19)
素敵で優れもの、Gemini日本語訳は
「今、日本の幕府の専制政治のもと、諸藩がそれぞれに力を誇示し、ロシア、ドイツ、
アメリカから大きな打撃を受け、国がほとんど国でなくなった状態であった。
明治維新以降、わずか30年で、日本は私たちの琉球を奪い、台湾を割譲したのである。」
現代語訳は
「今、日本の幕府が独裁政治を行い、各藩がそれぞれに力を誇示し、ロシア、ドイツ、
アメリカといった列強から大きなダメージを受け、国が滅亡の危機に瀕していた。
明治維新以降、わずか30年で、日本は私たちの琉球を奪い、
台湾を割譲するという行為に及んだのである。」《有難山の鳶烏》
梁啓超は「琉球」を奪取「台湾」を清王朝から譲り受けたと決めつけています。
英明な彼でも、この時点では、かように考えていたのです。
これにはちょいと聞き捨てならないので、史実に基づいて展開してみます。
「琉球」について、これには「日清修好条規」が絡みます。
1868年M01/09/08「一世一元の詔(明治改元の詔)」
1871年M04/07/29日清修好条規 調印(下記条文は旧字を新字体に変更 下漢文)
第一条
此後大日本国と大清国は弥(いよいよ)和誼(わぎ)を敦くし天地と共に窮まり無るへし
又両国に属したる邦土も各(おのおの)礼を以て相待ち聊(いささかも)侵越する事なく
永久安全を得せしむへし
嗣後大清国大日本国 被敦和誼 与天壤無窮 即両国所属邦土 亦各以礼相待
不可稍有侵越 俾獲永久
第二条
両国好(よしみ)を通せし上は必す相関(かんせつ)切す
若し他国より不公及ひ軽藐(けいびょう)する事有る時其知らせを為さは
何れも互に相助け或は中に入り程克く取扱ひ友誼を敦くすへし
両国既経通好 自必互相関切 若他国偶有不公及軽藐之事 一経知照
必須彼此相助 或従中善為調処 以敦友誼
(データーベース「世界と日本」〈代表:田中明彦〉日本政治・国際関係データーベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所 大日本国大清国修好条規 漢文)
第二条以下、第十八条までありますがそちらは端折ります。
第六条だけ「両国の交渉には漢文を用い、和文を用いるときには漢文を添える」と。
続く。