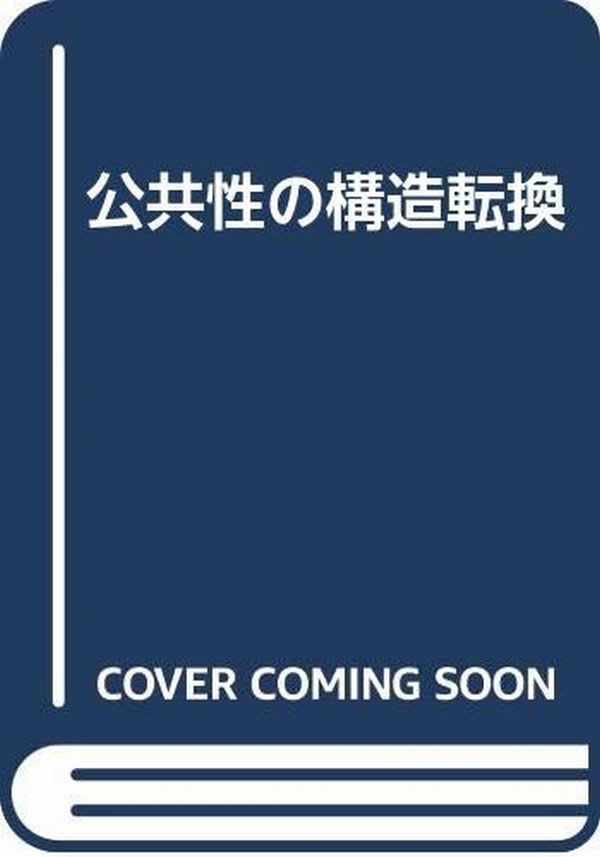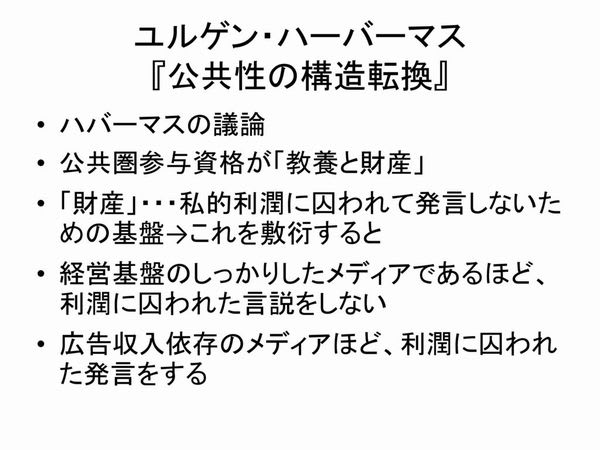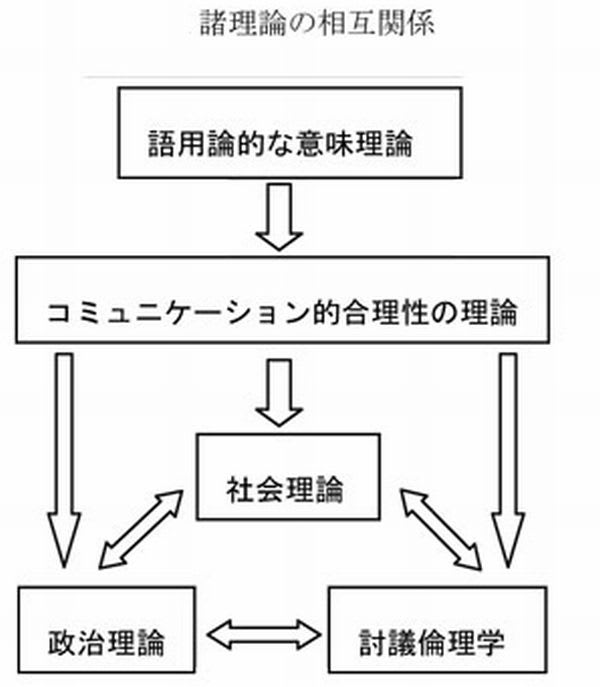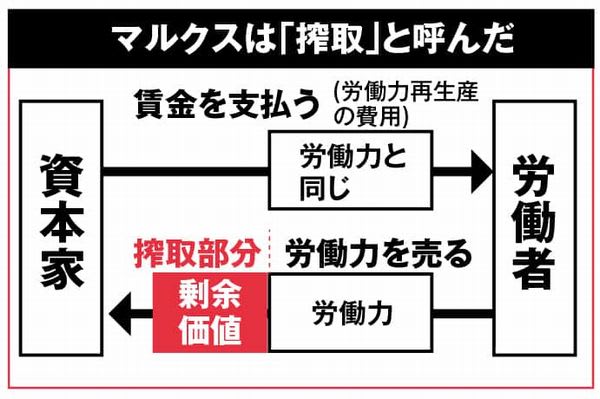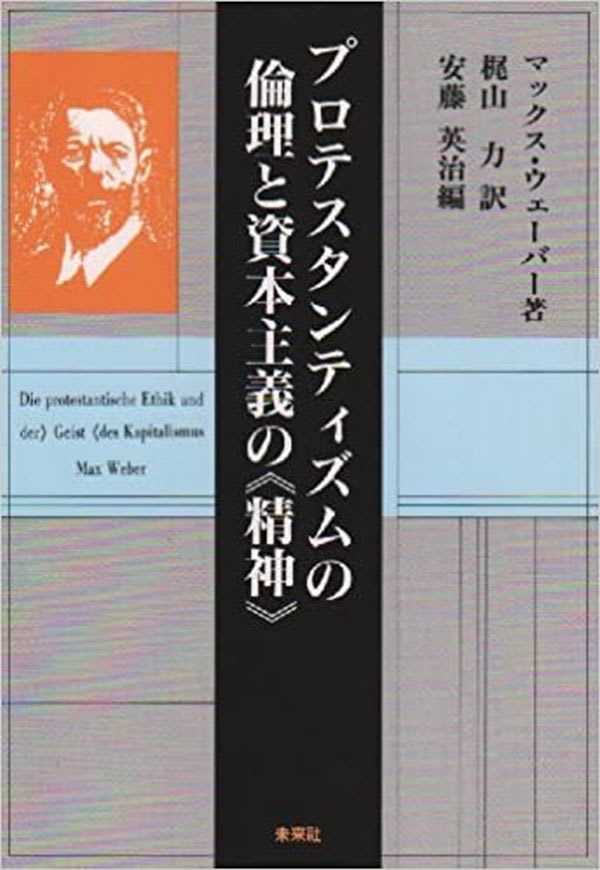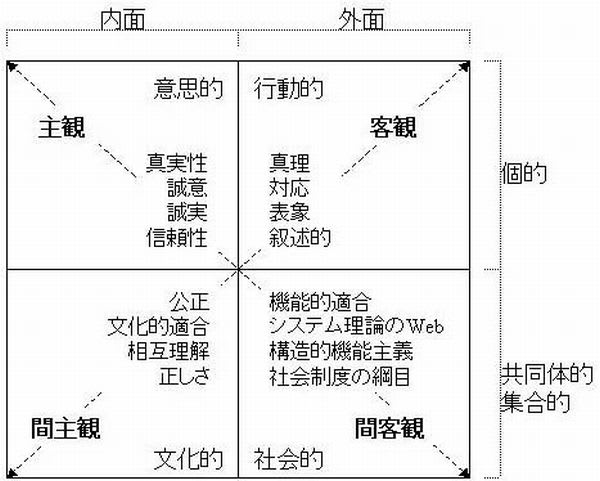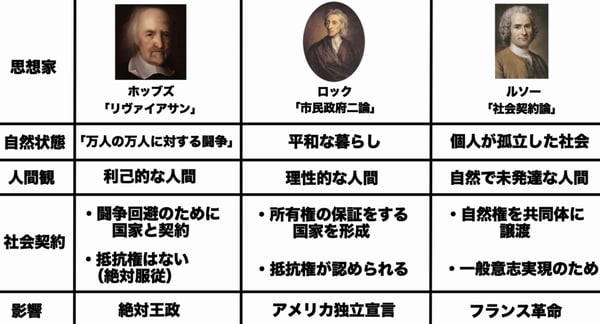🌸 相手の心を打つ「名フレーズ」(3)
⛳『人間の知と力は合一する
⛳『人間の知と力は合一する
原因が知られなくては結果は生じないからである』(ベーコン)
☆「人間は知識を得ることで、問題を克服する力を得る
原因がわからないと、結果が分析できないから」
☆ベーコンの知識を修得する術「帰納法」
*個別的な現象を一歩一歩段階的に吟味していく方法を説く
*結果より、一般的な原則を導き出す
*具体的な事例に当てはめていく
☆帰納法を行うためには
*人間が抱きがちな予断や偏見を排除するのが必要
*ベーコンはそれを「イドラ」と呼ぶ
⛳『心は、いってみれば、文字をまったく欠いた白紙で、
観念は少しもないと想定しよう』(ロツク)
⛳『心は、いってみれば、文字をまったく欠いた白紙で、
観念は少しもないと想定しよう』(ロツク)
☆「経験が心を強くする」
☆人間は経験を重ねるごとに成長していく
*より知性を備えた存在へと成長する
*経験をすることが大事で、経験が私たちを強くする
⛳『汝の意志の格率が、
常に立法の普遍的な原則に合致するよぅに行為せよ』(カント)
☆「誰もが納得してくれる基準で行為せよ」
☆人間に欲望がある限り、常に誘惑がある
*だからといって欲望に負けていいとはならない
☆カントは、正しい行いをするのは人間の義務だと言う
☆人間には自由があるとするが
*自由とは、自分で自分を律する自由である
*人間は自分で欲を抑えることができる
*盗めるのに、自由を行使して盗まないのが、人間の素晴らしさ
⛳『理想的なものは現実、現実的なものは理性的』(ヘーゲル)
⛳『理想的なものは現実、現実的なものは理性的』(ヘーゲル)
☆「理想と現実が一致するように努力せよ」
☆ヘーゲルは、理性を理想的なものと称えている
☆理想と現実には常には乖離があり、その溝はなかなか埋まらない
*ただ闇雲に理想を追い求めるのも、現実を直視しない無謀な態度
*両者が常に一致するよう「努力すべき」だと訴えた
*両者が常に一致するよう「努力すべき」だと訴えた
☆ヘーゲルの主張
*理想と現実の両方ともを互いの方向に引き寄せるよう努力が必要
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
⛳出典、『教養としての哲学』



相手の心を打つ「名フレーズ」(3)
(ネットより画像引用)