どんな仕事でもそうだが、特に資格が必要な仕事において、その専門性を高めるために自らの意志で自腹を切って学んでいる人というのはどれくらいいるのだろうか。
私は保育関係の仕事5年間、介護関係の仕事6年間の経験があるが、保育関係では自腹を切って学ぶということがほとんどなかった。職場での勉強会や仕事の一環としての外部研修への参加、やや強制的な書籍の購入はあったが、自ら保育に関する書籍を購入したり、外部の研修に参加したりということはなかった。休日はもっぱら気晴らしに費やした。
行政との関係や虐待に関することなど、わからないことは多かったが、積極的に「知ろう」「学ぼう」という気力に乏しく、その日その日の仕事に追われ流されていくというかんじで、人間関係に疲れ、保育の仕事そのものに興味を失ってしまった。
その後なんとなくの流れで介護の仕事につき、そこで初めて自ら学ぶという経験を得た。保育の仕事に比べてあまりにもヒマであり、時間が有り余り勉強する時間があったのと、なぜこんなにもヒマなのか?という疑問に対する答えを知りたかったのが学ぶ直接のきかっけだった。
書籍をひもとくまでもなく、ヒマな理由はすぐにわかった。画一的な介護と身勝手な介護の解釈が一体となって、職員のヒマ状態が生じていた。
私が最初に勤務したのは「ユニット型」と称される特別養護老人ホームである。全室個室で9~10人で1つのグループを形成しており、10グループあった。「少人数的で家庭的」であるとして、厚労省が推進して当時大流行であった。従来型の特養からやってきた介護職員などはユニット型に勤務しているというだけで、画期的なすばらしい介護をしていると思い込んでおり、従来型の特養に対し根拠なき優越感を持ち、いかにユニット型施設がすばらしいかということを機会あるごとに聞かされた。
私の目には「家庭的」を錦の御旗に、最低限の身体介護さえしない職務放棄とうつるものが多かった。
コミュニケーションの時間が取れないからおむつ交換の回数を減らそう、という意見が堂々と述べられていた。
……
こんなことを延々と書くつもりじゃなかった!
研修だ。専門性を向上させるための自らの学びについてだった。
とにかくヒマで、介護福祉士の国家試験を受けるには3年も働かなきゃいけないっていうんで、福祉住環境コーディネーターなるものを取ってみたり、介護の本を買って読んだりした。外部研修のお知らせが掲示板に貼られていたので申し込んだら、自分でお金を出さなきゃいけないこと、勤務時間ではなく公休を使って参加することなどを念を押され、不思議そうに申込書を渡された。事務方からは「変わった人」と思われたようだ。
職場からあてがわれた研修はつまらないもの、くだらないものがほとんどであったが、多少おもしろいと思ったものでも復命書を提出した時点で記憶から消えてる。
その後県外の研修にも参加するようになり、全国の介護関係者と話をすることもできた。今でも忘れられない思い出であり貴重な体験であったと思います。
ではまとめます。
あてがわれたものをありがたいと思う人間っているんでしょうか?もしいるとしたら、それは奴隷根性がしみついていると思います。
あてがったものをありがたいと思わせ、かつ自主的な人材であってほしいっていうのは従業員に曲芸を求めてるってことでしょうか?
協調性があって前向きでグローバルな人材…言ってる意味をわかってるんでしょうか?
教育訓練費は企業ではなく、労働者に支払うべきと思います。
アビバやNOVAが儲かっただけってのは労働者の責任じゃないからね!
私は保育関係の仕事5年間、介護関係の仕事6年間の経験があるが、保育関係では自腹を切って学ぶということがほとんどなかった。職場での勉強会や仕事の一環としての外部研修への参加、やや強制的な書籍の購入はあったが、自ら保育に関する書籍を購入したり、外部の研修に参加したりということはなかった。休日はもっぱら気晴らしに費やした。
行政との関係や虐待に関することなど、わからないことは多かったが、積極的に「知ろう」「学ぼう」という気力に乏しく、その日その日の仕事に追われ流されていくというかんじで、人間関係に疲れ、保育の仕事そのものに興味を失ってしまった。
その後なんとなくの流れで介護の仕事につき、そこで初めて自ら学ぶという経験を得た。保育の仕事に比べてあまりにもヒマであり、時間が有り余り勉強する時間があったのと、なぜこんなにもヒマなのか?という疑問に対する答えを知りたかったのが学ぶ直接のきかっけだった。
書籍をひもとくまでもなく、ヒマな理由はすぐにわかった。画一的な介護と身勝手な介護の解釈が一体となって、職員のヒマ状態が生じていた。
私が最初に勤務したのは「ユニット型」と称される特別養護老人ホームである。全室個室で9~10人で1つのグループを形成しており、10グループあった。「少人数的で家庭的」であるとして、厚労省が推進して当時大流行であった。従来型の特養からやってきた介護職員などはユニット型に勤務しているというだけで、画期的なすばらしい介護をしていると思い込んでおり、従来型の特養に対し根拠なき優越感を持ち、いかにユニット型施設がすばらしいかということを機会あるごとに聞かされた。
私の目には「家庭的」を錦の御旗に、最低限の身体介護さえしない職務放棄とうつるものが多かった。
コミュニケーションの時間が取れないからおむつ交換の回数を減らそう、という意見が堂々と述べられていた。
……
こんなことを延々と書くつもりじゃなかった!
研修だ。専門性を向上させるための自らの学びについてだった。
とにかくヒマで、介護福祉士の国家試験を受けるには3年も働かなきゃいけないっていうんで、福祉住環境コーディネーターなるものを取ってみたり、介護の本を買って読んだりした。外部研修のお知らせが掲示板に貼られていたので申し込んだら、自分でお金を出さなきゃいけないこと、勤務時間ではなく公休を使って参加することなどを念を押され、不思議そうに申込書を渡された。事務方からは「変わった人」と思われたようだ。
職場からあてがわれた研修はつまらないもの、くだらないものがほとんどであったが、多少おもしろいと思ったものでも復命書を提出した時点で記憶から消えてる。
その後県外の研修にも参加するようになり、全国の介護関係者と話をすることもできた。今でも忘れられない思い出であり貴重な体験であったと思います。
ではまとめます。
あてがわれたものをありがたいと思う人間っているんでしょうか?もしいるとしたら、それは奴隷根性がしみついていると思います。
あてがったものをありがたいと思わせ、かつ自主的な人材であってほしいっていうのは従業員に曲芸を求めてるってことでしょうか?
協調性があって前向きでグローバルな人材…言ってる意味をわかってるんでしょうか?
教育訓練費は企業ではなく、労働者に支払うべきと思います。
アビバやNOVAが儲かっただけってのは労働者の責任じゃないからね!












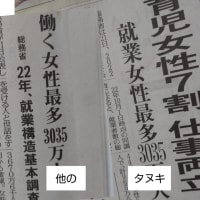
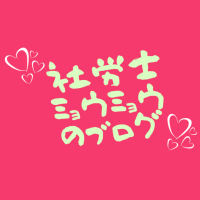
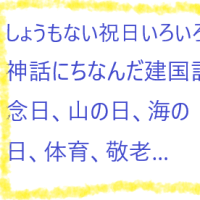




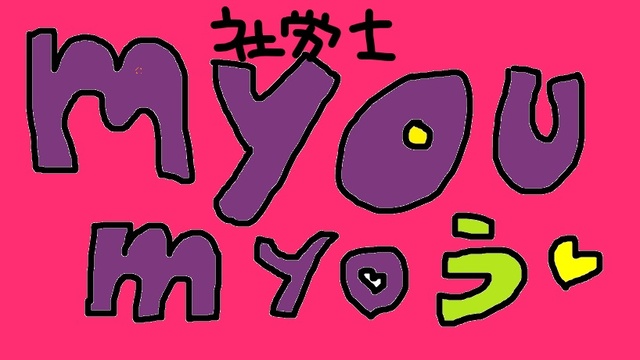

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます