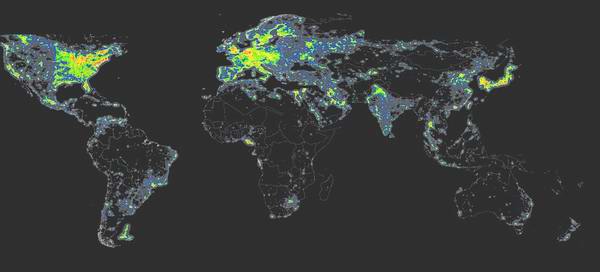昨夜、まれに見る星天の七夕でした。
旧暦の七夕とちがい、今の暦では、梅雨の時期に当たる7/7は、沖縄、北海道以外の日本各地では例年雨模様、曇り空の事が多く、織女と牽牛の逢瀬は数年~10年に一回くらいしか、星天に恵まれていません。
七夕に降る雨を催涙雨と云い、織姫と彦星が会えずに嘆く涙だとのことですが、昨夜は真夜中ごろより、すっかーんと晴れた星天で、いそいそと双眼鏡と一脚持って、かなり長い時間、天の川中心に星を眺めていました。
数日前から、近所の小さなお子さんがおられるお家では、七夕の笹飾りが飾られており、そういえば、いにしえの幼稚園児時代の私の写真にも、笹飾りを持ったカワイラシイのがあったなぁと思いだしておりました。
おそらくは、日本に住まう殆どの方が、このように小さな頃から、七夕の風習、歌、伝説に接してこられ、そのおかげで、7/7は星空観望を趣味とする方以外の、沢山の方も、夜の天気を気に掛け、冒頭に述べたように、珍しい晴れの時には、星空を見上げる、そんな星空観望の特異日、なのかもしれません。
実際に、この日のベガとアルタイル付近の星空に、普段となんら変わったところは無いのですが、それでも、こうやって七夕の伝説を思い起こし、アルビレオ、デネブをはじめとして、天の川近辺を眺めていると、なにかのイベントに遭遇している高揚感めいたものがあります。私がこんな場末のブログで稚拙な文章で諄くするまでもなく、遍く日本に拡がった星空観望の愉しみなのだと思います。
やがて、降りていくベガ、アルタイルの反対側から、天の川の星々のきらめきに負けない魅力を持つすばるが、今日は、木星、金星を従えて昇ってきます。すでにスピカは眩くきらめいています。
最後に、七夕のお願い、できれば、旧暦の七夕(ずっと星天の可能性が高い)にも夜空を見上げるような、新たな習慣ができればいいなぁと、そうすれば欲求不満の織姫と彦星が催涙雨にむせぶこともなく、星空観望の愉しみも拡がるだろうなぁと独りごちて、一旦この連載を終わります。
旧暦の七夕とちがい、今の暦では、梅雨の時期に当たる7/7は、沖縄、北海道以外の日本各地では例年雨模様、曇り空の事が多く、織女と牽牛の逢瀬は数年~10年に一回くらいしか、星天に恵まれていません。
七夕に降る雨を催涙雨と云い、織姫と彦星が会えずに嘆く涙だとのことですが、昨夜は真夜中ごろより、すっかーんと晴れた星天で、いそいそと双眼鏡と一脚持って、かなり長い時間、天の川中心に星を眺めていました。
数日前から、近所の小さなお子さんがおられるお家では、七夕の笹飾りが飾られており、そういえば、いにしえの幼稚園児時代の私の写真にも、笹飾りを持ったカワイラシイのがあったなぁと思いだしておりました。
おそらくは、日本に住まう殆どの方が、このように小さな頃から、七夕の風習、歌、伝説に接してこられ、そのおかげで、7/7は星空観望を趣味とする方以外の、沢山の方も、夜の天気を気に掛け、冒頭に述べたように、珍しい晴れの時には、星空を見上げる、そんな星空観望の特異日、なのかもしれません。
実際に、この日のベガとアルタイル付近の星空に、普段となんら変わったところは無いのですが、それでも、こうやって七夕の伝説を思い起こし、アルビレオ、デネブをはじめとして、天の川近辺を眺めていると、なにかのイベントに遭遇している高揚感めいたものがあります。私がこんな場末のブログで稚拙な文章で諄くするまでもなく、遍く日本に拡がった星空観望の愉しみなのだと思います。
やがて、降りていくベガ、アルタイルの反対側から、天の川の星々のきらめきに負けない魅力を持つすばるが、今日は、木星、金星を従えて昇ってきます。すでにスピカは眩くきらめいています。
最後に、七夕のお願い、できれば、旧暦の七夕(ずっと星天の可能性が高い)にも夜空を見上げるような、新たな習慣ができればいいなぁと、そうすれば欲求不満の織姫と彦星が催涙雨にむせぶこともなく、星空観望の愉しみも拡がるだろうなぁと独りごちて、一旦この連載を終わります。