2015年8月2日京都生まれの男の子、三代目アルファの成長日記です
ゴールデンアルファのブログ 「おいでアルファ」
あらためての記-血管肉腫と心タンポナーデ(12)
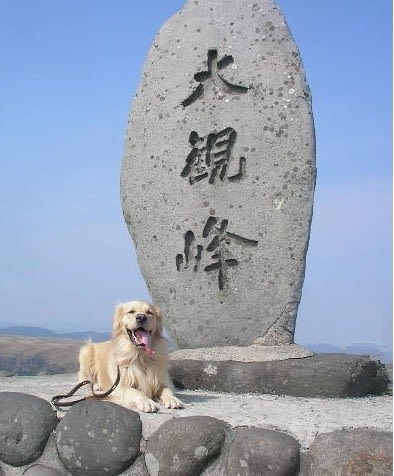
空組アルファと旅したのは
西は熊本から
■2012年6月6日(水)の記/犬の血液型
最初の心膜穿針の後と、二度目の時と違ったことは、今回は翌日丸一日、アルファの息づかいがハァハァと粗かったことでした。それでも、三日目あたりからその息づかいも治まって、見かけだけはすっかり元通りになりました。食欲もあって、このところ食べさせているヒルズの療法食の缶詰2缶を食器を舐め回して完食です。
この度抜いた血液は前回よりも少し多く350mlでした。先生に次はいつ来院すればいいか聞きましたが、やはり様子がおかしくなったら連れて来て下さいとのことでした。今のペースでは一週間で溜まる血液の量は約100㏄。これでは血液を抜くには適量ではなくもう少し貯量したほうがいいらしい。でも、アルファを苦しめないよう、次回は少し早めに10日くらいで検査をして貰おうとカレンダーに丸印を入れました。
三度目の心膜穿刺となれば、もしかしたら輸血が必要になるかもしれない、私は恐る恐るその可能性を尋ねました。そして、もしそうなった時、血液を提供してくれる犬はどのように探せばいいのかと。すると、この病院では供血犬がいるらしく、先生は『病院の犬がいるから大丈夫ですよ』と言いました。半ばほっとしながらも、輸血となれば多量の血液を要する大型犬の施術の難しさを痛感したのでした。

東は仙台まで
そうして各地に
沢山のお友達も出来ました
犬の血液型は「DEA」という方式で分類されます。「DEA」はDog Erthrocyte Antigenの略称で、「犬赤血球抗原」と訳されます。人はABO式ですが、犬の場合は、このDEA方式で、1~13の型があります。特にDEA1は、更に分類されてDEA1.1、1.2、1.3のタイプに分かれ、そ中のDEA1.1が重要ポイントになります。DEA1.1が陰性なら、相手の犬が陰性でも陽性でも輸血が可能なのだそうです。しかし、陰性の犬に陽性の輸血をすると、抗体が出来てしまい命に関わる重篤な輸血反応を招くとか。つまり表にすると以下のようになります。
DEA1.1陰性 DEA1.1陽性(受血犬)
(ドナー犬)
DEA1.1陰性 ○ ○
DEA1.1陽性 × ○
そして、ドナー犬側では、10㎏の体重の犬が輸血できる量は100~150ml。最大でも220ml。30㎏の体重の犬では、最大660mlの採血が可能とのこと。しかし、運良く適合したとしても輸血を続けていけば、いつか抗体が出来る可能性があり、何よりも輸血そのものは疾患を治療するものではなく、あくまで一時的な救命と対症療法であることを考えれば、これも暗澹たる思いになるのでした。
こうして心膜液除去が頻回に及ぶと、失血性貧血を招き輸血が必要になるのですが、アルファの死後、この病気に対する研究論文を通して、私の様々な疑問に答えて頂いた岩手大学の症例では、アルファと同じ心臓由来の血管肉腫による心タンポナーデを起こした犬に自家輸血を施して、緊急ながらも効果が得られたといいます。
自家輸血というのは、供血犬(血液を提供してくれる犬)に頼らず、心膜液内に溜まった血液を採ってそれを再び体内に入れる輸血のことで、自分の血液だから拒否反応もなく、緊急用の救命処置の一つとして有効だったそうです。ただ、それには出血後24時間以内の血液であることと、単純に言うと不純物を含まないことが条件で、アルファのように、既に血液内に腫瘍細胞が含まれていると、逆に輸血をすることによって腫瘍を拡散させることになり、非常に危険だということでした。そして、この自家輸血はあくまでも緊急用で、基本的な輸血は適合する犬から為されるのが正しい処置だということでした。
-続く-




