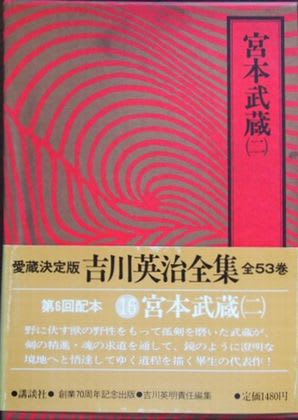
【若い功名心に燃えて関ケ原の合戦にのぞんだ武蔵と又八は、敗軍の兵として落ちのびる途中、お甲・朱実母子の世話になる。それから1年、又八の母お杉と許嫁のお通が、二人の安否を気づかっている郷里の作州宮本村へ、武蔵は一人で帰ってきた。
沢庵のあたたかい計らいで、武蔵は剣の修行に専念することを得た。可憐なお通を突き放してまで、彼が求めた剣の道とは…。だが、京畿に剣名高い吉岡一門の腐敗ぶり。大和の宝蔵院で味わった敗北感、剣の王城を自負する柳生の庄で身に沁みた挫折感。武蔵の行く手は厳しさを増す。一方、又八は堕ちてしまい、偶然手に入れた印可目録から、佐々木小次郎を名乗ったりする。
念願叶って、吉岡清十郎と雌雄を決する武蔵もし武蔵が勝てば、足利将軍師範格の技倆を超え、その名声は一躍、京畿を圧する。――武蔵は思いのままに戦った。だが、武蔵の得たものは心の虚しさであった。
今や、武蔵は吉岡一門の敵である。清十郎の弟・伝七郎が武蔵に叩きつけた果し状!雪の舞い、血の散る蓮華王院…。つづいて吉岡一門をあげての第二の遺恨試合。一乗寺下り松に吉岡門下の精鋭70余人がどっと一人の武蔵を襲う―。】
父の蔵書(吉川英治全集 全53巻 昭和55年に購入)で読んでます。なので、2段組で字が小さい!(ちょっとつらい… )
)
全4巻(文庫版だと全8巻)のうち第1巻と2巻を読んだのでとりあえず記録。
長篇です。一気読みが得意な私が2週間以上、少しずつ少しずつ読んでいる(読まない日もある)。漢字、仮名遣い、古い言い回しがむずかしい。
しか~し! 飽きることがないし、間があってもすぐに物語に入っていける。初め読みにくかった文も、今では格調高いというか、美しい、心地良いとさえ感じる。つまり、すっごく面白いのです。
武蔵の追求するのは「さむらい道」「剣の道」。それは
「神をも超えた絶対の道」
「神はないともいえないが、恃(たの)むべきものではなく、さりとて自己という人間も、いとも弱い小さいあわれなものーと観ずるもののあわれのほかではない」
試合の前、ふと神社に寄った武蔵は思う。
「自分は今、ここへなにを願おうとしたのか」
「ここへ来るまでにーいや常から朝に生きて夕べに死ぬる身と、死に習い死に習いしていた身ではないか」
「さむらいの味方は他力ではない。死こそ常々の味方である」
・・・かぁ~っこいい~!
「われ事において後悔せず」という武蔵も、吉岡の源次郎少年を斬ったことはひどく後悔する。修行を止め、いっそ剣を折ろうかとさえ思った。(罪のない、将来のある)人の命をうばうことの重さ・・・
少年の供養と自身のたましいに対する慚愧のため、仏像を彫る。
兵法の修行者なのになぜ、観音様を彫るの?と稚児僧に聞かれ答える。
「剣者が彫刻をするのは、剣のこころをみがくためだし、仏者が刀を持って彫るのは、やはり無我の境地から、弥陀の心に近づこうとするためにほかならない。
ー絵を描くのも然り、書を習うんでも然り、各々、仰ぐ月は一つだが、高嶺にのぼる道をいろいろに踏み迷ったり、ほかの道から行ってみたり、いずれも皆、具相円満の自分を仕上げようとする手段のひとつにすることだよ」
(生きてすることは何でもいい、すべて自分を磨くためなんだなあ。そう思ったら、何をやっても楽しいしやる気も出てくるなあ。)
修行は続く。そしてお通との恋も…。剣の道は人の道。武蔵はまだ22才。
(そして、武蔵の善意をも素直に受け取れず、自分本位な妄想から怒る又八と、しつこく武蔵を怨み続けるその母お杉婆の行く末は?)
星5つ 

































※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます