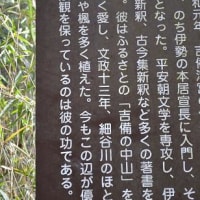昭和16年8月に出版されました当時の山陽新報(現在の山陽新聞)に掲載されました、矢尾牛骨氏の「宮内の今昔」について書いていたのですが、途中、私の浮気癖が出て、それとはほとんど無関係のような記事を書き綴ってまいりました。 ほんの一時と思っていたのですが、気が付いてみますと、時は、はや北風の冬が往き、花咲く春も遥か昔の事のように思え、今、時鳥が、”ちとせの松のふかき色かな”と詠ましめた吉備のお山から、頻りと聞こえる水無月も終わろうとしています。
ごめんなさい。一寸又横道に。
時間が早く過ぎ去る事を 「光陰矢のごとし」とか「隙を過ぎる馬」とか呼んでいるようですが、矢は分かるのですが、どうして馬なのでしょうか。鳥ではいけないのでしょうか。その事をちょっぴり調べてみました。
ご存じとは思いますが、これは山上憶良の歌から来ているらしいのです。ものの本によると、万葉集に
“二つの鼠競ひ走りて、目を渡る鳥は旦に飛び、四つの蛇争い侵して、隙を過ぐる駒夕べに走ぐ”
があります。この最後の言葉から出来たのだそうです。
それにしても、貧乏の歌を歌った山上憶良という人の学識の高さは何処から来たのでしょうか。偉大な情も言葉もその上調べも最高な歌読みです。あの柿木・山部大人と遜色のない歌人だっと思われて仕方ありません。
これもですが、高尚の山上憶良論を聞きたいものですね。どんよりとした梅雨空から「てっぺんかけたか」と、甲高い鳴き声が、今、吉備のお山から聞こえて来ます。