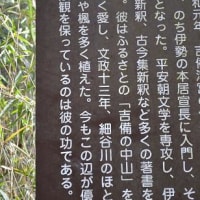さて、高尚先生は、更に、詞と情について書きます。
“・・・あさ夕にといはず。くるとあくとゝいへるは、詞つかりてしらべはわろくなれども、くるあくというは、のちへかヽりていふ詞にて、くるといふに、夜もすがら見る事こもり、あくといふに、ひねもす見る事こもりて、情ふかくなれり。情をおもひて、詞をもしらべをもととのへざるなり。”
と。
「ことば」の一つを選んで、詞と情を深く関連づけ、敢て、言葉余りの言葉を使ってこの歌の情をより細やかに表現したのだと云うのです。これは、先にあげた柿本ノ大人の“あはぢのぬじまの崎の”と詠んだ歌の心ばえに似ていると云うのです。
これも誠にその言わんとする所が日本の歌の核心に迫るような、それまでの人が、本居宣長を除いて、誰もがなしえていない歌評ではないかと、私は思っています。それが[歌のしるべ]なのです。