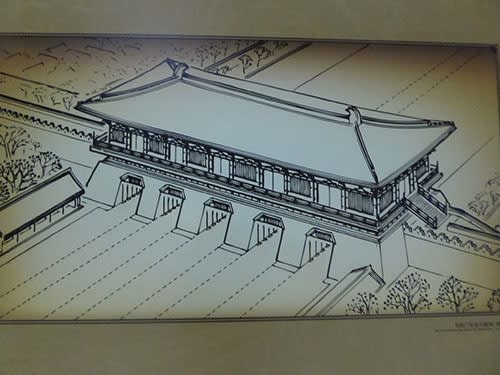▼麦積山入口前の掲示写真 第44窟「寂陵」の菩薩

寂陵(じゃくりょう)は西魏・文帝の皇后、
乙佛(おつふつ)氏の元陵墓。
何でこんなところに皇后の陵墓があったのかといえば、
乙佛氏は皇后を廃されたから。
時代は隋が建国される半世紀ほど前、北魏が東西に分かれた後。
文帝が即位して数年、西魏と東魏が北魏の正統性を争っていると
モンゴル高原の遊牧国家、柔然(じゅうぜん/蠕蠕(ぜんぜん)
の方がなじみ深い気がする)が南下して来た。
東魏と争っている中、柔然と敵対する訳にはいかないので
文帝は柔然の王女を妃として迎えることになり、乙佛皇后は
出家して息子の居る泰州(現天水周辺)に移り住んだ。
12人も子を生した(多くは夭折)ことからも判るように
文帝と乙佛皇后の夫婦仲は良かったが、露骨に下克上の時代。
宇文泰に実権を握られた傀儡皇帝に選択肢は無かったのだろう。
が、柔然の王女は輿入れしてわずか2年で逝去したので、
死因を怪しんだ柔然の王が兵を挙げ、
そのとばっちりで乙佛廃后は死を賜る。
時に乙佛氏は30歳(中国的に言えば31歳)。
535年 文帝の即位とともに皇后になる
538年 柔然の王女の輿入れに際して皇后を退位
540年 柔然の皇后の逝去に伴い賜死
…なんとも慌ただしい、というかお気の毒。
つーか、流産が多かったとしても、16歳で輿入れして
12回も懐妊したということが凄い。
文帝の死後、その遺言によって乙佛氏は文帝の永陵に
合葬されたそうだ。

▼屋外で編み物に勤しむ中国マダム。
30年前はどこの街にも歩きながら編んでいる強者がいたが、
最近はめっきり見かけなくなってしまった。

正午過ぎの麦積山景区入口は人気が無かった。

10時から観光を始めて3時間、13時過ぎに駐車場に戻ると
34路のバスは既に停まっていた。
天水には他にも見所はあるが、石窟の観光を終えて放心状態。
ただホテルで休みたい一心だ。
………早く西安に行こう
天水站(えき)から在来線だと西安まで4〜5時間。
天水南站から高鉄(新幹線)だと2時間弱。
そりゃぁもう当然高鉄ですよ。
天水南站への最短乗り換えを検索しようとスマホを見ると
………残念!!圏外〜〜!!!!
麦積山の駐車場、中国聯通(China unicom)は圏外でした。
ここ数年の中国旅行では、SIMフリーのスマホで
香港のプリペイドSIMを使っている。
昔は街に着くと一番最初に地図を購入していたが、
百度地図が概ね便利なので、かなり助かっている。
百度地図の罠にも時々嵌るけどね。
香港のSIMは今のところLINEもできるので超お勧めです。