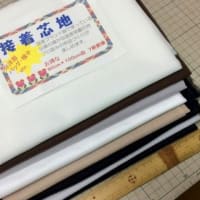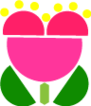本則課税と簡易課税の違いが今ひとつわからないのですが・・・
税務能力・経理能力に乏しい零細企業は、経営者自ら計算しなくてはならない。社会保険庁もなのですが、税務署は得になる方法を知っているにもかかわらず、税務署側からは絶対教えてくれない。有益になるしくみは、自分で調べるしかない。多分適正・公平な課税はなされていない。無知な人からは、・・・!”#$%&’危ない内容になりそうなので、割愛します・・・
今期、19年度の消費税になりますが、基準期間は17年度
17年度の課税売上が1000万円を超えると消費税の計算をしなくてはならない?
1000万円は対象外 10,000,001円は対象
課税売上って消費税込の売上ってこと?
簡易課税の届出すなわち「消費税簡易課税制度選択届出書」ってのを出していないので、「本則課税」の計算になります。
この前もった書類提出に関してもなんですが、税務署は教えてくれないんですね。減価償却資産の定率法・定額法に関しても、定率法を選択する場合予め「届」を出しておかないと認められない。これって何か意味があるんでしょうか。申告書と同時提出でも問題ないと思うのですが・・・
納税者に分からないような税の専門家しか知らない取り決めは、ちょっとおかしい・・・
私が、税務署員に「ウエディングドレスを3日で作れ」と言っているようなもん
本題からそれてしまった
そこで、本則課税の計算方法ですが、平成15年税の改正があってから、大矢野商工会であった説明会でいただいた、「これですっきり改正消費税」という冊子によると・・・
A:課税売上を売上と消費税に分けてその売上から4%の国税の消費税を計算する。
B:仕入れとかかわる経費を同じく4%の消費税を計算する。
A - B = 納める国税 ・・・ 4 %
納める国税 ÷ 4 = 地方消費税 ・・・ 1 %
納付税額 合計 5%
何か計算方法がおかしい
はじめから消費税 5%で計算して 後で 4 対 1 分けたら計算が簡単で早いのに
わざと分かりにくくしている?
ところで、この「課税期間における課税仕入れ等に係る消費税額」なんですが、経費の中には消費税がない経費があるんですね。大きなものは人件費、社長の給料・アルバイト代などですね。保険料とか健康診断の費用、印紙とか銀行利子なども消費税がかからないので、これに入りません。家賃は、自宅用は消費税が付きませんが、事業所は消費税込みとなっていますので、入れてもいいですね。出張費に関しては、議事録で定めてあるとおりです。
前もって届を出す方式の簡易課税なのですが、「これですっきり改正消費税」という冊子によると、多角経営の場合、業務ごとに売上を分けなければならないらしく、こっちとしては、その方が面倒です。また、簡易課税にすると、何かと制限があるらしく、融通がきかないらしい。例えば、1000万円の売上がないときに仕入れて残っていた商品に仕入先に払っていた仕入れにかかわる消費税が引けないとか???
税務署も、社会保険庁もその他、公共機関官公庁もなんですが、有益なことは聞かないと教えてくれない。その前に、一般人・納税者は、そういう専門家しか知りえない制度も何も知らないので、「聞けっ」と言われても何を聞くの?
今回ダウンロードした書類
消費税及び地方消費税確定申告書(一般用)(PDFファイル/121KB)
場所 国税庁ホーム ⇒ 左エリア の「消費税」 ⇒ 確定申告に関する情報ページを見る(確定申告書等作成コーナーはこちらから) ⇒ 消費税・地方消費税 ⇒ 消費税及び地方消費税確定申告書(一般用) ⇒ 消費税及び地方消費税確定申告書(一般用)(PDFファイル/121KB)
経費の内訳とかになんやかんやしてたらいただいた申告書が汚くなったので、国税庁のホームページからパクッてきました。
こちらの方が行きやすいかも・・・
国税庁ホーム ⇒ 左エリア 申請・届出様式 ⇒ 一番下の国税庁様式検索 ⇒ 課税関係 「消費税及び間接諸税関係」関係税目等 「諸費税」 を選び ⇒ 絞込み検索 クリック ⇒ 一番上の消費税及び地方消費税申告書(一般用)クリック
納付書はダウンロード出来ませんでした。
納付書を書き間違えたのですね。1枚しかなかったから、ダウンロードできないので、天草税務署に電話して送っていただくことにしました。また間違えるかも知れないので2枚送ってくださいとお願いしましたら、その時電話で対応された徴収統括官がていねいに5枚送りますと返されました。わたくし、そんなに間違いだらけのひとに見える?その徴収統括官「しょそんされたのですね」と聞かれました・・・「しょそん」って何?税務署に電話で話をすると、暗号みたいな言葉だらけで話の意味がよく分かりません。わたくし、ただ、文字を書き間違えただけなのですが・・・