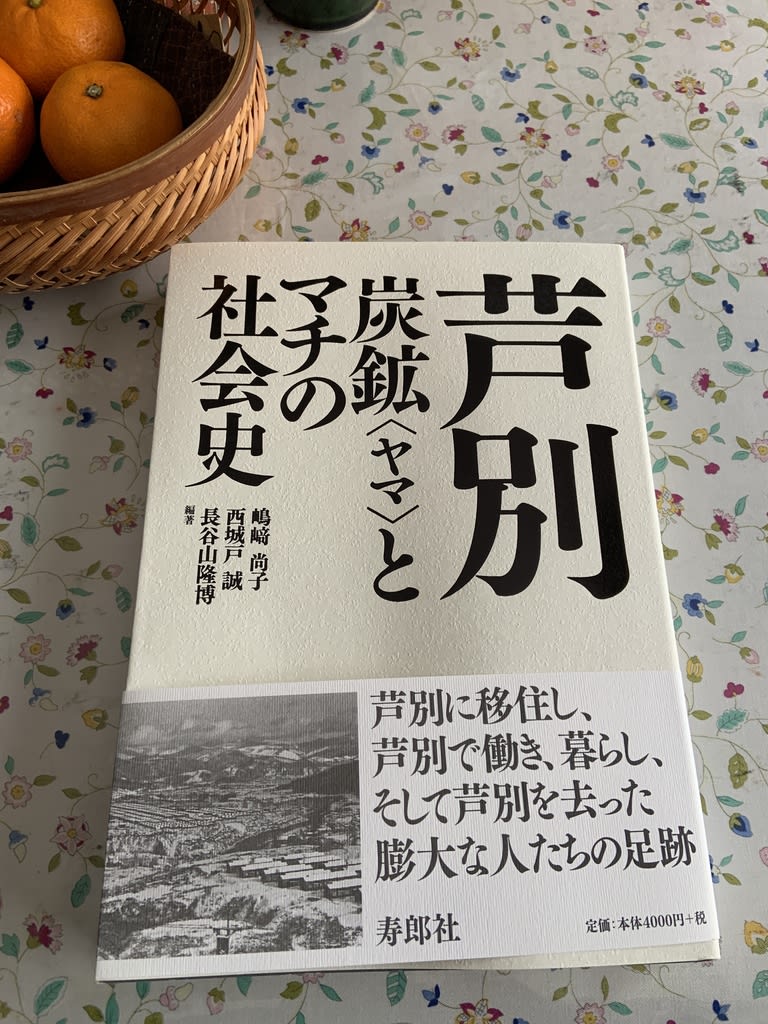朝食でイワシの丸干しを食べるようにしている。魚焼きレンジで炙って頭から丸ごと2〜3本を食べる。
ほろ苦さがなんとも言えず旨い。
青魚には、脳の健康をサポートするDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)といったオメガ脂肪成分が豊富に含まれているそうだ。
〝時すでに遅し〟か・・・。ささやかな抵抗だ。
近くのスーパーで消費期限間近かの2割引のシールが貼られたものがあると、妻の持っている買い物かごに勝手に入れる。
3本目刺しを2段重ねしたものが税抜きでかつては100円くらいだった。
福島原発の処理水放出で銚子沖の物が一時、60〜70円くらいになった。
それが125円になって暫く続いたが、近年、145円くらいになって、昨年あたりから158円になっていた。
昨日、何と一気に100円上がって258円になっていた。
見間違えかと確認した。
一度に6割、100円もの値上がりは今まで無かったことだ。
品不足、人件費高、ガソリン高、円安が続いているが、農業、漁業の一次産業や小規模・零細事業者は価格転嫁が難しいという。
ここにきて一気に調整を図っているようにも見える。
野菜に限らずスーパーでは毎日毎日価格が上がっている。
物価を追いかけて賃金と金利を上げるプロセスはやはり間違いだ。
価格転嫁の出来ない業態がたくさんあって経済が成り立っていることを考えると購買力が上がって物価が上がるのが順序だ。
一方で価格バブルで1億円を超える都心のマンションを現金で買う中国人がいるという。
購買力の無い日本から日本が海外に売られている。
イワシの丸干しのほろ苦さが広がる。