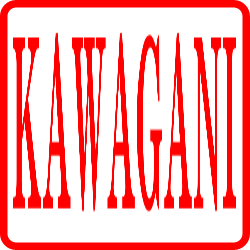『ヨミガエルガール・ジャスティス』① OUT OF LIMITS

「わー掛軸」
「どうぞ、ごゆっくりご覧になっていってくださいーー」
「さすがは花見城のお土産屋さんねーー」

「ここの土産物は工芸品が多いんだよ。ほかにも表具とかも扱ってるし。あと、やめられないとまらないアマビエえびんせんだってあるのさ」
「何それ?」
「うちのおかんが作った土産物のお菓子さ」
「へえーー」

「うわーー。これネットで今話題の。ええとーースーパーヒーローレインジマンのコスプレ衣装」
「スーパースターレインジさ。レインジマンじゃないさ。もう、こんなレプリカ品が!」
「このコスプレでインスタグラムにアップするのが流行ってるらしいよ」
「そ、そのようだね。じ、実は‥‥‥」
「レインジマンの何か正体とか知ってるの?。懸賞金まで出てるんだよねーー」
「レインジマンじゃない。スーパースターレインジさ。実は‥‥‥。ちょっと食堂で話そう」

「あたしゲイの方とお食事するの初めてーー」
「そ、そうじゃなくて・・・・・・」
「バイトの空き時間まだあるし、そこで伺うわ」

「実はスーパースターレインジと知り合いなんだ」
「え!ほんとにーー」
「ええ、ほんとさ。動画がアップされたので驚いてるらしい。彼は正義を貫いているだけで正体はごく限られた人にしか教えてないんだ。て、いうか、聞こえてる?なんでこんなかたちでキミと話さなきゃならないんだ!‥‥‥」

「食堂のおばちゃんにこう座って。って言われたから‥‥‥」
「にしても。食堂で客ふたりが背中合わせに食事するのは不自然だよね‥‥‥」
「飛まつ対策でしょ。で、あたしの話し聞いてくれる?」
「な、なに?」

「あたしセックスセラピーの講習会に出てるの。そこの患者さんの彼がね、講習の時に気に入られて、今ストーカーっぽくされてるんだ‥‥‥」
「それは困ったことだ」

「連絡してこないでほしいだけなんだけどねーー」
「そうか。僕からスーパースターレインジに相談してみてもいいか?。その彼の住所を教えてくれないか。スーパースターレインジは正義を貫いてくれるよ」
「ありがとう。ゲイの方と、このようなお話しが出来たのは初めて」
「い、いやーー‥‥‥」

わたしのお姉さんは花見城のバイトをしつつひとり暮らしを始めた。わたしは美容師になるために専門学校一本に絞った。
「それでは授業を始めます」

わたしはクスに告白したあと、同棲生活を決意した。お姉さんと両親には猛反対をうけ、膠着状態でいたけど、数日後、お姉さんに花見城のバイトの知らせが入ると、急にわたしの味方になってくれた。お姉さんは人文社会学のカレッジに入り、セックス依存症のセラピー講師を学ぶ傍ら、俳優やタレント業にも興味があった。花見城でバイトがある間はそこで一人暮らをして、それ以外の日は自宅からカレッジに通うことになったことで、わたしのほうの希望がかなった。

わたしは湧水市の美容師専門学校で同棲生活をしながら勉強を続けた。
「それでは実践に入ります。洗顔、洗髪を実践してみましょう。みなさん交代で洗顔、洗髪をしてもらいましょう」
両親の心配もわかる。クスには何も持ってないからだ。高校に入って卒業するまでにダルマ落としのように次々と持っていたものがなくなっていった。クスを知るジュニアハイスクール時代の友達も、クスはいつも失くしてしまう人だと、わたしに教えてくれた。幼い時、幼稚園の頃から、引っ越しの繰り返しで、そこにいてはどこかへ消えて行ってしまうと、そこでまた積み上げては失くしていると言っていた。ジュニアハイスクールの3年までにクスはさまざまなことで活躍し、手に入れたものが3年の夏ですべてが消えたと言っていた友達もいた。ハイスクールも地元に残らず、他へ消えて行ったという人もいた。クスがハイスクールの時、初めて学期テストで100点をとり、生まれて初めて全校で1番になったことがあると言っていたのに、ハイスクールを卒業したあとはその成績すら生かされず無駄に消えたようだった。

わたしたちの関係はゼロからのスタート。わたしはクスの収入を頼りに生活をしていかなければならないのだ。幸い、あの日の晩はわたしは避妊具を持っていた。

「コンドームを持って俺に会ったのか?」
「水裁は女子が多いでしょ。毎年のように保険体育でうざいくらい避妊や避妊具の授業があって。持ち歩くのがあたり前になっていたの。でも、実際に使ったのはクスが初めて。クスに使いたかった‥‥‥スキ‥‥‥」

わたしの強みは両親が専門学校の学費は払ってくれるということだった。学生生活の間だけといった条件つきではあるが、わたしとクスとの共同生活を許してくれた。でも、クスには何かを失う怖さがあるのだろうか‥‥‥。

「おかえりーー」
「ただいま」
「そろそろその洋服違うのにしてみたら?」
「着心地がいいんだよ。これ」
「わたし、何か仕立てようか。ハイスクールで習ったし。あ、ミシン持ってこなくちゃ」
「急がなくてもいいぜ」
「ねえ。スーパーに寄っていこ」
「あーうん、わかった」

クスが花見の街から出て行ってしまった。毎朝目が覚めるとそのことが頭を過る。

ただ単にあの時に会っただけだから。と、着地点で落ち着くと一日が動き出す。

花見工芸ハイスクールの登下校はハイカラな制服を着て行くが、授業になると作業着に着替える。男子より女子の割合がかなり少なかった。女子は花見工芸分校に多く入るらしい。単に普通科があるからだと聞いた。男子生徒は女子には興味はないのだろうか。わざわざ分校にまでして女子が入る割合を変える必要もないと思うけど、それがこの学校の伝統なのか。まったくわたしには理解できなかった。

授業はやたら見学が多い。そして寡黙に生徒たちは授業をしていた。

その日、学校が終わるとルクスが外で待っていた。
「よッ。おつかれ」
「バイトは終わったの?」
「さっきね」

「今晩出かけるところがある。着替えを持って駅前で集合だ」
「どこかへ行くの?」
「列車にまず乗って移動する。キミのバイクも移動できるようにしておいてくれ‥‥‥」

「ストーカーにストーカーするなと言いに行く」
「家賃取り立てに来るな!と言うものじゃない」
「そんなことはない。あ、今月の家賃お忘れなく」
「払わなかったら?」
「地の果てまで追いかける」

「居場所はわかるの?」
「ついてこい!。あ、ちょっとまって!グーグルナビをセットしてなかった」
「もう、何度も来たくないからね!」

「きみ!諏方サエさんに付き纏うな。メールを送ったりもするな!」
「誰だお前は?」
「ちょ!こっち来るなよ!来るなってば!!」

「俺は溜まってんだよ。野郎ども見てな!俺の精力絶倫パワーを!」
「ボスが動き出したら止まらないでぜ!!」
「ちょん切ってやるわ!」

「正義を貫くんだ!!」
「ぎゃーー!!この小娘が!!」
「ほーら、これでぐったりよ!!」
ベーコの炸裂は凄まじかった。瞬時に精力絶倫野郎をぐったりとさせた。

「ボスの代わりにわしらがいただくぜ!」
「そうはさせない。正義を貫くんだ!!」

一瞬の反撃もさせずにストーカーとその仲間たちを蹴散らせた。それにしても今日のベーコは容赦がなかった。こいつら全員単なる怪我では済まないくらいの、鋭く深くトドメを刺してしまった。

「夜明けになってしまったな。始発の列車までに戻ろう」
「そうね」

「やあーー。お見事でしたよ」
「誰だ?」
「わたしゃー。この辺をパトロールしてたものです。まさか、あの有名なレインジさんにお会いできるとは、じつにラッキーでした」
「だからあなたは誰?って訊いてるじゃない」

「申し遅れました。わたしゃーゆるこまマンと申します。正義のためならなんでもしまっせ」
「ここでただ会っただけじゃない」
「いやーー。ここで会ったのも何かの縁。わたくしとコラボしませんか」
「コラボ?」
「レインジさまに便乗させてくれませんか‥‥‥」
「スーパースターレインジだ」
「わたくしもホームページにアップしますので、ご用事のあるときにはご連絡をください」
「話だけは聞いておく。もうここには用はない。さらばじゃ、ゆるこまマン」


それから数日後、『ゆるこまマン』のコスプレレプリカと『スーパースターレインジ』のコスプレレプリカが土産物屋に並んだ。サブカル族とサブカル業界の食いつきの速さは尋常じゃなかった。

「よういスタッ!」
「よ、淀?‥‥‥。秀頼を、た、頼むぞ‥‥‥」
「淀にお任せあれ」

「殿下様!。お身体に触ります。お布団へお戻りくださりませ!」
「黙れ三成!」

「殿下」
「わ、わしは‥‥‥ここで・・・・・」
「殿下様ーー」
「夢のまた夢‥‥‥」

「カット!。MJさんクランクアップでーす」
「おつかれさまでしたーー」
「はーい。おつかれさまー」
「MJさん、今後の予定は?」
「はーい。そうねー。次からは天狗になって旅に出ますよーー」
「天狗ですか!」
「天狗シーム。僕の夢ね、だからしばらく巣ごもりするね。客観的に仙人になるよ。はーい」

「キミたちの自由は僕の自由。それではーー天狗で会いましょう」
「おつかれさまでしたーー」


「あ!開いた!」
わたしはまだ開けていないスマホアプリのパスワード認証の鍵を開けることが出来た。



そのアプリはメッセンジャーアプリ。アプリが開いた時、書き込まれたメッセージがピンクチーマーのところへ届いた。

「地獄谷めぐりをしてるところだが、なんのようじゃ」

「MJ。ベーコさんをどこへやった」
「ほおー。これはこれは以前、僕をとっ捕まえたキミじゃないか。今日は同じコスチュームの連れがきているようですな‥‥‥」

「隣の彼は旦那。夫婦チーマーよ。そしてエプロン姿のは妹。すでに奥様よ」
「奥様よ。奥様は魔女よ」
「そしてエンタシスマンにMJの居場所を教えてもらったわ」

「なんの用ですか?僕は不起訴だったでしょ」


「あれから警察に話しましたよ。でもね、どう見てもあれは心中だって言うんですよ。計画を企てたことには嘘は申しませんが」

「井戸の中に隠れてて、相手を引きずり下ろすなんてどうしても無理だろってね。はじめから僕も井戸の中で待ってたわけじゃないですからね。井戸の側で隠れてて、その隙に心中したんじゃないか、と、言うもんですからね。警察の判断は、僕は不起訴ということになりました」



「心中に至るいくつもの状況証拠はありましたからね‥‥‥」

「あの幻影怪物はどうしたの?あたしたちははっきり見たわよ。奥様は魔女よ」

「あれはボーカロイドと言いますか、着ぐるみショウを行ったわけですよ。僕たちは常に最新のサブカル技術をキャッチしてはブームを仕掛けていくわけですが、まあ、なかなかヒットしないもんです。今じゃ3DAVやボーカロイドも一般的ですが、僕たちのほうがいち早く便乗してたんですがね。結局、ものになったのはスライド映写会だけでした。まあ。あれは女性限定の地下ライブ劇場で、あなた方を招待してバトルをしたわけです。かつてのヒーローショウのように、僕の師匠が考案したキャラクターを再現したまでのことです。だけど、ベーコはなぜ蘇るんでしょうねーー」


「そのベーコさんをあなたはどうしちゃったわけ?ベーコはいるんでしょ?。教えなさいよ!」
「ベーコならいるでしょ。もとのベーコに戻したいなら、あのミニチュアベーコちゃんを殺せばいいことでしょ‥‥‥」
「そんなことできないわ!もっとほんとうのことがあるんじゃないの?奥様は魔女よ」
「それはあなたたちで調べがついているでしょうよ。僕の口から言えることは、あの骨壺の中身がベーコだよ。クリスチャンの世界では土葬から生き返るってことはまあ、ありえそうなことだけどね。火葬になったものは到底生き返らないじゃないかなーー。この国は火葬が主な国。僕はそこに重きをおいたまでです」

「ベーコさんを戻して!」

「だから言ったでしょ。あ、の、こ、を」
「許さないわ!」





私たちピンクチーマーと奥様は魔女そしてエンタシスマンが加わって、MJと戦ったが私たちに納得が得ることまでには至らなかった。

「わしは仙人になるのじゃーー」

「まて!MJ!」
「追うのは危険、そこはすぐ谷よ」
「MJは傘を使いながら谷底のほうへ逃げて行ったんだ」
「死体遺棄。それだけでも取り押さえる容疑はあるわ。MJを絶対探してみせる」