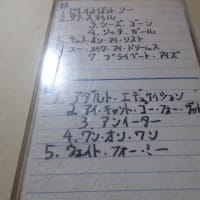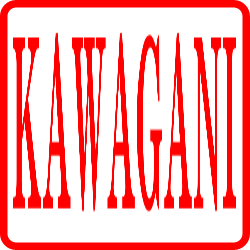初回
DQX毛皮を着たヴィーナス
前回
『毛皮を着たヴィーナス』ライオン
<餅>


帰宅しても彼女はベッドへははいらず、舞踏服を脱ぎすてて髪をといた。

それからわたしに暖炉に火を入れるように命じ、わたしが火をたくと、彼女は炉ばたに腰をおろして、じっと焔を見つめてもの思いにふけっていた。

「まだご用がございまっちでしょうか?ご主人さま」
彼女は首をを横にふった。


わたしはその部屋を出て柱廊を抜け、庭園へ通じる石段をおりいって、途中で腰をおろした。北風がアルノ河のほうから新鮮な冷気を運んできた。緑の丘はバラ色のモヤにつつまれて遠くまでひろがっていた。街のうえには金色の霧がただよっていた。

薄青い空には星が二つ三つ残っていた。

わたしは燃えたつ額を冷たい大理石に押しあてた。いままでの出来事はすべて子供だましのようなものだった。

________今こそ、ほんとうに、真剣なことが、恐ろしいまでに真剣なことがわき起ってきたのだ!
わたしは彼女の関係が近いうちに破局に達するであろうと予測した。がわたしには、それに対決する勇気が欠けていた。

わたしはただ恐ろしくてたまらなかった。熱狂的に愛しつづけてきた彼女が、わたしの手もとから失われていきそうだ。そう思うだけで、わたしは泣けてしょうがなかった。


日中、彼女は部屋に錠をおろしてとじこもり、わたしを遠ざけて黒人女をはべらせた。夕空に星が輝きはじめるころ、彼女は庭園を横切って歩いて行った。

わたしは探偵のように注意深い足どりで尾行した。

彼女は庭の一隅のヴィーナスの真道のなかへはいって、ドアを閉めた。

わたしは忍び足で近づいて、扉の隙間からそっとのぞき込んだ。わたしの目は燃えていた。彼女は女神の像の前に立つと、手を組み合わせてなにごとかを真剣に祈っていた。夜がふけてからであった。


わたしは廊下の一隅の聖人像の下に掛けてあった小さな赤いランプに火をつけて、片手でその光をおおい隠しながら、彼女の寝室へしのび入った。ドアの鍵はかけ忘れていた。わたしは彼女のベッドに近づいた。

彼女は神経的に疲れ切ってしまったのであろう。仰向けになって、胸のあたりに両手を組んで、祈るような格好で熟睡していた。わたしは静かにランプの光で彼女のすばらしい美貌を照らし出した。

それからわたしはランプをそっと床のうえに置き、ベッドのそばに身をかがめて、わたしの頬を彼女のふくよかなあたたかい腕に押しあてた。

彼女はかずかに動いた。

わたしは石にでも化したかのように、いつまでもいつまでも、そうしていた。が、ついに激しい戦慄がわたしを襲ってきたので、わたしは泣き出してしまった。わたしの熱い涙が彼女の腕のうえにボタボタと落ちた。

「ゼフェリン!」
彼女はおどろきの叫びをあげた。
「・・・・・」

「ゼフェリン」
彼女は今度はやさしい口調でいった___
「どうしたの? 病気なの?」

その声には無限の愛が満ちあふれていた。わたしは胸に赤熱の鉄棒を突きさされたように、声をあげて泣き叫んだ。
「わたしの気の毒な、不幸なゼフェリン」

彼女はそういって、いっそうやさしくわたしの髪の毛をなでながら、
「すまないわね。とってもすまないと思っているよ、わたし、でも、あなたのお力になることができないのよ。どんなに善意をもって考えても、わたしにはあなたをお救いする方法がわからないのよ」

「ああ、ヴァンダ、そうでしょうか・・・・」
わたしは苦闘のうちにうめいた。
「なあに?」

「あなたはもう、わたしを愛していないのですか?ほんのわずかの憐れみもかけていただけないのですか?あの美しい外国人が、あなたの心を完全にとらえてしまったのでしょうか!」

「そうね、わたし、嘘はつけないわ」
彼女はそういってから、ちょっとためらうように問をおいて____

「ああ、あの人は獅子のような男性で、強くて、美しくて、優しくて、わたしたち北国の人間のように野蛮じゃないわ。あなたにはすまないけれど、私どうしてもあの人をわたしのものにしなければならないわ。わたし自身をあの人にさしあげねばならないわ、あの人がもらってくだされば・・・・」

「でもヴァンダ、世間の評判を考えてください!」
「もちろん考えているわ。でも、わたしはあの人の妻になりたいの、もしあの人がもらってくださるならば・・・・」
「ヴァンダ、ボクを追い出さないでください。あの人はあなたを愛してなんかいやしない!」
「だれがそんなことをいうの?」

彼女はかっとなって、鋭い声で叫んだ。
「彼はあなたを愛してなんかいない!」
わたしはそうくり返して衷情(ちゅうじょう)を吐露し、わたしのものになって欲しいと哀願した。
しかし彼女は冷酷無情な表情と邪悪な嘲笑をわたしに投げかけて、

「あなたはいま、あの人がわたしを愛してなんかいないといったわね。いいわよ、そんならそれで、あなたは勝手にどんな気休めな空想でもするがいいわ」
と叫ぶが早いか、ぶいとむこうをむいてしまった。
「後世です。ヴァンダ、あなたは血肉をもった女性ではないですか。ボクと同じように人間の心臓をもってはいないのですか!」

「わたしは石像の女よ。あなたの理想とする毛皮を着たヴィーナスよ。そこにひざまずいて、祈りでも捧げるといいわ」

「ヴァンダ、お慈悲だから!」
「ホホホ!」
彼女は嘲笑的に笑いだした。

わたしは彼女の枕に顔をおしあてて涙を流した。
長い沈黙がつづいて、静かに身を起こすと、

「じれったい人ね!」
「ヴァンダ!」
「うるさいね。わたしは疲れたわ。ねむらせてちょうだい」
「後世ですから」
「わたしはねむりたいの!」

「そうですか!」
わたしはカッとなって飛びあがると、ベッドのそばにつるしてあった短刀をつかむと、さっさと鞘を払って、わたしの胸にあてて、
「ここで自殺します!」
と叫んだ。
「どうぞ、ご勝手に」
彼女はまったく気にもとめず、大きなあくびをして、
「わたし、とってもねむいのよ」
とくり返した。

わたしはどぎもを抜かれて、短刀を腕にに突き刺す勇気をくじかれてしまった。
「ヴァンダ、ほんのちょっとの間でいいから、ボクのいうことを聞いてください」
「ねむいんだってば!このわからずや!」

彼女は売女(ばいた)のように叫んで、ベッドから飛びおりて、わたしを足げにして、
「わたしがおまえの主人だってこと、忘れたの!」

といって、杵をふるって、わたしを打ちすえた。
わたしは拳を握りしめて、彼女を見かえしてさっさと彼女の寝室から飛び出した。

彼女は杵をほうり出して、ヒステリックに高笑いしていたが、それがかえって、彼女から離れようとするわたしの決意をいっそう強めた。

次回
『毛皮を着たヴィーナス』置手紙