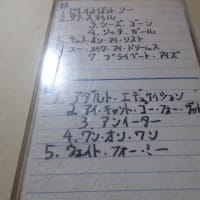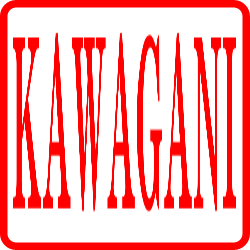初回
DQX毛皮を着たヴィーナス
前回
『毛皮を着たヴィーナス』慄然
<給仕>

憂鬱な愛の飢えと重労働の一ヵ月がすぎた。わたしがじりじりした気分でいると、彼女からつぎのような命令書がきた。

___奴隷グレゴールは今後は主人の身近の用向きに従うべきこと。ヴァンダ

翌朝早く、わたしは胸をどきどきさせながら、緞子のカーテンをかきわけて彼女のベッドの近くの暖炉にたき木を入れた。そこにはまた快いほの暗さがただよっていた。ベッドはたれ絹のむこう側に隠れていた。
「グレゴール、おまえなの?」
と彼女の声。
「いま、何時ころ?」
「九時をまわりましただっち」
「では、朝の食事を」

わたしは急いで食事を盆にのせてはこんできた。彼女は垂れ絹を引いて、裸の肩に黒い毛皮をひっかけた豊麗な半身をあらわにした。その魅力にわたしの頭は狂いそうだった。盆を支えたわたしの手は、わなわなふるえた。
「だらしがないわね、奴隷!」

彼女はそばの化粧台のうえのムチに手をかけた。わたしは懸命になってふるえをとめようとした。
食事がすんでしばらくして、わたしがつぎの間でひかえていると、ベルが鳴った。
「この手紙をコルシニ王子さまのもとへ届けてちょうだい」

わたしは急いで町に行って、王子にその手紙を渡した。王子は黒い目をした美貌の青年であった。わたしは嫉妬に燃え、憔悴しきった様子で、彼女に返事をとりついだ。
「とても顔色が悪いわね。どうしたの?」

と彼女は意地悪さをおさえて、わたしをからかった。昼の食事は、王子と彼女のさしむかいで、わたしは給仕を命じられた。ふたりの愉快そうな軽口のかわし合いに、わたしは目がくらんでしまった。

王子の酒杯にボルドー酒をそそぐとき、思わず手がふるえて、彼女のガウンのうえにまでブドウ酒をこぼしてしまった。
「なんて不作法な!」
彼女はわたしの顔をびしゃりと打った。

昼食後、彼女は馬車を駆ってカシスへ行った。馬車への乗り降りのとき、彼女はわたしの腕に軽くもたれかかった。それだけの接触でもわたしのからだには電流が走るような衝撃が感じられた。

午後の六時の正餐には、彼女は数名の男女を招待した。

わたしは給仕役であった。晩餐後は、バーゴラ劇場へ観測に出かけ、夜中近くに帰宅した。

数日後、わたしは、コーヒー盆を捧げて彼女のベッドのそばにひざまずいた。すると、彼女はとつぜん、わたしの肩に手をかけて、深々とわたしの目のなかをのぞきながら、
「なんと美しい目をしているのでしょう」
とやさしくささやいて、

「いまは特別に美しいわね、でも、おまえは非常に不しあわせだと思っている?」
「・・・・・」
わたしは黙ってうなずいた。

「ゼフェリン、まだわたしを愛していて?」
彼女は急に情熱的になって、はげしくわたしをひきよせた。コーヒー盆はひっくりかえり、壺やコップが床のうえにころがった。

「ヴァンダ!ヴァンダ!ヴァンダ!」
わたしは熱狂的に彼女に抱きついて、彼女の口といわず、頬といわず、ノドといわず、胸といわず噛みつくように接吻した。乳首をもぎっとってやりたいほどだった。
「あなたがボクを手ひどく扱えば扱うほど、ボクを裏切れば裏切るほど、ボクはますます狂いたって、あなたを恋し、嫉妬し、苦しみ悶えて死ぬかもしれません」

「わたしがあなたを裏切った?そんなこと一度もないわ。わたしは絶対にあなたに忠実だったわ。誤解しないでね。わたしの愛するただ一人のゼフェリンさんにね。あなたの服は、実は大切にタンスの奥にしまってあるのよ。さア、行って着がえてらっしゃい。いままでに起きたかずかずの事件は、みんな忘れてね。きっと忘れてくれるわね。あなたの苦しみは、わたしの接吻で、みんな吹き飛ばしてあげる!」

彼女は若い日のカテリーナ二世のように、部屋の中央に立って、タイヤの浮輪を腰にまいた。

それからふたりで長い間、長椅子にならんで恋を語り合った。彼女は、いまはまったく立派な淑女であり、わたしの優しい愛人になっていた。

「あなた、幸福?」
「いや、まだ・・・・」
「そーお、では」
彼女は柔らかいクッションによりかかって、仰向けになり、静かにジャケットのホックをはずして、半裸になって、貂の毛皮でふんわりと胸を隠しながら、
「いらっしゃいナ」

わたしは彼女の胸に抱かれた。彼女は蛇のような舌でわたしの唇の中までキッスした。
「幸福?」
「かぎりなく!」
「ホホホ!」

彼女は高らかに笑った。
わたしは長椅子のうえから彼女の足もとにおりて、両膝の間に身を沈めた。

わたしのかわりに給仕役を勤めた黒人女ハイデェは、上品で黒大理石で彫刻された美女のようなすばらしい胸をしていた。わたしがそれに気づいて、ちょっとうっとりしていると、この黒い悪魔は白い歯をむき出して、ほがらかに笑った。

それを横目で見ていたヴァンダは、黒人女が部屋から出て行くと、にわかに激高してわたしに飛びかかって、
「どうして、おまえはわたしの目の前で、ほかの女をじろじろ見るの!わたしをさしおいてあんな黒い悪魔を!」
と叫んで、悪魔のかぎりをわたしに投げつけた。
わたしはビックリした。彼女は唇まで真っ青にしてぶるぶるふるえている。激しい嫉妬だ!

彼女は壁の掛け針からムチを取ると、いきなりわたしの顔面をびしりと打ちすえた。それから黒人たちを呼んで、わたしを縛りあげて、暗い地下室にほうり込んだ。

鍵がかけられ、鉄のカンヌキがかけられ、また鍵がかけられて、わたしは完全に囚人になってしまった。何時間、何日経ったか、わたしにはわからなかった。餓死か、凍死か、わたしは悪寒(おかん)でふるえた。
「憎いヴァンダ!」
わたしはたしかに彼女を憎みはじめた。

ふと気がつくと、血汐のように赤い一筋が床を横切って流れた。押し開かれたドアから差し込む灯火の光であった。

彼女は貂の毛皮をまとい、たいまつの灯火を手にしてあらわれた。
「まだ生きているの?」
「ボクを殺しにきたのですか?」
わたしは低いしわがれ声でうめいた。

彼女は二足、三足、大股でわたしのそばへ歩みよると、しめった床に膝をついて、股の間にわたしの頭を抱え、
「病気になったの?あんたの目は病気みたいに光わよ。まだわたしを愛していてくださるの?わたし、わたし、わたしは、愛してもらいたいのよ」

彼女は懐中から短剣を出して鞘をふり払った。鋭い刃が赤い灯にきらりと光った。わたしはおどろいて飛びあがった。
____殺される? ?
だが彼女は、わたしを縛っている綱をぶつぶつと切って、
「ホホホ!」
とあやしく笑った。

次回
『毛皮を着たヴィーナス』大鏡