かくて安西景連は、里見義実の使者である金碗大輔を欺き、その足を留めることに成功した。その間に、密かに軍兵を手分けして派遣し、俄かに里見の両城へひしひしと押寄せた。
その一隊は二千余騎で安西景連がみずから率いており、滝田城の四方を囲み、昼夜を問わず攻め込んだ。
もう一隊は千余騎。蕪戸訥平を大将にして、堀内貞行が籠る東條城を囲ませて、両城を一気に攻め落とそうと、いやがうえにも攻め立てる。安西の軍勢は破竹の勢いであった。
この時、里見の両城は兵糧が非常に乏しく、凶作による飢えと労働に疲れ果ててはいたが、主家に対する恩義のためにどうにか戦い、寄せ手をものともしない勇士や兵士がいた。
しかし防ぎ戦う間に兵糧が尽きてしまい、もう七日間も満足な食べ物を口にしていない。士卒は我慢できずに夜な夜な塀を乗り越えて、死んだ敵の死骸の腰兵糧を取って、わずかに飢えをしのぐ者もいた。或いは馬を殺して食べたり、遂には死人の肉を喰らう者も出てきた。
里見義実はこれを憂えて、杉倉木曽介氏元らもろもろの士卒を集めて言った。
「安西景連は裏切り者である。誓いを破り、義に違う、悪知恵は今更言うには及ばないが、恐れるべき敵ではない。奴が両郡の兵を率いて我が両城を攻撃するのであれば、我も二郡の兵を持って奴の二郡の兵に備える。十二分に勝てなくても互角の戦ができるだろうに、私の徳が足らないせいで、五穀は実のらず倉庫は空になり、外には敵の大軍がいる。戦況はまだ分からないが、残りの力はもうない。例え我らに百人の樊噲、前漢の劉邦の勇士がいても、飢えてしまっては敵を討つことはできない。ただこの義実の心は一つ、この身のためにこの城中の士卒たちが殺されてしまうのは忍び難い。今宵、皆は闇夜に乗じて、西の城戸から脱出せよ。何とか逃げ切ることができるだろう。その時、城に火を放って、妻子を刺してから、この義実も死ぬと決めた。二郎太郎も落ちよ。その手立てはこの様にせよ」
と細かく説明するが、皆は一斉に反対した。
「ご命令ではございますが、禄を受けて妻子を養い、今、この困難に遭って、己だけ逃げることなどできません。ただ命のあるうちに、寄手の陣へ夜討ちして、名のある敵と刺し違え、里見の殿への君恩を泉下にご報告いたします。これ以外のことは露ばかりも望んでおりません」
と言葉を等しく返答するので、里見義実は何度も説得を試みるが、誰も承諾する様子はなかった。
この時、里見義実の息子である二郎太郎義成は十六歳になっていた。
父の仁愛、士卒の忠信、共に貴重なことと聞いてはいたが、このままでは決着が着きそうもないので、父の様子を見て、
「弱冠の私が違った意見を申し上げる訳ではないが、天の時は地の利に及ばず、地の利は人の和に及びません。城中、既に兵糧は尽きて、士卒は飢餓に襲われてていても、脱出しようとする者はおらず、しかしながら死を目の当たりにして、徳に寄り恩を思う、これこそ人の和のいたすところではありませんか。人の性は善であるから、もし寄手の軍兵にもことの善悪邪正を知っている者がいるでしょう。また兵糧が尽きても、毎日炊事の煙を立てれば、敵は我らの窮状がここまでとは気づかず、また急いで攻め込んでこないのは、父の武勇を恐れているからでしょう。この二つから計略を考えたのですが、大声の者を選んで、城の櫓に登って、寄手に対して安西景連の非道なる行い、盟約を破り、恩を仇として、不義の戦を起こした、というその罪を責めさせれば、安西の士卒もたちまち慚愧して、戦う心を失くすでしょう。その時こそ城から打って出て、ただ一揉みに突き崩せば、勝つ見込みもあるでしょう。この案はいかがでしょうか」
とさわやかに言うので、皆は感服して試してみようと言う。
里見義実は試みに声の高い者を選んで、安西景連の不義を数えてその罪を責めさせた。
しかし日頃は声が良く出る者であっても、飢えては息も続かない。また櫓は高く、堀は広いので、腹筋が切れそうになるまで口を張り、顔を赤く染めて心から罵ってはみたものの、敵の陣へは声は届かなかった。
果てにその者は涙に泣き濡れて、咳込むだけになってしまい、苦労はしたものの効果はまったくなかった。
その間、里見義実は、逃げ出そうとしない士卒を救う方法が他にないかと考えを巡らすものの、そうは簡単に敵を退ける手立ては思いつかなかった。
歩きながら考えようと杖を曳いて庭に出てそぞろに歩いていると、年来可愛がっていた犬の八房が、主人を見つけて尾を振って近づいて来た。久しく飢えている犬は、ひょろひょろとして足取りが定まらない。やせ衰えて、骨高く、眼は落ち込んで、鼻が乾いていた。
里見義実は犬を見て、その頭を右手で撫でてやり、
「ああ、お前も腹が空いたか」
と呟くのだった。
「士卒の飢餓を救おうと熱心に考えていたので、お前のことを忘れていた。賢さに差があると言っても、人は万物の霊長で、知恵があるものだ。教えに従い、法を守り、礼儀や恩義を知る者であるから、欲望を禁じ、情を堪え、飢えて死ぬのも天命であり時運であると思って、私は諦めた。犬畜生にはその知恵はない。教えも受けず、法も知らず、礼儀も恩義も弁えず、欲望を禁じることも知らない。主人が養うことによって一生を送るので、飢えて飢える理由を知らず、餌を求めてますます媚びようとするのもまた不憫だ。犬畜生は恥辱を知らない愚かな生き物かもしれないが、人より優れたところもあるのだ」
里見義実は身体を寄せる八房をもう一度撫でた。
「例えば犬は主人を忘れない、鼻でものを良く嗅ぎ分ける、これらは人の及ばないところで優れたところだ。だから古歌にも詠われている」
目を閉じて歌を思い出す。
思いぐまの、人はなかなかなきものを、あはれに犬の、主を知りぬる
【思いやりも人がなかなか持てないのに、犬は素晴らしいことに主人が誰かを知っている】
「慈鎮(慈円)和尚が詠んだと思う。今、試みにお前に問おう。犬は十年の恩を良く知ると言う。もしその恩を知るのであれば、寄手の陣へ忍んで、敵将安西景連を喰い殺せば、我が城中の士卒の命を救うことになる。そうすればその功績は第一だ。お前にできるか」
と微笑んで問えば、八房は主人の顔をつくづくと見上げて、その趣きを良く悟った様である。
里見義実はいよいよ犬を不憫に思って、頭をまた撫でてやり、背中を撫でてやり、
「八房よ、しっかり功名を立ててみせよ。成し遂げることができれば、魚でも肉でもたらふく食べさせてやろう」
と言ったが、背中を向け、断るような素振りに見えたので、里見義実は戯れにまた続けるのだった。
「それでは職を授けようか、或いは領地を知行しようか。官職も領地も望まないのなら」
とうとう里見義実は言ってしまった。
「お前を我が婿にして、伏姫を娶せようか」
と。
この時、八房は尻尾を振り、頭をもたげて瞬きもせずに主人の顔を熟視してから、わんと吠えた。里見義実は苦笑いして、
「伏姫は私と等しくお前を可愛がっているので、妻にしたいか。敵を倒したのであれば、婿にしてやろう」
と厳かに言うと、八房は前足を折って、主命を拝したかの様である。鳴く声は悲しく聞こえたので、里見義実は興から醒めて、
「馬鹿馬鹿しい。我ながら戯言を言ってしまった」
と独り言を言い、やがて奥の部屋に入ってしまった。
かくてその夜は、大将も士卒もこの世の名残りぞ、と思い定めて、里見義実は、宵の間はしばらく奥の間にいて、夫人の五十子、息女伏姫、嫡男義成を最初に、老臣の杉倉木曽介氏元を近くまで招き、皆で集まり、別れの盃を交わすのだった。
しかし柄の長い金製の銚子には酒が一滴もないので、水を代わりにして、酒の肴には枝付きの木の実が少々出された。
木の実は大方虫に食われていて、普通なら下賤の者でも食べない様な代物だったが、この時ばかりは大切なものであり、美味い食べ物であった。
今宵の席上はひっそりと静かであり、ただよもやま話や昔話について語り合い、最期を迎えることについては一言も触れることはなかったが、死ぬことを決めた主従はなかなかに勇ましかった。
こんな時であっても、武士の主君である里見の妻子たちは、長き別れを惜しむものの、音に出して泣くことはなかったが、心を推し量った侍女たちは、皆涙の泉をこらえ切れずに同じ悲しみに沈んでいた。
いかにも道理、と杉倉氏元らは思わず嘆いて、互いに眼を合わせた。七日間この方一度も食べていない人々もまた眼が窪み、頬骨が出て、まだ死ねないがいずれ土となるであろう顔色は、憔悴し、衰えて生気がなかった。
今宵十日の月が沈むころ討って出る、と予てからの軍令を聞いていた雑兵らも、思い思いに此処かしこに集まって、酒と例えて水を酌み交わした。
水盃に映る星の影、鎧の袖の霜もやがて消えようとする丑三つ時のころになった。
「時刻は良し」
と里見義実父子は手早く鎧を身に着け、五十子、伏姫はかしずく侍女たちが渡す太刀や薙刀を受け取った。遠くから風が運んでくる寺の鐘の音は、諸行無常の響きであった。
しかし突然、外から犬の鳴く声が聞こえてきたので、里見義実は耳をそばだてた。
「あれは八房だ。いつもとは違う鳴き声だ、皆聞くが良い。誰か見て来てくれぬか」
と言えば、承ったと返答して、二三人が素早く立って縁側から紙燭を灯した。
「八房、八房」
と呼び掛ければ、八房は踏み石に足を掛けて、生々しい人の生首を縁側に載せて守っている。
「これはどうしたことだ」
と目撃した者は戸惑い、里見義実のところに戻って来て、
「八房が人の生首を持って参りました」
と報告した。
聞いた主従は皆驚き、怪しんだ。その中で杉倉氏元は皆に振り返って、
「飢えると、人の亡骸を喰らうのも犬の習性だ。これ見よがしに持って来た首は、見れたものではないだろう。奥方や姫がおいでなのだ、早く追い払ってくれ」
その指示に従おうとした者たちを、里見義実は待てと呼び止めて、
「犬がいても問題はない。八房も飢えていたので、もし味方の死骸を傷つけているなら、そのままにはしておけまい。私も自分で見てみよう」
と言って立ち上がった。
杉倉氏元はもちろん、その場にいた士卒も侍女たちもどよめいて、ある者は蠟燭を取って先導しようとし、ある者は主人の後について、縁側も所狭しと集まった。
例の首を見ると、里見義実は眉根を寄せて、
「杉倉木曽介はどう見るか。鮮血に塗れて分かりにくいが、これは安西景連に似ていないか。洗ってみよ」
と言うので、杉倉氏元もまた訝りながら、首を手水鉢の近くに寄せて、柄杓で水を何回も掛けて血を洗い流した。
主従で首を良く見てみると、
「果たしてこれは敵将安西景連の首に疑いもない、間違いないだろう」
と里見義実が言うので、皆それを信じる様になった。首がある訳などは分からないが、人々は皆が及ばない軍功に、ひたすら犬の八房を羨んだ。
【戲言を信じて八房、敵将の首級を献上する】

首を咥えて、主に褒めて欲しがる忠犬八房さん。
その時、里見義実は感心して、
「この様に奇怪なことを見たが、前兆も後兆もない訳ではない。今こそ思い出される。皆、我がために、蜻蛉の様にはかない命を捨てると決意し、士卒をどうやって救おうかとも思ったが思いつかず、気晴らしかねて我が身一つで庭園へ行った折にこの八房がいた。飢えているその姿を見るに堪えず、八房を思い、哀れと思って、お前が寄手の陣へ忍び入り、安西景連を喰らい殺して城中の数百の士卒を救うことができれば、毎日魚肉に飽かさないと言っても、喜ぶ気配もない。所領を宛がおうか、重い官職を授けるかと言っても喜ぶ気配がない。でなければ日頃常にお前を愛する伏姫を妻に取らせようか、と言った時に、八房は喜んだ様な表情をして、尻尾を振りながら吠えた声音はいつもと違っていて、忌々しかった。戯言と思って出てしまった言葉は馬鹿馬鹿しいと独り言を言って、そのまま皆を集めて、最後の軍議を開くことに忙殺されていて、そのことは忘れていた。犬は言われたことをなかなか忘れないから、高麗剣ならぬ狛剣、当家の犬の剣は我が虚言を真実として、寄手の陣に忍び入り、二三千騎の大将である安西景連をいともたやすく殺して、その首をもたらすということは不思議というにもあまりある。奇跡だ」
と八房を近づけて、ひたすら褒めた。それを聞いた杉倉氏元らは愕然として舌を巻き、
「犬畜生でありながら、人よりも高い功を挙げたことは、すべて殿の仁心と徳義によるものだろうか。神明と御仏のお力によるものかもしれない」
と称賛した。
その時、物見に出していた兵士が庭から入って来てこう言った。
「敵に異変が起きている模様です、急に乱れ騒いでいる様子でございます。速やかに撃って出れば、勝利疑いございません」
と言うのを里見義実は聞くが早いか、
「そうであろう。時間を掛けるな、撃って出よ」
士卒を急き立てて、全軍に下知を伝えてから、大将みずから寄手の陣を襲おうとすると、若き里見義成が進み出た。
「安西景連が既に死んだのであれば、例え寄手は大軍であっても、追い払うことは大変容易いことでしょう。ですから我が軍の総大将が軽々しく出撃されるのはもったいございません。ここはこの義成に杉倉氏元を添えていただければことは足ります。どうかお許し下さい」
と乞い、庭から走り出し、部下が引いて来たやせ馬に身を躍らせて乗るのだった。杉倉氏元も士卒を励まして、
「八房が早くも安西景連を討取ったぞ。遅れる者は犬にも劣る、出でよ、進め」
そう叫んで三百余騎を二隊に分けて、里見義成は大手門から、杉倉氏元は搦手門から、城戸をさっと押し開かせて、乱れ騒いでいた寄手の陣へまっしぐらに突いて入っていった。
その勢いは日頃の何倍もあって突撃したので、敵軍はますます辟易し、逃げ出す者が半分もいた。早くも降参する者も出てきて、思い悩む者たちが迷っているうちにその夜は明けていった。
こうして里見義成と杉倉氏元は、山の様に積み蓄えられていた寄手の兵糧をすべて、城中へ運び入れた。そして戦の次第を里見義実に報告し、降参した敵兵たちをすべて許して、杉倉氏元に預けることにした。
そして、今朝から米を炊いて、籠城していた士卒らに粥を与えたが、一杯の他は許さなかった。長く飢えている状態だったので、急に満腹にさせると、すぐに命を落とすことになるからである。それだけでなく得た兵糧の半分を城外の人々に与えて、ようやくその飢餓を救った。人々は拝伏してこれを受け、皆でこれを分かち合い、充分に食べて命びろいをした。轍にはまった魚が水を得たようなものである。
この間に東條の城を攻めていた安西景連の老臣蕪戸訥平らは城を何重にも囲み、昼夜を置かず攻め立たてたが、東條城は滝田城よりも半月の貯えがあった。
堀内貞行は敵を追い払い滝田城の後詰をしようと始めから考えていたが、雨の夜、風吹く夕べには敵陣へ夜討ちを再三仕掛けるものの、味方の軍勢に対して寄手が大軍過ぎた。必勝を期したが、敵は新手を入れ替えるため、弱る気配はまったくなかった。
しかし安西景連がはかなく討たれ、滝田の包囲が急に解かれて、御曹司里見義成が杉倉氏元と共に大軍で東條を救援に来る噂が誰彼と言うことはなく流れた。城兵はそれを聞いて勇気百倍となり、寄手の兵たちはそれを聞いて大慌てとなった。
始めのころ蕪戸訥平は風聞を聞いても知らぬふりをして、部下の士卒を罵り、あるいは励ますものの、昨日に比べて今日は部下たちが落ち着かない。
単なる噂ではないといよいよ疑心暗鬼になり、怖気ついた蕪戸訥平は腹心の二三名を従えて、他の配下に黙って闇夜に紛れて逃げ出してしまう始末だった。
夜が明けて、寄手の軍兵は自分たちの大将が逐電したことをようやく知って、呆れ、戸惑い、身勝手な大将を憎み、腹を立てるのだった。仕方なく安西の残兵は協議して、東條城へ使者を出して、今更ながらおめおめと降参する他がなかった。
堀内貞行は、滝田の殿に子細を申せ、と騎馬の使者を送り出したが、その使者は途中で滝田城からの勝ち戦を告げる兵士に出会った。
滝田からの使者は東條に来着し、安西景連の落命とことの次第を告げ、噂通りに御曹司が大将、杉倉氏元を副将として出陣すること、東條城周辺の敵を追い払うこと、更に館山と平館の両城を攻めることを伝えた。
堀内貞行は謹んで君命を受け、使者を再度滝田に送って、安西討伐の勝ち戦の祝賀を伝えた。
御曹司の出陣と今か今かと待つ間に、以前から里見義実の徳を慕う安房郡と朝夷郡の民衆が、安西景連が滅んだと聞いて、館山と平館の両城を攻め立てて落城させた。
そして主な者が数十人が蕪戸訥平らの首を持って東條にやって来たその日に、里見義成と杉倉氏元が着陣したのである。
里見義成と杉倉氏元、堀内貞行らは詳細をしたためて、滝田の城に報告するとともに蕪戸訥平らの首も送った。
受け取った里見義実は、安房郡と朝夷郡の者たちを呼んで褒美を与えた。更に御曹司里見義成と杉倉氏元に御教書を下して、館山と平館の両城を守らせる様にした。
こうして四郡一か国を里見義実が治めることになった。
その勢いは朝日が昇るがごとく、徳とその恵みは雨が大地を潤すがごとく、邪悪なる者たちを走らさせ、善人たちが時を得たのだ。
これより安房の国では、夜は戸に鍵を掛けず、落ちているものを拾って盗む者はいなくなった。
向後の行方はいざ知らず、安房に騒がしい波風が立たなくなったので、隣国の武士と言えばもちろん、足利持氏の末子である足利成氏も、この時滝田に書を送って安房一国平定の功を称賛した。足利成氏はこのころ鎌倉公方として鎌倉府に戻って数年になってはいたが、里見氏のために更に室町将軍へ安房国主とする様に推薦し、治部少輔の官職を授ける様になったと言う。
里見義実は歓喜雀躍し、京と鎌倉に使者を送り、土産と進物をいろいろ献上した。
(第四代鎌倉公方足利持氏の末子を成氏と言う。去る1444年嘉吉三年に長尾昌賢が取りなして、鎌倉へ迎え入れ、鎌倉公方に就任させて早や十余年が経った。しかし足利成氏は故あって鎌倉に居続けることができなくなり、康永のころ、下総の許我へ移り住んでいた。ここに年代を記そうとすればこの年のころだろうか。足利成氏のことは九代記という書物に載っている。)
この様に喜ぶべきこと祝うべきことが続いたが、里見義実の心に引っ掛かるのは、初め安西景連に食料の援助のために使者として遣わされた金碗大輔のことであった。
里見義実は、
「彼は年が若いが、おめおめと何もせず、敵の虜囚となる者ではない。欺かれて討たれてしまったのだろうか。また兵の数の多少を計らずに、寄手に攻め込んであたら命を落としてしまったのか、そうでなければ、昨日今日までに帰ってこないことはあるまい。私が所縁のないこの土地を切り開き、ここに富貴を受けることができたのは、彼の親、金碗八郎孝吉の助けによるものである。臨終にその子を長狭郡の郡司とし、東條城の城主にする、と言ったのにいまだ果たせていない。それだけではない、納得できないのだ、金碗大輔の亡骸だけでも見れないのは本当に心残りである。樹を切って草を刈り払ってでも、行方を調べよ」
と四方八方へ人を送り出し、先々まで触れを出して隈なく捜索させたが、金碗大輔の行方は絶えて分からなかった。
その間に里見義実は士卒たちの勲功を一人一人に厳正に行い、所領を与え、職を進めた。褒美を与えることの始めに、犬の八房を第一の功と定め、朝夕の食事、寝泊まりするところを豪華にして、犬養の職や下僕を定めた。
外に出る時は先導の役を付け、中に入る時は見守り役を付けたので、飼犬への寵愛は人々の耳目を驚かせたが、当の八房は頭を垂れて、尾を伏せて、餌を食べず、夜も眠らず、去る宵の晩敵将安西景連の首を持ち帰った縁側に来て、立ち去ろうとしなかった。主君が出て来たのを見ると、縁側に前足を掛け、尻尾を振り、鼻を鳴らして、何かを乞い求める様である。
しかし里見義実はそうとは気づかず、みずから魚肉や餅などを折敷に載せて与えようとするが、八房は眼もくれず、尚も他のことを求めようとすることがしきりであった。
この様なことが度重なったため、さすがに里見義実も犬の心に気づいて、まさかと思い当たることがあった。たちまち八房への愛が醒めて、そばに来なくなった。犬養らが八房を遠くに連れ出そうとしても、ややもすれば猛り狂って従おうとしない。とうとう鎖を引きちぎって、止めようとする人に対して吠え、例の縁側から飛び乗って、奥へ向かってあちこちへ奔走し始めた。
しかし八房を追う犬養らは、遠慮して入れない扉があるので、手を挙げて、犬があちらの方へ、と叫ぶことしかできない。 男の力でもかなわない犬が猛り狂うので、侍女たちは皆恐れ、惑って立ち騒ぎ、ここかしこに走り、逃げ、八房はまたそれを追った。犬もろ共に人も狂って、障子と襖を押し倒し、叫び喚き、思わず伏姫のいる奥座敷へ追い込んでしまった。
この時伏姫は話し相手もなく、文机に肘を置いて枕草紙を読んでいた。
翁丸という犬が一条帝の飼い猫を驚かせてしまったことで、帝の勅勘を被って、宮中から捨てられてしまったこと、また許されて宮中へ戻ってきたことを素晴らしく書き記した清少納言の文才を羨み、
「昔はこんなことがあった」
と独り言を言い、その段を繰り返し読んでいた折、侍女たちが叫ぶ声がして、背後に走って来るものがあった。
その早さは飛んでいるようであり、寝床に立て掛けていた筑紫琴を横に倒しそうになって、伏姫の裳裾の上に臥したものを何だとばかりに見返せば、正体は八房であった。その顔は平常ではなかった。
「病気なのだろうか、嫌だなあ」
と文机を押しやって立とうとするが、犬の臥せた前足が長い袂に入って踏んでおり、動くことができない。十年飼い続けて、大きな子牛の様に力強い大犬が踏んでいるので、後ろを動かすことができないのだ。
伏姫は人を何回も呼び、世話係の侍女はすぐに飛んで来たが、犬に驚くだけで近づくことができない。
一人の侍女が箒を引っ提げてやって来て、畳を叩いてしっしと恐る恐る追い払うとするが、八房は眼を怒らせて、牙を見せて唸るばかりである。
唸り声が凄まじいので、侍女は恐がって、箒を捨てて後ずさりしてしまうのだった。
そこへ誰かが知らせたのか、里見義実が手槍を持ってやって来た。
戸口に立ちつくして恐れて混乱している女児たちを叱って、急いで前に出て来た。
「やおれ畜生のくせに、出て行け、さあ、出て行け」
【里見義実怒って八房を追い出そうとする】

里見義実さん、超激怒。怒りまくって激おこぷんぷん丸。
槍が長過ぎませんかねえ、そんな長いと、姫に間違って当たってしまいますよ!
昔、五帝の一人、嚳(こく)が高辛氏とも呼ばれていた時、犬戎(西戎)が襲来してきた。
帝はその侵略を憂いて征伐しようとしたが、勝てなかった。
帝は、天下に、犬戎の将、呉将軍を討取る者があれば黄金と家、また娘を娶らすとして、人材を求めた。
その中に飼犬がいた。その毛は五彩で名づけて盤瓠(はんこ)という。
命を下したのち、盤瓠は急に首を咥えて宮中に戻って来た。群臣が怪しんでこれを見ると、呉将軍の首であった。
帝は大いに喜びなさったが、娘を盤瓠に娶らそうとはしなかった。また功績を賞しようともしなかった。
宮中では議論をして報いようとしたが、結論が出なかった。
娘はその話を聞いて考えた。皇帝が命令を下したのに、信頼を違えてはならない、と。
帝はやむを得ず娘を盤瓠に嫁がせた。盤瓠は娘を得ると背中に背負って南山というところの石室の中に入っていった。そこは険しい山の中であり、他に人の住んでいる気配はなかった。
三年を経て六男六女が生まれた。そこで盤瓠は妻と別れた。
子供たちは五色の服を好み作った。皆、尻尾があった。
例の娘、母は後に皇帝に手紙を送り、子供たちを宮中にお迎え下さいと依頼したが、衣装が蘭の花の様であり、言葉が全く異なっていた。また急峻な山を好み、平らな土地を好まなかった。
皇帝は彼らの意を汲んで、名山廣澤を賜った。子孫たちは増えていった様である。
その一族は自分たちを号して、蛮夷という。今の長沙武陵の野蛮人がこれだ。
また北狗国の人は身体は人間だが頭部が犬で、長毛して衣服を着ないという。その妻たちは皆人である。男の子を生めば犬、女の子を生めば人となるという。五代史にそう書いてあった。
と、持っている手槍の取っ手の部分の石衝を差し出して追い出そうとするが、八房はちっとも動かず、きっと見上げて牙を出してますます雄叫び声が凄まじくなり、誰彼構わなく嚙みつきそうである。
里見義実は顔色を変えて怒り出し、声を荒げて、
「理も非も知らない畜生に物を言うのは無益の様だが、愛する主人を知らないのか。知らなければ思い知らせてくれよう」
と怒り、槍を取り直して突き殺そうするが、伏姫が自分の身を盾にして、
「お、お待ち下さい、父上。ご領主のご身分で、牛に悪戯する童の様に畜生の非を咎めて、自ら手を下すことなどいけないことでございます。少し思うことがございますので、曲げて私の我がままをお許し下さい」
そう言い掛けて眼を拭うので、里見義実は突こうとしていた短槍を引いて、脇に挟んだ。
「珍しい姫の諫言だ。言いたいことがあれば言ってみなさい」
父が娘を急がせると、伏姫は落ちる涙を拭い、顔を改めて清めた。
「はばかりがあることでございますが、今も昔も、我が国も唐の国も、賢い主君の政治は、手柄があれば必ず賞を与え、罪があれば必ず罰すると聞いております。もし手柄があるのに賞されず、罪があるのに咎められなければ、その国は滅ぶことでございましょう」
伏姫は八房を見つめた。
「例えば、この犬の様に功績があっても行賞されず、罪がないのに罰を被るとは不憫ではございませんか」
それを聞くや否や里見義実は、
「お前の意見は間違っている。安西という強敵が滅んだ時から、犬のために犬養の職を置き、食事には美味いものばかりを与え、寝るところにも良いものをやった。これでも賞がないと言うのか」
と詰ったが、伏姫をきっと頭を上げて、
「綸言汗の如しとは、一旦言葉を出したら取消しできない例えでございましょう。また君子の一言は四頭立ての馬車も及ばないと聖人の記した書物にある、と物の本にも記してございます。悲しいかな、父上は安西景連を討ち滅ぼして、士卒の飢えを救うため、この八房を婿とすることをお許しになったのではございませんか。例えそれが仮初めのお戯れでありましても、一度お約束なさったのであれば、綸言は戻りませんし、お言葉は四頭立ての馬車も及ばないのでございます。それでは犬が求める恩賞を許して上げて欲しいのです。八房が大功を挙げるに及んで、今更に約束を守らずに、代わりに山海のご馳走を与え、また豪華な住まいを与えて、ことが足りたとされたら」
里見義実を見た。
「もし人であれば、口惜しく、恨めしく思うことでしょう。人よりも大功がある犬畜生に与えるべき恩賞そのものに私がなっても、皆、前世の因果応報と思うでしょう。国のため、後世のため、娘を生きながら畜生道へ捨てて犬の伴侶としても、ご政道に偽りがないことを民衆に知らしめ、平穏無事に豊かに国をお治め下さい。そうしなければ、盟約を破り、約束に背く、あの安西景連と何が変わると人々が申すことでしょう」
父の戯言の通りに犬に嫁ぐと娘は言うのだ。
「浅はかな娘の、目先のことしか考えられない浅知恵も、世間も汚れも知らないことからこそ、深く嘆くのでございます。私の心を汲んでいただき、今日からは、恩と愛、二つの義を断ち切って、どうか我が身にお暇を下さい。子として親に自分を捨てよと願い、異類に従う娘は、三千世界を探しても、私の他におりませんでしょう」
と父に別れを掻き口説くその袖に落ちた涙の露は、ここ滝田の城のみに訪れた秋の気配であった。
里見義実はただ黙って娘の言うことを聞いていたが、最後には嘆き悲しみ、持っていた槍をからりと投げ捨てた。
「ああ、私は間違えた。間違えたのだ。法度は上の者が制するものだ。上がまず犯し、下の者が犯していく。これが大乱の基本である。私は八房に姫を与えるつもりはない。ないと言っても、言ってしまったことは、私の口から出て、犬の耳に入ったのだ。昔、中国の藺相如が完璧の故事の通りに、勇をもって夜光の珠を取り返したが、取り返しにくいのは口の咎である。この様に、災いは門に臥している犬であった、犬は我が身の仇だ」
こう嘆くのである。
「そう言えば昔を思い出すと、前兆があった。この子が幼かったころ、願を掛けるため忍んで洲崎の石窟へ詣でた時、途中に老人がいた。伏姫を見て差し招き、この子の多病と毎夜むづかる原因は、皆悪霊の祟りによるもので、詳細に説明すれば天の秘密を漏らしてしまう恐れがある。伏姫という名前によってみずから悟ることができれば、何かを得るだろう。帰ってその旨を主君に言え、と老人は言ったのだ」
恨みがましい口調になった。
「姫は1442年嘉吉二年の夏月伏日に生まれた。酷暑の三伏の義から名を取って、伏姫と名づけたのだ。その名前から考えよとはいかなることかといろいろ考えたが、まったく思い当たらなかった。有地無知三十里のことわざで、あの三国志の曹操を嘲り笑った秀才の楊修がここにいれば問うてみたかったが、長年経ってから、今日突然に理解することができた。伏姫の伏の字は人にして犬に従うということだ。この厄災は、おしめをしていたころから定まっていたことか。名詮自性、名前がそのもの自体の本性を示しているということなのだ。ここまで執念深く祟りをなす悪霊は誰かとはっきりとは知らないが、良く考えてみれば山下定包の妻であった玉梓だろう。あの淫婦は、主人を損ない、また忠良なる家臣を失わせるという隠れた悪事の噂がある。しかし一度は命を助けると言っておいて赦さなかった私に仇をなすことができず、私の子に憂いごとの限りを見せて、理屈に合わない恨みを返すつもりなのだ。そう言えばこの犬は母を失って、狸が育てたと聞く。狸の異名を野猫と言い、また玉面とも呼ぶ。その玉面を和訓で読めば、すなわち、たまつらだ。玉つさと玉つらと読み方も近いのも禍々しいのに気づかずに、いかにも賢しげに狸という字は里に従い、犬に従うことがあれば里見の犬になる性である、と思いながら飼い慣らして、可愛がってきたことが口惜しい。太陽は満ちた後は欠けていく、洲崎の翁が教え諭したことは、なるほど当たっていよう。今思えば百回悔い、千遍悔いても意味がない。畜生のために子を捨てて恥辱を残せば、たくさんの国を討ち従えて、今後長く百代の栄誉を受けたとしても、何が楽しいだろうか。面目ないことこの上ない」
と今までについて説き、心の底から説明した。そして反省して後悔する主君を見て、側で侍る侍女たちは慰めることもできず、大騒ぎの恐怖が今になって襲ってきて、泣くのだった。
皆の涙は滝の糸となり、それを見ていた伏姫は、苦しかった心のつかえをようやく撫で下ろし、
「私の侍女ですら堪えられない嘆きに悲しんでくれている。まして親の御心を推察してみれば、なさぬ不孝は罪が重うございます。しかし、一度鬼畜の犬に伴われて、父上の約束に嘘偽りがないことを証明すれば、命はもうなきものと思い定めております。しかし、この世に人として生まれて今まで育ってきた親の形見のこの身を、まざまざと畜生に汚される訳にはいきません。どうかご安心下さい」
と言って顔を赤らめた。
我が子が袖で顔を覆って顔を伏せると、里見義実は何度も頷き、
「よし、良く言った。遥か遠い異邦のことを考えると、高辛氏の槃瓠(はんこ)の話は私の心配ごとと同じだ。また東晋の干宝が著作の捜神記にこんな物語がある」
里見義実が語った話は以下の様な話だ。
大昔にある男性がいた。戦に遠征し、長い間家に帰らなかった。
妻は早く世を去ったが、一人娘がいた。年のころは二八だった。
またその家に牡馬がいた。娘は明けても暮れても父親を慕うあまりに、馬に向かって、
「お前、もし父上を乗せて帰って来てくれるなら、この身を任せましょう」
と言ってしまった。
これを信じて馬は手綱を断っていなくなってしまったが、数日経ってから、果たして馬は父を乗せて帰って来た。
以来、馬は嘶いて、何かを乞い求める様になった。
父はそれを怪しんで娘に事情を聞くと、娘は父を連れ帰ってくれば身を任すという約束をしたと答えた。
打ち捨てることはできない、と父は密かに馬を殺してしまい、皮を剥がして軒先に掛けてしまった。その時、娘は馬の皮を見て、
「畜生にして人に欲情した結果、報いはこんなに早かったのか。皮になっても、尚、私を娶ろうというのか」
と罵った瞬間、馬の皮は軒先からはたと落ちて、娘の身体をしかと押し包んだ。さっと吹き上げる風とともに、皮は空に飛び、空を登っていった。
次の日、庭の桑の樹に娘の亡骸が掛かっていた。その屍から虫が生まれて、これを蚕と呼んだ。
「これは信じがたい話だが、唐土では三国志の魏や晋の時代から言い伝えられてきた物語だ。この話の男性は、いやしくもことを命じておいて約束を守らないだけではなく、馬を殺してしまうなど、人にして心根が獣より劣っている」
里見義実の声は震えた。
「私がもし一時の怒りに任せて、犬の八房を殺してしまえば、捜神記の男性と同じになってしまう。そうは思っても、折り悪く、息子の義成と杉倉氏元には館山と平館の城を守れと遣わしているし、また堀内貞行は長狭郡の東條の城にいる。彼らの他には内々のことを語る者はなく、良くも悪くも心は一つ、今は思い定めた」
伏姫も父の顔を見上げた。
「おい八房、戯れではあったが、命じたことを成し遂げたお前の勲功はとても高い。伏姫を」
一瞬言葉が切れた。
「お前に与える。だからしばらく外に出て、待て。さあ、外に出よ」
と催促すると、八房は主人の顔色をつくづくと見てから、ようやく身を起こした。そして全身を震わせてから、静かに外へ出ていくのだった。
(続く……かも)










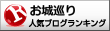

















ありがとうございます。
現代では、こういう話は聞きませんが、昔は多かったのでしょうね。
はたして、本当に犬や馬だったのでしょうか…
身分差別とかだったり?と思ったりします。
が、馬琴翁は物語として、言い伝えそのものだと思いますが、今読むとなんともおぞましく感じます。
「伏」この字が怖くなりました。
ご指摘の通り、本当に異類かどうか、正体は階級の違う人ではなかったか……
なあるほどですねえ。
さらにさらに
「綸言汗の如し」
お偉いさん方に言ってやりたい!
後継ぎどうするつもりだったんでしょうねえ。
伏姫にイケナイことするつもりだったと思えば、
しゃあなしですね。
綸言汗の如し、日本では後白河法皇に対して言われたのが最初だそうです。
偉い人も大変なんですねえ。
私なんか、いつも自分にも朝令暮改なんですぞ(笑)
貴殿におかれましては…
関西におられるかと思ったら関東におられたり…
今月初めは、南にもおられたし…北も廻られたし…
東奔西走って感じするんですが…神出鬼没かな