
南中仕切門から東に進んで、本丸外堀の南東隅まで来ました。嫁さんが左手の上図の景色を指して「これも絵になりますねえ、時代劇のロケで使ってるわけですね、水戸黄門の水戸城とか・・・」と言いました。

本丸の東虎口の櫓門と東橋です。櫓門の内側に塀が続きます。寛永改修時は、後水尾天皇の行幸に際して橋を二階建ての廊下橋とし、そのまま櫓門の二階を通って通廊を経て本丸御殿に入れるようになっていましたから、現在の東櫓門の二階建ての姿は、その名残であることが理解出来ます。
ちなみに廊下橋に続く溜蔵と橋の手前までの二階廊下は、昭和の初めまで残っていて、昭和五年(1930)に解体されましたが、その部材は現在も土蔵に保管されているそうです。今後の復元が計画されているのかどうかは知りませんが、元通りに建てると、現在の本丸東虎口への見学順路を遮断する形になります。それで色々と支障が生じるために、復元の話が持ち上がらないのかもしれません。

外堀沿いに左折して北にある上図の立派な長屋門に行きました。本丸東虎口への動線を北の鳴子門とともに遮断する防御線としての城門で、桃山門といい、寛永改修時の建築遺構の一部をとどめるものとして国の重要文化財に指定されています。

桃山門の案内説明板です。嫁さんが読み始めてすぐに私を振り返り、「寛永行幸時の絵図には、て書いてありますけど、そういう絵図があるんですか」と訊きました。
「あるよ。江戸幕府の京都大工頭を勤めた中井家に伝来してる古文書の古絵図のなかに二条城関連のものが幾つかあるんやけど、寛永行幸時の絵図、ってのは「二条御城中絵図」のことで、当時の城内の建物の配置や名称が詳しく記されてる。雑誌やお城の本に載ってる二条城の復元イラストは、だいたいこれを参考にしてるはず」
「その絵図、見ることが出来るんですか?」
「出来る。ちょっとスマホ貸してみ、君も見られるようにしておこうか・・・・・・・・はい、これ」
「あー、職場のデジタルアーカイブなんですねえ、ほんまに「二条御城中絵図」ってある、あっ、建物が三色に色分けされてる、あー、本丸の建物みんな描いてありますね、多聞櫓も天守閣もみえる・・、これ凄ーい、いまじゃ無くなってる建物が色々ある、面白いわあ・・・」
「で、ここ桃山門のあたりを見てみ?」
「ええーと、こっちか、これですかね・・・えっ、ええーっ、なに、建物がずらっと並んでるじゃないですか、ここにも御殿が建ち並んでいたんですか・・・」
「その左側の建物の名前、分かる?」
「あれ、逆さまになってますね、でも読めます、権大納言、です」
「そう。寛永行幸時の権大納言の居間なんやけど、当時の権大納言は誰だったか、君は分かるんやろ?」
「後水尾天皇の時でしょ、二条城に同行してるから武家伝奏(ぶけてんそう)も務めてる筈ね・・・、広橋兼勝(ひろはしかねかつ)は違うな・・・元和に亡くなってるから。すると次の三条西実条(さんじょうにしさねえだ )かなあ・・・」
「そういうふうにパッと人名を思い出せるのな、流石やな・・・。で、その権大納言の建物の南にある大きな建物の名前、見てみ?」
「ええと、えーと、これ?・・・えっ、行幸御殿?・・じゃあ、後水尾天皇の御殿がここに建てられてたの」
「そう。その絵図は寛永行幸時に建設された行幸御殿以下の建築群が全部描かれてる。これがずっと、こう、本丸まで長い建物で繋がって廊下橋で東門を通ってる。分かる?」
「うん、これ、この御長局って建物ですね。その左に中宮御殿があるのね、東福門院徳川和子の御殿ですね」
「その中宮御殿の上の部分が御長局と繋がるあたりに通路をはさむ二つの部屋がある建物があるやろ」
「うん、名前とか書いてないですけど、これが今の桃山門の位置になりますねえ」
「その部分だけ建物を残して、長屋門の形式に造り替えたのがこの桃山門なんだろうというわけや」
「なるほどー、だから北の鳴子門と全然違って立派な城門になってるわけですねえ、もとは行幸御殿や中宮御殿からの通廊下殿の建物だったのが、形を変えていまに伝わってるわけですか」

桃山門は、「二条御城中絵図」では御殿に連接する通廊下殿の建物にあたるようで、その間取りをほぼ活かして通路空間であった部分をそのまま城門の戸口に改造したような構えになっています。
そのため、上図のように門口は太い堅固な木を使って鉄板張りとしていますが、門口の上の軒は城門らしからぬ雅な宮廷建築の造りのままで、横の建物も御殿風の細い柱と広い白壁に包まれています。

脇戸も追加され、その横の壁にも格子窓を追加して監視機能を持たせてあります。もとの御殿通廊下殿の建物をどのように改造したかがよく分かります。

脇戸の内側です。城門の脇戸にしてはがっしりした造りになっていません。むしろ普通の扉板の造りです。

そして門の内部の左右にはこのような広い空間があります。上図は東側の部屋で、城門には珍しく、天井板がはめ込んであります。御殿の建築群の内部空間のひとつがそのまま残されているような雰囲気です。

こちらは西側の部屋です。屋根裏の木組みも全部見えますが、城郭建築の組み方ではありません。宮廷建築の組み方がそのまま残されているようです。

桃山門から上図の東櫓門までは、現在は土塁に沿った道になっていますが、寛永行幸時は御長局と呼ばれた長い通廊殿が東櫓門の前の廊下橋まで続いていたわけです。この御長局の北の突き当りに溜櫓と呼ばれる建物があり、これが本丸への廊下橋の連接部にあたっていたわけです。
その溜櫓は、前述したように昭和五年(1930)に二階廊下とともに解体され、その部材は現在も土蔵に保管されているそうですから、復元しようと思えば出来る筈です。当時の古写真でその姿を見ることが出来ますが、なかなか立派な建物です。出来れば元通りに復元してほしいなあ、と思います。

桃山門から引き返して、二の丸の南側へ進みました。まもなく右手、南側に上図の門が見えてきました。嫁さんが「これ、高麗門っていうんですよね」と言いました。そうだ、と頷いておきました。
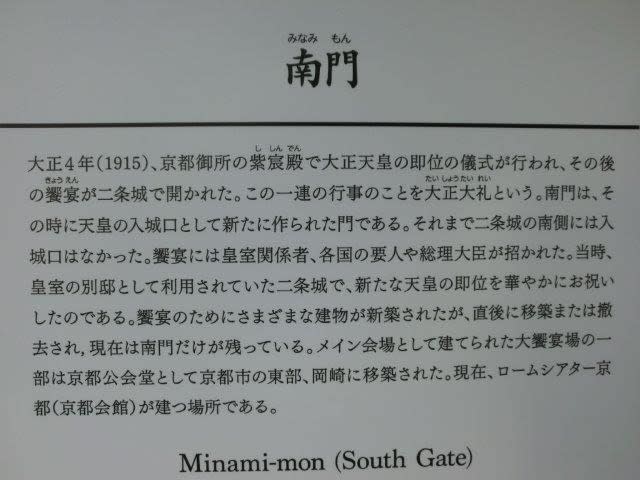
南門の案内説明板です。御覧の通り、大正天皇の即位式の饗宴に際して新たに設けられた門である旨が記されています。つまりは徳川期二条城にはもともと無かった門であるわけです。
「この門は、饗宴が終わってもそのままにして、撤去しなかったんですねえ」
「ここは当時は皇室の離宮やったからね、南向きなので、離宮の正式な門にあたるしね」
「そういうことですよね」
この南門とともに建てられた大饗宴場は、即位大典の儀式の後に解体撤去され、廃材が岡崎公園に建てられた京都公会堂の建物に転用されていますが、その京都公会堂も廃されて、現在は京都会館に建て替わっています。ロームシアター京都と呼ばれる建物のことです。 (続く)















