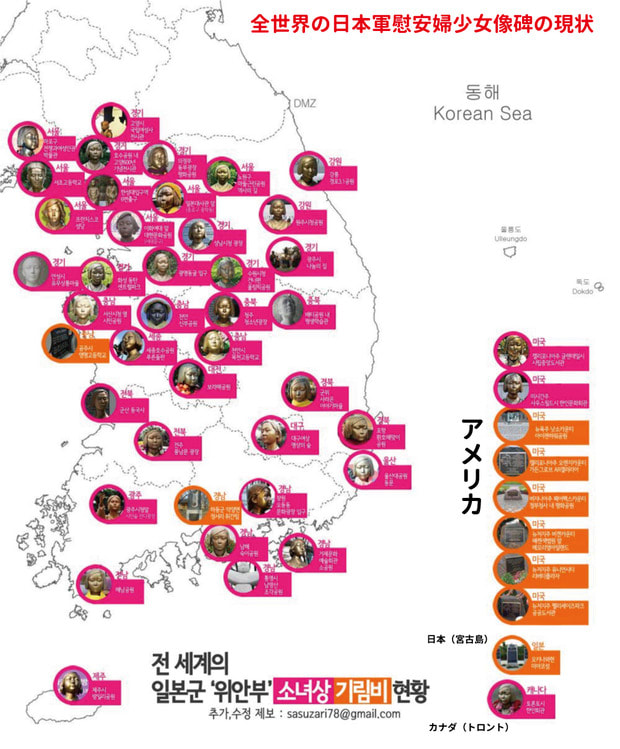司法試験経験者だがコロコロ変わる制度に振り回され、さらに意味不明のような意地の悪い短答式試験。
日本は欧米に比べて明らかに利権などが介在して制度設計能力が劣る無責任国家だ。犠牲にならないようによく考えることだ。
まして現在は、弁護士など食えない状況。
ちなみに海外では公務員の管理職などは皆、弁護士資格が要件となっている。すなわち司法試験通る価値がある社会制度になっている。
日本は判事、検事、弁護士の仕事以外に大企業の法務部くらいしか仕事がないが海外では弁護士資格が社会の多くの企業や公務員の昇進要件として評価されている。
司法試験に法科大学院はもはや無意味なのか?
6/23(土) 7:12配信 読売新聞(ヨミウリオンライン)
2002年にスタートした司法制度改革のもと、“目玉”の一つとして全国に70以上設立された「法科大学院」。近年は志願者数の減少などで各大学が運営に苦しみ、35の法科大学院が相次いで募集を停止する事態となっている。青山学院大学や立教大学といった私立の有名大学や、横浜国立大学も撤退を決めた。法科大学院はもはや役割を終えたのか。「予備試験」が11年にスタートし、法科大学院を修了せずに司法試験を受験できるようになったことで、存在意義が薄れたとする声もある。長く法曹界を取材するフリージャーナリストの秋山謙一郎氏が解説する。
司法試験に法科大学院はもはや無意味なのか?
写真はイメージです
◆エリートに学歴は必要なし?
昨年11月、地味ながらも、法曹界で注目されるニュースが報じられた。
法務省が発表した、法科大学院を修了せずに司法試験の受験資格を得るための「予備試験」の合格者に関する報道だ。同年の合格者は前年比39人増の444人。予備試験は2011年から始まり、6年連続で過去最多を更新した。また、『17年1月の出願時に高校生で、史上最年少となる18歳(12月末時点)の合格者も誕生した』(読売新聞2017年11月10日付)
今年5月には司法試験の「本試験」が実施された。6月上旬に発表された本試験の「短答式試験」の「(本試験)合格に必要な成績を得た者」の最低年齢は19歳。報道にあった予備試験の最年少合格者が、短答式をパスしたようだ。
9月には「論文式試験」も含めた本試験の最終合格者が発表される。もし、この受験者が最終合格すれば、19~20歳で司法修習生に、20~21歳で法曹(裁判官、検事、弁護士)の道へと進むことも可能になる。
予備試験の受験資格には、年齢、学歴、受験回数などの制限が設けられていない。合格すれば「正規ルート」とされる法科大学院修了者と同等の扱いが受けられ、司法試験の「本試験」にチャレンジすることができるのだ。
司法試験に法科大学院はもはや無意味なのか?
画像はイメージです
◆学歴・年齢不問「高校生でも受験可能」
予備試験の制度は11年に旧司法試験の廃止に合わせて新設された。例えば、17歳の高校2年生が予備試験に合格、翌年、司法試験に合格すると、法科大学院はおろか、大学にも通わず、(生まれ月によっては)19歳で法曹職に就くことも考えられる。正規の法曹養成ルートとされる法科大学院を修了すると、最短でも法曹職に就くのは25歳だ。
19歳と25歳――経験がモノをいう法曹の世界で6歳の差は大きい。こうした背景もあってか、今、法曹を目指す受験生らの間で「予備試験ルート」の人気はうなぎ登りだ。司法試験受験者らが集まる予備校でも、「予備試験対策」の講座を用意しており、「予備試験合格からの司法試験合格率」をウリにする予備校もある。
だが、元々予備試験は、経済的な事情などにより法科大学院で学ぶことができない人への「救済措置」として設けられた。それが当初の理念とはかけ離れ、一部の秀才たちの間で“飛び級”制度的に活用されているのが実態だ。
事実、17年の444人の予備試験合格者たちの内訳をみてみると、うち321人が現役学生(大学生・214人、法科大学院生・107人)で占められていた。ここ数年、同様の傾向にある。
今、法曹を目指す大学生の間では、大学進学後に予備試験を受験し、合格したら即、本試験合格を目指すという流れが定着しつつある。法科大学院は「予備試験に合格できなかった人が行くところ」(東京大学法学部生)と軽く見られがちだ。
大学在学中に予備試験に合格しても、本試験に合格できなければ、法科大学院に進学して司法試験合格を目指す人もいる。一方、予備試験合格だけで本試験にも合格した人は、法曹を目指す人たちだけでなく、法曹関係者からも“エリート”として認められる。
◆予備試験合格者の大躍進
実際、予備試験組の躍進は目覚ましい。
17年の司法試験合格者数は1543人。この中で合格者数、合格率共にダントツのトップは“予備試験組”である。予備試験に合格した受験者は400人、うち290人が本試験に合格した。合格率は72.5%に上る。
この年、合格率で第2位となったのは京都大学法科大学院(修了生)の50%、合格者数の第2位は慶応大学法科大学院の144人だった。
現行の司法試験制度に移行する前、法曹を数多く輩出してきた大学には、ほかに東京大学、早稲田大学、中央大学などがある。これら大学の法科大学院の司法試験合格者数・合格率は、東京大学法科大学院が134人・49.45%、早稲田大学法科大学院が102人・29.39%、中央大法科大学院119人・26.1%だった。
かつて数多くの司法試験合格者を輩出してきた大学の法科大学院の実績が振るわないのも、優秀な法曹志望者の大半が、予備試験の合格を目指すからだ。
こうした中、今や、法科大学院は“末期症状“ともいえる様相を呈している。ピーク時には全国に74校あった法科大学院だが、18年までに熊本大学、新潟大学などの国立大学や、青山学院大学、立教大学といった有名私立大学を含む35校が学生募集を停止。残る39校のうち10校は定員の半分以下、さらに7校は10人以下しか志願者が集まらないという不人気ぶりだ。今月5日には、横浜国立大学が2019年度、法科大学院の募集を停止すると発表した。
◆希望から絶望へ……
司法制度改革の目玉として、04年にスタートしたいわゆる新司法試験制度。法科大学院の設置はその「核」とされた。当時、全国に68校あった法科大学院の募集定員は計5590人、そこに計4万810人が受験した。実際に入学したのは計5767人。多少の辞退者はいただろうが、実質倍率で約7倍という「狭き門」だった。
法科大学院の門をくぐれば「法曹への切符を手にしたも同然」と錯覚したのは、当の学生のみならず、法科大学院や法曹界なども同じだった。
「市民が容易に司法サービスを受けられるよう法曹の数を増やす」――政府の「司法制度改革審議会」は、合格率が3%未満と極めて低かった旧司法試験を見直し、新たにスタートする法科大学院に対して、「その課程を修了した者のうち相当程度(例えば7~8割)が新司法試験に合格できるよう、充実した教育をすべき」と求めた。
そして、日本弁護士連合会(日弁連)なども、「修了生の7割が法科大学院を出れば法曹になれる」といったPRを盛んに行った。
……だが、現実はそうならなかった。
06年に行われた法科大学院1期生たちの合格率は48.3%にとどまった。旧司法試験の合格率からは大きく上昇したが、日弁連などの「7割」という想定は大幅に下回った。法科大学院が乱立し、法曹の質が低下するのを危惧した法務省などが合格者数を抑えた面もあったとされる。
その後も、前年に不合格になった人たちの再受験などで、合格者数は増加傾向が続いたが、合格率は下降線を描き、09年にはついに30%を切った。
◆受験機会喪失者続出の「三振ルール」
国家試験の受験産業関係者の間で、こんな説がささやかれている。一部の大学の医学部は、合格する実力のない学生に国家試験を受験させない、と言われている。合格率を高めるための措置だ。見かけの合格率が高ければ大学の評価は高まり、受験生も集まる。いわば大学の「経営判断」だという。
この例と同様に、設立から間もない頃の法科大学院にも、合格の見込みのない学生に司法試験を受験させなかった例があったという。
これは、当時の「三振ルール」に起因する。
旧司法試験では、大学さえ卒業していれば誰もが何度でも試験に挑戦できた。合格さえすれば法曹への道が開かれるため、何度もチャレンジする人は大勢いた。このため、大学卒業後に5年、10年と「司法浪人」し続け、落ち続けてあきらめた時、就職もできなくなっていた……いわゆる「多浪」が問題化していた。
新司法試験制度のもとでは、法科大学院修了、または予備試験合格によって司法試験の受験資格を取得すると、5年以内に3回までの受験で合格しなければ、受験資格そのものを失うという制度になっている。20~30代というキャリアを積むべき時期に就労機会を奪う多浪問題への配慮から、受験回数に制限を設けた。これが「三振ルール」だ。
しかし、このルールは結局、数多くの「受験資格喪失者」を生み、新たな問題につながった。
司法試験に法科大学院はもはや無意味なのか?
写真はイメージです
◆法科大学院と司法試験のズレ
1999年から進められた司法制度改革の一環で、高度な専門性や「リーガルマインド(法的思考力)」が養われた法曹の輩出を目的として設立された法科大学院だが、実質的には「予備試験免除という特典つきの専門学校」となっているのが実情だ。
これには致し方ない面がある。法科大学院生は「司法試験合格」を目指しており、求めるのは試験突破のための“受験テクニック指南”に尽きる。講義で高度な学問的知識やリーガルマインドを身に付けるのは二の次だ。
実際に、関西にある私立の法科大学院で教鞭(きょうべん)をとる弁護士は「研究職を養成することを目的とした大学院ではないのだから、(学問を研究する)講学的な内容の授業は必要とされない。学生の受けがいいのは『答練(答案練習)』と『実務の裏話』だ。司法試験合格に定評のある予備校のテキストを用いて授業をすると、学生は喜ぶ」と明かす。
「三振ルール」を設けたうえ、法科大学院設置の目的と司法試験自体がかみ合っていない……このような事情が、三振して受験資格を失う人を次々に生むことになった。「三振者」が続出したため、15年からは「5年で5回」、つまり「五振ルール」に緩和された。
◆法律関連職につけない「法務博士」も
法科大学院を修了すると「法務博士」の学位が得られる。しかし、「博士」といっても研究職養成型の大学院で法学を修めた「法学博士」ではない。
三振(五振)した後、研究職を養成する大学院の博士課程を修了し、「法学博士」の学位を取得しても、大学や研究機関で職に就ける保証はない。その時点では30歳を超えているケースが大半とみられ、公務員、民間企業への就職も年齢的に厳しい。つまり、法曹資格を持たない“三振(五振)法務博士”の行き場は無いに等しい、ともいえるのだ。
これらの法務博士たちの中は、予備試験を受験し直したり、法科大学院に再入学したりして法曹資格をつかみ取った「復活組」もいるにはいる。しかし、夢破れた多くの人のその後は「よくわからない」(兵庫県弁護士会所属2年目弁護士)というのが実態だ。
その大半は、民間企業の法務部門などに就職したか、あるいは非正規雇用で食いつないでいるか……。いずれにせよ法曹以外の進路を歩んでいるとみられる。
◆法科大学院は「無用の長物」か?
前述した法科大学院の実情は、法曹を目指す人たちの間では常識となっている。法曹を目指すなら近道である「予備試験ルート」で……と考えるのも仕方がない面がある。
事実、法科大学院2期生となる05年度の入学生以降、志願者は激減、15年にはついに1万人を割り、17年は8159人と、初年度の約5分の1に減少した。
法科大学院で学んだとしても法曹になるのは難しく、回り道する分、年はとるため、ほかの進路に進むことさえ危うくなる。受験生が二の足を踏むのも当然と言える。
司法制度の破綻に対し、警鐘を鳴らし続けてきた鈴木秀幸弁護士(愛知県弁護士会)は、「ベルリンの壁が崩壊するように、皆、(法科大学院から)予備試験へと雪崩を打っている」という。
今や、「無用の長物」と化した感のある法科大学院は、「最終的には(合格実績の高い)“LLセブン”(東京、京都、一橋、神戸、慶応、早稲田、中央の各大学法科大学院)だけが残るのではないか」との声も一部の法曹関係者らから上がっている。
ただ、法科大学院を設置する大学側も、おいそれと学生募集停止に踏み切れない事情がある。法科大学院設置のために採用した専門教員の雇用の問題、そして、募集停止で「法曹養成で実績を出せなかったことで白旗を上げた」と世間から見られ、大学全体のイメージダウンにつながる恐れがあるためだ。
◆同期の年収格差「26歳800万円」VS「40歳300万円」?
現状では法科大学院修了者なら、最短で26歳、予備試験合格者なら、大学卒業後、司法修習を受けたと仮定すれば24歳で、法曹に就く。
前出の2年目の弁護士は41歳。三振後に合格したいわゆる「復活組」だ。彼は「若いうちに優秀な成績で合格すると裁判官や(企業法務などを取り扱う)大手渉外系事務所への誘いがありますが、それはごく一握り。残りの人たちのなかにはいくら知識があっても、依頼者らと話ができない、コミュニケーション下手の人は(小さな事務所への)就職もままなりません」と事情を明かす。
予備試験に合格、26歳で弁護士登録し、大手渉外系事務所に就職した司法修習同期生と自分を比較すると、収入の差は歴然という。「同期の1年目の給与(手取り額)は800万円程度と聞いた」という。それに対して、小さな事務所になんとか就職したこの弁護士の昨年の年収は「手取りで300万円ほどだった」とこぼす。
学力・知識を武器に最短ルートを進む「予備試験組」と、“回り道”にも見える「法科大学院組」。法曹界では両者の評価に大きな開きがある。しかし、市民にとっての“いい弁護士”とはどういった弁護士だろう。少なくとも、若くして司法試験に合格したエリートとは限らないのではないだろうか。
筆者は、依頼者の声にしっかりと耳を傾け、ニーズに的確に応えて、事件をきちんと処理してくれる弁護士こそが、いい弁護士だと考えている。それは絶対に学力だけでは測れないはずだ。司法試験合格後に入所する、司法研修所のカリキュラムをより充実させ、リーガルマインドとコミュニケーション力を高めることこそが急務である。
フリージャーナリスト 秋山謙一郎