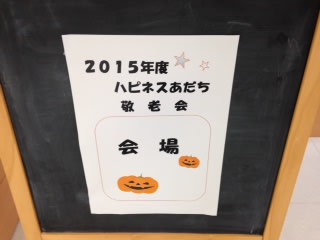9月21日はハピネスあだち敬老会の日でした。
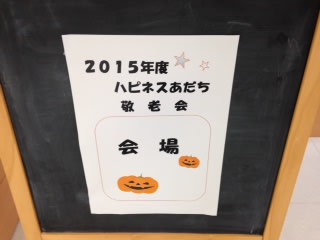

本日は敬老の日、天気も良好で多くのご家族様が来訪されました。会場は熱気に包まれていました。
2015年度ハピネスあだち敬老会の司会進行は3Fユニットリーダー杉本、2Fユニットリーダー加藤が務めました。一生懸命司会をこなしていました。

まずは施設長の挨拶の後、家族会会長より、お祝いの一言をいただきました。

各長寿になられた方のお祝いをしました。みなさんこれからも健康元気に生活してください。
その後、二胡のボランティアの皆さんがお祝いの演奏してくれました。


入居者様利用者様も口ずさんでいた「浜辺の歌」は、心が和みました。

二胡の皆さま、ボランティアに来ていただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

今回は職員余興を取り入れました。新人職員による大流行体操!?とりんごの唄に合わせた振付体操の2曲を披露しました。会場と一体になった瞬間でした。夜遅くまでの練習ご苦労様です。


最後は入居者様の写真を見ていただきながらのエンディングロールです。音楽と写真がマッチしていて感動的でした。


2015年度敬老会実行委員長は2F森サブフロアリーダー、会の全体を指揮していました。また職員余興を終えた新生たちです。おつかれさまでした。

ハピネスあだちが誇る家族会より、今回も多大なるご支援をいただきました。お花とカラータオル2本セットを、全入居者さんへプレゼントしていただきました。

いつもありがとうございます。
また本日は手話のボランティアの方にも来ていただきました。入居者様も喜んでいました。
ハピネスあだちは、これからもよりよい生活援助を続けてまいります。