札幌市東区に今年5月開設した特別養護老人ホームひかりの(社会福祉法人豊生会)から特養部門長とフロアリーダーが研修に入りました。
二日間と短い研修ではありましたが、昨日の看取り事例発表会にも参加したくさんの学びができたと感想をいただきました。
お気をつけてお帰り下さい。
札幌にも仲間ができました。

指導にあたった内山特養部門マネージャー(左端)とカレーフェアにて記念写真です。
札幌市東区に今年5月開設した特別養護老人ホームひかりの(社会福祉法人豊生会)から特養部門長とフロアリーダーが研修に入りました。
二日間と短い研修ではありましたが、昨日の看取り事例発表会にも参加したくさんの学びができたと感想をいただきました。
お気をつけてお帰り下さい。
札幌にも仲間ができました。

指導にあたった内山特養部門マネージャー(左端)とカレーフェアにて記念写真です。
千住介護福祉専門学校の介護福祉科3名の実習は今日で終了です。
お疲れ様でした。高齢者にきちんと寄り添える介護職をめざしてください。

カレーフェアに参加する実習生3人の記念写真です。
2013年9月27日は委託給食会社淀川食品の協力をいただき、カレーフェアです。
おいしくいただきました。
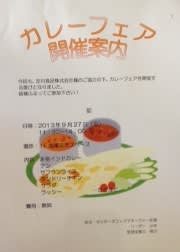
カレーは2種類です。

各自カップへ

ナン、サフランライス、サラダ、鶏肉、飲み物もあります。

ざっと、こんな感じになりました。

各部門から集まってきました。

なぜか年齢別にテーブルには集まります。

こちらは学習療法サポーターの面々

井上フロアリーダーは忙しいので一人席

美味しくいただきました。
厨房の皆さま、管理栄養士のお二人、ありがとうございました。
2013年9月26日医療法人社団悠翔会との合同看取り援助事例発表研修会を開催いたしました。
今さらに特養は、重度の方の受入れを期待されています。在宅から病院を経て様々な介護施設から入居してくる方、在宅において家族が中心となって在宅医療やケアを利用し生活している方が、その限界を超えた時に入居する方がほとんです。特養ハピネスあだちは地域医療と連携しながらも、安易にまた病院へ戻す、すなわち入院させていまうことが適切なのかどうか悩んできました。入居者の声や、真の家族の期待に応えることを考え続けた結果、辿り着いたのが「看取り援助」でした。
ユニット型特養は制度上こそ介護施設ではありますが、「もうひとつの在宅」をめざし、支援が必要な状態になった方に適した「生活の場」を提供しています。私たち特養も「在宅」のひとつであり、地域の中にあるのです。
私たちが行っている特養の看取り援助と、在宅療養支援診療所が取組んでいる実際の在宅の看取りの事例を持ち寄り、それらの共通点と相違点を確認し、また連携し合うために開催した研修会です。
共通点は看取り援助は入居者(患者)と家族が主体であり、我々はサポーターであること、情報を共有し連携し合う関係性を構築しなければならないことなどでした。また特養はユニット内のお別れ会を通して他の入居者とも支え合うことができること、それがグリーフケアへつながることもメリットとして再認識をすることができました。
また医師の立場から看取り援助を語る佐々木医師の言葉に多くの職員が感銘を受け、勇気をいただきました。
だからこそ、まだまだ標準化していない「看取り援助」ですが、この機会を通して新たな領域へ向かっていくことになるだろうと期待をしています。
発表はハピネスあだち4事例、ハピネス都筑1事例、悠翔会3事例です。
またハピネスあだちにて看取り援助を経験されたご家族さまからも発表をしていただきました。
研修会発表風景
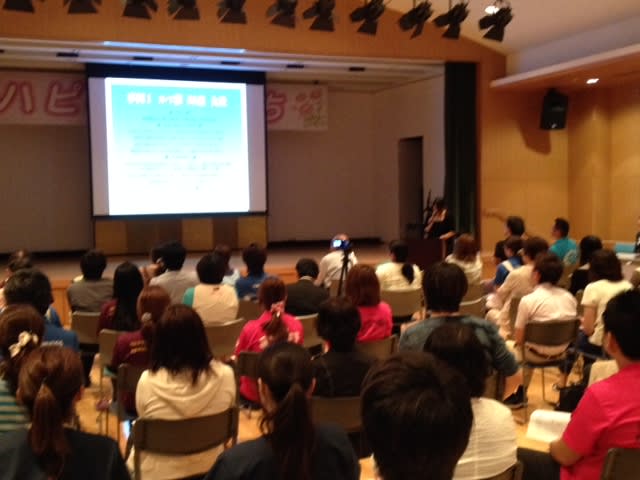
在宅療養支援診療所の看護師からの事例報告です。

真剣に耳を傾ける参加者です。悠翔会からも20名ほどの参加をいただきました。

この発表風景は悠翔会の各診療所へ同時中継されました。会場へお越しになれなかった多くのスタッフの方々にも情報は届いたそうです。

最後には医療法人社団悠翔会理事長の佐々木淳医師から在宅医療の立場で「看取り援助」について情報提供をしていただきました。

これからさらに連携を深め、地域へ向け看取り援助の取り組み発信をめざしてまいります。
研修会終了後の懇親会にて、悠翔会の佐々木淳医師とハピネスあだち施設長小川が記念写真。

なお、12月上旬、ハピネスあだち地域貢献事業オープン講座を開催します。
テーマは「(仮題)在宅と特養の看取り援助」です。
講師には悠翔会理事長の佐々木淳医師を予定しております。
参加をご希望される方はハピネスあだちまでお問い合わせください。
TEL03-5839-3630
2013年9月25日、東京都の実地指導を受けました。対象事業は特養、ショートステイ、デイサービスです。
たくさんのご指導をいただき、職員がたくましくなりました。
大きな改善指摘もなく、無事に終了です。逆に十分な施設運営を評価していただきました。
実地指導風景

担当の監査官から指導をうける職員たち、真剣そのものです。

9月19日の職員全体会議では10月3日開催の東京都社会福祉協議会主催「アクティブ福祉」での研究課題発表の事前発表を井上4階フロアリーダーが行い、みんなで聞きました。
研究課題テーマは「家族看取り援助勉強会」です。なかなかの出来栄えでした。
発表を傾聴するハピネスあだち職員たち

発表する井上4階フロアリーダー
サポーターは小比類巻2階フロアリーダーです。

9月19日、台湾の看護技術学院の教授や学生(看護師)11名の視察を受け入れました。
皆さま、とても熱心に学んでいる姿が印象的でした。
「日本に来て、学んで良かった」とおっしゃっていただきました。
その学校のパンフレットです。

大理石にてデザインされた「ハピネスあだち」の名入りの楯をいただきました。

9月19日、横浜市社会福祉協議会高齢福祉部会施設運営研究会主催のセミナーにて「いのちをつなぐ看取り援助」というテーマでハピネスあだちの看取り援助の取組みの情報提供をしてきました。
看取りの社会背景、制度面、特養の経営面、職員教育等はハピネスあだち施設長・小川が看取り援助の事例発表はハピネス都筑施設長(もとハピネスあだち医療サービス部門マネージャー)の小林悦子が担当しました。
たくさんの方が一生懸命聞いて下さったのでとても話し易く進めることができました。
看取り援助に対する社会の受けとめ方が急激に変わろうとしていることを感じます。
しかし多くの施設がどこから手をつけてよいのか分からないという意見もたくさん聞かれます。
これも、ハピネスあだちで人生を終えた方々のいのちから学び、それを引き継ぐ作業です。

ハピネスあだち施設長 小川利久
台風18号が通り抜けた9月16日、お一人のご入居者が旅立ちました。ハピネスあだちがめざす「いのちをつなぐ看取り援助」の達成です。
職員一同、ご冥福をお祈り申し上げます。
ユニットにて行われたお別れ会に並ぶ職員たち

敬老会にご協力をいただいた家族会役員会の方々もお別れ会に参加して下さいました。

ご家族と職員で見送りました。
敬老会を終えた時だったこともあり、こんなにたくさん集まったお別れ会ははじめてかもしれません。

特養ハピネスあだちには家族会があります。
今日の敬老会も共同開催、誘導などにご協力をいただきました。
記念品のカラータオル3本組みも全ご入居者さんへプレゼントしていただき、ありがとうございました。
これがご入居者さんの笑顔の源です。
家族会役員の皆さまがそろって話し合いです。

会場を見守る家族会役員の皆さま

いつもご協力、ありがとうございます。
家族会の存在は、ハピネスあだちの自慢のひとつです。
ハピネスあだちには全国初の聴覚障害者ユニットがあります。
今日の敬老会は手話ボランティアに来て下さった方が、相手に合わせて筆談をして下さいました。
臨機応変な対応に感謝申し上げます。

9月16日はハピネスあだち敬老会でした。いつも敬老の日ですが、今日はいつもよりさらに心をこめて敬老させていただきました。台風18号でご家族様のご来訪が遠のくことが心配されましたが、家族会役員の皆さまを中心に盛り上げていただきました。
会場は熱気ムンムンです。

まずはご近所の大正琴のボランティア「桜琴の会」の皆さまに演奏をいただきました。
美しい音色でした。

デイサービス職員の下山田も一員です。

演奏後の記念写真です。

今日の司会進行は4階生活援助員の樺沢、はじめは誰でも慣れない役目ですが、一生懸命さは伝わりました。

各フロアからご入居者様の歌が披露されました。
二階は「高原列車は行くよ」です。明るくなります。

三階は「富士の山」、雄大な歌です。

4階は「365歩のマーチ」、自然と参加された方々の身体が動き出しました。

最後は家族会の二瓶会長からご挨拶をいただきました。
家族会からはカラータオル3本セットを全入居さんへプレゼントしていただきました。

いつもありがとうございました。
また敬老の生活援助を続けてまります。
9月14日、定例の家族看取り援助勉強会を開催いたしました。今日は各フロアの看取り援助事例と看護師からの看取り援助事例を発表しました。
事例から学ぶ個別援助でもあります。

また先日、母親を看取られたばかりの息子さんから体験談を話していただき、複数の家族の情報の共有と意志の統一の大切さをアドバイスしていただきました。
ありがとうございました。
