日銀が悩む「銀行リスク」 緩和副作用、景気の重荷に
政策決定、弱まる物価最優先
経済 2018/12/19 1:31日本経済新聞 電子版
低金利で金融機関の経営が悪くなると、貸し出しの抑制などで景気が下押しされる「銀行リスク」を日銀が意識し始めている。
黒田東彦総裁が講演などで懸念を示し、日銀内では物価の動きよりも金融機関の経営の分析に力点が移りつつある。
世界経済の先行きが曇り金融緩和が長引く中、日銀は緩和の副作用に神経をとがらせている。
黒田総裁の発言に副作用への意識がにじむ(10月31日の記者会見)
黒田総裁の発言に副作用への意識がにじむ(10月31日の記者会見)
この秋、日銀の内部で「いさかい」が起きた。引き金になったのは10月22日に公表した「金融システムリポート」だ。
半期に一度発表するリポートで10月は初めて、低金利が長引くと銀行の収益が悪くなる「金融の脆弱性」について数値を示して警鐘をならした。
米連邦準備理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)の先行事例をもとにした分析結果は、ここ数年の低金利が景気変動のリスクを強めているということだった。
リポートの作成部署は銀行の考査を担う金融機構局。ここに金融政策を立案する企画局から異論が出た。
「なぜこの手法を公表する必要があるのか」。政策委員も、低金利の弊害ばかり強調する内容に苦言を呈した。
企画局からみれば短期金利をマイナス0.1%、長期金利を0%程度に誘導する現行の緩和策を身内に批判されたように映った。
だが金融機構局の関係者は「仮に次の景気後退局面が来ると、金融の弱さが実体経済の重荷になる」と警戒する。
これを踏まえ、10月31日公表の経済・物価情勢の展望(展望リポート)には「金融機関の先行きの動向に注視する必要がある」との文言が新しく加わった。
展望リポートは企画局が政策を進めるうえでの判断材料を示している。ここがターニングポイントになり、黒田総裁らが金融機関への金融緩和の副作用を公に口にするようになった。
黒田総裁は11月5日の講演で「緩和の継続が収益力低下を通じて金融機関の経営体力に累積的な影響を及ぼす」と懸念を表明。
2日後には布野幸利審議委員も「強力な緩和を続ければ金融仲介機能が停滞するリスクもある」と語った。
「金融機関の収益を改善するために金融政策を行うことはない」。
7月31日、長期金利の誘導に幅を持たせるように緩和策を修正したとき、黒田総裁は記者会見でこう言い切った。3カ月ほどで、意識は様変わりした。
力点がかわったのは、金融緩和が長引くことがはっきりしてきたためだ。
日銀は目標とする前年比2%の物価上昇が少なくとも2020年度まで達成できないと認めている。
一方で低金利は金融機関を追いつめる。利ざやが縮む地方銀行は18年4~9月期に、全体の7割で最終損益が赤字か減益に陥った。
金融機構局と企画局の綱引きは、16年2月にマイナス金利政策を導入した際にもあった。
当時は企画局が主導して短期金利をマイナスに下げ、金融市場に「サプライズ」をもたらした。
これに銀行は「(家計や企業の)懸念を増大させる」(三菱UFJフィナンシャル・グループの平野信行社長)と猛反発。金融機構局は政策委員のメンバーらに銀行幹部との面会の場を設け、反応を伝えて回った。
マイナス金利を決めた16年1月の公表文では、金融政策は「経済・物価のリスク要因を点検」して決める方針を掲げていた。
ただ銀行の声は無視できず、長短金利操作を始めた16年9月の公表文は「経済・物価・金融情勢を踏まえ、必要な政策の調整を行う」に転換した。
判断材料に入れた「金融」への意識が、ここにきて強まっている。
「スルガ銀行の不祥事は低金利が遠因になっている」。
日銀ではこんな声も聞こえる。6カ月の業務停止命令につながったずさんな不動産融資が許されるものではないが、収益重視に走る背景には低金利による運用環境の悪化もある。
銀行が収益を落とし続けると、いつかは金融仲介機能が傷む。
一方で米中の貿易戦争は景気後退を招くリスクすらある。
日銀が19~20日に開く金融政策決定会合では今の緩和策が維持される見通しだが、大規模緩和の先行きは一段と見えづらくなっている。
政策決定、弱まる物価最優先
経済 2018/12/19 1:31日本経済新聞 電子版
低金利で金融機関の経営が悪くなると、貸し出しの抑制などで景気が下押しされる「銀行リスク」を日銀が意識し始めている。
黒田東彦総裁が講演などで懸念を示し、日銀内では物価の動きよりも金融機関の経営の分析に力点が移りつつある。
世界経済の先行きが曇り金融緩和が長引く中、日銀は緩和の副作用に神経をとがらせている。
黒田総裁の発言に副作用への意識がにじむ(10月31日の記者会見)
黒田総裁の発言に副作用への意識がにじむ(10月31日の記者会見)
この秋、日銀の内部で「いさかい」が起きた。引き金になったのは10月22日に公表した「金融システムリポート」だ。
半期に一度発表するリポートで10月は初めて、低金利が長引くと銀行の収益が悪くなる「金融の脆弱性」について数値を示して警鐘をならした。
米連邦準備理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)の先行事例をもとにした分析結果は、ここ数年の低金利が景気変動のリスクを強めているということだった。
リポートの作成部署は銀行の考査を担う金融機構局。ここに金融政策を立案する企画局から異論が出た。
「なぜこの手法を公表する必要があるのか」。政策委員も、低金利の弊害ばかり強調する内容に苦言を呈した。
企画局からみれば短期金利をマイナス0.1%、長期金利を0%程度に誘導する現行の緩和策を身内に批判されたように映った。
だが金融機構局の関係者は「仮に次の景気後退局面が来ると、金融の弱さが実体経済の重荷になる」と警戒する。
これを踏まえ、10月31日公表の経済・物価情勢の展望(展望リポート)には「金融機関の先行きの動向に注視する必要がある」との文言が新しく加わった。
展望リポートは企画局が政策を進めるうえでの判断材料を示している。ここがターニングポイントになり、黒田総裁らが金融機関への金融緩和の副作用を公に口にするようになった。
黒田総裁は11月5日の講演で「緩和の継続が収益力低下を通じて金融機関の経営体力に累積的な影響を及ぼす」と懸念を表明。
2日後には布野幸利審議委員も「強力な緩和を続ければ金融仲介機能が停滞するリスクもある」と語った。
「金融機関の収益を改善するために金融政策を行うことはない」。
7月31日、長期金利の誘導に幅を持たせるように緩和策を修正したとき、黒田総裁は記者会見でこう言い切った。3カ月ほどで、意識は様変わりした。
力点がかわったのは、金融緩和が長引くことがはっきりしてきたためだ。
日銀は目標とする前年比2%の物価上昇が少なくとも2020年度まで達成できないと認めている。
一方で低金利は金融機関を追いつめる。利ざやが縮む地方銀行は18年4~9月期に、全体の7割で最終損益が赤字か減益に陥った。
金融機構局と企画局の綱引きは、16年2月にマイナス金利政策を導入した際にもあった。
当時は企画局が主導して短期金利をマイナスに下げ、金融市場に「サプライズ」をもたらした。
これに銀行は「(家計や企業の)懸念を増大させる」(三菱UFJフィナンシャル・グループの平野信行社長)と猛反発。金融機構局は政策委員のメンバーらに銀行幹部との面会の場を設け、反応を伝えて回った。
マイナス金利を決めた16年1月の公表文では、金融政策は「経済・物価のリスク要因を点検」して決める方針を掲げていた。
ただ銀行の声は無視できず、長短金利操作を始めた16年9月の公表文は「経済・物価・金融情勢を踏まえ、必要な政策の調整を行う」に転換した。
判断材料に入れた「金融」への意識が、ここにきて強まっている。
「スルガ銀行の不祥事は低金利が遠因になっている」。
日銀ではこんな声も聞こえる。6カ月の業務停止命令につながったずさんな不動産融資が許されるものではないが、収益重視に走る背景には低金利による運用環境の悪化もある。
銀行が収益を落とし続けると、いつかは金融仲介機能が傷む。
一方で米中の貿易戦争は景気後退を招くリスクすらある。
日銀が19~20日に開く金融政策決定会合では今の緩和策が維持される見通しだが、大規模緩和の先行きは一段と見えづらくなっている。










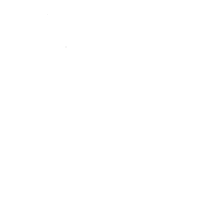

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます