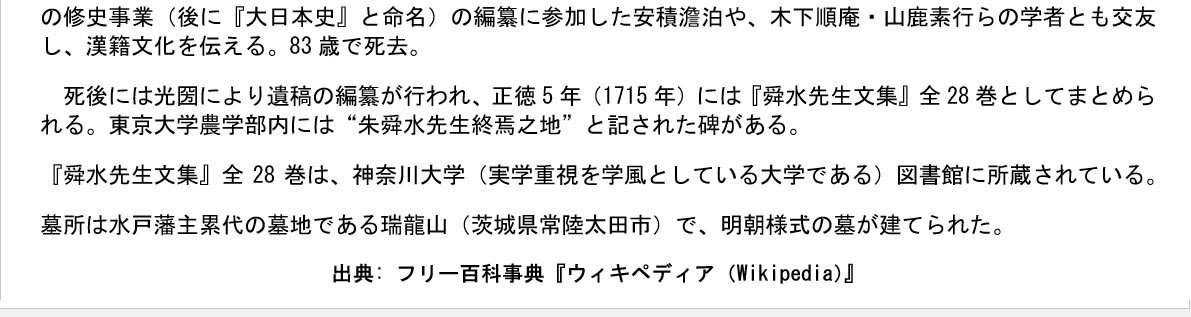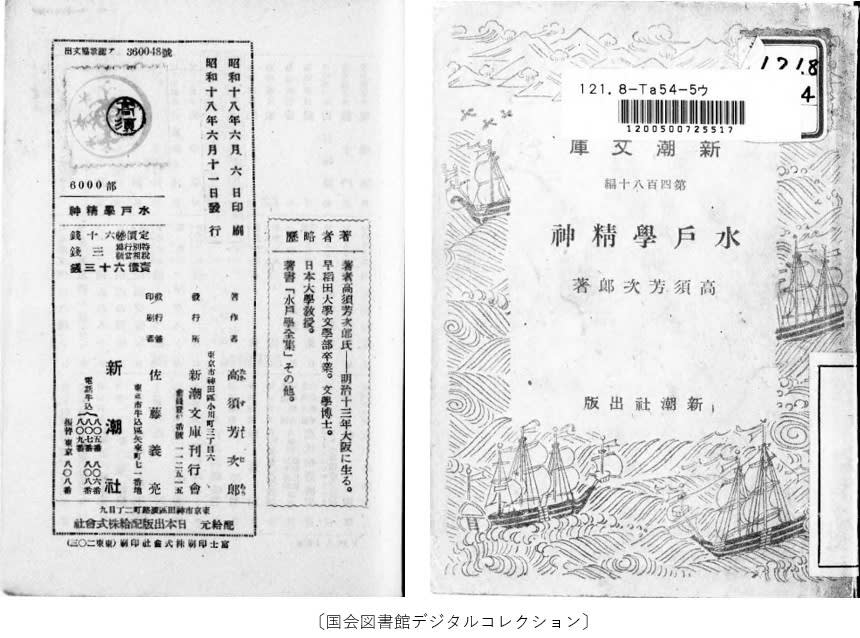
高須芳次郎著『水戸學精神』 
第三 水戸義公の思想と人物 
(一)水戶學の源流
〔朱舜水の「崇儒」の考へ、經世實用の學〕
水戸學の源流について考へるとき、當然、念頭に浮んでくるのは、水戸義公及びその實師、朱舜水の二人である。この二人あって、始めて水戶學が誕生すべき機像を得ると 同時に、しっかりした基礎をも据えたのである。勿論、義公が主たる地位にをり、朱舜水が客たる位置を占めたのは云ふ迄もない。それに、朱舜水なくとも、水戶学は、當然、義公たちによってて、創始せられたにちがひなかった。けれども朱舜水が存在したことによって、義公が思想・學藝の上に少なからぬ力を得たことは、否めない。
義公が修史の志を起したのは、正保二年(1646年)、十八歳の時で、朱舜水を招聘したのは寛文元年、三十八歳の時だった。そして朱舜水は、もう六十六歳になってゐた。從って人物も相當に練れてをつたし、學問の素養も亦十分にあった。蓋し朱舜水は、明の遺臣として平生、明朝を悽復する念願のために、再三、日本へ來り、安南方面にも行き、いろいろ、苦勞しただけに儒者によく見る迂腐の氣味は全くなかった。
人によると、朱舜水は朱子學派に最も近い學者と見るが、それは、誤りではないにしても、見解が窮屈過ぎると思ふ。また彼の教へを受けた安積澹泊は、朱舞水が古學派に属した一人だと見てゐるか、それも見やう次第のことに過ぎない。いづれかといへば、朱舜水は、朱子學、陽明學、古學などについて、該博な知識を持ったが、彼の中心思想を爲すものは、經世實用の學であり、それを裏づけてゆくものは、史學だった。
例へは 『資治通鑑』を非常に愛讀した如きは、彼が、抽象理論を排して具體的理論を重んじた傾向を明白に示すものである。朱舜水は、學問の主眼として、實功・實用を尚ばねばならぬ旨を語つてゐる。水戶義公も亦彼が、この點に優れてゐるのを認め、先生は眞の經済の學問なり。假令曠莫無人の 野にて都邑を一つ興起せんに、士農工商それぞれの者を集めざらんには事成就せまじ。然るに先生一人おはせば、恐らくは不足なくして都邑成すべし。先生は詩書禮樂より田畑の耕作、家屋の造様、酒食鹽醤のことまで、細密に究得せる人なりと云った。
蓋し彼は早くから經世に志し、學問を以て自任したのではなかった。從って或思想上の一派に偏ることは、彼の志でなかったらう。彼の思想的經路において、ある時代には陽明學に、またある一時期は朱子學に、それから古學にといふ風に推移し、それらの長所を摂取して、彼獨自の見解に起つに至つたのであらう。朱舜水が大義名分を尊重したのも、主として、朱子學から来た影響だとして、片づけるのはどうかと思ふ。
かう云ふ風に見ると、彼は思想上の獨立學派で、或一派にこだはらない。然しその学風が水戶學構成の上に相當の交渉を有した事は、想像するに難くない。水戶學では大義名分を重んじ、經世實用の學を尊み、史學上に特殊の興味を感するなど、いづれも朱舜水の學的傾向に似通った一面がある。
それらは、一概に朱舜水が義公に與へた理想上の感化によるものとは、云ひ切れない。 けれども水戸學に於ける主要点—敬神崇儒といふ中で、「崇儒」の考へは、確かに朱舜水によって鼓吹せられ、それが義公その他の學者をも動かしたであらうことは、相察するに難くない。また經世實用の學において、支那に於ける有力な學者の意見を採取するについても、朱舜水が相當に貢献したであらうことも、推想される。

〔模範的儒者、朱舜水〕
それに舜水は、模範的儒者ともいふべきタイプを備へてゐた。その性質は剛直で、固く節義を守り、平生軽々しく談笑しないで、言動の上によく禮意をつくし、清貧にゐて、少しも憂ひなかった。そして最後まで明朝恢復を志して、そのため、相當の運動資金を 蓄へることに力めたこと、日本の風俗を愛し、楠木正成を心から尊敬したことなど、水戶の人々に、よい感化を及ぼしたであらうと思ふ。
以上の意味で、舜水は、水戸學に相當、關係交涉が深いので、その存在を重視しなければならぬ。
(二)水戶義公の學殖及び思想
〔習俗に囚はれず、獨自の見解〕
水戶義公は、水戶學の創建者として、中心人物として、最も重耍な役割を演じたことは、餘りに明白すぎる位だ。義公の『西山公隨筆』を讀むと、いかにも、個性が、はっきりしてゐて、少しも習俗に囚はれず、何事についても、獨自の見解を持ったことがわかる。更に『常山文集』を手にして見ると、彼が単なる大名ではなく、學者、文人として、相応の技倆を備へたことも亦わかる。
從って義公が思想上において、一家の見識を支持し、世儒の考へに拘泥しなかったことは勿論である。彼は一面においては、國家中心主義者で、特に大義名分を尊重した。が、決して偏狭な考へに囚はれないで、神道、儒敎、佛教など、各種の思想に博く亙り、 そのいづれに對しても公平な批判をなす立場にゐた。
彼の自傳に「物に滞らず、事に着せず、神儒を尊んで神怖を駁し、佛老を崇めて佛考を排す」といふ所以は、要するに、彼が濶達な性質のもとに色想上中正の態度を執ったことを示すのである。 勿論、それにしても、中心點を忘れたのではなく、大體において神道を第一位とし、儒教を第二位とし、老子の哲學については、唯興味あるものとしてこれを味わい、佛敎の非國家的な一面を見逃さなかったやうである。
〔大義名分を高調〕
それから國家中心主義に立脚する上において、大義名分を高調し、大日本史編述について「皇統を正閏し、人臣を是非し、輯めて一家の腕を成す」と云ってゐる。
當時の諸侯・武人らが、大義名分に暗く、將軍の存在をはっきり意識して、これに敬意を拂ふことは知ってゐても、天朝に對しては、丸で沒交涉であるかの如き感を抱いたものが多かった。それは、つまり、日本の國體について、何ら自覺するところがない爲めで、何を措いてもさうした欠陥を取り除くために、大義名分を高調しなければならなかった。
義公は、早くこの點に心づき、さうした精神を具體的に表現するために『大日本史』の編纂の志を起したのである。
義公以前に出た文献の中で、日本國體を明かにし、大義名分を高調したものに、『神皇正統記』がある。また義公とほぼ同じ時代の學界で、この方面を開拓する事に力めた山鹿素行の『中朝事實』もある。素行は日本中心主義の先駆者で、日本國體を說明するについて、相常、行き出いた學的態度に據った。『中朝事實』が不朽の生命を有し、今日、読んで、尚ほ啓發さるる點が多いのは、素行の思想家として、いかに獨自の長所を有したかを示すものである。
素行は、確かに時代に先駆した新思想家だった。かうした意味において、義公も亦思想上、先駆者の地位に立つ一人だと云へる。彼の生活した時代は、江戶幕府の全盛期で、 唯將軍の武断的覇道政治を謳歌してをれば、それで宜かったのだ。ところが、義公は、さうしたことで滿足しなかった。
〔將に來らんそする時代の新潮に鋭感、趣味多才の人〕
江戶幕府がその勢力を支持し得る所以は、天朝の御蔭であって、その深大な恩澤に酬ゆるには、天朝を崇重し、國體を尊敬して、大義名分の存在を明かにすることが第一義だと信じた。
故に義公の卓見があると同時に、將に來らんそする時代の新潮について、彼が、いかに鋭感の人だったかが推察される。
それに『桃源遺事』によると、「和學・漢學は勿論、諸宗の佛教・神書・医書・算數・詩文・聯句・詩餘・和文・和歌・武芸等、何によらず、御存知遊ぱされ候」とあるから、義公の博學とその趣味の廣かったことがわかる。
のみならす、義公は自身、『十三経』に句讀を施し、『左傳』の系図などをも作り、平生、『戦國策』『國語』『荀子』なども愛讀し、唐宋時代の文章にも親しみ、自由に漢詩・漢文をも作った。
この點においても亦諸侯中、彼に匹敵すべき人物が殆どなかったであらうと思はれる。
彼の言文を収めてある『常山文集』を見ると、その詩は淡雅・平明で、東洋文人風の 趣味を表現し、その文章は、短い、氣の利いたものの上に、殊によく彼の個性を端的に打出してゐるやうに思ふ。
例へば、種々の絵画に加へた賛などは、殊に短いが、義公の精神思想がよく現はれてゐて、しかも汲んで盡きない妙味がある。その中には往々、彼獨自のウヰットの閃きを示したものが少くない。唯、少しく理趣に墜しやすい點が微瑕だ。
〇便 面
鳥あり、烏あり、大鵬此に搏つ。
浪あり、浪わり、北溟、此に翻るか。
一たび之を揺せば、則ち九萬里の風、縮んで此にあり。
九夏三伏の時、これを動かせば、我に炎熱あることを知らず。
此に於て、逍遥として遊び、他に求むること勿れ。
〇三教醋を嘗むるの圖に題す
甕あり、醋あり。人あってこれを嘗む。
その酸といひ、その苦しといひ、
その味なしといふ指を染めて、これを味へば、則ち顰楚異るなし。
佛老の我が儁に於けるも亦然るか非か。
それこれ三か、果して一か。
道といはんか、甕といはんか。
以上、その一例として掲げたか、義公の手腕が優に一家を爲してゐることを知り得られる。
從って、義公が文人としても、學者としても、思想家としても相当の地位を占むべき人物であることが、はっきり、證明されてゐる。唯思想家として彼の思索が、どの程度迄、周密であつたか、またどの方面に、獨創味を發揮したかといふ點は、必すしも一々吟味する必要はあるまい。
〔参考〕