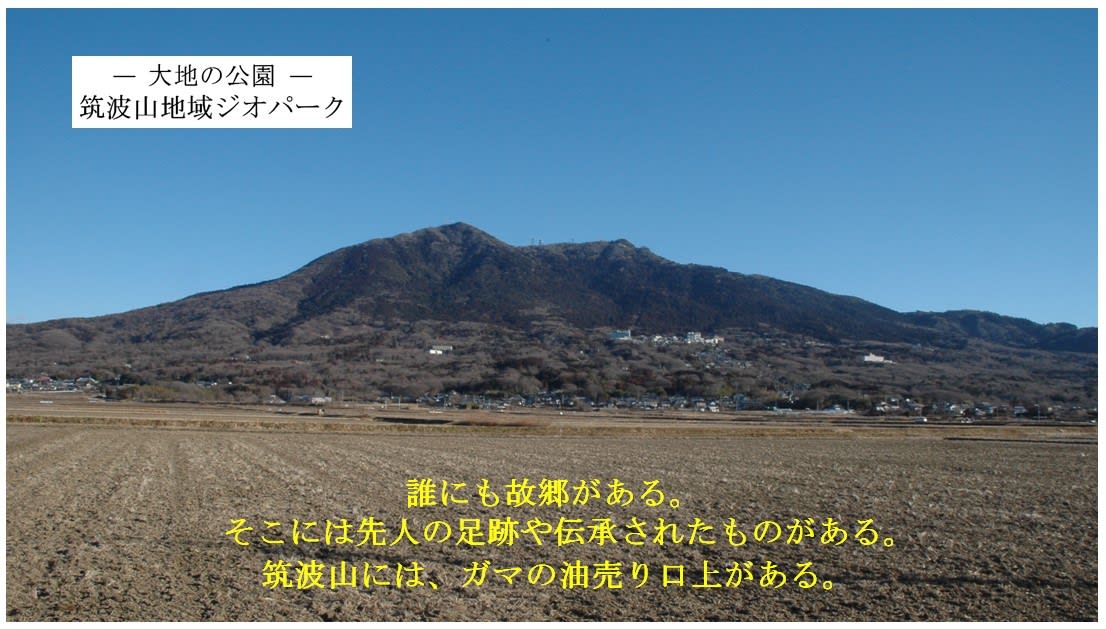
定府制、「江戸の邸と水戸と他国のごとくなり」
江戸時代において参勤交代を行わずに江戸に定住して将軍や藩主に仕える者を「定府」いった。
参勤交代を行う交代寄合を除く旗本・御家人は、江戸に定住して将軍に仕えたため定府である。
諸大名にあっては、徳川家康によって江戸定住が定められていた水戸徳川家(水戸藩)と、
老中・若年寄・寺社奉行など幕府の公職にあって江戸城に詰めている藩主(主に譜代大名)は、
江戸に定住する必要性があったので、当然に定府となる。
御三家のうち、水戸だけ尾・紀両家とくらべて官位が一段低く、領地も半分程度であり、かつ定府制であったのは何故だろうか。
官位は、尾・紀両家の従二位権大納言に対して、水戸家は従三位権中納言であり(頼房だけ正三位)、
領地は尾張家の54万石(のち62万石)や紀伊家の55万石に対して、
水戸家はわずか25万石(のち28万石、三代綱條の時、新田の至筒を加えて35万石)で、隔たりがはなはだしい。
これを差別待遇と考えた水戸側の諾書には、頼房の豪気俊英を幕府が恐れて大領地を与えなかった、
などと評判して、「威公年譜」にもその事を明記している。
しかし領地は三子の幼少の時にすでに定まったのであるから、
頼房の豪英云々ということは後代の理由付けにすぎない。
そこで三子に対する家康の愛情に、何かのわけがあったのではないか、との疑いも出て来る。
家康の駿府時代の生活記事が多い「駿府記」「当代記」など当時の記録には、
家康が義直・頼宣の2人を傍から離さず、可愛がった事が所々に書かれ、
2人の姿がきらびやかに浮かんでいるが、
頼宣とわずか一つ違いの弟頼房はそれほど出ておらず、はなはだ影がうすい。
家康の上洛の時は、義直・頼宣2人を同伴したが、頼房は同伴しなかった。
大坂の陣にも、夏冬とも家康は上の2人を同伴したが、
頼房だけ駿府にとどめられた。明らかに差別が認められる。
頼房は頼宣と同じく「於萬の方」の所生であるから、
生母の身分違いによる差別ではないが、
何かの事情で家康の情愛が兄たちよりも薄かったのではないだろうか。
水戸家だけ定府制であった理由もまた、はっきりしない。
前記のように、将軍の名代、天下の副将軍だから他の大名のように参勤交代せず、
常時江戸に住まねばならなかったといわれているが、
これは後代の憶測で、頼房はすでに少年時代から2人の兄と違って定府であった。
この3人の兄弟は1616(元和2)年4月、父家康の死後、間もなく江戸に屋敷を与えられたが、
義直は駿府を引き払って名古屋へ去り、その年の冬、江戸へ参勤した。
頼宣は駿府城主であるから、その地に留まり、翌年参勤した。
しかし頼房は江戸へ引越して新邸に住み、国元へは赴かなかった。
そしてその後も義直は1617(元和3)年春江戸から帰国し、
年内に江戸へ参勤、翌四年春帰国、同5年冬江戸参勤した。
頼宣もまた元和3年8月江戸から駿府に帰り、
翌4年冬参勤、同5年春帰城、その年8月紀伊国に移り、6年冬参勤、
翌7年春帰城というように国元と江戸とを往来し、
寛永年中に入っても、ほとんど連年または1年おきに参府している。
諸大名の参勤交代制度が確立したのは、1635(寛永12)年武家諾法度の改定以来のことで、
諸大名は1年在府、1年在国で毎年定期に交代し、
とくに関東大名は半年交代としたが、
水戸家と老中・若年寄など役付大名は定府とした。
そのほか諸大名の分家の小大名など定府の家もいくらかあった。


御三家のうち、水戸家だけ定府とした事情は不明であるが、
幕府の政策として、御三家のうち一家は江戸に常住して万一の変事に備えさせる方針を採り、
江戸に近い水戸家を定府としたのであろう。
したがって将軍の名代、天下の副将軍という説も、この辺の事情から作られたものかも知れない。
水戸家ではこの定府制を迷惑と考えたのか、
1730(享保15)年、幕府へ隔年ごとに「在所への御暇」を願い出たことがある。
幕府では、尾張殿.紀伊殿は前から隔年に「御暇」を遣わされ、
水戸殿には隔年と定まってはいないのだから、同様に取計らうことはできない、
2年置きほどの「御暇願」ならば許されるかも知れないが、
差当たり保養などの名目で臨時に「鷹場への御暇願」を出されたらよかろう、と答えている。
ついに、尾.紀両家同様の取扱い振りに変えることができなかった。
したがって歴代の水戸藩主は常々江戸に生活の本拠を置き、時に賜暇を得て国元へ行き、
数か月滞在して再び江戸へ戻るのが、普通の状態であった。
歴代のお国入りを見てみると、
初代頼房が53年間に11回、
二代光圏が30年間に11回、
三代綱條29年間4回、
四代宗尭23年間2回、
五代宗翰37年間2回、
六代治保40年聞1回、
七代治紀12年聞1回、
八代斉惰14年間なし、
九代斉昭16年間3回、
十代慶篤25年間1回である。
三代以後帰国が少なくなるのは、財政難のためでもあるが、
ほとんど不在城主同様の状態がつづいている。
定府制が水戸藩の構成と水戸人の生活に及ぼした影響
この定府制は水戸藩の構成と水戸人の生活に、いろいろの作用と影響とを及ぼした。
まず藩全体の構成では、おのずから国元よりも江戸邸の方の比重が大となった。
特に光圏の時代までは、家臣たちは水戸在住、江戸交代勤番が本来の建て前であったが、
次代綱條の時代に江戸住居が多くなり、
さらに第六代治保のとき、諸土の交代の煩労を少なくするため、多く江戸に移住させた。
このため、国元から江戸勤番の士のほか、江戸常勤の士が他藩よりは比較的多かったが、
その実数は明らかでない。
重臣以下諸役人が江戸にも常勤して、
藩主の命令を受けて国政を指図したので、政治の重心は江戸にあった。
そのために、江戸邸・水戸城間の連絡に支障が起こりやすく、
また双方の意志が疏通せず、時には、それが対立、抗争の種をまくこともあった。
また江戸常住の藩主と国元の士民との間も、常々水戸の生活を共にする目か少ないので、
危急の場合、藩主の統制力が国元へ十分に及ばなかった。
天保以降の水戸藩の動揺と分裂には、この弱点がもっとも端的に現われている。
次に財政経済面でも定府制のため江戸邸の消費生活が膨張し、
その上、江戸と水戸との生活の程度に大きな差があったので、
藩士の経済生活にもいろいろ支障が起こりやすかった。
江戸の者と国の者との風俗・気風の相違もまた藩中の団結を弱めた。
藤田東湖は「常陸帯」に定府の弊を論じて、江戸の狭い長屋住居が人間の性質を「狡黠」にし、
「剛毅朴訥」の気風を失わせ、
「江戸の邸と水戸と他国のごとくなり、
定府の人は水戸の人を田舎ものと嘲り、
水戸の士は定府の士を軽薄ものと謗り、政事の妨になり」云々と記している。
このような宿弊を改めるため、
天保改革のとき「諸事水戸表を根本に定める」方針で、
江戸の士200余人の水戸帰住を断行したが、これがまた混乱と不平の種となった。
さらに文化の面では、天下の政治の中心地に常住することが、
特に前期では江戸中心の傾向が強かったのでたとえば学者を招聘し諸士の識見を高めるなどの利点があった。
このため逆に、上記、藤田東湖の言葉にある「田舎もの」である水戸の士民に
直接感化をおよぼして土着の文化を育成することが少なかった。
黄門様の諸国漫遊、世直し
幕末になって、講談師がこれらの伝記や十返舎一九作の滑稽話『東海道中膝栗毛』などを参考にして
『水戸黄門漫遊記』を創作したと考えられている。
内容は、「天下の副将軍」こと光圀がお供の俳人を連れて諸国漫遊して世直しをするというものである。
水戸藩が「定府制」をとっていたため、
藤田東湖の「江戸の邸と水戸と他国のごとくなり」で
定府の人は水戸を嘲り水戸の士は定府の士を軽薄も謗り」という関係にあったから、
“世直し”をしなければならぬ問題を抱えていたにもかかわらず、
水戸藩の外、江戸では年貢取立ての厳しさに見られる苛政の実態は知られなかったであろう。
徳川幕府が衰退した幕末から維新後の明治・大正・昭和の大戦前にかけて
徳川氏への評価が著しく低下したにもかかわらず、
黄門物がもてはやされた背景には、
実在の光圀が天皇を敬い楠木正成を忠臣として称え、
『大日本史』編纂したことに代表される“名君”の側面が誇張されたことや
水戸学が尊王論や天皇制・南朝正閏論に多大な影響を及ぼしたことが関連している。



























