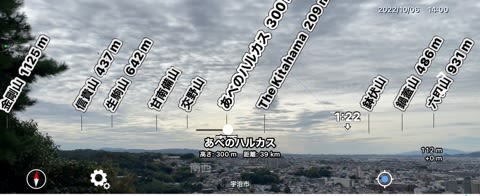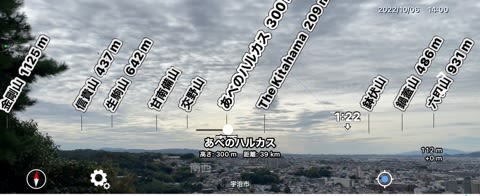「老化という“病”を治す時代」が現実味を帯びてきた。細胞レベルで見る“老化の本質”【医師が解説】
幻冬社ゴールド onlain より 221006 乾 雅人
老化とは「抗えない生理現象」ではなく、「病」である…。
今、医学の常識が一転しつつあります。
WHOが2019年に採択した「IDC-11(国際疾病分類)」でも、明確に“老化”の概念が盛り込まれました。老化研究はどのようにして始まり、現在どの段階まで進んでいるのか。
銀座アイグラッドクリニック院長・乾雅人医師が「細胞レベルで見る“老化の本質”」を解説します。
⚫︎人類はすでに不老不死を叶えていた?
「老化は治る」。嘘のような本当の話です。前稿で『老化は治療対象の疾患である』ということが世界最先端の研究者たちの間ではもはや常識であることを述べました(【⇒関連記事:「老化は“病”である」。世界保健機関(WHO)も肯定…驚愕の“新常識”】)。この“医学の常識”がひっくり返ることで、日常にある“医療の常識”、それを担う“医師の常識”も変わるであろうことも。読者の方の健康寿命が変わり、日常が変わり、ライフプランが変わるのです。
このグレートローテーションはいかにして起きたのか? よりよくご理解いただくために、細胞レベルで“老化”の本質を捉えてみようと思います。次稿の『遺伝子レベルで見る“老化の本質”』と併せて読むことで、理解がいっそう深まると思います。
ではさっそく、今回の本題に移ります。
『テロメア点滴』をご存じでしょうか? 不老不死が叶うともてはやされ、『1回1億円』のアンチエイジング医療等といった都市伝説を聞かれた読者の方もいらっしゃるかもしれません。なんとも胡散臭い話だと思いませんか?
このテロメア及び、それを延長するテロメラーゼの研究者であるエリザベス・ブラックバーン博士は2009年10月5日、ノーベル医学賞・生理学賞を受賞しています。そう、実は、人類はすでに、『不老不死』の現実的な手段を手にしていたのです。
⚫︎細胞レベルで見た老化研究の始まり、老化細胞の発見
ここで、細胞研究の歴史を紐解いてみます。
物事を深掘りする際には、細分化して整理するのが鉄則です。ボヤっと全体像を眺めているだけでは二進も三進もいきません。
一人の人間という“個体”に対する研究は、こうして、生物としての基本単位である“細胞”レベルに細分化して始まることになりました。
世界中の研究者がしのぎを削る中、1961年、最初の転機が訪れました。「生殖細胞や幹細胞といった特殊な細胞を除き、(体)細胞は無限に分裂できる」という“医学の常識”がひっくり返ったのです。
発見者の名前にちなみ、現在、細胞分裂回数の限界は“ヘイフリック限界”と呼ばれています。細胞は50~60回程度の細胞分裂をしたら、その後は細胞分裂をすることができず、締まりのない外観を呈するようになります。
これが老化細胞と呼ばれる状態です。
あくまで実験室での単純で理想的な環境での出来事ではありますが、複雑怪奇な生体内の環境でも同様のことが起きている可能性は高いです。“細胞”の老化を通じて、“個体”の老化に対する洞察が得られた一大転機となったことは論を俟(ま)ちません。
そして、このヘイフリック限界こそ、先述のテロメアと密接に関わっています。
⚫︎細胞分裂のたびに短くなるテロメアを延長できれば…?
テロメアとは染色体の末端に位置する、TTAGGGという塩基対の反復配列を意味します。telomereとは、ギリシャ語で「末端」を意味するtelosと「部分」を意味するmerosからなる言葉です。靴紐を保護するキャップ部分のようなもので、細胞が分裂するたびに、保護キャップであるテロメアが短くなっていく。
いよいよテロメアが短くなり、より中枢にあるDNA(染色体)を保護することができなくなったら、細胞は老化細胞になり機能停止する、といった具合です。
では、このテロメアを延長することができたならば? 細胞はヘイフリック限界を突破し、無限に細胞分裂を繰り返し、生存することが可能なのでは?という仮説が成り立ちます。
こうして、テロメアを延長するテロメラーゼに対する研究が過熱します。これが『1回1億円点滴』の都市伝説の正体です。そして、不老不死を得た“細胞”が出現します。
ただし、それはがん細胞として。
テロメラーゼによるテロメア延長は、細胞をがん細胞にする諸刃の剣だったのです。現在、テロメア研究は“老化”に対する研究としては一旦落ち着き、“がん”に対する研究としてより注目を浴びるようになっています。
⚫︎老化細胞は「“がん細胞化”を防ぐ仕組み」でもあった
後に、実は、生体内ではテロメア長が十分残っているにも関わらず、老化細胞となる細胞の存在が判明します。丹念な観察の結果、抗がん剤投与や放射線被ばく、戦争や災害などの強いストレス等々に晒された場合に、生体内に老化細胞の出現が確認されるようになりました。
昨今では新型コロナ感染症の際に、肺組織で老化細胞が出現している症例が確認されたとの発表もあります。
これが意味するところは何か? 実は、老化細胞に至る仕組みとは、むしろ、個体を防衛するための仕組みとも解釈できるのです。
仮にテロメア長が十分残っていても、あまりに強いストレスでDNAの修復がうまくいかない場合、細胞分裂をすると“がん細胞化”する可能性が高いのです。そのような場合には、細胞はアポトーシス(細胞自殺)を来すか、老化細胞となって免疫細胞により除去されるのを待つことになります。生物個体にとって、非常によくできた仕組みとも言えるのです。
老化細胞の存在が判明し、個体が老化するに従って、その数が生体内で増加することもわかりました。老化細胞の生成数が増えれば増えるほど、除去し切れずに残存する老化細胞も増えます。
では一体、生体内で残存し続ける老化細胞の役割は何なのでしょうか? リストラも辞職も免れた“老害社員”、窓際族のように、ただ存在するだけなのでしょうか?
⚫︎体内に残存し続ける老化細胞は生活習慣病をもたらす
古くから、細胞老化した細胞は周囲に炎症や発がん作用のある物質を放出することが知られています。2010年頃、各種状況を包括する概念が提唱され始めました。「老化細胞随伴症候群(Senescence-associated secretory phenotype; SASP)」です。
体内に残存する老化細胞は周囲に炎症性物質を放出し、結果的に、高血圧や糖尿病、脂質異常などの生活習慣病に至るのです。
実は、メタボリックシンドロームでも、炎症による症候群という意味では一緒です。内臓脂肪として肥大化した脂肪細胞から、周囲に炎症性物質が放出されます。結果、やはり高血圧や糖尿病、脂質異常などの生活習慣病に至るのです。
生体内で起きている仕組みは、かくも類似しています。SASPのイメージも付きやすいのではないでしょうか?
ほか、動脈壁を構成する血管内皮細胞が老化細胞となった場合、周囲に炎症を起こし、線維化を経て動脈硬化を来します。
あるいは、肺組織や気道に老化細胞が出現すると、周囲に慢性炎症が生じ、線維化が進行します。結果、呼吸がしづらくなり、医学的には拘束性障害(吸えない)や閉塞性障害(吐けない)を来すのです。
さらに、コロナ後遺症は老化細胞の出現によるSASPが原因である可能性も指摘されています(大阪大学HP*参照)。
*参考:大阪大学微生物病研究所『新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染は細胞老化を引き起こすことで炎症反応が持続することを発見(原研がNat Aging誌に発表)』(http://www.biken.osaka-u.ac.jp/achievement/research/2022/167)
このように、老化細胞に伴う炎症が、身体内の各種で不具合を生じる原因となるのです。短期では、がん抑制機構として働く老化細胞が、長期では炎症に伴う症候群を発症する原因でもあったのです。
こうして、細胞レベルで見る老化研究は、「老化細胞除去薬(セノリティクス)」が主テーマとなっていきます。老化細胞を取り除けば、SASPを一網打尽にできるのでは? 個体の老化により発症する老年症候群(老化症との違いは前稿を参照)を一網打尽に治療し、人類が老化という病を克服できるのでは? そんな世界が見えてきたのです。
これは夢物語ではなく、現実の話です。2016年には、白血病の治療薬であるダザチニブと、ケルセチンというサプリメントの同時投与が、セノリティクスの臨床試験として実施されました。本邦でも、東京大学医科学研究所で研究されているGLS-1阻害剤が注目を集めています。数年以内に実臨床まで応用される、手に届く未来の話なのです。
⚫︎医学はどこまで万能なのか?
先述のダザチニブとGLS-1阻害剤。いずれも抗がん剤であることは非常に興味深い話です。
抗がん剤投与により老化細胞が生じ、その老化細胞を除去するために抗がん剤を投与する。何とも摩訶不思議な話です。医学はかくも複雑怪奇な学問で、すべてが叶うような魔法の薬はなく、医師もまた万能ではないのです。それでも、人類は膨大な先人たちの偉大な叡智、巨人の肩に乗り、歩みを進めてきました。今回もまた、同じく。
⚫︎“老化の本質は何か?”
極めて深淵な問いです。一つの学問、一つの切り口だけで結論を出すことは、「木を見て森を見ず」に陥りがちです。複数の学問、複数の切り口から総合的に判断し、それをretrospective(回顧的)に評価して、やっと本質の辺縁が掴めます。
『細胞レベルで見る“老化の本質”』だけで答えは出ないのですが、読者の方の理解が深まる一助になれたのなら、望外の喜びです。次回の『遺伝子レベルで見る“老化の本質”』と併せて、深掘りしていただければ幸いです。『人類は老化という病を克服する』。
乾 雅人 医療法人社団 創雅会 理事長
銀座アイグラッドクリニック 院長
メディテラス株式会社 代表取締役