コールダー・ウオー ドル覇権を崩壊させるプーチンの資源戦争/マリン・カツサ著/渡辺惣樹訳/草思社/2015
久々に見つけた快著、怪書と言うべき本。
著者の着眼点には脱帽する。
宮崎正弘は、この本の価値に気づいている。発刊当時の書評を読んでおきたい。
http://melma.com/backnumber_45206_6210257/
宮崎正弘の国際ニュース・早読み(北京の中央警備にも異変か?)
2015/05/21
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」
平成27年(2015)5月21日(木曜日)
通算第4546号
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◆書評 ◇しょひょう ▼ブックレビュー ◎BOOKREVIEW◆
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
静かに確実にロシアがドル基軸体制を揺らし始めた
「ペトロダラー」というサウジをビルトインしてきたドル基軸体制の弱体化
♪
マリン・カツサ著、渡辺惣樹訳『コールダー・ウォー』(草思社)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
国際政治学上、この書物は画期的意味を持つばかりか、近年最大の問題作と言える。
従来の地政学、宇宙時代の地政学を越えて、中国の野望である「超限戦」がとかれ、ハッカー戦争が語られた。
いまも軍事地政学の考え方の主流は、これらの思想が基本にある。
しかし、本書は、石油経済学の視点から通貨戦争を読み解く、従来的発想の延長線上にあると雖も、これをプーチンの世界戦略にひっかけての革新的な問題提議である。
つまりプーチンは「十五年にわたって次なる冷戦の戦い方を研究してきた(中略)。闘いの武器は軍事力ではない。世界のエネルギー供給をコントロールする力、それがプーチンの新型兵器」だという。
なるほど意表を突く視点であり、全米でベストセラー入りしている事態も頷ける。
表向き、中国の軍事的脅威は可視的であり、南シナ海で現実に中国は他国の領海にある岩礁を侵略している。その軍拡テンポは凄まじく、しかも傲然とアジアの覇権を言いつのり、人民元がドルに代替するなどとえらそうである。
ロシアの資源戦略上のゲーム・チェンジという現実は、たとえ数字、貿易統計上は可視的であっても、プーチンが公言することがないため、ロシアの意図する新しい戦略は判然としなかった。
ところがプーチンの『実績』をみると、既に世界石油の15%がロシアから船積みされ、ルーブル決済の貿易相手国が増えているという事実。つまり著者が説くように、「新冷戦」の最中であり、いずれペトロダラーというドル基軸体制を終焉させるばかりか、米国支配の世界システムが崩壊すると予測するのである。
「ペトロダラー」というサウジアラビアを体制内にしっかりとビルトインしてきたドル基軸体制が弱体化しつつある。
この「ペトロダラーというドル基軸体制」を発明したのはニクソンだった。
1971年にドルの金兌換体制を終わらせ、以後、ニクソンはサウジアラビアに肩入れして、こう囁いた。
「サウジを防衛し、サウジをまもるためにはどんな兵器でも売却する」うえ、サウジ王室を未来永劫、保護する。その見返りは「石油販売はすべてドル建てにすること、そしてもう一つは、貿易黒字部分で米国財務省証券を購入する」。
これが米国の「最高のメカニズムの完成であった」。
世界は「石油購入のためにはドルを貯めなくてはならなかった。世界的な需要が高まるドルを連邦準備銀行は殆どゼロコストで発行することが出来た」(79p)。
しかし時代は変わった。というより米国は自らの愚策を重ねることによって、自らを弱体化させてしまったのだ。
いまやロシアの石油埋蔵は世界一であり、ガス、レアメタル、ウランなどにも恵まれ、ガス輸出の顧客をパイプラインを敷設して次々と拡大してきた。日本のガス輸入の10%はロシアからである。
ロシア原油生産はいまでは日産1200万バーレル。「世界の石油消費量は日に8500万バーレルであり、うち5500万バーレルは国際間取引によって調達されている」。ロシアから輸出される石油は世界の取引の、じつに15%である。
他方、イラン、イラク、サウジアラビアの石油生産は世界の20%を占める。
▼中東の混乱はロシアにとって有利な状況になるカード
中東が混乱を極めることはロシアにとって有益である。制裁を受けるイランは闇で石油を処分しているが、買い手はロシアと中国である。GPsの観測を逃れてイランから積み出されるタンカーは、表向き「行く先不明」と発表されている。
サウジは増産を続行し、原油代金を劇的に下げるエンジン役をいまも実行しているが、困窮しているのは表面的にロシアに見えて、じつは米国のシェールガス開発をつぶすことにある。
だからプーチンはロシアの苦境を二年間と踏んでいるのだ。
なぜならサウジは米国の中東政策に立腹し、とくにシリア攻撃とイスラエル政策に大きな不満を抱く他方、バーレンの危機にサウジは一国で対応したが、米国はなにもしなかった。そればかりか、チュニジア、リビア、エジプトで「アラブの春」に味方した。サウジの米国不信は確定的となった。
そしてプーチンはある時点からイスラエルへ急接近を開始した。
オバマがイスラエルを敵視し始める前のことである。
それは2000年にイスラエル沖合に巨大なガス田が発見され、またイスラエル国内に膨大なシェールガス埋蔵が確認された時点と合致する。ロシアはガス田開発に協力し、イスラエルでのガス商業生産は2004年に開始された。そして送油施設に巨費を投じているが、この施設防衛にイスラエルは米国を当てにせず、かわりにロシア海軍に依拠する。
中東のパワーバランスは劇的に替わり、グレートゲームの基本律が音もなく変調し、とどのつまり、石油決済のドル機軸体制は根底が脅かされる状況になったのである。
あまつさえ米国のイラン制裁は、かえってドル基軸体制を弱体化させたと著者は分析する。
つまりインドはイランに送金できないから現物の金で原油代金を支払い、中国は武器と消費財で支払い、ロシアとはバーター取引を実行し、じつは韓国も密かにウォンで支払っている形跡がある。トルコは第三国経由で金塊をテヘランを届けた。まさにドル機軸が脅かされ、サウジアラビアが、そのうちドル機軸から脱出する試みをはじめるだろう、と著者は不気味な予測をするのである。
ロシアに接近するイスラエル、サウジアラビア、そしてイラン。人民元決済を拡大する中国はこの動きに便乗し、通貨スワップ、人民元決済の拡大と世界有数の市場での人民元取引を増加させている。
こうした現実の大変化に日本はじつにのほほんとしているようだ。
◇ ◇
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜










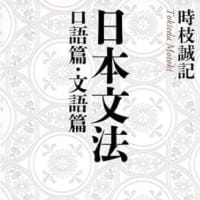




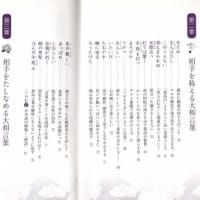
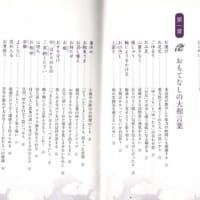
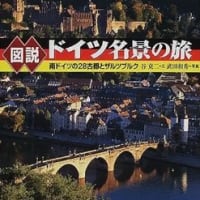
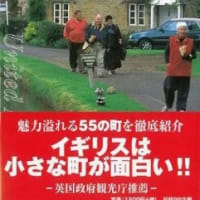
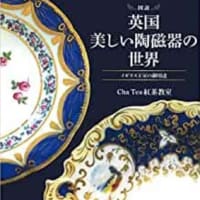






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます