ビルマの竪琴/竹山道雄
もともと「赤とんぼ」という子供向け雑誌に掲載されていたが、小説として認知された名作である。
ビルマ戦線に従軍し生き残った残留日本兵が僧となり、戦死した方の遺骨を拾い集める決意をし,それを実行するためビルマに残留するというシナリオの小説である。
小説は、童話風に書かれ、時代を越えて名作の一つとして評価を受けている。なお、作者は、評論家、独文学者であり、日本人に希望を与えたいいう一心でこの小説を書き、信じられない話だが小説はこの一作だけしか書いていない。
小説も素晴らしいが、この小説のあとがきにも良い話が書いてある。
読む世代は、中学生~大学生が適している。
架空の話だと思っていたが、調べてみると小説のモデルが実は存在する。
http://plaza.rakuten.co.jp/cinecitta80/diary/200902200000/
「ビルマの竪琴」のモデル…僧侶・中村一雄さん
2008年12月17日 92歳で死去「兵隊たちの魂が凝縮されているようだ」。ミャンマー(旧ビルマ)で拾った大きなタマムシは、戦場の残酷さと裏腹に美しい輝きを放っていた。大切に保管され、遺品として仏前に供えられている。
福井県の永平寺で修業中の1938年に徴兵され、フィリピンなど東南アジアを転戦。多くの死者が出たインパール作戦に参加し、ビルマで終戦を迎えた。
所属した「吉本隊」約20人は英軍の捕虜となりながらも収容所で合唱隊を編成、「荒城の月」や「さくら」などで兵士の心を慰めた。ビルマで同様に終戦を迎えた友人の高橋良雄さん(87)は「収容所でコーラスの指揮をしていた姿をよく覚えている」としのぶ。
ドイツ文学者の竹山道雄さんが書いた小説「ビルマの竪琴」の主人公、水島上等兵のモデルになったとされる。竹山さんは同じ部隊にいた教え子から、合唱隊の話を聞いたという。
復員後は群馬県昭和村の雲昌寺の住職に。一生をかけて戦争犠牲者の鎮魂と償い、平和交流に力を注いだ。30人程度の参拝団でたびたびミャンマーを訪問。慰霊にはいつも、終戦間際に現地の土を素焼きにして作った小さな茶わんを使って水をくんだ。
「武者一雄」というペンネームで自らの体験を書いた児童文学「ビルマの耳飾り」はビルマ語に訳され、同国の文学賞を受賞した。98年には、私財を投じて同国キンウー市に戦争の犠牲者を悼む慰霊塔を建立したほか、小学校の建設費用を寄付したこともある。
長男の真一さん(60)は「現地の人々に迷惑をかけ、罪滅ぼしをしたいという気持ちが常にあったのだと思う。ミャンマーのことを話す父の顔はとても生き生きしていた」と振り返った。
http://shisly.cocolog-nifty.com/blog/2008/01/post_ddce.html
2008年1月10日 (木)
竹山道雄「ビルマの竪琴」
ビルマ(ミャンマー軍事政権)といえば、竹山道雄(1903-1984)の「ビルマの竪琴」という児童文学を思い出す人が少なくないだろう。この名作は二度の映画化などで今日でも若い人が御覧になっているようだが、かなり批判的な内容が目につく。加害者責任を直視していない、戦争を感傷的にとらえ、軍国主義への反省はするが、侵略や戦争犯罪のことは忘れて、日本人の死者への鎮魂だけにとどまっている、つまり反戦文学としてなまぬるいという批判である。また昔に梅棹忠夫が指摘したことで有名であるが、要約すれば「ビルマでは長年修業を積んで僧になるので、水島上等兵は簡単に坊さんにはなれない、また戒律は厳しく歌舞音曲にたずさわることはできない、竪琴はもちろん歌うことはしない。ビルマは経済的には遅れているが、文化的には高度な文明国である。」はたしてこれらの今日的批判は正当なものであろうか。
物語の設定上には相当の無理があるものの、文学としてみると、ケペルはやはり竹山道雄「ビルマの竪琴」は不朽の名作であると考えている。(市川崑の映画については未見なのでここでは触れない)
竹山道雄の「ビルマの竪琴ができるまで」によると、昭和21年に雑誌「赤とんぼ」の編集長・藤田圭雄に、何か児童向きの読物を書いて欲しいと頼まれた。藤田も竹山とは同じドイツ文学出身である。
竹山は次のような空想が頭に浮んだ。
「モデルはないけれども、示唆になった話はありました。一人の若い音楽の先生がいて、その人が率いていた隊では、隊員が心服して、弾がとんでくる中で行進するときには、兵たちが弾のとんでくる側に立って歩いて、隊長の身をかばった。いくら叱ってもやめなかった。そして、その隊が帰ってきたときには、みな元気がよかったので、出迎えた人たちが、君たちは何を食べていたのだ、とたずねた。鎌倉の女学校で音楽会があったときに、その先生がピアノのわきに座って、譜をめくる役をしていました。「あれが、その隊長さん」とおしえられて、私はひそかにふかい敬意を表しました。
これがビルマの竪琴の原型モチーフであるという。作品とはかなり異なるであろう。一説には、戦死した教え子の中村徳郎をモデルにしたとも伝えられる。
竹山は最初、舞台を中国の奥地にするつもりであった。ここで日本兵が合唱をしていると、敵兵もつられて合唱をはじめ、ついに戦いはなくなった、という筋を考えた。ところが、日本人と中国人とでは共通の歌がない。日本でもよく知られ外国人も知っている歌といえば、「庭の千草」や「埴生の宿」や「蛍の光」などである。そうすると相手はイギリス兵。場所はビルマのほかにはない。だが、竹山はビルマに一度も行ったこともない。昭和21年当時、満足なビルマの資料などほとんどなかっただろう。空想によるファンタジーという部分が多い。戦争をテーマにした作品だけにノンフィションと思われる人も多いだろうが、ドイツ文学者の竹山「ビルマの竪琴」はファンタジー童話なのである。そして国境を越えた人類愛を歌った作品として稀有な成功をおさめている。最近、映画「ビルマの竪琴」をミャンマーの人が観てどう思うか(2時間以上の作品をわずか25分にカットして調査している)ということから原作の竹山「ビルマの竪琴」にまで批判が発展するのを知り奇異に感ずる。戦後すぐに書かれた作品には、まだ戦争が実体験として読者も観客もあったので、この原作も日活映画「ビルマの竪琴」も広く日本人の心の中に共感をもって迎えられたと思う。また竹山道雄の評論家としてのその後の政治的思想や活動は詳しく知らないが、この作品そのものは独立性をもっており、その価値は少しも損なわれていないと思う。
もともと「赤とんぼ」という子供向け雑誌に掲載されていたが、小説として認知された名作である。
ビルマ戦線に従軍し生き残った残留日本兵が僧となり、戦死した方の遺骨を拾い集める決意をし,それを実行するためビルマに残留するというシナリオの小説である。
小説は、童話風に書かれ、時代を越えて名作の一つとして評価を受けている。なお、作者は、評論家、独文学者であり、日本人に希望を与えたいいう一心でこの小説を書き、信じられない話だが小説はこの一作だけしか書いていない。
小説も素晴らしいが、この小説のあとがきにも良い話が書いてある。
読む世代は、中学生~大学生が適している。
架空の話だと思っていたが、調べてみると小説のモデルが実は存在する。
http://plaza.rakuten.co.jp/cinecitta80/diary/200902200000/
「ビルマの竪琴」のモデル…僧侶・中村一雄さん
2008年12月17日 92歳で死去「兵隊たちの魂が凝縮されているようだ」。ミャンマー(旧ビルマ)で拾った大きなタマムシは、戦場の残酷さと裏腹に美しい輝きを放っていた。大切に保管され、遺品として仏前に供えられている。
福井県の永平寺で修業中の1938年に徴兵され、フィリピンなど東南アジアを転戦。多くの死者が出たインパール作戦に参加し、ビルマで終戦を迎えた。
所属した「吉本隊」約20人は英軍の捕虜となりながらも収容所で合唱隊を編成、「荒城の月」や「さくら」などで兵士の心を慰めた。ビルマで同様に終戦を迎えた友人の高橋良雄さん(87)は「収容所でコーラスの指揮をしていた姿をよく覚えている」としのぶ。
ドイツ文学者の竹山道雄さんが書いた小説「ビルマの竪琴」の主人公、水島上等兵のモデルになったとされる。竹山さんは同じ部隊にいた教え子から、合唱隊の話を聞いたという。
復員後は群馬県昭和村の雲昌寺の住職に。一生をかけて戦争犠牲者の鎮魂と償い、平和交流に力を注いだ。30人程度の参拝団でたびたびミャンマーを訪問。慰霊にはいつも、終戦間際に現地の土を素焼きにして作った小さな茶わんを使って水をくんだ。
「武者一雄」というペンネームで自らの体験を書いた児童文学「ビルマの耳飾り」はビルマ語に訳され、同国の文学賞を受賞した。98年には、私財を投じて同国キンウー市に戦争の犠牲者を悼む慰霊塔を建立したほか、小学校の建設費用を寄付したこともある。
長男の真一さん(60)は「現地の人々に迷惑をかけ、罪滅ぼしをしたいという気持ちが常にあったのだと思う。ミャンマーのことを話す父の顔はとても生き生きしていた」と振り返った。
http://shisly.cocolog-nifty.com/blog/2008/01/post_ddce.html
2008年1月10日 (木)
竹山道雄「ビルマの竪琴」
ビルマ(ミャンマー軍事政権)といえば、竹山道雄(1903-1984)の「ビルマの竪琴」という児童文学を思い出す人が少なくないだろう。この名作は二度の映画化などで今日でも若い人が御覧になっているようだが、かなり批判的な内容が目につく。加害者責任を直視していない、戦争を感傷的にとらえ、軍国主義への反省はするが、侵略や戦争犯罪のことは忘れて、日本人の死者への鎮魂だけにとどまっている、つまり反戦文学としてなまぬるいという批判である。また昔に梅棹忠夫が指摘したことで有名であるが、要約すれば「ビルマでは長年修業を積んで僧になるので、水島上等兵は簡単に坊さんにはなれない、また戒律は厳しく歌舞音曲にたずさわることはできない、竪琴はもちろん歌うことはしない。ビルマは経済的には遅れているが、文化的には高度な文明国である。」はたしてこれらの今日的批判は正当なものであろうか。
物語の設定上には相当の無理があるものの、文学としてみると、ケペルはやはり竹山道雄「ビルマの竪琴」は不朽の名作であると考えている。(市川崑の映画については未見なのでここでは触れない)
竹山道雄の「ビルマの竪琴ができるまで」によると、昭和21年に雑誌「赤とんぼ」の編集長・藤田圭雄に、何か児童向きの読物を書いて欲しいと頼まれた。藤田も竹山とは同じドイツ文学出身である。
竹山は次のような空想が頭に浮んだ。
「モデルはないけれども、示唆になった話はありました。一人の若い音楽の先生がいて、その人が率いていた隊では、隊員が心服して、弾がとんでくる中で行進するときには、兵たちが弾のとんでくる側に立って歩いて、隊長の身をかばった。いくら叱ってもやめなかった。そして、その隊が帰ってきたときには、みな元気がよかったので、出迎えた人たちが、君たちは何を食べていたのだ、とたずねた。鎌倉の女学校で音楽会があったときに、その先生がピアノのわきに座って、譜をめくる役をしていました。「あれが、その隊長さん」とおしえられて、私はひそかにふかい敬意を表しました。
これがビルマの竪琴の原型モチーフであるという。作品とはかなり異なるであろう。一説には、戦死した教え子の中村徳郎をモデルにしたとも伝えられる。
竹山は最初、舞台を中国の奥地にするつもりであった。ここで日本兵が合唱をしていると、敵兵もつられて合唱をはじめ、ついに戦いはなくなった、という筋を考えた。ところが、日本人と中国人とでは共通の歌がない。日本でもよく知られ外国人も知っている歌といえば、「庭の千草」や「埴生の宿」や「蛍の光」などである。そうすると相手はイギリス兵。場所はビルマのほかにはない。だが、竹山はビルマに一度も行ったこともない。昭和21年当時、満足なビルマの資料などほとんどなかっただろう。空想によるファンタジーという部分が多い。戦争をテーマにした作品だけにノンフィションと思われる人も多いだろうが、ドイツ文学者の竹山「ビルマの竪琴」はファンタジー童話なのである。そして国境を越えた人類愛を歌った作品として稀有な成功をおさめている。最近、映画「ビルマの竪琴」をミャンマーの人が観てどう思うか(2時間以上の作品をわずか25分にカットして調査している)ということから原作の竹山「ビルマの竪琴」にまで批判が発展するのを知り奇異に感ずる。戦後すぐに書かれた作品には、まだ戦争が実体験として読者も観客もあったので、この原作も日活映画「ビルマの竪琴」も広く日本人の心の中に共感をもって迎えられたと思う。また竹山道雄の評論家としてのその後の政治的思想や活動は詳しく知らないが、この作品そのものは独立性をもっており、その価値は少しも損なわれていないと思う。










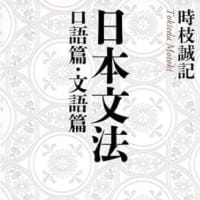




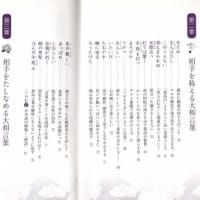
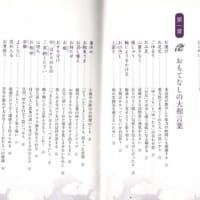
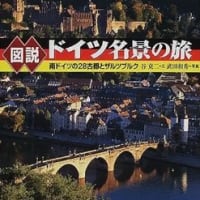
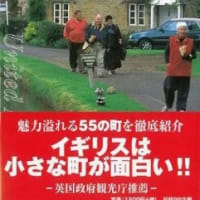
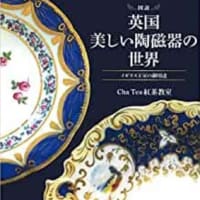






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます