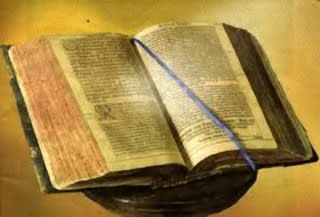秋虫の声12選
マツムシ 0:02
スズムシ 0:41
カンタン 1:18
アオマツムシ 1:45
エンマコオロギ 2:35
ツヅレサセコオロギ 3:07
ミツカドコオロギ 3:48
オカメコオロギ類 4:27
クマコオロギ 5:03
クサヒバリ 5:51
ヤマトヒバリ 6:25
カネタタキ 6:51
ヒガシキリギリス 7:25
ハヤシノウマオイ 8:11
トヨタ白川郷自然學校 https://toyota.eco-inst.jp/
秋虫の声12選
マツムシ 0:02
スズムシ 0:41
カンタン 1:18
アオマツムシ 1:45
エンマコオロギ 2:35
ツヅレサセコオロギ 3:07
ミツカドコオロギ 3:48
オカメコオロギ類 4:27
クマコオロギ 5:03
クサヒバリ 5:51
ヤマトヒバリ 6:25
カネタタキ 6:51
ヒガシキリギリス 7:25
ハヤシノウマオイ 8:11
トヨタ白川郷自然學校 https://toyota.eco-inst.jp/
【クリック】
コロナより死者が多い「熱中症」で、経済活動を止めないのはなぜか
一部引用
全国でコロナの1.7倍の患者、
東京で8倍の死者を出す病とは
厚生労働省の発表によれば、全国で今月10日から16日までにPCR検査で陽性と確認されたのは7281人。また、NNNの集計では、東京都で8月に入って24日までに新型コロナで亡くなったのは20人である。
では、全国でコロナの1.7倍の患者を生み出し、東京でコロナの8倍にもなる死者を出している病は、いったい何かというと、「熱中症」である。
連日のように日本列島を襲う殺人的な暑さで、熱中症による死者が急増しているのだ。
厚生労働省の統計によれば、熱中症で亡くなった人は2010年が統計史上最多の1731人、記録的な猛暑だった18年も1581人にのぼっている。
東京都でひと月弱だけで170人というハイペースなのだから、47都道府県合計の死者はかなりの数に膨れ上がるはずだ。
熱中症のリスクは
日本でなぜ軽視されるのか
なぜこうも、われわれは熱中症のリスクを軽視しているのか。いろいろなご意見があるだろうが、筆者はその根底に、日本人が「暑さで倒れる」ということに慣れ切っていること、
もっと言えば、「夏なんだからそういうこともあるよ」という、どこか当たり前のことのようにそれを受け入れていることが、大きな理由としてあるのではないかと思っている。
《子供の熱中症死を続出させる「根性大国ニッポン」の狂気》(2018年7月26日)という記事の中で詳しく述べたが、実は日本人が「夏になると熱中症でバタバタと人が死ぬ」という状況に慣れたというか、「日常風景」として受け入れるきっかけとなったものがある。
最近はバタバタと子どもが死んだので、ようやく少し配慮をするようになったが、高校野球に代表される「根性部活」では、声出し、上級生の身の回りの世話、大きな声で挨拶などなど、
本来スポーツとは無縁の「精神修養」を強いる。
日本軍と同じで、心を鍛えれば個人は凄まじい力を発揮して、強いチームをつくれるという考え方が、いまだに根強いのだ。
「暑さでぐったりする」ということに慣れさせて、「倒れたら立ち上がる」ことを子どもたちに強いる。長らく部活動では、人の命より「暑さのなかで鍛える」ということの方が、優先されてきたのである。
「熱中症」というのは、日本型根性教育の中で、弱い者を「ふるい」にかける試練の1つとして認められてきたのだ。
つまり、我々の社会は「暑さで死ぬ人」を織り込み済みで回っているのだ。
これこそが、我々が「熱中症」をそこまで「恐ろしい病」だと思えない最大の理由ではないか、と筆者は考えている。
この殺人的な暑さの中でも、いまだに来年もオリンピックをやろうと考えている人がかなりいる。
「今年は残念だけど、来年の夏こそ甲子園に行って球児たちの活躍を見るぞ」と楽しみにしている人も多い。
今のままの認識では、高齢化の進む日本の熱中症死者が凄まじい数にのぼることは、目に見えている。
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/jtown/trend/jtown-310786
一部引用
「たまたま電車に迷い混んだ個体が、電車内の温度がセミにとって快適なため居着いてしまったのかもしれませんね。 アブラゼミは涼しい環境を好む傾向があるとのことです」
アブラゼミにとっても、今年は耐え難い猛暑ということだろうか。ツイッターユーザーからは、セミに同情する声が多数寄せられていた。
「セミさんも涼んでるのでしょうか」
「外に出たら命取りになりかねんので大目に見てやってください」
「暑過ぎて涼んでるね セミもwww」
世界中から偏見がなくなる ― いつ? Ⅱ
「わたしには夢がある」。今から50年前の1963年8月28日,米国の公民権運動の指導者マーチン・ルーサー・キング2世が,最も有名な演説の中でそう言いました。
キング牧師は,人を引きつけるその言葉を繰り返して,いつの日か人々が人種偏見のない生活を楽しむようになるという自分の夢つまり希望を言い表わしました。
その願望は米国の聴衆に向けて語られたものですが,夢の本質的な部分は多くの国の人々にも受け入れられてきました。
その演説の3か月後,1963年11月20日には,100余りの国々が,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言を採択しました。
その後の数十年間に,他の世界的規模の行動計画も採択されました。そのような大々的な努力が払われたのですから,当然,それはどんな結果をもたらしてきたのか,という問いが生じます。
2012年3月21日,パン・ギムン国連事務総長はこう述べました。
「人種主義,人種差別,外国人排斥,およびそれに関連した不寛容を防ぐとともに一掃するための,価値ある条約や手段が数多くある。また,そのための包括的な世界的規模の枠組みもある。にもかかわらず,
今なお人種主義が原因で世界中の多くの人々が苦しんでいる」。
人種主義その他の偏見との闘いの点で幾らか成功している国や地域においてさえ,いまだに次のような疑問が残っています。そうした進歩によって本当に人々の根強い偏見が取り除かれたでしょうか。
それとも,単に偏見が表に出ないようにされただけでしょうか。それは差別を防ぐ一助となるだけで,偏見を根絶する点では無力だ,と考えている人もいます。
なぜそうなのでしょうか。なぜなら,差別は目に見え,法律で処罰できる行為であるのに対し,偏見は人々の内奥の考えや感情に関連した,容易には規制できないものだからです。
ですから,偏見を根絶しようとする試みは,差別行為を単に抑制するだけではなく,特定の集団の人々に対する考えや気持ちをも変えさせるものでなければなりません。
しかし,そのようなことが本当に可能でしょうか。可能だとしたら,どのようにしてするのでしょうか。
では,そうした変化を遂げられること,またそうするのに助けになるものがあることを理解するために,幾つかの実例を見てみましょう。
世界中から偏見がなくなる ― いつ? Ⅲ
偏見を克服するのに聖書が助けになった へ続く>>>