つづくと言って、ほったからしにしてあった
JUNEシリーズのつづきです。
1983年、「一生女は愛さない」というキャッチで
女性たちを虜にした「アナザーカントリー」の登場、
そして1987年の映画「モーリス」は、
「もう、こういう形でしか純愛映画は作れないのかもしれない」
とまで評された。
男性の同性愛は、女性たちの最高の娯楽にまで到達した。
「一生女は愛さない」という男に、なぜ女性が熱狂したのか。
女にだらしなく、女の尻ばかりを追う男性よりも、
女性をはねつける、女性の誘惑を退けることの出来る男性が、
女にとっては逆に凛々しくまぶしい存在だった?
が、それよりも私は、女性性が、人類にとって最上のもの、
という既成概念を否定…または覆したからではないかという気がしている。
既成概念の打破に、女性が反応したのだと思っている。
私にとって、同性愛とは、マイノリティの象徴だった。
自分自身の、世間に対する違和感への自覚、それは、
自分がマイノリティであり、異端であり、少数派である
ことの自覚だった。
常にボードレールの言うエニウェア・アウト・オブ・ザ・ワールド、
ここではないどこか、ほかの世界に自分の居場所がある…
それを信じていた。
それほど今いる場所に違和感を持ち、自分の場所を
見い出せなかった自分、
だから、ホモセクシュアルに対しても、同じ意味での
シンパシーがあった。
同性愛も、当時の社会では確実にマイノリティだった。
私は、彼ら同性愛者に対するシンパシーがあった。
自分自身が異端であると自覚していたから、
彼らを同類と見る感覚があったのだと思う。
そうして、同性愛者に感じるシンパシーのもう一つは、
彼らの美的感覚のゆえだった。
レオナルドにしてもミケランジェロにしても、
そして20世紀のルキノ・ヴィスコンティにしても
(彼らはみなバイセクシュアルだったが)、
ヘテロの男性には生み出せない美の感覚を持っていた。
だから私は彼らを深く尊敬した。
彼らは女性美のみでなく、男性の美も理解していた。
そして、男性の美をも女性美と等しく扱った。
ミケランジェロは、女性の彫刻を彫る時、男性をモデルにした。
そういうことの出来る者は、ゲイでありバイだからではないか。
彼らには何らかの女性的資質を持っているから、
そういう美を生み出し理解することが出来るのではないか。
そんな風に考えた。
ヘテロの男性には、レオナルドのようなアンドロギュヌス的
美の感覚を持ち合わせない。
むしろそうしたものは、女性のものである。
女性的な資質がある男性だから、美を生み出せるのではないか。
だから、私は彼らゲイの人やバイの人の美の感覚を、
私の感覚にもっとも近いものとして感じた。
「永遠に女性なるものが我らをひきてゆかしむ」
これは男性側の論理にすぎない!
と私は感じていた。
古来より女性美は、美の規範とされて来たが、
それは男性の論理ではないのか。
女性の美は果たして最上の美なのか…。
女性美を男性は賛美するが、そこに違和感を感じていた。
女性美は、本当に美として最上のものなのか。
女性は男性の理想の生きものではない。
女性の外観だけを見て女性を礼賛し理想化する、
女性に夢を持つことは男性にとって必要なことなのだろう。
しかし女は現実に生き、どろどろとした内面を抱え、
苦悩する存在でもある。
女性の外観だけで女性を判断する男性は、
女を何も分かっていない。分かろうとしない。
女性を理想化するのではなく、女性の外面だけを見るのでなく、
女性の感覚を、女性の感性を、女性そのものを理解してほしい。
…
ギュスターヴ・モローの「死せる詩人を運ぶケンタウロス」
という絵を見た時、衝撃があった。
今も私にとって、密かなワン・アンド・オンリーだ。
初めて見た時、何か禁断の果実を味わったような、
見てはいけないものを見た、そんな罪悪に似た感覚があった。
だが、これが、私の感覚なのではないか…。
躊躇いながら、私には、これを最上のものとする感覚があった。
モローのことも、一時同性愛者ではないかと疑っていた。
だが彼には内縁の妻がいて、生涯結婚はしなかったものの、
ストレートだったらしい。
「印象派の画家たちが戸外で太陽の光を研究しているあいだに」
と例によって澁澤龍彦が言う。
「太陽の光や青空を、これほど忌避した画家もめずらしいのでは
ないだろうか」
モローについては、長くなりすぎる恐れがあるので、
これ以上の深入りはなしにするが、
澁澤もこの画家を倒錯の美、異端と認識している。
モローは、印象派と完全に重なる時代、やはり明らかに
一人違うところにいた画家だったことは確かだ。
ヘテロの男性にももちろん素晴らしい芸術家、作家がいる。
当たり前ながらむしろそちらの方が数が多い。
けれども、彼ら、一流の作家たちも必ず、
女性性を信奉してはいても、それ以外に対しての
偏見や、差別の意識はなかったはずと、信じている。
稲垣足穂のA感覚とV感覚に対する考察が、
私の助けになった。
従来の男性は、V感覚でしかものを考えて来なかった。
(V=Vagina)
しかし、一番すぐれているのはVではなくAである。
(A=Anus)
芸術家たちは、すべてA感覚の持ち主である…
世の中には今もV感覚であふれている。
男性が求める感覚。
単にVaginaがあればそれでよしとする感覚。
Vという側面でしか物ごとを考えない感覚。
でも、A感覚は違う。
そこには性の抽象化がある。
男性・女性という区別なく、生々しい性とは
別の次元に理想を見、美を見る。
自らの中に男性性と女性性の感覚を合わせ持つ、
そしてそれゆえに性を抽象化させる。
それがレオナルドの到達した理想の美の世界、
ヘテロ的な感性では達することの出来ない
美の世界がそこにある。
それが、A感覚ということだと私は思った。
究極の美は男性性や女性性を超えたものであり、
A感覚的なものなのではないか。
男性がVを信奉する限り、A的美は彼らには
理解できないだろう。
私の根深いコンプレックスは、タルホによって
解放されたのかもしれない。
学生時代、女子校だったので、女性同士の疑似恋愛も、
当然経験した。
私には、憧れる同級生がいた。
その子は、美人だったわけではない。
ディベートの得意な、
先生方に平気で議論を吹っ掛けるようなタイプの、
学級委員タイプではないが、理論派の女の子だった。
その頭のいい、弁の立つところに憧れていた。
私はずっと憧れつづけ、大学に入っても憧れつづけていた。
相手は私の名前を認識している程度だった。
だいぶ経って、もう仕事をしている時に、偶然彼女に
真正面から出会った。
子連れで、平凡な主婦になっていた。
私は一目で彼女と気づいたが、向こうは私を覚えていなかった。
私はとても残念に思った。
私を認識されなかったからではない。
彼女が平凡な女になっていたことにショックを受けたのだ。
弁の立つ彼女なら、将来はどんなに優秀な人物になるだろうかと
考えていたからだ。
もう一人、同級生でこちらは完全にボーイッシュなタイプの
女の子がいて、憧れていた。
彼女が文化祭の劇で、男子の格好をして、学生服を着て
主役を演じた時、下級生の女の子にすごく人気が出た。
女子校ではよくあることだ。
私も同級のその子のファンになった。
ざっくばらんな子で、話しやすいいい子だった。
その子も、学校を出てすぐに結婚した。
女の子が同性に憧れる。
それも、私の中では自然な情動だった。
テニスの女子選手、ナブラチロワに憧れていた。
彼女はレズであることを隠さず、恋人とのバカンスを
写真に撮られても平気だった。
その生き方を、かっこいいと思っていた。
早すぎたジェンダーフリーだったのかもしれない。
ボーイズラブは、今やありふれた女性の娯楽のひとつになった。
市民権を得て、大っぴらに享受出来る時代になった。
ありふれた…。何と、開かれた時代になったのだろう。
男性同士、女性同士、そんなことは関係ない。
美しいものは美しく、かっこいいものはかっこいい。
男性・女性に限らず、いいと思うものはいいのだ。
そんな当然のことを、マイノリティと思い、異端と思い、
肩身の狭い思いをしていた自分、
自分が同性愛に今もこだわるのは、
ゲイの人たちと感覚が近いということ、
マイノリティーへのシンパシー、という
この二つのことからだ。
その当時の自分を今そっと、励ましてやりたい。


美術館・ギャラリーランキング
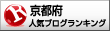
京都府ランキング
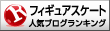
フィギュアスケートランキング
↓ブログ村もよろしくお願いします!

にほんブログ村

にほんブログ村
JUNEシリーズのつづきです。
1983年、「一生女は愛さない」というキャッチで
女性たちを虜にした「アナザーカントリー」の登場、
そして1987年の映画「モーリス」は、
「もう、こういう形でしか純愛映画は作れないのかもしれない」
とまで評された。
男性の同性愛は、女性たちの最高の娯楽にまで到達した。
「一生女は愛さない」という男に、なぜ女性が熱狂したのか。
女にだらしなく、女の尻ばかりを追う男性よりも、
女性をはねつける、女性の誘惑を退けることの出来る男性が、
女にとっては逆に凛々しくまぶしい存在だった?
が、それよりも私は、女性性が、人類にとって最上のもの、
という既成概念を否定…または覆したからではないかという気がしている。
既成概念の打破に、女性が反応したのだと思っている。
私にとって、同性愛とは、マイノリティの象徴だった。
自分自身の、世間に対する違和感への自覚、それは、
自分がマイノリティであり、異端であり、少数派である
ことの自覚だった。
常にボードレールの言うエニウェア・アウト・オブ・ザ・ワールド、
ここではないどこか、ほかの世界に自分の居場所がある…
それを信じていた。
それほど今いる場所に違和感を持ち、自分の場所を
見い出せなかった自分、
だから、ホモセクシュアルに対しても、同じ意味での
シンパシーがあった。
同性愛も、当時の社会では確実にマイノリティだった。
私は、彼ら同性愛者に対するシンパシーがあった。
自分自身が異端であると自覚していたから、
彼らを同類と見る感覚があったのだと思う。
そうして、同性愛者に感じるシンパシーのもう一つは、
彼らの美的感覚のゆえだった。
レオナルドにしてもミケランジェロにしても、
そして20世紀のルキノ・ヴィスコンティにしても
(彼らはみなバイセクシュアルだったが)、
ヘテロの男性には生み出せない美の感覚を持っていた。
だから私は彼らを深く尊敬した。
彼らは女性美のみでなく、男性の美も理解していた。
そして、男性の美をも女性美と等しく扱った。
ミケランジェロは、女性の彫刻を彫る時、男性をモデルにした。
そういうことの出来る者は、ゲイでありバイだからではないか。
彼らには何らかの女性的資質を持っているから、
そういう美を生み出し理解することが出来るのではないか。
そんな風に考えた。
ヘテロの男性には、レオナルドのようなアンドロギュヌス的
美の感覚を持ち合わせない。
むしろそうしたものは、女性のものである。
女性的な資質がある男性だから、美を生み出せるのではないか。
だから、私は彼らゲイの人やバイの人の美の感覚を、
私の感覚にもっとも近いものとして感じた。
「永遠に女性なるものが我らをひきてゆかしむ」
これは男性側の論理にすぎない!
と私は感じていた。
古来より女性美は、美の規範とされて来たが、
それは男性の論理ではないのか。
女性の美は果たして最上の美なのか…。
女性美を男性は賛美するが、そこに違和感を感じていた。
女性美は、本当に美として最上のものなのか。
女性は男性の理想の生きものではない。
女性の外観だけを見て女性を礼賛し理想化する、
女性に夢を持つことは男性にとって必要なことなのだろう。
しかし女は現実に生き、どろどろとした内面を抱え、
苦悩する存在でもある。
女性の外観だけで女性を判断する男性は、
女を何も分かっていない。分かろうとしない。
女性を理想化するのではなく、女性の外面だけを見るのでなく、
女性の感覚を、女性の感性を、女性そのものを理解してほしい。
…
ギュスターヴ・モローの「死せる詩人を運ぶケンタウロス」
という絵を見た時、衝撃があった。
今も私にとって、密かなワン・アンド・オンリーだ。
初めて見た時、何か禁断の果実を味わったような、
見てはいけないものを見た、そんな罪悪に似た感覚があった。
だが、これが、私の感覚なのではないか…。
躊躇いながら、私には、これを最上のものとする感覚があった。
モローのことも、一時同性愛者ではないかと疑っていた。
だが彼には内縁の妻がいて、生涯結婚はしなかったものの、
ストレートだったらしい。
「印象派の画家たちが戸外で太陽の光を研究しているあいだに」
と例によって澁澤龍彦が言う。
「太陽の光や青空を、これほど忌避した画家もめずらしいのでは
ないだろうか」
モローについては、長くなりすぎる恐れがあるので、
これ以上の深入りはなしにするが、
澁澤もこの画家を倒錯の美、異端と認識している。
モローは、印象派と完全に重なる時代、やはり明らかに
一人違うところにいた画家だったことは確かだ。
ヘテロの男性にももちろん素晴らしい芸術家、作家がいる。
当たり前ながらむしろそちらの方が数が多い。
けれども、彼ら、一流の作家たちも必ず、
女性性を信奉してはいても、それ以外に対しての
偏見や、差別の意識はなかったはずと、信じている。
稲垣足穂のA感覚とV感覚に対する考察が、
私の助けになった。
従来の男性は、V感覚でしかものを考えて来なかった。
(V=Vagina)
しかし、一番すぐれているのはVではなくAである。
(A=Anus)
芸術家たちは、すべてA感覚の持ち主である…
世の中には今もV感覚であふれている。
男性が求める感覚。
単にVaginaがあればそれでよしとする感覚。
Vという側面でしか物ごとを考えない感覚。
でも、A感覚は違う。
そこには性の抽象化がある。
男性・女性という区別なく、生々しい性とは
別の次元に理想を見、美を見る。
自らの中に男性性と女性性の感覚を合わせ持つ、
そしてそれゆえに性を抽象化させる。
それがレオナルドの到達した理想の美の世界、
ヘテロ的な感性では達することの出来ない
美の世界がそこにある。
それが、A感覚ということだと私は思った。
究極の美は男性性や女性性を超えたものであり、
A感覚的なものなのではないか。
男性がVを信奉する限り、A的美は彼らには
理解できないだろう。
私の根深いコンプレックスは、タルホによって
解放されたのかもしれない。
学生時代、女子校だったので、女性同士の疑似恋愛も、
当然経験した。
私には、憧れる同級生がいた。
その子は、美人だったわけではない。
ディベートの得意な、
先生方に平気で議論を吹っ掛けるようなタイプの、
学級委員タイプではないが、理論派の女の子だった。
その頭のいい、弁の立つところに憧れていた。
私はずっと憧れつづけ、大学に入っても憧れつづけていた。
相手は私の名前を認識している程度だった。
だいぶ経って、もう仕事をしている時に、偶然彼女に
真正面から出会った。
子連れで、平凡な主婦になっていた。
私は一目で彼女と気づいたが、向こうは私を覚えていなかった。
私はとても残念に思った。
私を認識されなかったからではない。
彼女が平凡な女になっていたことにショックを受けたのだ。
弁の立つ彼女なら、将来はどんなに優秀な人物になるだろうかと
考えていたからだ。
もう一人、同級生でこちらは完全にボーイッシュなタイプの
女の子がいて、憧れていた。
彼女が文化祭の劇で、男子の格好をして、学生服を着て
主役を演じた時、下級生の女の子にすごく人気が出た。
女子校ではよくあることだ。
私も同級のその子のファンになった。
ざっくばらんな子で、話しやすいいい子だった。
その子も、学校を出てすぐに結婚した。
女の子が同性に憧れる。
それも、私の中では自然な情動だった。
テニスの女子選手、ナブラチロワに憧れていた。
彼女はレズであることを隠さず、恋人とのバカンスを
写真に撮られても平気だった。
その生き方を、かっこいいと思っていた。
早すぎたジェンダーフリーだったのかもしれない。
ボーイズラブは、今やありふれた女性の娯楽のひとつになった。
市民権を得て、大っぴらに享受出来る時代になった。
ありふれた…。何と、開かれた時代になったのだろう。
男性同士、女性同士、そんなことは関係ない。
美しいものは美しく、かっこいいものはかっこいい。
男性・女性に限らず、いいと思うものはいいのだ。
そんな当然のことを、マイノリティと思い、異端と思い、
肩身の狭い思いをしていた自分、
自分が同性愛に今もこだわるのは、
ゲイの人たちと感覚が近いということ、
マイノリティーへのシンパシー、という
この二つのことからだ。
その当時の自分を今そっと、励ましてやりたい。

美術館・ギャラリーランキング
京都府ランキング
フィギュアスケートランキング
↓ブログ村もよろしくお願いします!
にほんブログ村
にほんブログ村










