昨年末に、海堂尊著『蘭医繚乱 洪庵と泰然』(PHP)を読み、読後印象をご紹介した。この時、初めて佐野栄寿(常民)が緒方洪庵の適塾で学んだ一人だということを知った。読後に少し調べていて、佐野常民が明治維新後に日本赤十字社の創設者になった人物であることと、『火城』という小説があることを知った。
それがきっかけでこの歴史小説を年初の一冊に組みいれた。
読了後に、本書の「あとがき」や奥書を読んで知ったことから、まずご紹介したい。
 PHP文庫表紙 1995年9月出版
PHP文庫表紙 1995年9月出版
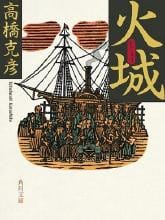 角川文庫表紙 2001年11月出版
角川文庫表紙 2001年11月出版
冒頭の写真、[新装版]は2007年12月に刊行された単行本である。
元は1992年5月にPHP研究所より単行本が刊行されていた。上掲の通り、文庫化が既に行われているのに、単行本として新装版が出版されたということが私にはちょっと驚きであり、このことがまず印象的である。それは著者自身も感じていたようだ。「新装版に寄せて」という本書末尾の一文に、その経緯が記されている。ここでは触れない。
一方、この箇所はご紹介しておきたい。
「佐賀のすばらしさは、国のために一丸となって無駄な回り道を厭わなかった点にある。揺れ動く時勢に惑わされることもなく、ただひたすら定めた目標に向かって歩き続けた。こんな道を今の日本が選べるだろうか?」(p355、1992年3月記)
「人は人のために働いてこそ価値がある。これは私の近頃の実感なのだが、佐野常民ほどその生き方を貫いた人はいない。彼は佐賀藩のために在り、日本の未来のためにすべてを捧げた。・・・・・過去を描くことがすなわち未来を読み解くことだと、私は佐野常民の起伏に満ちた人生を通じてはっきり教えられた」(p357、2007年10月記)
もう一つは、著者が歴史小説を手掛ける嚆矢となったのがこの『火城』だということを初めて知った。
「泣く、ということはひとつの才能である」という冒頭文から始まる。佐野栄寿の特異性がここにあったという。冒頭で、一瞬、エッ!と感じた。『葉隠』が家訓として重視された肥前佐賀藩においてである。佐野栄寿が泣くという特技を人々が結果的に受け入れたということがまずおもしろい。当時の風潮とは真逆の行動を必要とあらば自然に貫いたのだから。最初の節の末尾に、「男の名は佐野栄寿、後の常民。/ 日本赤十字社の生みの親である」(p6)と記す。
佐野栄寿は、佐賀藩士下村家の五男として生まれた。11歳で親戚である藩主侍医佐藤常微の養子となり、佐藤家で先に養女となっていた駒子と20歳で結婚した。この小説は、25歳の時に、藩主鍋島直正(のちの閑叟)の命により、蘭学習得のために京都に留学するところから始まり、文久元年の秋までを描く。この年の7月に栄寿に蒸気機関製造命令が出されたのである。つまり、日本赤十字社のことは、後年のことであり、この歴史小説には登場しない。
栄寿は京都で広瀬元恭に就いて蘭語と化学を2年間、大坂の適塾に入りさらに2年間学んだ後、藩命により江戸に赴き、伊藤玄朴の塾で学ぶ。この塾の塾頭になった栄寿がある事件の当事者となる。この事件の動機を栄寿は黙して語らない。だが、この事件が栄寿にとり大きな転機となっていったのは間違いがないと思う。
ここでストーリーの進展において面白い点を指摘しておきたい。司馬遼太郎の作品スタイルと同様に、ストーリーの要所要所で著者自身が顔を出し、己の解釈、仮説を加え、ストーリーに織り込んでいく。これが大きな要素になっている。ストーリーの推進力にもなっていく。
ストーリーの導入部で、適塾時代のエピソードが紹介される。藩命で潤沢な費用を支給されている栄寿は、塾生仲間に全21巻の辞書『ズーフ・ハルマ』を書き写してもらい、その謝礼に一説では7両を支払ったという。このエピソードを記した後、栄寿のスタンスが記されている。栄寿にとり辞書は蘭書を読み解く道具。「蘭学の理解よりも、蘭学の実践を意図していた栄寿にとっては、・・・・蘭語を自由に操れるようになるのが栄寿の本来の、目的ではない。自分の語学力が足りなければ別の人間がそれを正しく読めればいい。中に何が書いてあって、それが佐賀藩の将来にどう役立つか、こそが栄寿の一番の関心だった」(p10)と。これが栄寿の行動原理になる。この行動原理を実践に移したプロセスがこのストーリーともいえる。
このストーリーのテーマと特徴をご紹介しよう。
1.佐野栄寿の行動原理が実践されるプロセスを描き出す。それがメインストーリー。
栄寿の目指したのは、佐賀藩において自力で蒸気船を建造することだ。この目標をぶれずに遂行するためには、藩の方針を変容させることにも果敢に挑戦し、協力者を集め、結果をだす。やがて、栄寿の視野は、佐賀藩という規模から、日本の存在という次元にステップ・アップしていく。
栄寿は舎密の口入れ屋だと自称する。目標を達成するために、石黒寛二、中村奇輔という優秀な蘭学の徒二人と京都で機巧堂を営む田中儀右衛門(カラクリ儀右衛門)を口説いて佐賀に連れて帰る行動に出る。この人材確保・活用のプロセスが描かれていく。
尊王、開国、攘夷という思想に翻弄される世間をよそに、佐賀においては精錬方という位置づけで技術力の確立に邁進する生きざまがここにある。
2.佐賀藩主鍋島直正、後に閑叟と号した人物を、栄寿の活躍を支えた力として描く。
江戸時代の末期において、鍋島閑叟がどのような見解をもち、何をなそうとしたかがわかる。時代の推移を明察し、佐賀藩が何をなすべきかを見とおした英邁な人物像が浮かびあがる。だが、それ故に孤高な存在だったことだろう。
佐賀藩の行動がぶれなかったのは、この藩主によるところが大きいと感じた。
3.佐賀藩という組織。この藩の方針と実状のおもしろさが加わってくる。
幕領である長崎を防御するという役目を担う佐賀藩の特殊性がある。出島とオランダを介して、西洋の情報を得やすい立場にあった。それ故に彼我の差も実感し、具体的な危機感も発生する。藩主の方針のもとに反射炉の建造を進める。それは自力で大砲を製造する技術力を確立することを目指していた。火術方には技術力を高める上で七賢人と称される精鋭が集っていた。薩摩藩と同様に、当時の先端を歩む開明度の気風がある。一方、幕藩体制下において、自己防衛のために、二重鎖国を方針としていた。栄寿など枢要な人材の留学などを積極的に推進する一方において、藩領から他藩領へ人々が出ることを禁じ、一方他藩領から人が入るのも制限するという状況だった。情報漏洩の遮断策だ。『葉隠』という家訓を奉じた藩に別の顔があるところがおもしろい。また、開明のスタンスが実践されている一方で、佐賀藩にも攘夷を唱える一派がいたようである。
4.栄寿の眼と思考を介して、江戸幕府をはじめ諸藩並びに世間の動向、併せて蘭学の世界の動向が点描されていく。その中でも、栄寿が、彦根藩の頭脳となっていく長野主馬(後に主膳ろ称す)に着目していくところが興味深い。
著者は伊東玄朴と栄寿との対話の中で、玄朴に次の言葉を語らせる。
「人が従うのは力や金にではない。真摯な心と存ずる」(p313)
「この時代にあって、先の世に思いを馳せるとは、常人にたやすくできることではない。いかに殿様がお許しになられたと申しても、貫くには並大抵でなかろう。それでも、やり遂げて下され。陰ながら祈っておりまする」(p317)
このストーリーは、この言葉を栄寿とその仲間が目標に邁進するプロセスとして描き出したとも言える。
藩主閑叟は栄寿に語る。「儂は大砲を並べることで佐賀を日本の火城たらしめんとした。だが・・・・・・・・思惑とは異なっても、すでに佐賀は火城となっておる。」(p289)
「大砲も火なれば、蒸気も火。・・・・・・おまえの火がからくり儀右衛門という火を佐賀に呼びよせたのだ。こけおどかしの松明となるか、そうでないかは、これからの働きにかかっておる」(p290)
本書のタイトル「火城」はここに由来するようだ。
尊王攘夷や国学の思想が渦を巻き、騒乱を惹起している最中に、思想とは一線を画し、西洋諸国に対峙していく道を模索していた一群の人々がいたことを本書で知った。江戸時代の末期を眺める視座が広がった気がする。
栄寿がジョン万次郎と関りを持ち、一助の策をめぐらしたというくだりを興味深く読んだ。栄寿ならやったことだろうなと思う。ここにも人を活かす心が息づいている。
ご一読ありがとうございます。
補遺
鍋島直正 :ウィキペディア
佐野常民 揺ぎなき博愛精神 :「Sagabai.com」(佐賀市観光協会)
佐野常民と三重津海軍跡の歴史館 ホームページ
佐野常民の歩み
枝吉神陽 ~佐賀の「吉田松陰」~ :「Sagabai.com」(佐賀市観光協会)
伊東玄朴 :ウィキペディア
からくり儀右衛門(田中久重)の生涯 :「久留米市」
田中久重 :ウィキペディア
佐賀県の歴史第2章 嵯峨における幕藩体制 :「佐賀県」
明治維新の先駆的役割を果たした佐賀藩 :「佐賀県」
久留米からくり振興協会 ホームページ
蒸気船雛形(外輪船) :「佐賀城本丸歴史館」
蒸気車雛形 附貨車他 一台 :「さがの歴史・文化お宝帳」
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
それがきっかけでこの歴史小説を年初の一冊に組みいれた。
読了後に、本書の「あとがき」や奥書を読んで知ったことから、まずご紹介したい。
 PHP文庫表紙 1995年9月出版
PHP文庫表紙 1995年9月出版 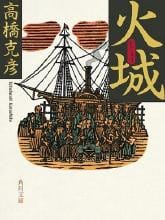 角川文庫表紙 2001年11月出版
角川文庫表紙 2001年11月出版 冒頭の写真、[新装版]は2007年12月に刊行された単行本である。
元は1992年5月にPHP研究所より単行本が刊行されていた。上掲の通り、文庫化が既に行われているのに、単行本として新装版が出版されたということが私にはちょっと驚きであり、このことがまず印象的である。それは著者自身も感じていたようだ。「新装版に寄せて」という本書末尾の一文に、その経緯が記されている。ここでは触れない。
一方、この箇所はご紹介しておきたい。
「佐賀のすばらしさは、国のために一丸となって無駄な回り道を厭わなかった点にある。揺れ動く時勢に惑わされることもなく、ただひたすら定めた目標に向かって歩き続けた。こんな道を今の日本が選べるだろうか?」(p355、1992年3月記)
「人は人のために働いてこそ価値がある。これは私の近頃の実感なのだが、佐野常民ほどその生き方を貫いた人はいない。彼は佐賀藩のために在り、日本の未来のためにすべてを捧げた。・・・・・過去を描くことがすなわち未来を読み解くことだと、私は佐野常民の起伏に満ちた人生を通じてはっきり教えられた」(p357、2007年10月記)
もう一つは、著者が歴史小説を手掛ける嚆矢となったのがこの『火城』だということを初めて知った。
「泣く、ということはひとつの才能である」という冒頭文から始まる。佐野栄寿の特異性がここにあったという。冒頭で、一瞬、エッ!と感じた。『葉隠』が家訓として重視された肥前佐賀藩においてである。佐野栄寿が泣くという特技を人々が結果的に受け入れたということがまずおもしろい。当時の風潮とは真逆の行動を必要とあらば自然に貫いたのだから。最初の節の末尾に、「男の名は佐野栄寿、後の常民。/ 日本赤十字社の生みの親である」(p6)と記す。
佐野栄寿は、佐賀藩士下村家の五男として生まれた。11歳で親戚である藩主侍医佐藤常微の養子となり、佐藤家で先に養女となっていた駒子と20歳で結婚した。この小説は、25歳の時に、藩主鍋島直正(のちの閑叟)の命により、蘭学習得のために京都に留学するところから始まり、文久元年の秋までを描く。この年の7月に栄寿に蒸気機関製造命令が出されたのである。つまり、日本赤十字社のことは、後年のことであり、この歴史小説には登場しない。
栄寿は京都で広瀬元恭に就いて蘭語と化学を2年間、大坂の適塾に入りさらに2年間学んだ後、藩命により江戸に赴き、伊藤玄朴の塾で学ぶ。この塾の塾頭になった栄寿がある事件の当事者となる。この事件の動機を栄寿は黙して語らない。だが、この事件が栄寿にとり大きな転機となっていったのは間違いがないと思う。
ここでストーリーの進展において面白い点を指摘しておきたい。司馬遼太郎の作品スタイルと同様に、ストーリーの要所要所で著者自身が顔を出し、己の解釈、仮説を加え、ストーリーに織り込んでいく。これが大きな要素になっている。ストーリーの推進力にもなっていく。
ストーリーの導入部で、適塾時代のエピソードが紹介される。藩命で潤沢な費用を支給されている栄寿は、塾生仲間に全21巻の辞書『ズーフ・ハルマ』を書き写してもらい、その謝礼に一説では7両を支払ったという。このエピソードを記した後、栄寿のスタンスが記されている。栄寿にとり辞書は蘭書を読み解く道具。「蘭学の理解よりも、蘭学の実践を意図していた栄寿にとっては、・・・・蘭語を自由に操れるようになるのが栄寿の本来の、目的ではない。自分の語学力が足りなければ別の人間がそれを正しく読めればいい。中に何が書いてあって、それが佐賀藩の将来にどう役立つか、こそが栄寿の一番の関心だった」(p10)と。これが栄寿の行動原理になる。この行動原理を実践に移したプロセスがこのストーリーともいえる。
このストーリーのテーマと特徴をご紹介しよう。
1.佐野栄寿の行動原理が実践されるプロセスを描き出す。それがメインストーリー。
栄寿の目指したのは、佐賀藩において自力で蒸気船を建造することだ。この目標をぶれずに遂行するためには、藩の方針を変容させることにも果敢に挑戦し、協力者を集め、結果をだす。やがて、栄寿の視野は、佐賀藩という規模から、日本の存在という次元にステップ・アップしていく。
栄寿は舎密の口入れ屋だと自称する。目標を達成するために、石黒寛二、中村奇輔という優秀な蘭学の徒二人と京都で機巧堂を営む田中儀右衛門(カラクリ儀右衛門)を口説いて佐賀に連れて帰る行動に出る。この人材確保・活用のプロセスが描かれていく。
尊王、開国、攘夷という思想に翻弄される世間をよそに、佐賀においては精錬方という位置づけで技術力の確立に邁進する生きざまがここにある。
2.佐賀藩主鍋島直正、後に閑叟と号した人物を、栄寿の活躍を支えた力として描く。
江戸時代の末期において、鍋島閑叟がどのような見解をもち、何をなそうとしたかがわかる。時代の推移を明察し、佐賀藩が何をなすべきかを見とおした英邁な人物像が浮かびあがる。だが、それ故に孤高な存在だったことだろう。
佐賀藩の行動がぶれなかったのは、この藩主によるところが大きいと感じた。
3.佐賀藩という組織。この藩の方針と実状のおもしろさが加わってくる。
幕領である長崎を防御するという役目を担う佐賀藩の特殊性がある。出島とオランダを介して、西洋の情報を得やすい立場にあった。それ故に彼我の差も実感し、具体的な危機感も発生する。藩主の方針のもとに反射炉の建造を進める。それは自力で大砲を製造する技術力を確立することを目指していた。火術方には技術力を高める上で七賢人と称される精鋭が集っていた。薩摩藩と同様に、当時の先端を歩む開明度の気風がある。一方、幕藩体制下において、自己防衛のために、二重鎖国を方針としていた。栄寿など枢要な人材の留学などを積極的に推進する一方において、藩領から他藩領へ人々が出ることを禁じ、一方他藩領から人が入るのも制限するという状況だった。情報漏洩の遮断策だ。『葉隠』という家訓を奉じた藩に別の顔があるところがおもしろい。また、開明のスタンスが実践されている一方で、佐賀藩にも攘夷を唱える一派がいたようである。
4.栄寿の眼と思考を介して、江戸幕府をはじめ諸藩並びに世間の動向、併せて蘭学の世界の動向が点描されていく。その中でも、栄寿が、彦根藩の頭脳となっていく長野主馬(後に主膳ろ称す)に着目していくところが興味深い。
著者は伊東玄朴と栄寿との対話の中で、玄朴に次の言葉を語らせる。
「人が従うのは力や金にではない。真摯な心と存ずる」(p313)
「この時代にあって、先の世に思いを馳せるとは、常人にたやすくできることではない。いかに殿様がお許しになられたと申しても、貫くには並大抵でなかろう。それでも、やり遂げて下され。陰ながら祈っておりまする」(p317)
このストーリーは、この言葉を栄寿とその仲間が目標に邁進するプロセスとして描き出したとも言える。
藩主閑叟は栄寿に語る。「儂は大砲を並べることで佐賀を日本の火城たらしめんとした。だが・・・・・・・・思惑とは異なっても、すでに佐賀は火城となっておる。」(p289)
「大砲も火なれば、蒸気も火。・・・・・・おまえの火がからくり儀右衛門という火を佐賀に呼びよせたのだ。こけおどかしの松明となるか、そうでないかは、これからの働きにかかっておる」(p290)
本書のタイトル「火城」はここに由来するようだ。
尊王攘夷や国学の思想が渦を巻き、騒乱を惹起している最中に、思想とは一線を画し、西洋諸国に対峙していく道を模索していた一群の人々がいたことを本書で知った。江戸時代の末期を眺める視座が広がった気がする。
栄寿がジョン万次郎と関りを持ち、一助の策をめぐらしたというくだりを興味深く読んだ。栄寿ならやったことだろうなと思う。ここにも人を活かす心が息づいている。
ご一読ありがとうございます。
補遺
鍋島直正 :ウィキペディア
佐野常民 揺ぎなき博愛精神 :「Sagabai.com」(佐賀市観光協会)
佐野常民と三重津海軍跡の歴史館 ホームページ
佐野常民の歩み
枝吉神陽 ~佐賀の「吉田松陰」~ :「Sagabai.com」(佐賀市観光協会)
伊東玄朴 :ウィキペディア
からくり儀右衛門(田中久重)の生涯 :「久留米市」
田中久重 :ウィキペディア
佐賀県の歴史第2章 嵯峨における幕藩体制 :「佐賀県」
明治維新の先駆的役割を果たした佐賀藩 :「佐賀県」
久留米からくり振興協会 ホームページ
蒸気船雛形(外輪船) :「佐賀城本丸歴史館」
蒸気車雛形 附貨車他 一台 :「さがの歴史・文化お宝帳」
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)

















