蔦屋重三郎をどのように描き出すのかという興味から、NHKの大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」を見ている。この蔦重が写楽の絵を世に送り出した。蔦重と写楽はいわばセットである。
先日、このタイトルが目に止まった。勿論、手が出る。両者に関心があるので・・・・。
本書は、2024年11月に単行本が刊行された。書下ろし作品。
本書のタイトルにまず着目しよう。タイトルにはルビが振られている。標題では意識的にタイトルに付記されたルビを外した。このタイトルを遠目で見た時、最初に「憧れ」に目が止まり「あこがれ」と読んでいた。手に取ってみると、背表紙の「憧れ」には「あくが」とルビが振られている。表紙には、「憧れ」と「写楽」の間に、「あくがれしゃらく」と小さくルビが振られている。
『新明解国語辞典 第5版』(三省堂)を引くと、「あこがれる/憧れる」は載っている。「(自下一)(「あくがる」の変化)①理想的な存在とする所の者に心が強く惹かれ、会って見たい、近づきになりたいと切に望む。②理想的な生活環境を実現しているものとして、自分も早くそれにあやかりたい(そこに行って見たいと思う。)」と説明。「あくがれる」は載っていない。
「あくがる」は古語なのだ。『学研全訳古語辞典 改訂第二版』を引くと、「あくがる/憧る」が載っている。「自動詞・ラ下二。①心が体から離れてさまよう。うわの空になる。②どこともなく出歩く。さまよう。③心が離れる。疎遠になる」と説明している。
大辞典レベルになると、さすがに両語が載っている。手元の『日本語大辞典』(講談社)を引くと、「あこがれる/憧れる」は、「(下一自)心をひかれる。思いをよせる。むねをこがす。あくがれる」と説明し、一方「あくがる/憧る」は、「古語(下二自)①物事に心をひかれて、ふらふら歩く。②心ひかれて、落ち着かなくなる。思いこがれる」と説明する。
遠回りな書き出しになったが、「あくがれ」と読ませることで、写楽を対象とする二つの意味合いをはっきりと重ねている。その上で、写楽に迫って行くという構造なのだ。これは読みながら理解したこと。
本作では、この「あくがる/憧る」は、鶴屋喜右衛門が蔦屋重三郎の口から零れた言葉として聞き取り、要領を得なかった言葉なので、山東京伝に尋ねてみたという文脈で出て来る。その時、京伝は西行法師の歌を引用して説明する。ここに由来する。(p89)
あくがるる心はさても山桜 散りなんのちや身に帰るべき
本作の本筋は、写楽自身を描くストーリーではなくて、「もう一人」の写楽、「ほんもの」の写楽を探すというプロセスにある。写楽探しのミステリー小説に仕立てられているおもしろさにある。
時代設定は、寛政8年の「夏」「秋」「冬」にかけて。その冬に遂に「真相」が解明されるという4セクションで構成される。各セクションの後には、「ある記憶」という回想がパラレルに進行していく。壱、弐、参、四という具合に。このパラレル・ストーリーとして記憶を語るのが蔦重なのだ。
「終 寛政10年3月」が最後の閉めとなる。喜右衛門と京伝の会話の場面で終わる。
その会話で地本問屋の喜右衛門は「ようやく、手前は写楽から足を洗えます」(p266)と京伝に語る。喜右衛門の思いは深い。
メイン・ストーリーに入ろう。こちらに本書のタイトルが直接的に繋がっている、
「あくがる」には、2つの意味合いがある点を巧妙に構造化していく。現在の私たちが普通に使っている「心をひかれる。思いをよせる」という意味合い。上記の「どこともなく出歩く。さまよう」という意味合い。これが写楽に関わる。
御三卿田安家の家臣を務める唐衣橘州が、写楽の絵を愛好し、寛政6年5月の興行を写した大首絵、特に「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」に心ひかれていた。この絵を肉筆画として描いて欲しいという思いを抱いていた。
「写楽の役者絵は、寛政6年5月興行分、同7・8月興行分、同11・閏11月興行分、寛政7年正月興行分に大別でき、熱心な贔屓ほど寛政6年5月興行分の絵を好むきらいがある」(p10)つまり、唐衣橘州その人も、その類の贔屓だということに。
唐衣橘州の要望を引き受けたのは、鶴屋喜右衛門。彼は日本橋近くの通油町の一角に店を構える仙鶴堂という江戸では老舗の地本問屋の主人。唐衣橘州は狂歌作者でもあり、著作者として、喜右衛門とは関わりがあった。
松平定信の寛政の改革を経る過程で、仙鶴堂では学術書や実用書という物の本を商う比率が高くなり、浮世絵や戯作という華やかな色合いの地本を商う比率が下がり、低迷している状態だった。地本問屋として、喜右衛門は内心忸怩たる思いを抱いていた。
喜右衛門が橘州の所望を引き受けたのは、勿論、写楽の素性は斎藤十郎兵衛との噂を聞き知っていたからである。八丁堀地蔵橋に住む阿波蜂須賀公抱えの猿楽師だと。
喜右衛門は斎藤十郎兵衛を訪れ、橘州所望の肉筆画を描くことを依頼した。だが、かなりの時日が過ぎた後、その思惑は頓挫する。
斎藤は写楽として絵を描いたのは事実だが、自分が描いていない役者絵で写楽名の作品が6名あると白状したのだ。その一人の絵が「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」だった。
喜右衛門は、橘州の要望を叶えるために、本物の写楽探しをしなければならない状況に追い込まれる。勿論、本物の写楽を突き止められれば、耕書堂蔦屋重三郎とは別に、地本問屋として、新たに仕事を依頼するという思惑、算段が内心にあった。
喜右衛門は、本物の写楽を求めて、「あくがる」ことに・・・・。つまり、写楽探しに江戸をさまよい、あちらこちらと出歩く仕儀となる。
勿論、いくら地本問屋の主といえど、己一人で探せるわけがない。
たまたま、いつものように、だしぬけに仙鶴堂を訪ねてきた喜多川歌麿に、事情を説明すると、歌麿は興味を持ち協力をすると言う。ここから本物の写楽探しがは決まっていく。ここから喜右衛門と歌麿による聞き込み調査と推理が積み重ねられていく。まさにミステリー小説となる。
目次の次の内表紙には、写楽の役者絵が「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」を筆頭に6枚挿画とし描かれている。
誰に聞き込みをするかが興味深い。される側の名前を列挙してみよう。
曲亭馬琴、十偏舎一九、北斎宗里、大田南畝、市川蝦蔵、河原崎座の河原崎権之助、二代目中村仲蔵、山東京伝、市川男女蔵、谷村虎蔵、四代目岩井半四郎、二代目小佐川常世、内田米棠、歌川豊国、斎藤十郎兵衛、藤一宗らである。
浮世絵好き、芝居好き、戯作好きには惹かれる有名人が登場し、応答する流れとなる。
喜右衛門は地本問屋の寄り合いの折に、蔦屋重三郎には斎藤十郎兵衛に絵の仕事を依頼していると伝えてはいた。だが、本物の写楽探しをしているという噂を耳にした蔦重は、写楽探しを無意味なもととして、喜右衛門の前に立ちはだかる者として要所要所で現れてくる。勿論、読者にとっては、興味津々の度合いがエスカレートしていく要因になる。
蛇足になるが、著者が本作において、「憧れ」という語句を使用している箇所で、通読していて気づいた箇所を明記しておこう。見過ごしがあるかもしれないが・・・・。
p75、p89、p181、p215、p241、p251、p252 である。
最後に、喜右衛門と蔦重の思いが記されていて、印象深い箇所を引用しておきたい。
まずは鶴屋喜右衛門の思いから:
*世の中に向き合う仕事でもあるのは百も承知です。でもね、あたしたち版元が、面白いもの、学びになるもの、綺麗なもの、すごいものを作ることから目を背けちゃいけない。最近、そう考えるようになりました。 p169
面白いものを企んで作るのが、版元の本義だって言いたいだけですよ。・・・手前ら版元は、面白いもんで世の中の横っ面を叩かなくちゃならないんですよ。今、この瞬間(とき)だって。 p170 → 寛政の改革、倹約令の余波・影響がある時点
*斎藤も、本物の写楽も、勝川春章が源流にあった。-----同じ絵師に私淑していたのだ。しかし、あり方はまったく違う。斎藤は無邪気に元絵を写し、本物の写楽は元絵の先にあるものを描こうとした。善し悪しはないが-----この違いは途轍もなく大きい。 p205
*才は花だ。盛りがあり、終わりの日がやってくる。
版元とは、花の盛りを捉えて花卉を摘み、並べ売る仕事なのかもしれない。
古い花は心底で咲かせ、新たな花の糧とするべきだったのだ。 p206
次に蔦屋重三郎の思い: この箇所、大河ドラマの蔦重に通じているように感じる。
*一等前を走る人間は自分の手綱を緩めることが出来るんです。でも、誰かに追随する人間は、やることが極端になる。なぜなら、手綱を自分ではなく、他の人に委ねているからです。 p136
*沢山作り、大いに売る。そうすることで、江戸をーーーーー世の中を変える。 p260
著者は、本作により、写楽二人説という仮説を提示した。
さらに、なぜ写楽の作品が上記の期間に限定せざるを得なかったのかにも、大胆な仮説を提示したことになる。
写楽の役者絵のいくつかについて、その読み解き方を仮設の一部として取り込んでいるところに斬新さを感じた。それは状況設定のフィクションと絡んでいることなのかもしれないが、おもしろい発想と思う。
幾人もの作家が、写楽を題材とした作品を発表している。ここに、新たな仮説が提示されたと言える。東洲斎写楽、一層おもしろくなったと言える。
ご一読ありがとうございます。
補遺
東洲斎写楽 :ウィキペディア
東洲斎写楽の生涯 :「刀剣ワールド浮世絵」
浮世絵史上最大のミステリー!謎の絵師・東洲斎写楽ってどんな人?
:「北斎今昔」(アダチ版画研究所)
勝川春章 :ウィキペディア
鶴屋喜右衛門 :ウィキペディア
蔦屋重三郎 :ウィキペディア
山東京伝 :ウィキペディア
江戸三座役者似顔絵 :「e國寶」
【AROUND蔦重】⑰ナゾの絵師、東洲斎写楽――蔦重、大いに売り出す:「美術展ナビ」
役者絵(歌舞伎絵)の画像 :「刀剣ワールド浮世絵」
蔦屋重三郎の記事 :「美術展ナビ」
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
こちらの本も読後印象を書いています。「遊心逍遥記」に掲載。
お読みいただけるとうれしいです。
『安土唐獅子画狂伝 狩野永徳』 徳間書店
『三人孫市』 中央公論新社
『洛中洛外画狂伝 狩野永徳』 Gakken
先日、このタイトルが目に止まった。勿論、手が出る。両者に関心があるので・・・・。
本書は、2024年11月に単行本が刊行された。書下ろし作品。
本書のタイトルにまず着目しよう。タイトルにはルビが振られている。標題では意識的にタイトルに付記されたルビを外した。このタイトルを遠目で見た時、最初に「憧れ」に目が止まり「あこがれ」と読んでいた。手に取ってみると、背表紙の「憧れ」には「あくが」とルビが振られている。表紙には、「憧れ」と「写楽」の間に、「あくがれしゃらく」と小さくルビが振られている。
『新明解国語辞典 第5版』(三省堂)を引くと、「あこがれる/憧れる」は載っている。「(自下一)(「あくがる」の変化)①理想的な存在とする所の者に心が強く惹かれ、会って見たい、近づきになりたいと切に望む。②理想的な生活環境を実現しているものとして、自分も早くそれにあやかりたい(そこに行って見たいと思う。)」と説明。「あくがれる」は載っていない。
「あくがる」は古語なのだ。『学研全訳古語辞典 改訂第二版』を引くと、「あくがる/憧る」が載っている。「自動詞・ラ下二。①心が体から離れてさまよう。うわの空になる。②どこともなく出歩く。さまよう。③心が離れる。疎遠になる」と説明している。
大辞典レベルになると、さすがに両語が載っている。手元の『日本語大辞典』(講談社)を引くと、「あこがれる/憧れる」は、「(下一自)心をひかれる。思いをよせる。むねをこがす。あくがれる」と説明し、一方「あくがる/憧る」は、「古語(下二自)①物事に心をひかれて、ふらふら歩く。②心ひかれて、落ち着かなくなる。思いこがれる」と説明する。
遠回りな書き出しになったが、「あくがれ」と読ませることで、写楽を対象とする二つの意味合いをはっきりと重ねている。その上で、写楽に迫って行くという構造なのだ。これは読みながら理解したこと。
本作では、この「あくがる/憧る」は、鶴屋喜右衛門が蔦屋重三郎の口から零れた言葉として聞き取り、要領を得なかった言葉なので、山東京伝に尋ねてみたという文脈で出て来る。その時、京伝は西行法師の歌を引用して説明する。ここに由来する。(p89)
あくがるる心はさても山桜 散りなんのちや身に帰るべき
本作の本筋は、写楽自身を描くストーリーではなくて、「もう一人」の写楽、「ほんもの」の写楽を探すというプロセスにある。写楽探しのミステリー小説に仕立てられているおもしろさにある。
時代設定は、寛政8年の「夏」「秋」「冬」にかけて。その冬に遂に「真相」が解明されるという4セクションで構成される。各セクションの後には、「ある記憶」という回想がパラレルに進行していく。壱、弐、参、四という具合に。このパラレル・ストーリーとして記憶を語るのが蔦重なのだ。
「終 寛政10年3月」が最後の閉めとなる。喜右衛門と京伝の会話の場面で終わる。
その会話で地本問屋の喜右衛門は「ようやく、手前は写楽から足を洗えます」(p266)と京伝に語る。喜右衛門の思いは深い。
メイン・ストーリーに入ろう。こちらに本書のタイトルが直接的に繋がっている、
「あくがる」には、2つの意味合いがある点を巧妙に構造化していく。現在の私たちが普通に使っている「心をひかれる。思いをよせる」という意味合い。上記の「どこともなく出歩く。さまよう」という意味合い。これが写楽に関わる。
御三卿田安家の家臣を務める唐衣橘州が、写楽の絵を愛好し、寛政6年5月の興行を写した大首絵、特に「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」に心ひかれていた。この絵を肉筆画として描いて欲しいという思いを抱いていた。
「写楽の役者絵は、寛政6年5月興行分、同7・8月興行分、同11・閏11月興行分、寛政7年正月興行分に大別でき、熱心な贔屓ほど寛政6年5月興行分の絵を好むきらいがある」(p10)つまり、唐衣橘州その人も、その類の贔屓だということに。
唐衣橘州の要望を引き受けたのは、鶴屋喜右衛門。彼は日本橋近くの通油町の一角に店を構える仙鶴堂という江戸では老舗の地本問屋の主人。唐衣橘州は狂歌作者でもあり、著作者として、喜右衛門とは関わりがあった。
松平定信の寛政の改革を経る過程で、仙鶴堂では学術書や実用書という物の本を商う比率が高くなり、浮世絵や戯作という華やかな色合いの地本を商う比率が下がり、低迷している状態だった。地本問屋として、喜右衛門は内心忸怩たる思いを抱いていた。
喜右衛門が橘州の所望を引き受けたのは、勿論、写楽の素性は斎藤十郎兵衛との噂を聞き知っていたからである。八丁堀地蔵橋に住む阿波蜂須賀公抱えの猿楽師だと。
喜右衛門は斎藤十郎兵衛を訪れ、橘州所望の肉筆画を描くことを依頼した。だが、かなりの時日が過ぎた後、その思惑は頓挫する。
斎藤は写楽として絵を描いたのは事実だが、自分が描いていない役者絵で写楽名の作品が6名あると白状したのだ。その一人の絵が「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」だった。
喜右衛門は、橘州の要望を叶えるために、本物の写楽探しをしなければならない状況に追い込まれる。勿論、本物の写楽を突き止められれば、耕書堂蔦屋重三郎とは別に、地本問屋として、新たに仕事を依頼するという思惑、算段が内心にあった。
喜右衛門は、本物の写楽を求めて、「あくがる」ことに・・・・。つまり、写楽探しに江戸をさまよい、あちらこちらと出歩く仕儀となる。
勿論、いくら地本問屋の主といえど、己一人で探せるわけがない。
たまたま、いつものように、だしぬけに仙鶴堂を訪ねてきた喜多川歌麿に、事情を説明すると、歌麿は興味を持ち協力をすると言う。ここから本物の写楽探しがは決まっていく。ここから喜右衛門と歌麿による聞き込み調査と推理が積み重ねられていく。まさにミステリー小説となる。
目次の次の内表紙には、写楽の役者絵が「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」を筆頭に6枚挿画とし描かれている。
誰に聞き込みをするかが興味深い。される側の名前を列挙してみよう。
曲亭馬琴、十偏舎一九、北斎宗里、大田南畝、市川蝦蔵、河原崎座の河原崎権之助、二代目中村仲蔵、山東京伝、市川男女蔵、谷村虎蔵、四代目岩井半四郎、二代目小佐川常世、内田米棠、歌川豊国、斎藤十郎兵衛、藤一宗らである。
浮世絵好き、芝居好き、戯作好きには惹かれる有名人が登場し、応答する流れとなる。
喜右衛門は地本問屋の寄り合いの折に、蔦屋重三郎には斎藤十郎兵衛に絵の仕事を依頼していると伝えてはいた。だが、本物の写楽探しをしているという噂を耳にした蔦重は、写楽探しを無意味なもととして、喜右衛門の前に立ちはだかる者として要所要所で現れてくる。勿論、読者にとっては、興味津々の度合いがエスカレートしていく要因になる。
蛇足になるが、著者が本作において、「憧れ」という語句を使用している箇所で、通読していて気づいた箇所を明記しておこう。見過ごしがあるかもしれないが・・・・。
p75、p89、p181、p215、p241、p251、p252 である。
最後に、喜右衛門と蔦重の思いが記されていて、印象深い箇所を引用しておきたい。
まずは鶴屋喜右衛門の思いから:
*世の中に向き合う仕事でもあるのは百も承知です。でもね、あたしたち版元が、面白いもの、学びになるもの、綺麗なもの、すごいものを作ることから目を背けちゃいけない。最近、そう考えるようになりました。 p169
面白いものを企んで作るのが、版元の本義だって言いたいだけですよ。・・・手前ら版元は、面白いもんで世の中の横っ面を叩かなくちゃならないんですよ。今、この瞬間(とき)だって。 p170 → 寛政の改革、倹約令の余波・影響がある時点
*斎藤も、本物の写楽も、勝川春章が源流にあった。-----同じ絵師に私淑していたのだ。しかし、あり方はまったく違う。斎藤は無邪気に元絵を写し、本物の写楽は元絵の先にあるものを描こうとした。善し悪しはないが-----この違いは途轍もなく大きい。 p205
*才は花だ。盛りがあり、終わりの日がやってくる。
版元とは、花の盛りを捉えて花卉を摘み、並べ売る仕事なのかもしれない。
古い花は心底で咲かせ、新たな花の糧とするべきだったのだ。 p206
次に蔦屋重三郎の思い: この箇所、大河ドラマの蔦重に通じているように感じる。
*一等前を走る人間は自分の手綱を緩めることが出来るんです。でも、誰かに追随する人間は、やることが極端になる。なぜなら、手綱を自分ではなく、他の人に委ねているからです。 p136
*沢山作り、大いに売る。そうすることで、江戸をーーーーー世の中を変える。 p260
著者は、本作により、写楽二人説という仮説を提示した。
さらに、なぜ写楽の作品が上記の期間に限定せざるを得なかったのかにも、大胆な仮説を提示したことになる。
写楽の役者絵のいくつかについて、その読み解き方を仮設の一部として取り込んでいるところに斬新さを感じた。それは状況設定のフィクションと絡んでいることなのかもしれないが、おもしろい発想と思う。
幾人もの作家が、写楽を題材とした作品を発表している。ここに、新たな仮説が提示されたと言える。東洲斎写楽、一層おもしろくなったと言える。
ご一読ありがとうございます。
補遺
東洲斎写楽 :ウィキペディア
東洲斎写楽の生涯 :「刀剣ワールド浮世絵」
浮世絵史上最大のミステリー!謎の絵師・東洲斎写楽ってどんな人?
:「北斎今昔」(アダチ版画研究所)
勝川春章 :ウィキペディア
鶴屋喜右衛門 :ウィキペディア
蔦屋重三郎 :ウィキペディア
山東京伝 :ウィキペディア
江戸三座役者似顔絵 :「e國寶」
【AROUND蔦重】⑰ナゾの絵師、東洲斎写楽――蔦重、大いに売り出す:「美術展ナビ」
役者絵(歌舞伎絵)の画像 :「刀剣ワールド浮世絵」
蔦屋重三郎の記事 :「美術展ナビ」
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
こちらの本も読後印象を書いています。「遊心逍遥記」に掲載。
お読みいただけるとうれしいです。
『安土唐獅子画狂伝 狩野永徳』 徳間書店
『三人孫市』 中央公論新社
『洛中洛外画狂伝 狩野永徳』 Gakken














 新装版表紙
新装版表紙
 PHP文庫表紙 1995年9月出版
PHP文庫表紙 1995年9月出版 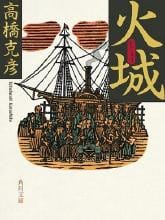 角川文庫表紙 2001年11月出版
角川文庫表紙 2001年11月出版 




