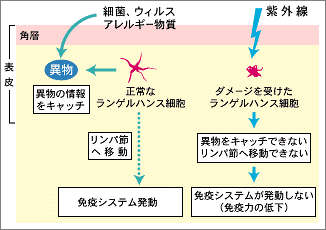神経成長因子(NGF)を用いた新しいタイプの点眼薬に、網膜細胞および視神経細胞を保護する作用がみられ、緑内障患者の視力を回復させる可能性もあることが、イタリアの研究で示された。NGFの点眼により緑内障を治療できる可能性を示した研究は今回が初めてであると、イタリア、ローマ大学のStefano Bonini博士は述べている。
米緑内障研究財団(Glaucoma Research Foundation、カリフォルニア州)によると、緑内障は視神経が徐々に侵され視力低下や失明の原因にもなる眼疾患で、年齢問わず発症するが、特に高齢者ではリスクが高い。世界で失明原因の第2位となっており、米国では約400万人が罹患し(約半数は自覚がない)、約12万人が失明している。米国では緑内障が失明原因の10%を占めているという。最新の治療によって眼圧を軽減し、進行を遅らせることはできるが、失われた視力を回復する治療法はこれまでなかった。
著者らは、過去の研究でヒト組織中にみられる蛋白(たんぱく)であるNGFがパーキンソン病やアルツハイマー病患者の脳組織の治療に有益であることが示された点に着目。発症の仕方が似ていることから、緑内障は「眼のアルツハイマー病」とも呼ばれるという。今回の研究では、緑内障を誘発したラットにNGFの点眼薬を2通りの用量で投与した結果、特に高用量で網膜神経が死滅する比率が有意に低下することがわかった。
次に、進行した緑内障患者3人を対象にNGF点眼薬を使用し、治療前、治療開始後3カ月、治療終了後3カ月に眼機能を検査した結果、2人に視力の改善が認められ、もう1人は治療後に視力の安定がみられた。さらに、視野、視神経機能、対比感度および視力の改善は、初回の点眼薬投与から18カ月後でも維持されていた。
ただし、Bonini氏によると、現在NGFは臨床で使用できず、今回の結果についても大規模な臨床試験による裏付けが必要であることから、この治療法がすぐに利用可能になるわけではないという。しかし、理論的にはこの知見が眼疾患のほかさまざまな神経変性疾患の新しい治療選択肢につながる能性があると、研究チームは述べている。
米国科学アカデミー発行の「Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)」オンライン版より
米緑内障研究財団(Glaucoma Research Foundation、カリフォルニア州)によると、緑内障は視神経が徐々に侵され視力低下や失明の原因にもなる眼疾患で、年齢問わず発症するが、特に高齢者ではリスクが高い。世界で失明原因の第2位となっており、米国では約400万人が罹患し(約半数は自覚がない)、約12万人が失明している。米国では緑内障が失明原因の10%を占めているという。最新の治療によって眼圧を軽減し、進行を遅らせることはできるが、失われた視力を回復する治療法はこれまでなかった。
著者らは、過去の研究でヒト組織中にみられる蛋白(たんぱく)であるNGFがパーキンソン病やアルツハイマー病患者の脳組織の治療に有益であることが示された点に着目。発症の仕方が似ていることから、緑内障は「眼のアルツハイマー病」とも呼ばれるという。今回の研究では、緑内障を誘発したラットにNGFの点眼薬を2通りの用量で投与した結果、特に高用量で網膜神経が死滅する比率が有意に低下することがわかった。
次に、進行した緑内障患者3人を対象にNGF点眼薬を使用し、治療前、治療開始後3カ月、治療終了後3カ月に眼機能を検査した結果、2人に視力の改善が認められ、もう1人は治療後に視力の安定がみられた。さらに、視野、視神経機能、対比感度および視力の改善は、初回の点眼薬投与から18カ月後でも維持されていた。
ただし、Bonini氏によると、現在NGFは臨床で使用できず、今回の結果についても大規模な臨床試験による裏付けが必要であることから、この治療法がすぐに利用可能になるわけではないという。しかし、理論的にはこの知見が眼疾患のほかさまざまな神経変性疾患の新しい治療選択肢につながる能性があると、研究チームは述べている。
米国科学アカデミー発行の「Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)」オンライン版より